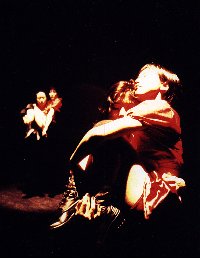 CRUSTACEA
CRUSTACEA
クルスタシア。'95年1月、それぞれ異なった環境でダンス歴を持つ4人のメンバーにより発足。作・振付の濱谷由美子ら、東京在住組と関西在住組との遠距離恋愛的活動から始まった「温和なパンク志向」のパフォーマンス・ユニット。コミカルでアグレッシヴ、スピード感あふれるダンスを展開。「昭和のお色気」的雰囲気を醸し出す。女性用補正下着や浴衣などの衣裳で、フェミニストの誤解を受けたり、音楽でもアーティスティックな舞台では絶対に使われないカラオケ演歌を使ったりと、ローテクで斬新な発想から、あくまで日本表層文化にこだわるNew Japanese Danceを標榜。キッチュ、ハレンチ、スタミナ、がキーワード。
濱谷由美子。'72年大阪生まれ。6歳よりクラシック・バレエを始める。10年間環バレエ・スタジオに在籍。その後、クラシック・バレエ表現に興味を持ち、'92年木佐貫邦子のダンス・アンサンブル・メンバーのneoに参加。以降多数の作品に出演。次第にダンスに限らず、多方面との関わりを持ちながらクリエイトすることに興味を持ち、CRUSTACEAを結成、企画・演出・振付を行う。
回るとか倒れるとか、そういう動詞にしてしまえば単純な動きの連鎖に、これまでいかに多くのダンサーが挑戦してきたことか。いわゆるダンスとしてだけではない、旋回舞踊とか五体投地にまで通じて、大げさではなく何か別の世界の何ものかに通じてしまうような恐ろしさ(?)がある。
CRUSTACEAの2人が提示したのは、瞬間ごとに終わってしまうことの痛切と、その後に果たして救済が用意されているかということについての、彼女たちなりのシンプルな回答だったように思う(5月21日「2P(要冷蔵)」トリイホール・ダンスセレクション)。ふだん彼女たちが多用する観客に対するコケットリィ=翻って自己慰撫のような態度がまったく見られず、見ようによっては別ユニットのようだったことそのものについては、ここではいったん留保しておく。これまでの彼女たちの作品の延長として今回の作品を判断することが有効なのかどうかが、速断したくないからだ。
すさまじい昏倒が繰り返されることが、まるで時を刻むように思えたのだが、それがとても美しく見えたことによって、ぼくはぼくたちの不断の日常というものは本当は美しいものであってよいということ、つまり既に救われた存在であってよいこと、を痛切に感じることができたように思う。(P.A.N.Press vol.34)
東山ダンスミニシアター 2001年3月25日(日) 京都市東山青少年活動センター○ロビープロジェクト−CRUSTACEA
体操服とブルマーに身を包んだ浜谷由美子と椙本雅子が、吹き抜けロビー2階の空中廊下を舞台に、B級ポップな、いわゆる「おばかダンス」を次々と繰り出した。いわゆるコケティッシュで、脳天から何かが突き抜けたようなあっけらかんとしたダンスで、ロビーは爆笑の渦に包まれた。ただ楽しい、面白い、それだけでいいじゃないかという覚悟のようなものが見えてくるのが、CRUSTACEAのこの手のダンスの最大の美点だ。
親指を噛んで媚びるようなしぐさをして見せたかと思うと、マッチョみたいに筋肉を誇示するようなポーズをとる。そんふうに女らしさとして求められているものや男らしさとされているもの等々を自由に軽妙に組み上げていくことで、すべてを無化してしまうような力がある。
ぼくたちは彼女たちの余興みたいなダンスを見て笑いながら、他のあらゆるシリアスなダンスがつまらなく思えてしまうのではないかという、ある種の不安にとらわれていた。
CRUSTACEA「Beach(バカンスロングバージョン)」
浜谷由美子と椙本雅子の従来からのメンバーに加え、ワークショップに参加したメンバー4人を加えての公演。ザブーン、ザブーンという波の音にスチールギターがかぶっただけで、笑えた。うまく外してしまういいセンスを持っている。白いバスローブ姿のメンバーのしんがりで浜谷が登場する。6人の瞳にはお星様が輝いている。バスローブの合わせからのぞく太股がまぶしい。
……彼女たちの作品を見ていると、本当によく笑ってしまうのだが、一つには彼女たちのブリッコぶりのおかしさ、アッケラカンとしたセクシーさによっている。それらが湿度をもっていないのは、体育会系のダイナミックな動きのキレと、明快に戦略化されたコケットリィによるのだと思う。そのような明快さによって、新しいメンバーも用意にコンセプトを共有することができたのだろう、ダンス・ユニットとしてもよくまとまっていたように思う。
先ほども述べたように、彼女たちのダンスは確かに笑えるのだが、これはなかなか難しいことのようだ。「娘版Guys」「7 Color」「きれいはきたない きたないはきれい」といくつかの女性ダンサーによるプロデュース公演を見てた印象で言うと、女性の身体によって笑うことは、難しい。女性が踊るということが、何か本質的に笑うという方向性と相容れないものを持っているのかもしれない。
その前に、ダンスによって笑うというのはどのようなことだったのかを、考えておいたほうがよいのかもしれない。たとえばサイトウマコトの作品の中で印象的に覚えているのだが、靴を脱ぎ、そのにおいを嗅ぎ、遠ざけて顔をしかめるという一連の動きの繰り返し。初めは笑う。それが繰り返され、動きの単位として作品を構成する要素となったことがわかると、笑いの種から動きのモチーフに変化している。
あるいは、ユーモラスな動き。安来節のようだったり、タコ踊りのようだったりするもの。これはおおむね振り真似としてのおかしさである。この場合、ダンサーは観る者よりも一段低い場所にわが身を置かないと、笑いというものが流れない。笑うことは、「笑い者になる」ということからもわかるように、一面では上下関係の現われであろう。
これはぼくの男としての先入観かもしれないが、女性の身体というものは、崇敬の対象であっても、笑いの対象にはなりにくいのではないか。まずそのことによって、女性の身体は笑いの対象になりにくいのではないか。女性ダンサーの身体は、女神になるか女王になるか少女のままでいるかしかないのではないかと思う。それを拒否すれば、機械にならざるを得ない。
CRUSTACEAはそれを巧妙に回避できていると思うのだが、おそらくエッチでコケットリィであることをあらかじめ自身に規定していることによる。つまり、女性のダンスの身体が何かをあらわすことによって、否応なくセクシーだったりコケティッシュだったりするのを、先取りして押し出してしまう。それによって、そのような性格づけに伴いがちな湿り気を排除することができている。
椙本の動きがずいぶんシャープになり、客席へのアプローチがよりアグレッシヴになっているのがよかった。けっして浮遊感のあるダンスではないのだが、逆に地面を押し下げるような力が出てきている。(1999年3月16日、TORII_HALL)
インタビュー/ハマタニはなぜこうなのか?
前々から、一緒にストリップ見に行こうとか、通天閣の下で大衆演劇見ようとか言って、そのままになっている。今日は高級ホテルのレストランで、ハマタニに聞く。
J 今度はどんなエッチなステージにするの?
H エッチですかぁ?
J エッチでしょお、ランジェリーとか、セーラー服とか、バスローブ、スチュワーデス(10月、大阪)とか、オジサン喜ぶ基本じゃない。
H そうですかぁ。
J あれぇー? そういうこと、意識してないんですか? たとえば、親指を口にくわえてリズムに合わせてうなずくとかすると、普通、媚びてるとか、煽情的とか言われますよ。それで、フェミニズムのおばさまに叱られるわけよ。
H 私はね、変なふうにとられると困るんですけど、女の子が好きなんですよぉ、で、女の子がかわいく見える、ってことを一番に考えてる、それだけなんですけど。
……とにかく、今回は、浴衣(ゆかた)をまとってバリバリのモダンダンスを、狂ったように踊りまくるのだそうだ。
H みんながね、温泉行きたいって言ったんですよ。私もだけど。で、じゃあ、連れてってあげるわって、それで今度の公演です。
J それって、メンバー、怒らない?
H 怒ります。でも、ほんとに行ったんです、琵琶湖パラダイス。
J お客さんも、温泉気分で見ればいいんだ、きっと。お風呂上がって、大広間で始まる歌謡ショーや剣劇って感じで。
H 芸術って言葉をあんまり使いたくないんです。
J 気楽に見てもらいたいって言う意味ですか?
H それもあるんですけど、<スター>になりたいんですよ。芸術っていうよりは、芸能。
J シリアスな意味での自己表現っていう感じはしないですよね。自分自身をさらけ出すとか。そういう点で、これまでのダンスをやってきた人、見てきた人から理解されにくいのかもしれない。むしろ、音楽とか衣裳とかがコンセプト・メークのはじまりにあるんでしょ? それはあえてそう構えているわけ?
H それは、でも、感覚でしょう。
J ダンスっていつも一人称だったじゃない。それが合わないんじゃないのかな。自分のルーツとか、そういうのを掘ったり戻ったりすることより、いま現在のほうが興味がある?
H ノスタルジックじゃないですね。あんまり、昔にさかのぼって踊りたくはないですねぇ。ソロでやろうと思ってないから、っていうこともあるだろうけど。
J CRUSTACEAのステージでとても印象的な、音楽のこと。
H もうね、CD100枚以上、聞くんですよ。マンボとか、ブルースとか。今回は小唄や端唄。それでイメージを作っていくんです。
J それは、そのまま、ステージで使うの?
H 全然。曲決めるときは、また聞き直すんです。
J 大変ですね。
H だいたい覚えてる。
J あらゆる方面にわたって、天才ですね。
H はい(爆笑)。
見ることは考えることだろうが/考え至った途端もう彼女は遠い
CRUSTACEA伝説のクラブ公演「'96_in_MILK」の様々な意味で刺激的な映像を、当の本人たちは舞台の隅に置かれたソファでさざめきながら見ている/ぼくたちは映像を見、映像を見ている彼女たちを見ている/何ケ月か前に東京で行われた熱いステージを映像で見ているというのは不思議な疎外感だ/まして、彼女たちが目の前にいて、踊っていないということ!/対象化などという簡単なことじゃないよな/「ISH vol.2〜fantastic_cafe」はそのようなティージングから始まった/まず、これまでコケットリィと装われた部分が、さらに強さを増し、アグレッシヴになっているのに驚かされた/エッチでゴージャスなランジェリー姿にエプロンを着け、それをひらひらさせて挑発する/そのようなエッチという仕掛けには、男の沽券にかけてもひっかかれない/サトウノゾミというナイスバディな女はボンドガールみたいに脚を組んでカッコつけて二人の動きを見てるし/スレンダーなハマタニは意地悪そうな目つきで客席に視線を投げて楽しんでるし/彼女たちの仕掛けのストレートさ、それに素直に乗れないことが悔しい一方、自分で自分を面白がっている/いくつもの落とし穴を持っている/観客にも、自分たちに対してさえも/見ていて<毒を食らわば皿までも>ってな気分になる/そのスリルに興奮しているのだが、いつの間にかエッチな興奮とないまぜになってたりして、悔しい/やっぱりまんまとはまってしまっているのだ、甲殻類(クルスタシア)の罠に/もう一つ、男女の性役割についての罠も見てみよう/アラキミズホという男がポケットからエプロンを取り出し、女たちがエプロンを着ける/無音の中でダンスが続き、やがて女たちは男にエプロンをくくりつける/……これはどのようにも図式的で単純な読み方が可能だが、彼女たちの動きはそんなふうに読まれてしまう危うさを、かえって楽しんでいるように見える/「へぇーっ、そうなの、そうなのかしら」/ある見方、解釈を手にしたかと思うと、彼女たちは既にそのはるか前方に逃げ去っている/CRUSTACEAへの思いは、決して報われない(1997.2.17)(「JAMCi」1997年6月号掲載)
CRUSTACEAは、4人の女性による「温和なパンク志向」を標榜するパフォーマンス・ユニットだ。9月28日に横浜のSTスポットで「ISH vol.1−love」を見た。サブタイトルに通じるのだろうが、股を拡げて見せたりスカートをちょっとめくって見せたりといった少女的でコケットリィなポーズも、執拗な反復や機械的なスピードでさらりとかわし、見る者に何の思いも残さない。たしかに彼女たちのかわいらしさは微笑にあたいするが、それを思い切った速さで振り切っていくメカニカルな潔さが心地よい。反復が動きに意味を与え重ねるのではなく、かえって意味をなくしてしまうのが面白い。身体をただの器官として無機的に動かしていることがひじょうに新鮮にストレートに入ってくる。彼女たちの決定的な新しさは、動きへの思い入れや意味づけにかんして、意図して削ぎ落としているのではなく、もともとなかったようにしか見えないところだ。結果的に、ステージ上での彼女たちの身体は大きく見えない。等身大と言ってよいのだろう、アウラをあえて持たないことが鮮やかな軽さとなっている。やっと冒頭の話題に戻るが、彼女たちの動きはたしかにポップを装ってはいるものの、そうであることを彼女たち自身が突き放していることで、ただのポップにはとどまらない。既存のメソッドに拠っていても、既存であることをじゅうぶんに意識し、その延長線上ではなくかえって宙吊りにして見せるから凡庸にとどまらない。壊すことや外すことによってではなく超えてしまえることを、みごとに見せた爽やかな公演だった。
まず、コケティッシュということについて、批判的な観客があったそうだ。男に媚びるようなしぐさは許せないとか何とか。しかし、コケットリィというのは、武器だ。籠絡という言葉もある。それを意識的に戦略的に舞台上の表現として効果的に活用できていたのなら、それは鮮やかなことではないのか。また、彼女たちの美点は、そのコケットリィに拘泥しないところだ。舞台上に異性が存在したわけではないので、そのコケットリィは観客に向けられていたと言っていいと思うが、彼女たちにはそうしてせっかく引き寄せた観客の視線を直後にさっぱりと軽やかに振り捨てていく潔さがあって、それが実に心地よかったのだ。媚びたしぐさをしても、一瞬後にはカラカラと大笑して相手を奈落に突き落とすようで、それは本当には媚びとは言えないのではないだろうか。もちろん突き落とされる快感というものもあって、crustaceaに狂ってしまったら最後、そのような形の快感を求めてしまい、それはそれで一つの愛、タイトル通りにloveの一つの形であると思うのだが。
ぼくはそれに対してスピードという言葉を使ったが、濱谷自身は自分たちの動きは決してスピーディではないと思う、というようなことを言った。こじつけめいて聞こえるかも知れないが、それは前の動きにこだわらず、振り捨てて次の動きに移っていく「潔さ」と先に述べたようなものが、軽さ、快さとなって動きに速度を与えているということではないだろうか。
もう一つ、反覆ということについて。「反復が動きに意味を与え重ねるのではなく、かえって意味をなくしてしまうのが面白い」と書いたが、ぼくはこのことについてずーっと考えている。今年の二月に見た、スーザン・バージ振付、冬樹・森美香代ら七人の日本人ダンサー、いちひめ雅楽会から成るコラボレーション、MATOMAの新作「うぶすな」を見てこう書いたりもした……信仰と大地と生命の合一が美しい単調を支えていた/ここではさまざまな動きが執拗なまでに反覆される/不思議なことにこの反覆はその動きの印象を強調し固定化するよりも、消尽し無化する……(「JANCi」1996年6月号)。「うぶすな」の反覆と、CRUSTACEAの反覆とを同様に論じることはたいへん難しくまた無理もあろうが、「JAMCi」でも引用した三浦雅士の「どんな些細な行為でも繰り返せば舞踊になる」(「バウシュ」から。初出1993。『バレエの現代』所収)という道筋とは、ほぼ逆の方向性を、両者は持っているような気がしてならない。それが「日本」ということの特質であるのかどうか、今は定めて言うことはできない。
(JAMCi '95.12)+(視聴覚通信16号)
![]()