関西国際大学公開講座「災厄を綴り、継いでいくために~阪神・淡路大震災を表現する」
2000.1.22.
一部訂正増補の上、震災・まちのアーカイブから『震災と言葉』として刊行
1部400円(送料180円) お申込みは、078-781-8891季村様
演劇の言葉、ひとりの言葉
![]()
■ 講座の何ヵ月か後に-補足と若干の解説
「震災後」という言い方をよくする。「戦後」に近いニュアンスだ。ぼくたちの一つの時間の基点として、一九九五年一月十七日がある。あれは震災の前だったから、……もう五年以上昔のことになるのか、とか。そういう言い方が通用するのは、あるいはごく一部のいわゆる「被災地」の人々の間でだけかもしれないが、それによって醸し出される一つの空気というものがある。それはある時期なら(または今もある人々にとっては)復興の槌音というような建設的な響きであると捉えられているかもしれないが、むしろ現在のぼくには、空白や空漠というような言葉が最も近いように思われる。それは、ちょうど震災の直後、三宮などの繁華街のそこここで崩れかけたビルをユンボなどと呼ばれているらしい恐竜のような機械たちが壊そうとしている時に、「その埃で白くなった空気の向こうに、そもそも街はなかった」と思おうとした、そういう気分だ。
ある時期においては、そのような空漠と誰もが親しかったから、誰とでも仲間のような会話ができたりした。今は震災後ということをそのような空漠として持っている人はあまり多くないし、持っている人でもそんなことは忘れている時間のほうが長くなっているかもしれない。ぼくがそうだ。
それでもぼくたちは、共に震災を経験したということで、何かが語り合えるような気がする。たとえば、震災にふれたものであれば、絵画でも演劇でもダンスでも、なんでも観てみたい(あるいは、すべて観たくない)というような、共通の地平が生まれたのではなかっただろうか。それをたとえば東浩紀『郵便的不安たち』(朝日新聞社、一九九九)の言葉によって説明してみようか。
東は書いている、「サブカルチャーの進展にともない価値観は急速に相対化され、結果として各趣味を共有する人々はきわめて閉鎖的なグループを形成し(オタク化)、それらグループ間のコミュニケーションは急速に困難になっていった」、と。つまり現在の一般的な状況としては、美術館に行く人、劇場に行く人、詩を読む人、はバラバラであり、それぞれに「オタク」化してきている。これについて彼は、フランスの思想家リオタールが七〇年代末に「特定の新たな文化的モードに注目するためではなく、むしろ逆に、複数のモードが混在し、どれもが支配的になることなく並立し続ける文化状況の到来を警告するため」に社会の「ポストモダン」化という言葉を打ち出したことを挙げ、「リオタールは、社会のポストモダン化を『大きな物語』の解体ととらえた」と紹介している。「それは言い換えれば、社会全体をひとつにまとめ上げる意味づけのネットワークが機能不全に陥ることを意味する」……と。
ネットワーク社会と呼ばれる現在ではあっても、実のところぼくたちはこうして、システムとしてのネットワークは存在していることになっていながらも、そのケーブルが各所で寸断され、砕片化、孤立化された世界を生きているのかもしれない、そういう実感はある。しかしたとえば震災という出来事は、現実のライフラインを絶望的に寸断したが、様々な意味で、世界の砕片化を強引にでも押しとどめ、楔を打つものとなる可能性は抱えていたように思うのだ。
震災を「大きな物語」というような批評的言辞で指し示すことには、何だかぼくも生理的な抵抗があるのを感じる。物語は完結するものだが、震災はまだ完結していないということで、ためらいがあるのかもしれない。それでもぼくは、現代詩や演劇や現代美術やダンスといった、個々のジャンルとしてはタコ壷化、鑑賞者の側からはオタク化している現在の芸術表現が、この震災という大きな物語が被さることで、スコーンと普遍性を持ちうる契機があるのではないかと、いまだに期待している。
ぼくがこの公開講座で、まず震災後の美術から語り始め、続いて演劇という異なるジャンルの話題に移ったのは、上述のように、震災という「大きな物語」が共通項となれば、ジャンルを横断して表現のプロセスを共有することになるのではないかと考えたからだ。本当なら美術の作品を解説すべきだったかもしれないが、あえて仕掛けとしての美術行為を取り上げてみたのも、そのためだ。
当日は、演劇のナマな雰囲気を感じていただきたくて、ビデオを多用した。もちろんライブ感は伝わらない。でも、驚いたことに、ビデオを見て涙ぐんだり、鼻をすすったりしている人が多かった。それを目にしたぼくも、コメントしようとして絶句しそうになった。いわゆる小劇場演劇と呼ばれているものが、こんなに素晴らしいとは思わなかったと言って下さる人も多くて、わが事のようにたいへんうれしかった。
■ 被災の中心から少し離れて
この三木市でも一部の地域で家が全半壊するなど大きな被害があったようですが、たとえば本学では、図書館の書架、本棚ですが、は倒れませんでした。神戸大学附属図書館では、書架がまるで龍の骨のように波打って倒れていたのと比べると、このあたりの揺れ、被害など、取るに足らないものだったといえるでしょう。仲間内では、このへんは震度4かせいぜい5ぐらいだったんじゃないかなんていってましたが、どうでしょう。普通なら、震度4とか5とかいったらもう大変で大騒ぎなんですが、当時はそうじゃなかったですよね。実際、このあたりは、阪神間の被災の中心地への後方支援基地のような役割をしてくださっていたというふうに聞いています。ありがとうございました。当時、おにぎりを作ってくださったりした方も、この中にはいらっしゃるのではないでしょうか。このような被災地からの遠さについて、たとえば震災直後に大阪では冬物のラストバーゲンやバレンタインセールで賑わっていたという「落差」について、憤られた方も多かったのですが、私は大阪に出かけた時に、大阪が無事で何もなかったことについて、一種の安堵感を持っていました。ここは無事でよかったなと。それと同じことを、震災の翌週からの毎日の通勤の中で、この三木の街に対して、よかったなと思っていたのではなかったかと思います。
しかし、今になって思えば、三木の街の多くの皆さんにとって、阪神間、被災地の中心部というのは、つい何年か前まで住んでいたり、勤め先や学校があったり、親戚、知人、恋人がいたりという、すぐ近くの場所であるにもかかわらず、そしてご家族や親戚、友人知人の中に被害にあわれた方も多かったにもかかわらず、三木の自分の家は無事だったということで、何か焦りのような、何かしなければいけないというような思いをお持ちになってしまったのではないでしょうか。
実は、私が今日ここでこのようにお話しをさせていただくのは、まさにそのような焦りを、被災地の真っただ中にいながら家族にも勤め先にも家屋にも被害がなかったということにおいて、持っていたことを中心に据えて書いた文章が、高校の国語の教科書に掲載されるという、一つの話題性に支えられています。その文章についてはこのお話しの後半部分で、時間が残っている限りふれさせていただくことになります。
それに加えて、私は9年ほど前から現代美術や演劇、そして最近は特にダンスや宝塚歌劇についてと、舞台芸術(パフォーミング・アーツといってもいいでしょうが)を中心に、自分で出すミニコミやいくつかの雑誌、本に文章を発表してきました。もちろんそれには、いくつかの、編集者との幸運な出会いや、タイミングのよさ、友人知人からの望外のお誘いということがあって文章を発表する場というものを与えていただいているのだと思っています。ちょっぴり加えれば、少しの執念。そんなところでしょうか。
震災後、なんの被害にもあわず、なにもできなかったという負い目を持ったまま時を過ごしてまいりましたが、自分に半ば言い聞かせるように、「ぼくの仕事は、見続けることだ。ぼくにとっては演劇やダンスや美術を、見続け、それを記録に記憶にとどめ伝えていくことだ」という、もしかしたら一人よがりな使命感に燃えているといってもいいかもしれません。
ですから、というのもおかしいかもしれませんが、私自身は震災について何の状況論的なお話しもできません。政府や県・市からの援助がどうとか、地域の防災態勢とか、コミュニティの問題とか、そういうことについて、個人的に無責任な世間ばなし程度の感想は持っていますが、それについて今日はお話しいたしません。そういう視点が抜けていることについては、あらかじめご了承をいただいておきたいと思っています。
■ 震災直後の美術家の動き
さて、今日の私のお話しは、2つのテーマから成っています。まず一つ目は、震災の後、美術や、そして主に演劇はそれをどう描いてきたかということ。もう一つは、私が震災をどう文章にしたかということ。この二つのことは、私の中ではかなり緊密に響きあっているのですが、今日はその関連性までお話しすることは難しいかもしれません。二つの話を放り出すようなことになってしまうかもしれませんが、どうぞご容赦ください。
 さて、震災と演劇についてというメインテーマに入るまえに、震災後の現代美術について少しふれておきましょう。美術については、多くの美術家がチャリティ・オークション、ウォール・ペインティング、避難所で子どもと絵を書く、などと様々な活動を行ないました。いくつかの新聞記事や案内のはがきをご紹介しておきましょう。
さて、震災と演劇についてというメインテーマに入るまえに、震災後の現代美術について少しふれておきましょう。美術については、多くの美術家がチャリティ・オークション、ウォール・ペインティング、避難所で子どもと絵を書く、などと様々な活動を行ないました。いくつかの新聞記事や案内のはがきをご紹介しておきましょう。
*右写真は、ギャラリー夢創館(神戸市灘区)での「創造に向けてのガレキ」展(1995.4.24~5.1)ちらし及び参加申込書
また、おそらくはそれらの社会的活動が個人の内面で結実したのだと思うのですが、何人かの美術家が震災体験を核とした優れた作品を発表しました。それは今、芦屋市立美術博物館で開催中の「震災と表現」展や兵庫県立近代美術館で開催中の「震災と美術-1.17から生まれたもの」展で、一つの集約がなされています。これらの展覧会は、ぜひご覧いただきたいと思います。
 時間がありませんので、震災直後の美術の動きの中で、二つ、私が印象に残っていることをご紹介しておきましょう。一つは、今はもう大阪に移ってしまいましたが、神戸にあった画廊、シティ・ギャラリーが3月に開いた「WE
ARE
HERE」という展覧会です。「私はここにいます」、複数形なら「私たちはここにいます」。覚えてらっしゃるでしょうか、震災直後、倒壊した家の瓦礫の中に、「○○小学校の体育館にいます。全員無事です」などと書かれた立札が立っていたこと。個展自体は、美術家たちの小品を展示したもので、阪神間の美術家たちの、実質的な存在証明でもあり、そして、美術家が自分がこのような大きな体験を経た後にどのような形で自分の存在を証明するかということを問う、たいへん厳しい展示でもあったわけです。「ここ」というのは、地理的な意味であると同時に、「自分は(自分たちは)このように『表現』ということに倚っている者なのだ」というアイデンティティを表明する作業でもありました。
時間がありませんので、震災直後の美術の動きの中で、二つ、私が印象に残っていることをご紹介しておきましょう。一つは、今はもう大阪に移ってしまいましたが、神戸にあった画廊、シティ・ギャラリーが3月に開いた「WE
ARE
HERE」という展覧会です。「私はここにいます」、複数形なら「私たちはここにいます」。覚えてらっしゃるでしょうか、震災直後、倒壊した家の瓦礫の中に、「○○小学校の体育館にいます。全員無事です」などと書かれた立札が立っていたこと。個展自体は、美術家たちの小品を展示したもので、阪神間の美術家たちの、実質的な存在証明でもあり、そして、美術家が自分がこのような大きな体験を経た後にどのような形で自分の存在を証明するかということを問う、たいへん厳しい展示でもあったわけです。「ここ」というのは、地理的な意味であると同時に、「自分は(自分たちは)このように『表現』ということに倚っている者なのだ」というアイデンティティを表明する作業でもありました。
もう一つ、京都の美術家が中心となったピントゥーラ(Pintura 地震にあった子供たちと絵を描く会)というグループのものでしたが、避難所や被災地の小学校や幼稚園で子供たちと絵を書こうというボランティア活動。このこと自体はたくさんの例があったと思います。でも、正直に言って、いきなり避難所に行って、知らない人に、いきなり「さあ、絵を書こうね」って言って紙とクレパスを渡されても、困っちゃいますよね。そこで彼らは、面白い仕掛けを考え出しました。
大きな模造紙を用意します。お天気がよくないとだめなんですが、外に出ます。模造紙を広げて、その上に立ちます。すると、模造紙の上に自分の影が映りますね。その影の輪郭を、クレパスでなぞっていくんです。これで、太陽の角度によって等身大×何十%かの伸び縮みのある自分が描かれます。そして、その輪郭の中に自由に色を塗り、顔を描き、自画像を作っていきましょう、と。あるいは、模造紙の上に寝そべって、その輪郭をとっていく。以下同。そういうことです。
 京都の小さな画廊でその展示を見たのですが、これは素晴らしいと思いました。まず、絵が上手でも下手でも、輪郭がちゃんと書けます。デッサン力が問われない。これはいいですね。私なんか、助かります。そして、ほぼ等身大ですから、大きな動きが出来ます。寒さやさびしさや不安で縮こまっていた子供たちに、大きな腕の動き、目の動きを与えることが出来たはずです。そして、おそらくは無意識の内にでしょうが、自分を見つめることができていたでしょう。自分の輪郭をはっきりと描く。そのことで、自分がここにいること(I'm Hereですね)、この厳しい日々の中で、自分がちゃんとここにこうしていることを、改めて刻み込むような作業だったと思います。そしてその中を塗り込んでいく。これも無意識の内に、自分の内面を再構築するような、一種の「癒し」の作業となったのではないでしょうか。
京都の小さな画廊でその展示を見たのですが、これは素晴らしいと思いました。まず、絵が上手でも下手でも、輪郭がちゃんと書けます。デッサン力が問われない。これはいいですね。私なんか、助かります。そして、ほぼ等身大ですから、大きな動きが出来ます。寒さやさびしさや不安で縮こまっていた子供たちに、大きな腕の動き、目の動きを与えることが出来たはずです。そして、おそらくは無意識の内にでしょうが、自分を見つめることができていたでしょう。自分の輪郭をはっきりと描く。そのことで、自分がここにいること(I'm Hereですね)、この厳しい日々の中で、自分がちゃんとここにこうしていることを、改めて刻み込むような作業だったと思います。そしてその中を塗り込んでいく。これも無意識の内に、自分の内面を再構築するような、一種の「癒し」の作業となったのではないでしょうか。
美術家にとって必要なのは、このような集団による作業を、どのようにして個人の内面に定着していくかということだったと思います。その達成を、ちょうどその人がということではないにせよ、今芦屋市立美術博物館や兵庫県立近代美術館で見ることが出来ます。
■ 震災直後の演劇―「VOICE」
一方、演劇という作業は、どこまでも集団による、生ま身の時間芸術です。ライブという言葉がありますが、まさに目の前でスタッフも出演者も観客も同じ時間と空間を共有する芸術です。それだけに、演劇は観客に大変な苦痛を強いてしまうこともあります。映画以上に、途中で退席しにくいものですし、生々しい。震災の翌年の成人式で、なまなましい演劇をやって、途中で退席者が相次いだりしたという新聞記事を見たことがあります。リアルなのはいいのですが、リアルに不愉快というのは相当いやなものです。率直にいって、私もいくつかの、途中で退席しようかと思った「震災劇」を見たことがあります。
ここで、いくつか、震災を扱った演劇の中で、私がかなりレベルが高いと思った作品を紹介しましょう。まずは、震災からわずか三ヶ月半ほど、五月初旬のゴールデンウィーク、といっても当時のぼくたちに「ゴールデンウィーク」などという意識はなかったと思いますが、神戸の北野のシアターポシェットという小さな劇場で上演された「VOICE」という作品をご紹介しましょう。メンバーは当時高校生。神戸市のいくつかの高校で毎年行っている合同公演が震災で中止になったことから、なんとか自分たちの力ででもできないか、ということで企画された公演でした。作・演出は当時舞子高校の三年生だった中井由梨子。仲間のひとりの体験を核としたものだったそうです。家が全壊した家族の日々を、ある意味ではそのまま描いたような劇です。息子の進学問題について、県立高校を落ちたら私立に行かせてほしいという息子を軽くいなして「働きよ」と言うのさえも、何だか暖かいユーモアに包んでいます。いよいよ家が解体撤去されるという直前、おばあちゃんそのに促されて崩れかけた瓦礫の中、アルバムを探しに行くのが一つのクライマックスです。そして、ラストの少女の長い独白。自分が経験したこの事実を、歴史という長い時間の軸から見よう、そしてその歴史を作っていくのは、他ならぬ自分たちだという、前向きな決意で締めくくられます。
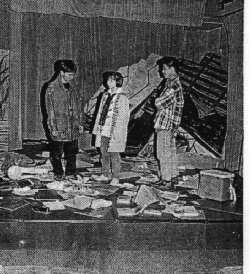 この劇を、私はたまたま新聞で知って見に行きました。スシ詰めの小さな劇場の、舞台のセットに組まれた壊れかけの家は、まだそこここに残っていたものでしたし、観客のほとんどは出演者の関係者、ということはこの地で何らかの形で震災を体験した人たちだったはずです。この公演を見終えて、たった三ヶ月半で、この高校生たちがこんなにも自分たちの置かれた場所や状況を的確に、淡々と、いくぶんかはユーモラスに描きえたことに、本当に驚いたのでした。
この劇を、私はたまたま新聞で知って見に行きました。スシ詰めの小さな劇場の、舞台のセットに組まれた壊れかけの家は、まだそこここに残っていたものでしたし、観客のほとんどは出演者の関係者、ということはこの地で何らかの形で震災を体験した人たちだったはずです。この公演を見終えて、たった三ヶ月半で、この高校生たちがこんなにも自分たちの置かれた場所や状況を的確に、淡々と、いくぶんかはユーモラスに描きえたことに、本当に驚いたのでした。
作者の中井由梨子や一部の出演者が、現在「TAKE IT EASY!」という劇団を結成し、意欲的な公演を続けています。ぼくが彼女たちを応援できるのは、いつもぼくたちにとって重要な大問題に、臆することなく正面から向き合い、格闘しているところです。震災体験を核としたこのような劇を作ることができたことで、いわばやむを得ずでしょうか、大きなテーマを抱え込んでしまったことが、今もなお彼女たちの芝居づくりに大きな手ごたえ感を残しているのではないかと思います。前回公演は、「核」という作品だったのですが、宗教と臓器移植の問題を正面から捉え、しかもおしゃれな作品になっていたのには感心させられました。
■ 遠さと静かさ-場面を禁欲する 桃園会①
続いてご紹介したいのは、「VOICE」とは対照的な世界です。桃園会(とうえんかい)という劇団のもので、作・演出の深津篤史は昨年「岸田國士戯曲賞」という、演劇界では非常に権威のある賞を取りました。「カラカラ」というタイトル。やはり震災から数ヵ月、京都で上演された短い作品を、伊丹のアイホールで「改訂版」の形で上演したもの。ぼくは伊丹で見ました。設定はややわかりづらいですが、避難所となった体育館で少女が勉強している。この人は江口恵美というチャーミングな女優なのですが、少年のようにも見える。もう一人の登場人物は、車椅子に乗っています。はしぐちしんという、現実に学生時代に事故で車椅子生活を余儀なくされている役者です。以前、時空劇場という、今は解散してしまいましたが、やはり素晴らしい劇団にいて、今は清流劇場という劇団に所属している人です。家庭教師にも見えますが、ボランティアのお兄さんでしょうか、彼と少女との会話の端々には、大きな出来事を経てしまった後という共通体験に基づく、微妙で危ういバランスが感じられます。
カラカラというのは、何かが揺れる音、それもおそらくは、あの大きな揺れではなく余震によって、たとえば避難所の洗面所のプラスチックのコップに挿した歯ブラシが立てる音や、外の建物の 何かが外れかけているような音を想像してみてください。
何かが外れかけているような音を想像してみてください。
男、鞄か何かから赤いゴムまりを取り出し、
男 ごほうび。うん。
と、少女に手渡す。
男 ちょっと子供っぽすぎましたか。
少女 …ううん。
少女、それを手に取り、落とす。
少女 ドカーン。
まりはころころと少し転がる。少女、少し男の方を見て、また落とす。
少女 ドカーン。
 まりは学生の方へ転がってゆく。少女は、またそれを手に取り、
まりは学生の方へ転がってゆく。少女は、またそれを手に取り、
少女 ドカーン。
女 お姉ちゃん、相手したげよっか。こう見えても昔、お姉ちゃんバスケット選手。ね。
少女はまりを握って首を振る。
女 一人でやっててもつまんないでしょ。ほら、ね。
女、バスケのまねをする。と、耳からイヤホンがはずれる。
少女 何聞いてるの。
女 え……。
やや間。少女はまりを落とす。
女を相手にせず、転がっているまりをチラと見て、
少女 Jリーグ!
と言って蹴る。まりはソデに転がっていく。
女はイヤホンを再び耳に入れる。
まりの転がっていった先に、先程の兄。反対ソデには友人。二人は先刻と変わらないが、手に軍手をはめている。
兄が転がったまりを拾う。
女 また、増えてる。
兄 パス。
と、男に向かってまりを放る。しかし、彼の手に届く範囲ではない。友人がそれをキャッチ。少しドリブルして、学生の頭越しに、
友人 パス。
兄がそれをキャッチ。
女 ……読み方間違えてる。あの子はそんな名前じゃない。
兄と友人は口にマスクをする。そして無言でパスを繰り返す。二人はだんだんと生き生きしてくる。
カラカラと何かが風に鳴る音。
少女は立ち尽くし、学生は布団にぺたりと座り込んで呆然としている。
こうして一部分をご紹介しても、何がなんだかかよくわからなかったかもしれませんね。でも、安心してください、全部見てもよくわかりません。ただ、少女が、ボールをついて「ドカーン」というということの意味。これは震災の揺れを少女なりに再現または追体験している、一種の模倣の遊びによる代償行為でしょう。そして、ラジオのイヤホンを耳に挿している女(藤野節子という実に魅力的な女優です)が「あの子はそんな名前じゃない」という、つまり彼女はラジオで好きなポップスとかを聞いていたのではなく、犠牲者の氏名を読み上げるあの放送を聞いていたのだということ。そんなことが折重なってイメージが作られているのだと、ここだけご覧いただいて言えることは、私としてもその程度なことです。しかし、イメージとしては、水晶のように清冽で強烈です。
■ 向こう側からの訪れ-再会によって浮き上がる遠さ 桃園会②
 この劇には、そして深津の劇はいつもそうなのですが、ちょっと難解で緊密な散文詩のような味わいがありました。深津は、この「カラカラ」という音や、ボールをつく音などを重要なモチーフとし、学校の体育館という場所をずいぶん膨らませて、連続的に面白い試みをしました。それが「カラカラ-トートの書#桜の園 遠山の場合」「カラカラ-トートの書#桜の園 吉永の場合」等に続いていく連作です。この二つの作品は、同じ時間、同じ設定で、一方は体育館の屋根裏の中、一方はその外を舞台にして、出たり入ったりする人物が全く裏表になっているように拵えられています。だから、一つの芝居だけ見ると、袖にはけてしまった役者が、もう一つの芝居では同じ時に舞台に現れる、そういった構造になっているわけです。
この劇には、そして深津の劇はいつもそうなのですが、ちょっと難解で緊密な散文詩のような味わいがありました。深津は、この「カラカラ」という音や、ボールをつく音などを重要なモチーフとし、学校の体育館という場所をずいぶん膨らませて、連続的に面白い試みをしました。それが「カラカラ-トートの書#桜の園 遠山の場合」「カラカラ-トートの書#桜の園 吉永の場合」等に続いていく連作です。この二つの作品は、同じ時間、同じ設定で、一方は体育館の屋根裏の中、一方はその外を舞台にして、出たり入ったりする人物が全く裏表になっているように拵えられています。だから、一つの芝居だけ見ると、袖にはけてしまった役者が、もう一つの芝居では同じ時に舞台に現れる、そういった構造になっているわけです。
この設定そのものが、深津の芝居の作り方の本質に根差していると思います。それは、手短かに言うと、ここではない場面については触れないということではないでしょうか。小説でも演劇でも、作者が全知の神の視点に立って、「実はここに立っている男は、三日前までは○○だったんだ」などと解説することがありますが、深津の劇でそのようなことはありません。結果的に非常にわかりにくい劇になってしまうわけですが、ぼくはこの深津のわかりにくさをとても気に入っています。震災のような、様々に、週刊誌的な興味も含めて、現象の向こう側まで言及したくなりがちな大きな悲惨な事実に対してでも、厳しく禁欲的な表現は変わりません。けっして神秘化しているわけではなく、現実というものに対する、非常に誠実なあり方だと思っています。
次に見ていただくのは、「吉永の場合」のほうです。この劇で大きな特徴の一つに、場面設定を震災から二年後に開かれた小学校の同窓会としたことが挙げられます。かつて同じ時間を共有した彼らも、今は社会人だったり結婚して家庭に入ったりしています。同じ中学、高校へ進んだ者もいれば、よそへ出て行って本当に久しぶりの再会の者もいます。小学校を出て十数年、震災の体験も共有していません。ですから、吉永の母親が震災で亡くなったことだって、知らない友達がいるし、新聞のあの「犠牲者一覧」で知った友達がいる。知らない友だちが「ああ、そうだ。吉永さんとこも大変だったんでしょ。家族の人とか、元気?」と、何の悪意もなく尋ねる、それが実に残酷なドラマになるわけです。よくある、しかし見事な設定です。
木元 私、あの時毎日新聞読んだよ。
吉永 うん。
木元 何故だと思う?
吉永 何故って、やっぱり心配だから?
木元 吉永さんは、いい人だね。
吉永 どういうこと?
木元 ごめん。ケンカ売ってるつもりないんだ。
吉永 うん。
木元 毎日、私、
吉永 私もラジオで聞いたよ。
木元 え。
吉永 一晩中やってんのよ。誰かのラジオ。みんな黙って聞いてる。二時間くらい繰り返し、繰り返し。
木元 うん。
吉永 吉永って呼ばれて、ああ、そうかって思った。
吉永は、「カラカラ改訂版」の少女と同じ江口恵美で、これは無関係だと思われますが、木元は改訂版でラジオを聞いていた藤野節子です。こうして、ラジオを聞く(新聞を読む、テレビを見る……)という行為の意味が、確認されるわけです。吉永は、もちろん自分の家族(母)が亡くなったことを知っているわけですが、ラジオや新聞を通じて、初めて「そうか」と思う。おそらく、母を失ったことが、外部のマスメディアという媒体を介することによって、初めて客観的な事実という形で現実のものとして突きつけられたということだったのだと思います。
続いて、この作品のラストの部分もご紹介しましょう。吉野という女性がチェーホフの「桜の園」を朗唱しているところに吉永がかぶさるところから、劇のラスト、徐々に照明が暗くなる、いわゆる溶暗までです。
吉永 一生が過ぎてしまった。まるで生きたおぼえがないくらいだ。どれ、ひとつ横になるか。ええ、なんてざまだ。精も根もありゃしねぇ。もぬけのからだ。
吉永、振り返る。
吉永 吉野さん?
吉野 うん。
吉永 ラジオで聞いたよ。
吉野 吉永、記憶力いい。
吉永 うん。
遠くでサイレンの音。
吉野 火事だよ。
吉永 うん。
吉野 見える?
吉永 うん。見える。
サイレンの音、複数に。
吉永 火事だ。
サイレンの音、とだえる。
吉野 吉永さん。
吉永 何?
吉野 (ボールをつく)どーん。これは?
吉永 うん。
吉野 どーん。これはあの時聞いた音。
吉永 うん。(本を開く)
吉野 どーん、どーん、どーん………
吉永 はるか遠くでまるで天から響いたような音がする。それはツルのきれた音で、しだい悲しげに消えていく。そして…そして遠く庭のほうで、木に斧を打ち込む音だけが聞こえる。聞こえる。
赤い砂がサラサラとこぼれ落ちてゆく。
途絶えた。
溶暗。静かに音楽。
お気づきのように、ボールをついて「ドーン」と言うのは、改訂版から引き継がれたモチーフです。そしてここでそのボールをついていた女、吉野は、一人だけなんだか少し若い格好をしていました。実は、ウイングフィールドという心斎橋にある小さな素敵な劇場で観ていたのですが、吉永が「吉野さん?」と呼びかけるなりハッとした瞬間に、劇場にいた私たちにはわかったのです、吉野というのは、実はもう震災で死んでいた者だったということを。このような、文字だけではなかなか伝わりにくい微妙な空気を絶妙に描き得たということ、これは演劇というものの栄光だと思います。
■ 再会によって浮き上がる残酷さ 芝居屋坂道ストア
このように、震災を同窓会の視点から描いて成功した作品は、他にもあります。芝居屋坂道ストアという、宝塚北高校の演劇科OGを中心とした劇団。実は、旗上げ公演が震災の前日と前々日の連休、自分たちの成人式と翌日だったそうですが、彼女たちの第七回公演「あくびと風の威力」もそうです。これは不思議な時間の流れです。現在を、あたかも過去であるかのように振り返る。そのことによって、現在も、過去もみごとに客観視され、淡々と、そして語弊を恐れずにいえば、美しく描かれたのだと思います。
 時は西暦二〇〇五年、震災から十年後、小学校六年生の同窓会の前夜、一人の女・なお(岡知美)の部屋にたくさんの同窓生が集まってきます。ところが実はその中の一人・涼ちゃん(大木なつ美。実は震災の直前に転校してきた生徒だったんですが)を除いて、震災で命を落とした者たちなのです。
時は西暦二〇〇五年、震災から十年後、小学校六年生の同窓会の前夜、一人の女・なお(岡知美)の部屋にたくさんの同窓生が集まってきます。ところが実はその中の一人・涼ちゃん(大木なつ美。実は震災の直前に転校してきた生徒だったんですが)を除いて、震災で命を落とした者たちなのです。
歳月の経過によって、震災という大きな災厄に対する冷静な視点を持たせた一方、それだけの歳月を経てもなお冷静になれないことがあるということを痛切に表現しえています。この同窓会が二〇〇五年、震災が一九九五年、この劇の初演が一九九八年です。つまり、ここでぼくたちは、いったん未来に行き、震災という十年前の過去の出来事を振り返ります。
この劇の中では、死者たちが生者を非難します。ピアニストになるって言ってたのに、と。死者たちは当時のままです。口々に「○○したかった」と列挙します。それに対して生者は「実際にやってみると、たいしたことないねんで」と慰めますが、「それはやってみたから言えることだ」と反論されます。
亜矢さん なおは当たりくじやったな。
なお 当たりかなぁ。
時津 はーずれー。
亜矢さん おっかしいな。
なお ほんまにくじ運みたいなもんやなぁ。
亜矢さん そやな。でも運が悪かったじゃ片付かんねんやん。
なお わかってる。
亜矢さん わかってるけどわかってない。
時津 わかるはずがない。
なお うん。
亜矢さん 亜矢な、制服着てみたいねん、帰り道に喫茶店とかハーゲンダッツとか寄って、ポプラ並木を自転車で走り抜けるねん。
カワベ 亜矢さんらしいな。
時津 ドラマやな。
なお うん、私も思ってた。でも実際はそんなええもんちゃうで。
亜矢さん ええの!
なお 無いねんってなかなか。並木道もハーゲンも。
カ・亜・時 ハーゲン? ハーゲンやって。ハーゲンダッツのこと? 知らんかったー。
亜矢さん あ、それから、パンストもはいてみたい、ハイヒールはいて階段上りたい、徹夜したい、飛行機乗りたい、
カワベ 居酒屋でワリカンしたい、
時津 電報打ちたい、
亜矢さん タバコ「フー」ってふかしたい、レースのブラジャーしたい、大人料金で地下鉄乗りたい、アルバイトしたい、ぶ厚―い手帳持って予定いっぱい書き込むねん。
時津 ないくせに。
亜矢さん バーに行って
カワベ 「あちらの方から」
亜矢さん って言われたい、お見合いで
時津 「あとは若い人同士で」
亜矢さん も言われたい。
なお 最後2つは難しいけど、他はやってみると何でもないで。
亜矢さん いや、そんなはずはない。亜矢できること全部したいねん、結婚もしたい、子供産んで、おばちゃんになって、ばーちゃんにもなりたい。しょーもないことでもいいから
カ・亜・時 何でもし尽くすねん。
亜矢さん だってなぁ、こんなおもろいことあったんか、しまったー、知らんかったーって思うのいややもん。……
やろ。
なお うん。
亜矢さん うん……か。せっかくやのにな、なお。しまったな
ぁー、亜矢、ほんま。
震災というものの本質の一つ、つまり「突然の断絶」ということの残酷さを、女の子の十年間にはどんなことがありえたのかという現実、そして断絶させられてしまった者からすれば夢想ですね、としてひじょうに具体的に言い当てているのではないでしょうか。震災がなければ、特別だったり大切だったりするとは思わずに過ごしてしまう当たり前の日常を、この劇はそれを体験することができなかった少女たちという視点で、痛切に叫んでいるわけです。でも死者たちはやさしくって、あとで「ちょっとゆうてみたかっただけやねん」と、はにかんで見せます。普段はやさしい少女たちでも、何かのきっかけで激しい思いを噴出させてしまう、そういう瞬間を描き出すのも、演劇の劇的ということの意味だと、おわかりいただけるのではないでしょうか。実際、この芝居屋坂道ストアという劇団は、いつもそういう厳しい瞬間をキリキリと描くように思います。関係とか人となりとか、様々なものがその一点に収斂する、そんな瞬間をみごとに見せてくれる劇団だと思います。
■ 宮沢賢治との共振―死者との本当の別れ
 このような、死者が立ち現れることによって多くのものが見えてくるという劇、まさに劇的ということで劇なのですが、は、他にもあります。たとえば、神戸高校演劇部が上演した作品、水野陽子作「破稿(やぶれこう)・銀河鉄道の夜」は、震災後ちょっとやる気をなくしてしまっている演劇部の女子高生を中心に、前向きに(あるいは当たり前に)進もうとしている友だち・サキ(宇仁菅綾)と、震災で亡くなってしまった友だち、正確に言えばその幽霊とで成り立っている劇です。この劇は、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を下敷きにした、井上ひさしの「イーハトーボの劇列車」という戯曲を主人公が朗読するシーンから始まり、北村想という劇作家の「想稿・銀河鉄道の夜」という戯曲を演劇部で上演した思い出を交えています。いわばこの三つのテキストを下敷きにしているということで、劇の言葉が豊かな支え、重層性をもっています。
このような、死者が立ち現れることによって多くのものが見えてくるという劇、まさに劇的ということで劇なのですが、は、他にもあります。たとえば、神戸高校演劇部が上演した作品、水野陽子作「破稿(やぶれこう)・銀河鉄道の夜」は、震災後ちょっとやる気をなくしてしまっている演劇部の女子高生を中心に、前向きに(あるいは当たり前に)進もうとしている友だち・サキ(宇仁菅綾)と、震災で亡くなってしまった友だち、正確に言えばその幽霊とで成り立っている劇です。この劇は、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を下敷きにした、井上ひさしの「イーハトーボの劇列車」という戯曲を主人公が朗読するシーンから始まり、北村想という劇作家の「想稿・銀河鉄道の夜」という戯曲を演劇部で上演した思い出を交えています。いわばこの三つのテキストを下敷きにしているということで、劇の言葉が豊かな支え、重層性をもっています。
それと同時に、私は自分自身の実感としてもあるのですが、というのは、私の「風景が壊れている…」でも、一ヶ所だけ非常にわかりづらい形で、フッサールの現象論を解説したある思想家の文章を引用しているところがあるのですが、震災のようなとんでもなく大きな体験に基づいて何か表現しようとすると、自分ひとりの言葉ではとても頼りなく思えてしまうのですね。否定的に言うと権威に頼るというような感じに取られるかもしれませんが、そうではなくて、何かしら他者の声が必要なのです。他者の声を呼び込んで一緒になって声を出してもらおう、そういう切実さがよんどころなく出てきたのではないかと思います。
主人公のカナエ(三谷恭子)は震災で演劇部の仲間で親友のトウコ(松本知佐)を亡くしました。数ヵ月たって高三になった彼女は、でも受験勉強に身が入らず、時間があるともう引退したはずの演劇部の部室に来ては基礎練習や本読みを一人で繰り返しています。彼女には死んだはずのトウコの姿が見えています。というより、いつも側にトウコがいて、絶えず話しをしています。一言で大雑把にいってしまえば、カナエは現実を逃避しているように見えますが、つまりはトウコがいた頃、あの日より前の時間にいるような状態を作り出すことで、なんとか自分を支えている。でも、ついにトウコからもそろそろじゃないかと切り出されます。それに対してカナエがこらえていた思いを一気に吐き出す、激しい場面から始まるシーンです。
トウコ カナエ、好きな芝居のせいにしたらあかんやん。
カナエ ……あの日から……。
トウコ ……。
カナエ ……トウコがおらんようになった日、私には……なんかが……なんかが足らへんねん。……だってそうやん! 小学校からずっと一緒やったやん。嬉しいことでも悲しいことでも、なんでも一緒やったやん。ねぇ覚えてる? 内緒で飼っとったミケがおらんようになった時、夜中まで探しまわったやん。夏休みの宿題、毎年三十一日は二人で徹夜しとったし。学校さぼって、ぴあに何時間も何時間も電話したけど結局チケットとれんくてさあ……。私あれから寄り道もしてへんねんよ。ソニプラにも、ボディーショップにも、ミスドにもマクドにも甲南書房にも……。一人でなんかよう行かん。……トウコがおらんと私……あかんねん……。
トウコ ……なあ、サキの少女の台詞覚えてる?
カナエ え?
トウコ 「むかしパルドラの野原に一匹の蠍がいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたの。するとある日その蠍の何百倍も大きいイタチが現れて、それで蠍はそのイタチに見つかって食べられそうになったの。蠍は一生懸命にげてにげたけど、とうとうイタチに押さえられそうになったの。そのとき、いきなり前に井戸があって、蠍その中に落ちてしまったの。それで、もうどうしてもあがれないで、蠍はおぼれはじめたの。そのとき、蠍はこういってお祈りをしたのよ。――ああ、わたしはいままで、いくつもの命をとったかわからない。そして、その私がこんどイタチにとられようとしたときはあんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、なんにもあてにはならない。どうして私は、私のからだを、だまってイタチにくれてやらなかったろう。そしたら、イタチも一日生きのびたろうに。どうか神さま。私の心をごらんください。こんなにむなしく命をすてず、どうかこの次には、まことのみんなの幸せのために私のからだをおつかいください――そしたら、いつか蠍はじぶんのからだが、真っ赤な美しい火になって燃えて、よるのやみをてらしているのを見たって。あの火、そうだわ。」……何回も聞いたから覚えとうやんね。
カナエ ……。
トウコ ……私、死んだ時な、「なんでなん?」って思ってん。私は他の人よりも悪いことをしたんやろかって思って、悔しかった。……私、絵本が描きたかってん。でも何も残さへんうちにこうなった。井戸に落ちた蠍の気持ちがようわかってん。でも、蠍は夜の闇を照らす火になれたけど、私には何もない。私は絵の一枚も、文の一行も残せへんかった。
カナエ ……。
トウコ カムパネルラとジョバンニの別れのシーンの台詞覚えとう? 車掌役の佐竹君が「ああ、この切符は違います。これは三次空間のものです。」ジョバンニが
「え? どういうこと?」
「この切符はまだなのです。」
「まだって、さっき、どこまでもいけるっていったじゃないか。」
「はい。しかし、それはまだなのです。」
「カムパネルラ……」
「この人はあなたのお友達ですね。この人は今夜遠いところに行くのです。」
「僕も一緒に行くんです。」
「それはできません。」
「そんな。カムパネルラ、僕、君といっしょにまっすぐ行くんだよねえ。」
……このあとは?
カナエ 「ジョバンニ。いっしょに行けない。でも、みんながカムパネルラだ。君の出会うすべてのひとがカムパネルラだ。」
トウコ この時、これがどういう意味かって話し合ったよね。カムパネルラは死んでしまったから、ジョバンニと一緒には生きていけないけど、ジョバンニがこれから生きている人たちとこの世界をよりよくしていって欲しいっていう賢治の願いなんちゃうかなってことになったよねえ。覚えてる?
カナエ ……うん。……覚えてる。
トウコ 私も、もうカナエとは一緒におられへん。でも、カナエが頑張っとったら、何やってもええねん。それで何かが残せたって事かなって、そう思えるんよ。
カナエ ……。
トウコ 生きとうってそれだけですごいことやんか。雨に濡れて歩いたり、髪が風に揺れたり、走って汗かいたりすることがどんなにいいか。私のことは忘れて欲しくない。でも、そんなふうに引きずられるのは迷惑や。カナエは生きてんねんで!
カナエ ……そうやねんね。……トウコ……。
トウコ 頑張ってくれる?
カナエ ……頑張ってみるわ。
美しい、素晴らしいシーンでしょう。宮沢賢治のジョバンニやカンパネルラがこんなにも哀しくリアルに立ち現れたことがあったでしょうか。そして、いわゆる神戸弁の「……しとう」「覚えとう」などという言葉の音が美しく響いたのも、印象的な公演でした。生きてここに在ることの素晴らしさを、芝居屋坂道ストアが個々に具体的に列挙したのに対して、ここでは「雨に濡れて歩いたり、髪が風に揺れたり、走って汗かいたり」と抒情的に描く一方、一緒に演劇を作り上げようとした日々を具体的に生き生きと回想して、痛切です。
ここで私が強調したいのは、ソニープラザがどうとか「ぴあ」がどうという、非常に具体的な固有名詞の連続と、宮沢賢治の一節が、ほとんど等価に美しく響いていることです。ソニープラザといえば、神戸の人ならさんちかの、Seidenの地下のあそこだな、と思います。銀座にも四条河原町にもソニープラザはあるし、全国各地にマクドナルド(関西ではマクドと略すわけで)はあるでしょう。そんな日常的な風景が、このように昇華されたことに、ちょっと言いようがないほど感動したのでした。
■ 遠望する地名、あふれる思い PM/飛ぶ教室
ちょっと先を急いで、次にご紹介するのは、同窓会ではありませんが、やはり久々の再会です。これは非常にリアルな部分のある、事実に基づいて取材され構成された作品です。タイトルも「滝の茶屋のおじちゃん」。そうです、山陽電鉄の、あの滝の茶屋です。PM/飛ぶ教室という劇団を主催する蟷螂襲という人の作品で、昨年のOMS戯曲賞(扇町ミュージアムスクエア主催)を受賞しました。前半は、ノブという男の父親の話。山陽電車の運転士で、震災のちょうどその時「神戸高速走ってて、大開の駅過ぎてすぐ」のところで揺れて脱線したという、ものすごい経験をしたという話を、当の父親からじゃなくて、父親の葬儀のときにその上司から聞いたという話などが、蟷螂の劇特有のすごい長台詞で展開されます。
次に引用するのは、劇の後半、震災前から行方をくらましていたノブの話です。台本では、一見会話が成立しているように見えますが、ほとんど相方は「……」と沈黙ですので、ノブの長台詞です。
ノブ 話、戻そかあ。
慎二 ………。
ノブ なあ、慎二。
慎二 ………。
ノブ おまえの知らんかった、オレの塩屋暮らしの話や。
慎二 ………。
ノブ テレビのニュースで見た。山電の塩屋の駅が全壊してた。電車はおろか、ひとっこひとりいてへん、壊れてしもた駅の絵ぇやった。時間止まるいうのは、たとえばこんな絵のことなんやと思た。
慎二 ………。
ノブ 地震のことは、そら知ってた。帰ろと思わへんかったわけやない。けど、足がすくむ感じになった。その頃のオレには、神戸はものすごう遠い町になってた。捨ててきたつもりやなかったのに、二度と帰ることのない場所やと思てたわけでもないのに、壊れた神戸は、どっかよその国の遠い町に思えてしょうがなかった。
慎二 ………。
ノブ けど、塩屋の駅のことテレビで見た時、久しぶりにオレのなかで、ピンッと糸が張れたんや。広島の解体現場で燃やされる市電見てたおかげやったんかもしれん。それまで意識したことなかったけど、じいちゃんにもろてるはずの血ィやったんかなあ。それが、騒いだ。
慎二 ………。
ノブ オレがいてた解体屋の親方に、神戸へ行かしてほしい言うた。できたら、山電の塩屋の現場へ行かせてくれ言うてたのんだ。親方、神戸の組合へ話つないでくれた。知り合いの産廃のダンプに便乗さしてもろて、塩屋へ入った。二月やった。
珠子 ………。
ノブ 笑てしまうぐらい、おまえとこの酒屋、至近距離にあったでェ。
慎二 ………。
ノブ 駅舎の解体が始まった。傷んでもない線路も撤去することになった。なんせすぐ海側JRが通ってる。山側は幅の狭い道路やろ? 駅つぶして線路どけてしまわんと工事車両が入る場所もなかったんや。なにもない更地にせんことには、新しい駅の工事にはかかれんかった。あの二月、JRはもう新快速走らしとった。あの電車、東へはどこまで走れとんのかなあて、みなで言うてた。
慎二 ………。
ノブ ヘヘ……。
慎二 ………。
ノブ 雪がきつかった日ィあったん覚えてるか、慎二。
慎二 ………。
ノブ あったんや、そんな日ィが。……二月やったか、もう三月にはいってたんか。
慎二 ………。
ノブ 見かけたん、おまえとこの店の軽四。おまえが運転してて、助手席には珠子がおった。
慎二+珠子 ………。
ノブ チラッと一瞬見ただけやったけどうれしかったあ。
慎二+珠子 ………。
ノブ いや、ほんまや。ヘヘ………。
慎二+珠子 ………。
ノブ 生きた心地した。オレら生きとんや思た。塩屋へ来たかいあったァ思た。
慎二 ………。
親から、家から離れて遠く広島の地で震災を迎えたノブの、震災への屈折した複雑な関わり方をみごとに表わした部分です。
私はこの作品が上演されるのを知っていて、実は見に行くことができなかったんです。まだ幼稚園の頃だったか、母に連れられて、滝の茶屋の駅で降りて、おそらくは母が内職で作っていた手芸品か何かを持って坂道を登って行ったことがあったのを、なぜだか鮮明に覚えているんですね。震災についての記録でも記憶でも、何でもそうでしょうが、地名というものには特に、どこかで否応なくそのような個人的な記憶に直結してしまう。一時期、「神戸」という地名を聞くだけで、涙が出そうになったことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、幼い頃に滝の茶屋のその家の帰り道、坂道から見えた海がきらきらと光っていたのを、鮮明に覚えているように思っているんです。それから後の私たち一家には、どういえばいいんでしょうか、いくつもの別れやら喪失やらがあったんですが、そういうことを思うと、ちょっとよう見に行かんかった、わけです。
で、この作品が戯曲賞を取って台本が出版され、それを通勤の神戸電鉄の中で読んでいて、もう泣きそうになってしょうがなかったんですね。見ればよかったという思いと、見ずにすませたいというのと、両方まだ持っています。三月に演出と役者を変えて再演されますが、どうしようか、まだ迷っています(結局、観に行きました)。
■ 新たな視点の獲得-演劇でこそ描ける世界
さて、思い切って、整理していきたいと思います。震災をテーマにした演劇で失敗した、と私に思えたものは、概してなまなまし過ぎたり、必要以上に声高だったりしたものだったように思います。いくつかの作品では、光や音まで使って被害の大きさを生まに観客に突きつけたり、当時の混乱をデフォルメまでして再現してみたり、社会的矛盾に対する一方的な怒りをぶちまけたりと、非常に過剰な表現が多く見られました。自分を「被害者」という立場に一面的に置いたものがあったことも指摘しておいたほうがいいでしょう。私自身の個人的な好悪もありますが、概してそれらは、世界や状況を客観的に見ることに成功していなかったのだと思います。
私は、文学、そして芸術の意義というものは、正しい答えが複数あるというところにあると思います。ですから、一つの真実だけを探り出して提示するのでは、ダメなのだと思います。何人かいれば、それぞれに真実があって、それが三すくみ、四すくみになってどうにも身動きできないような状態、それを描くのが文学や芸術、特に演劇ではそのような現場をリアルに描きやすいのではないかと、思っています。
ここまで私がご紹介したようないくつかの作品は、震災を静かに語っているように思えました。直後に上演された「VOICE」は、高校生たちによる、自分たちの時間を失いたくないという思いのこもった、奇跡のように率直で純粋な作品でした。
しばらくして、深津の「カラカラ」の初演及び改訂版という、これは半ば普通の演劇であることを放棄し、避難所の風景の一コマを切り取った、スナップショットのような作品が生まれます。深津自身そのモチーフを慎重に暖め、「吉永の場合」「遠山の場合」をはじめとした実験を行います。芝居屋坂道ストアの「あくびと風の威力」でもそうですが、震災から数年たって、同窓会という設定で、当時の仲間、同じ学校だった者が集まる、既に死んだ者も含めて。
死者との、共時性とでも呼んでおきましょうか、それは「破稿・銀河鉄道の夜」でも哀切きわまる形で現れます。女の子の人生が突然切断されることの悲しみについても同様です。「あくび……」の死者たちの叫びが残酷に聞こえたのは、死者たち自身の突然の切断への戸惑いや怒りがストレートに出たわけですし、「破稿……」の死者が優しいのは、親友の人生が突然切断されたことで自分を失いかけている女の子への励ましの眼ざしがあるからでしょう。
PM/飛ぶ教室の「滝の茶屋のおじちゃん」は生きている者だけが集まっているのですが、そこで語られているのは、かなり生々しく震災の当事者であった父親のエピソードや人柄であり、後半で語るのは震災のとき神戸にいなかった息子です。この息子の震災への関わり方が、微妙かつ奇妙に父親の関わり方とシンクロしているのが、ひじょうに興味深く思えます。
ある一つの大きな災厄と、どのように向き合っていくかという時に、現在という時間の距離ではちょっと足りない、と思いきって未来へ飛んでいくこと、これは実に絶妙な視点の獲得だったと思います。また、死者をよみがえらせようという祈りのような切実な思い、それをみごとに自然に舞台の上に現しえたことについては、改めてコメントのしようもありません。震災という一つの災厄の後に、京阪神の若い演劇人、中には当時高校生だった者も多かったのですが、彼らがこのようにすぐれた表現を獲得したことを、ひじょうにうれしくありがたく、頼もしく思ったのでした。
■ 被害を受けなかった者の言葉
さて、冒頭にも述べましたように、私は、家族や親戚・知人に死者もなく、家もつぶれず、職場もつぶれず、いわゆる被害がありませんでした。神戸の東端、魚崎という被災地の真っ只中にいながら、おそらくそれは希有なことだったと思います。被害がなかった、ということがどういうことだったか。それに真っ向から言及したお芝居もありました。やはり神戸高校演劇部の「青い街」(作=前田真奈美)という劇です。主人公は、被災地の避難所となった体育館でボランティア活動をしていますが、ちょっと最近疲れ気味。自分なんかがボランティアをやっていていいのだろうかと疑問に思っています。ご覧いただくのは、神戸アートビレッジセンターでの再演のもようですが、三面舞台で向こうを向いて喋っている部分もあり一部聞き取りにくいですが、ご容赦ください。福井というおばあちゃんが「遊気舎」という劇団の魔瑠、ボランティアの高校生のナオコが初演からずっとこの役を演じている河部文です。
 ナオコ …そのことなんですけど…、うちボランティアやめるかもしれないんです。
ナオコ …そのことなんですけど…、うちボランティアやめるかもしれないんです。
福井 え?
ナオコ いや、まだ決めたわけじゃないんですけど。
福井 どうしたん急に?
ナオコ もうすぐ高三やから、進路のこと考えなあかんし、将来のこととか、受験勉強もせなあかんし。
福井 受験も大切やもんね。
ナオコ そうやなくて、何かちょっと休みたいなって…
福井 そうやね。ナオコちゃんずっと仕事しとったもんね。
ナオコ ていうか、なんかしんどくなっちゃったっていうか。最近どんだけやっても役に立ててへんような気がして、何のためのボランティアかわからなくなっちゃったんです。どうしたらええのかわからなくて。
福井 ナオコちゃん、手、出してごらん。
ナオコ、手を差し出す。
福井、お守りを出す。
ナオコ お守り?
福井 ナオコちゃんは考え込みすぎや。息抜きもせんと、どんな事でもずっと悩んでたらそりゃぁくたびれてしまうよ。せやからね、私は神様にお願いすることにしてるんよ。
ナオコ 神様なんておるんですか? うちは信じられへんのです。だって、そんなもんがおったら地震なんか起こらんかったやないですか。うちらの街ぐちゃぐちゃにしてたくさんの人つらい目にあわせて。死んだ人らが何したって言うんですか? 願いかなえてくれるって言うんやったら、神戸を元に戻してくださいよ!
福井 ナオコちゃん…?
ナオコ …うちは、家族も家も友達も、ほんまに何もなくさんかったんです。つらい思いしてる人がおるっていうの、わかってたつもりやたけど、どっかでうちの周りの人はちゃうっておもっとって。アサミが、友達がそんな思いしてるのなんて、全然わかれへんかった。そんなうちがいくらボランティアしたって誰も助けてあげられへん。うちには、なにもできへんねんよ。
福井 そりゃあ、ナオコちゃんのゆうとうように誰もほんとの気持ちなんかわかれへんし、大切なものを失った悲しさなんて、失わなかった人にはわからへんと思うよ。でも私はがんばってくれてるナオコちゃんらにはほんまに感謝してる。ほんまにつらいとき一番ほしいのはそばにおってくれる人なんやもん。ナオコちゃんらがおってくれたから、私は独りぼっちにならへんかった。
ナオコ 違うんです。ほんまのことゆうたらうち、死んだんが自分の家族とか友達やなくてよかったって思ってしまったんです。つぶれたんが自分の家じゃなくてよかったって思ったんです。つらい思いしてる人見るたびに自分じゃなくてよかったってどっかで思ってるような、そんなやつなんです。
福井 …私な、終戦の天皇陛下さんの放送聞いたときな、空襲で死にはったようけの人とか、「お国のために」ゆうて戦地で死んでったぎょうさんの兵隊さんらには申し訳ないけど、「ああ、これで死なずにすんだ」って思ってしもたんよ。
ナオコ ……
福井 ナオコちゃん。
福井がゆっくりナオコに近づく。
福井 私はナオコちゃんがおってくれてほんまによかったとおもっとうよ。それだけは忘れんといてな。
福井、もう一度ナオコにお守りをわたし、深々と礼をする。
福井 ごめんな、挨拶しに来ただけやのに長話してしもて。もう帰るね。山崎さんとかによろしく伝えてください。ほんまにお世話になりました。
このあと、避難所の体育館を去って長野の妹のところに身を寄せるという福井に、ナオコは精一杯深く礼をして見送ります。このシーンからだけでも、多くのことを考えさせられます。ボランティアということの本質についてとか、人は他人の悲しみを悲しむことができるかとか、多くのお年寄りが戦災と震災を重ねて受け止めようとしたこととか、神様のこととか。そういう重い問題をボランティアの高校生が短い期間に一身に引き受け、性急に結論を出そうとしているいじらしいほどの姿。それに対して福井というおばあちゃんは、長い人生の歳月の後の、自分や他者、多くのものに対するいくつもの断念を踏まえて、理屈を超えた思いを直接ナオコに手渡すことによって、ナオコの激しい自責を癒します。
実際、ここでのナオコの自責は相当激しいものです。この前の場面で、彼女は友達のアサミから、小学校から仲のよかった友達が震災で亡くなった話を初めて聞き、激しく動揺します。そのことを直接のきっかけとして、ボランティアの女の子たちの日々を描いた劇が、鋭い螺旋を描いてものごとの本質に切り込んでいきます。
ナオコの「うちは、家族も家も友達も、ほんまに何もなくさんかったんです」という一種の告白は、私自身の体験と重なっています。私自身はナオコほどストレートに表現することもできないし、途中でいわば思考停止をしてしまっているのではなかったかと振り返ってしまいます。しかし、表面上の被害を受けなかったことが、かえって痛みを伴うものでもありえたという、この被災の本質の一面を、多くの人が身に受けていたことを証左するものだと思います。
ご覧いただいたビデオは、先ほどご覧いただいた「破稿・銀河鉄道の夜」と同じく、いるかHotelというユニットが再演した公演のものです。主宰者の谷省吾は、遊気舎という劇団の俳優ですが、この二つの作品に深い愛着(というか、執念)をもって、再演を繰り返し、とうとう東京公演も果たしました。そのような形で若い高校生たちの表現が継がれ広められていくようになったことを、本当にうれしく、ありがたく思います。
■ 震災を体験するとはどのようなことか
さて、震災から一年半ほどを経て、冒頭にも述べましたように、以前から尊敬していた詩人の季村さん(今日あとから自作解説をしてくださるんで大変楽しみなんですが)に「震災にまつわる本を作るので、君も何か書かないか」と電話がかかってきて、そのコンセプトが郵送されてきて来た時、私はほとんど初めて、ナオコのように被害を受けなかったということで震災を「体験」した自分というものに正面から向き合おうと思ったのです。
震災後書き散らしたいくつかの文章に比べても、教科書に掲載されるこの「風景が壊れている、そして私も……」は、自分で言うのもおかしいですが、かなり凝った作りをしています。それは、季村さんからのアドバイスというかコンセプトに「被災地の外の人に伝えるための文体をいかに獲得するか」という、非常に回答困難なテーマがあったからです。
私の震災体験とは何か。何度も繰り返しますが、何も被害を受けなかったということです。繰り返しになりますが、自宅も職場も、家族も親戚も友人も、思いつく範囲の人も物も、すべて無事でした。もちろん、自宅の中は脱水機にかけられたみたいにグチャグチャでしたが、そんなの、この震災では被害の内に入りません。
そうして、震災のあの瞬間、一月十七日午前五時四十六分からのことを思い出そうとすると、シャットアウトとしか言いようのない、外界の出来事を拒否して自分、自分たちの殻に閉じこもって自分を守ろうという姿勢でしかなかったことに思い当たるのです。
揺れの瞬間、私は隣で寝ていた妻の上に覆い被さっています。これでずいぶん株を上げました。しばらくして明るくなって、外を妻と歩きました。後になって思うと、私は外界の状況をまったく把握できなくなっていたのです。近くの小学校の体育館の卓球台の上に、毛布にくるまれて横たわる十数人の人がいた。それを私は理解できず、他の人はみんな体育館の床の上に寒々と寝ているのに、どうしてあの人たちだけ特別なんだろうと思いました。きっとそれを口に出して、隣りの妻に聞いたんだと思います。そして妻が答えるか答えないかの瞬間、私はそれがご遺体であることに気づくのです。今から思えば、どうしてそんな当たり前のことに気付かなかったのか、不思議でしょうがない。しかも、あとで妻に聞くと、妻は妻で、その時私にそう聞かれたことを覚えていないというのです。
あるいは、自宅の四軒ほど南のお宅がペシャンコにつぶれていましたが、その屋根の上で茶髪の青年たちが「あかんわ、あかんわ」と言っている。何をしているんだろうかと、不審に思ったのです。やはり今から思えば、なぜ不審に思ったのか、自分のことながら理解できません。このことが、今日お配りした資料の一ページ目に転載させていただいた二つの新聞記事(神戸新聞、朝日新聞)の両方に引用されていることからも、いかにこれが、いわば馬鹿げた、普段なら信じられないことだったかがおわかりいただけるといっていいでしょう。
被害がなかったという外面的な引け目がありました。そしてそれ以上に、外界のことがほとんど理解できないほどに自分の殻に閉じこもって自分を防御しようとしていたという引け目あるいは自責。私の震災体験の核は、やや自虐的、露悪的に言い過ぎているかもしれませんが、そこにあるように思いました。これに、季村さんが提示して下さったテーマ「風景が壊れるということ」を絡め、風景以上に自分自身が壊れてしまったことを語ったのが、この文章です。筑摩書房の教科書編集部によると、被災地の中心にいながら、被害を受けなかったことで、かえって焦りや自責をもっている、結果的に大きな悲劇の同時代にいながら自分たちは何も出来ないというような意味で全国的な広い普遍性を持ちうるだろうと、評価されたようです。
この文章などを収めた『生者と死者のほとり~阪神大震災、記憶のための試み』は、季村さんたちのご尽力で人文書院という京都の素晴らしい出版社から出されることになり、写真も装丁も非常にレベルの高い本になりました。そのお陰だと思うのですが、筑摩書房の高校国語教科書の編集委員の目に止まり、いくつかの候補の中から、高等学校国語教科書「ちくま現代文改訂版」に収録されることになり、今年の4月から全国のいくつかの高校で採用されることになったわけです。
そのことについて、私自身、一つの特権的な高みから皆さんに何かをお話しするような気にはまったくなりません。そもそもが自分自身の引け目や自責の念とか、無力感、崩壊感から出ている文章ですから。これから教科書に掲載されて全国の何人かの高校生の読みにさらされるわけですが、本当はおそろしいんです。私自身の底の浅さとか考えの足りなさを若い人たちにえぐり出されるような気がして。しかし、それをも含めて、私という普通の、一介の大学の事務屋さんが自分の体験と何とか向き合おうとした過程が、過程として共有できれば、そこから高校生の誰かが次のステップに踏み出てくれるのではないかと、そのようなことは、期待しています。
 そういう願いも込めて、最後に、銀幕遊学◎レプリカントというユニットが、「神戸の壁」の前で行ったパフォーマンスを見ていただきましょう。長田にあって、戦争でも震災でも残った、一枚の壁。この壁の所有者のお孫さんが芸術系の大学の学生だったこともあって、この前でたくさんのパフォーマンスが行われました。そしてこの壁は、淡路へ移されることになりました。そのように、この震災の体験も、何かシャープな形で明日へ、次の世紀へと継がれていけばよいのだが、と思っています。
そういう願いも込めて、最後に、銀幕遊学◎レプリカントというユニットが、「神戸の壁」の前で行ったパフォーマンスを見ていただきましょう。長田にあって、戦争でも震災でも残った、一枚の壁。この壁の所有者のお孫さんが芸術系の大学の学生だったこともあって、この前でたくさんのパフォーマンスが行われました。そしてこの壁は、淡路へ移されることになりました。そのように、この震災の体験も、何かシャープな形で明日へ、次の世紀へと継がれていけばよいのだが、と思っています。
《作品データ》
① 「VOICE」
作・演出=中井由梨子
初演=一九九五年五月、シアターポシェット(神戸・北野)
ビデオは、当時のNHKニュースから
② 「破稿・銀河鉄道の夜」
作=水野陽子、原案・演出=谷省吾
初演=一九九六年十月
ビデオは、いるかHotel提供
台本は、『高校演劇SELECTION'98』(晩成書房)
③ 桃園会「カラカラ改訂版」
作・演出=深津篤史
初演=一九九五年八月、アイホール(伊丹)
ビデオ、写真は、劇団提供
台本は、劇団販売
④ 「カラカラ―トートの書#桜の園 吉永の場合」
作・演出=深津篤史
初演=一九九七年四月、ウイングフィールド(大阪、東心斎橋)
ビデオは、劇団提供
台本は、劇団販売
⑤ 芝居屋坂道ストア「あくびと風の威力」
作・演出=角ひろみ
初演=一九九八年、神戸アートビレッジセンターKAVCホール(新開地)
ビデオは、劇団販売
⑤ PM/飛ぶ教室「滝の茶屋のおじちゃん」
作・演出=蟷螂襲
初演=一九九八年十一月、ウイングフィールド(東心斎橋)
台本は、『OMS戯曲賞vol.5』(一九九九、扇町ミュージアムスクエア)
⑥ 「青い街」
作=前田真奈美 演出=谷省吾
初演=神戸高校版:一九九五年十月
いるかHotel版:一九九八年一月、神戸アートビレッジセンターKAVCシアター
ビデオ・台本は、いるかHotel提供
写真撮影=神本昌幸
⑦ 銀幕遊学◎レプリカント「壁」
構成=佐藤香馨
ビデオは、劇団提供
※ ビデオ、台本、写真をご提供いただいた劇団の皆様に、この場を借りて深く感謝いたします。![]()
![]() ホームへ戻る
ホームへ戻る
Copyright:Shozo
Jonen,2000 上念省三