アンサンブル・ゾネ(岡登志子)
Ensemble
Sonne
'91年より、ドイツ・NRW州立Folkwang大学('27年クルト・ヨース、ジーゴード・レーダーによって設立され、ピナ・バウシュ、スザンネ・リンケ、ラインヒルト・ホフマンらを輩出している)にて活動を開始。Rotterdam
dance festival、Leipzig
dance
festival他に参加。ダンサーの意識と、ニュートラルな状態(呼吸・重力・空間を感じることによって身体を解放する)に向かう身体が結びつくことによって生まれる動きを、舞踊として昇華していくという作業に基づいています。それは、われわれの日々の動作やしぐさ(=生きるために必然的に生まれる動き)がすくいあげられ純化されたものといえるでしょう。現代に生きる私たちの共通の身体を通して、人間の実存を問う作品づくりを目指しています。
岡登志子
故法喜晶子、和田敦子に師事。1990年ドイツ・NRW州立フォルクヴァング芸術大学舞踊科(1927年クルト・ヨース、ジーゴード・レーダーによって設立され、ピナ・バウシュやスザンネ・リンケを輩出)卒業。ドイツ、イタリア、オランダにて自作発表。'94年より活動拠点を日本に移し、作品を発表すると共に、各地でワークショップを開催。'96年、'98年にはバニョレ国際振付賞東京プラットフォームに出品。
「闇の中の道」
2002年1月11日
神戸アートビレッジ・センター
岡登志子を中心としたこのグループの公演で、これまでと違いが際立ったという意味で印象に残ったのは、まず照明、そして音または笑い。
照明に関しては、以前から担当している岩村原太が、いい意味でひじょうに中途半端で曖昧な明るさ/暗さを駆使し、いつもに増して微妙で特異な空間を創り出した。タイトルからも想像できるように闇が主体となりながらも、天井からブランコのように吊り下げられた蛍光灯によるところが大きかったと思うが、バルテュスの絵画に見られる自然光のような、光の粒子が粒々になって浮遊しているような空気ができており、まったく初めて見る光の空間が出来上がっていたことに驚いた。
また、灯りがつくことで見えるようになるのではなく、かえってシルエットになってしまって見えなくなる、というパラドキシカルな効果。いくつかのシーンで、照明が壁面に創り出す空間の模様がマーク・ロスコの絵画のように美しかったことも、印象に残っている。
アンサンブル・ゾネの作品は禁欲的で、まず身体が動くことそのものを目的としているようだったり、言葉に還元できるような意味の連なりとなることを絶対に排するような厳しいものだった。たとえば公演のタイトルにもあらわれていたのだが、「落ちる」という言葉もしくは行為をめぐって淡々と展開するものだったりした(「おちてゆく瞬」)。一般的な意味でのリズムやノリも見えず、ぼくはこのような彼女の志向をたいへん好ましく思っていたが、一方で観る者にはいささかつらい、禁欲的に過ぎるようなところがあるような気もしていた。
今回の公演では、既に見てきたような岩村の照明の斬新さに加え、フリッツ・シテェレという男性アーティスト(パフォーマーと呼んだほうがふさわしいか)からの、自由自在な音の生成だった。冒頭からプルプル言ったり舌打ちしたり、何かを噛むようなクチャクチャした音を立てたりしていたが、それはまだおとなしいものだったようだ。クラリネットを吹いてノイズを出したり、チョプチョプと口で音を立てたりと、要するに、一人ユーモラスな格好で歩き回り、作品の空気をかき混ぜる役割を果たしていたようだ。彼は音を担当していたわけではあるが、考えてみれば、空気と音との関係というのは、振動によって空気を震わせて音を出すということなのだから、まさに「空気をかき混ぜる」というわけだったのだ。そして、そうだとして、本質的な意味で音によって作品の空気をかき混ぜるという意味で音が機能することは、かなり希れで貴重なものだったといえるだろう。
さて、そのような音と光に包まれて、岡を中心とするダンスは、これまでの作品に比べてかなり奔放でスケールの大きな動きを見せたといえよう。一つにはファビオ・ピンクというブラジル出身の男性ダンサーの鋭く自由な動き。そして伊藤愛、松嶋博英というメンバーの成長。
ファビオは、プロフィールによると一昨年(2000年)、日本財団の奨学生として能と日本舞踊を学ぶために来日したそうだ。あとで岡に聞いたところによれば、彼がおさらいで舞った「黒髪」は絶品だったとのこと、観たかった。というのも、そういう先入観なしに見ても、彼の身体の角度の変え方、すり足めいた身体の重心を変えない動き方が、日本的であるということ以前にひじょうに魅力的で、止まっていることと動くことの間の懸隔にあるドラマをみごとに見せていると思ったからだ。
日本舞踊であろうがダンスであろうが、形や姿勢が定まっているということで、すべての動きが流れるように美しい。身体を上下に沈めたり、リズムをつけて歩いたり、松嶋と何か争うようなしぐさを見せたり、動きの一つ一つがそうでしかありえないように的確だった。
伊藤が、動きも姿もひじょうに美しくなった。先に述べた、バルテュスのような空間だと思わせたのは、一つには伊藤の姿の美しさのせいだ。何かに引っ張られるような動きや、腕も足も直角に曲げて片脚で立ったような形の面白さとか、一つ一つの形・動きが丁寧に分節されているようで、理知的な動きであるように見えた。これはおそらく岡の身体についての思想を十全に体現できていたといえるだろう。
ファビオとの関係性について考えると、特に伊藤と彼との二者の関係性は見極めにくいとはいうものの、感性の絶対値が等しいのではないかと思った。あるいは、逸れ具合、逸脱の大きさといってもいい。+か−かはその時々で様々でありうるが、その振幅の大きさが等しく、ために作品の中での個々のダンサーのありようが、ひじょうに収まりいい。
松嶋が奇妙にアンバランスなスキップみたいなステップを踏むのが、面白かった。ドドドと音を立てて歩き、ピョンピョーンと跳ねるのも、不思議だ。この作品全体に奇妙に漂うユーモラスな雰囲気をあらわしている。ちょっと大げさな動きとか、狂言のような振りでファビオと絡んだり、あくまで真面目くさっているだけに、おかしい。
このような、作品全体を微温的におおうユーモアの空気が、これまでのゾネの作品からはあまり感じられなかったもので、しかしながら振り返ってみれば、先にも述べたように、このような逸れ方は、以前から底を流れていたような気もする。今回は、それがシテェレという存在によって、ひじょうに明確な形で見えたのであって、最初に岡が下駄を履いて、最後に伊藤が下駄を空中に持って歩かせるように動かして、出てきたのも、足の音という意味で作品のモチーフとして重要だったとしても、むしろただユーモラスな小道具として笑っていればよかった。岡としてはちょっと気楽な楽しい作品として創ったのかもしれないが、それだけにたくさんの要素が盛り込まれた、いろいろ楽しく考えることのできる作品だった。
「Moment
in Dropping おちていく瞬」
1999年2月27日、於・神戸アートビレッジセンターKAVCホール
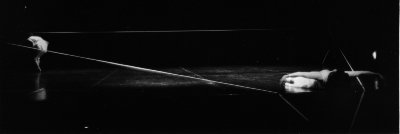 数年前に伊丹で上演された「落ちていく瞬」をメンバーを変えて再演したPart1、その主題<Dropping>に基づく即興のPart2。振付(Choreograph)と即興(Improvisation)を対比させ、同一主題にアプローチするという試み。チラシに記されたコンセプトは、「即興と振付 ダンスと音楽という空間に関する二つの位相によってダンスを多義的に表出させる試み」「drop=おちるという行為をテーマとする、おとされるのではなく、自ら大きな力を受けとめながらおちていくときに生まれる<永劫の瞬>を移ろいゆく空間にヴィジュアルとして残す試み」とあって、主宰の岡登志子の強いコンセプトメーキングに基づいた作品提示であったことが知れる。
数年前に伊丹で上演された「落ちていく瞬」をメンバーを変えて再演したPart1、その主題<Dropping>に基づく即興のPart2。振付(Choreograph)と即興(Improvisation)を対比させ、同一主題にアプローチするという試み。チラシに記されたコンセプトは、「即興と振付 ダンスと音楽という空間に関する二つの位相によってダンスを多義的に表出させる試み」「drop=おちるという行為をテーマとする、おとされるのではなく、自ら大きな力を受けとめながらおちていくときに生まれる<永劫の瞬>を移ろいゆく空間にヴィジュアルとして残す試み」とあって、主宰の岡登志子の強いコンセプトメーキングに基づいた作品提示であったことが知れる。
岡が形づくる世界で魅力的なのは、そのようにコンセプトが強いにもかかわらず、それがおそらくは内面化・深化というプロセスによってだろう、あらわれとしては非常に洗練されていて、直接的ではないにもかかわらず、何十分かの作品を見終えるとそのコンセプトの核らしきものがきちんとこちらに植えつけられている、というところだ。
Part1におかれた振付作品「おちていく瞬」は、舞台に白いテープが三角に張られていて、二人のダンサーが舞台からはみ出るように横たわっている状態から始まる。腕を開いていって水平になると弛緩し、腕が落ちる。息を吐くことで緩むことによって作られる動き。伊藤愛の動き、表情が静かに鎮まった心地好い緊張をたたえ、巽知史との遠いシンクロがすばらしい。
伊藤の呼吸、特に吐く動きと途中から沿う形で岡が現われる。動きが定まっていて美しいなぁとか、音楽がパーセルに変わったなぁとか思っていると、不意に、「ぼくのからだのなかには、日々落ちていくものがある」という思いまたは言葉が重くぼくの中で落ちた。
吸う、吐く、立つ、座る、そのようなことは、人が生きている中で意識せずに自然に繰り返されている。それが舞台の上で事改めて提示されることで、象徴性を帯びたり厳粛さをまとったり、要するに意味を持つことができる。たとえば爪先立ちで小走りすることが、精神の揺らぎやふるえを表わしているように思う。そんな意味の集積が、不意にぼくの内部をシンクロさせるような形で現われた思いまたは言葉だったように思う。
身体が傾く。一定の傾きを超えると、倒れ落ちるように動く。これは力が働いていない動きであるように思える。また、伸び上がった結果として、伸ばしたゴムが巻き戻るように、縮むこと。張られたテープが切れること。そのようなときの動きとは、動こうと志向されたものではなく、何かの動きの結果として自然に発生しているものだ。あるいは、何かの動きの跡だといったほうが適切かもしれない。落ちるとは、上がったり伸びたりしたことの跡だと。
第2部「Imprivisation
from Moment in
Dropping」は、音楽に内橋和久を迎えた、4人のダンサーによるもの。内橋の操るダクソフォンという、木でできた奇妙な擦音を出す楽器が、意識的にか自然の、たとえば動物の鳴き声のような音を出すので、妙に牧歌的な雰囲気が醸し出されている。でもそのような中で、いつ落ちるのか、と待っているような気分になっている自分がおかしい。
この間、岡はずーっと下手手前の椅子に座っていて、動かない。他の3人が下手奥に引っ込むと、岡に淡いライトが当たり、一瞬伸び上がると、沈んだ。伸び上がるからこそ落ちること、リリースと呼吸といったことを再確認しながら、硬そうな上半身と柔らかそうな下半身の対比を作り、主にその上半身によって不安や危うさを表現できているように感じられた。
一連のぼくの印象は、岡自身の創作意図とはややずれているのではないかと、心配している。冒頭に引いたチラシの文章の中で、彼女は「おちる」という行為に意識をおくと書いたが、むしろぼくは「おちる」という行為の前にある動きの結果としての落下という運動を見ていた。当然のことながら、彼女は動きに対してぼくよりずっと意識的であるのだろう。ぼくがこの二つの作品を見ながら感じたことの一つに、人間は動いているのが本当なのか、止まっているのが本当なのか、ということがある。力を加えている状態と、そうでない状態とか、あるいは力を加えられていないけれども動いているという状態もある。動きの状態の様々な相について、様々に思いをめぐらしながら見ることができた。
ダンスを語る−
not
critic, but analysis
1998年9月23日、「アンサンブル・ゾネ Dance
Analysis 動きを観ることからvol.1」が東灘区民センター小ホールで行われた。岡登志子を中心とした面々が、鮮やかにダンスの味わい方を開いてくれるのを、落ち着いた会場の雰囲気もあってしっとりした気分で確かめることができた。前後・左右・上下という基本的な動きとそのバリエーションをソロと群舞で見せる。観客を自由に移動させて様々な方向から見せる。無音で見せ、音楽をつけて見せる。そのような一連の共同作業によって、ぼくたちはダンスが、身体という空間と、ホールという空間によってどれだけ豊かに変化しうるものかを知り、そこで「私」と「踊る人(たち)」との関係性がどれほど微妙なバランスによって成立しているのかも知ることになった。
岡は、自ら自作を分析して見せた。それは言葉による分析であるよりは、対比して見せることで見る者が好悪や優劣を判断し、その理由を考えるということだった。そのような思考の展開は、そのまま見る者が作品の成立過程を自分の中で再現するという作業だったはずで、このとき空間の中ではいくつもの時間と思考過程が流れたことになる。
中でも、岡がソロ「地の上で」のソロ・ピースを無音で踊り、続いて内橋和久のテープをバックに踊って見せたのは面白かった。ソロの息詰まるような求心力が、音の介在によってずいぶん融和され、否定的な意味ではなくホッとするような気持ちになる。神経を研ぎ澄まして一点に集中させるのではなく、複数の対象に分散させることで、かえって見えてくる世界がある。ポツポツとはじかれるギターの弦の音が、身体の動きの一つ一つを読み解く標べのように思えた。
「批評ではなく分析(または解析)」と題したのは、'98新進振付家作品公開クリニック(クリティックではなく。10月4日、万博ホール)でバニョレ国際振付賞ディレクターのロリーナ・ニクラス女史がそう言っていたからだ。ぼくは残念ながら午前の2作品だけで退席したのだが、15分程度の作品を上演した後で、ダンサーたちと女史を中心としたフリートークの形で作品を読み解くことを目指したものだった。そこではバニョレの「よいダンサーを世界市場に売り出す」というマーケティング指向や、バニョレにおいてもダンスと非ダンス(パフォーマンス的なものとか)の境界を模索しているという話を新鮮に聞いたりもできた。
「論」という字は「あげつらう」とも読む。ダンスを語ったり論じたりすることは難しく、せっかくの多様で豊かな世界を矮小化したり、自らの狭量な世界観やひとりよがりの好悪を押しつける危険と隣り合っていることは承知している。ダンスを語るこの二つの企画を通じて、ダンスを開く言葉を共有することの大切さを痛感した。ぼくもまたよい解読者、分析者でありたいと願っている。この小さな紙面が、その糸口となればいいのだが。(PAN
PRESS掲載)
垂直に崩折れていくことの美しさと書いたからには8月19日のアンサンブル・ゾネ舞踊公演(京都・府民ホールALTI)に触れないわけにはいかない。前半の岡登志子とヴィオラ・ロガーによる「おちていく瞬」では、ステージを横切るように大きく三角形に浮かせた白いテープを、最後で後ろ向きに倒れて切っていくシーンが衝撃的だった。テープの存在によって舞台のバランスは微妙なものとなっており、二人の関係性がそこに紡ぎだす均衡、緊張、すべての動きが、落ちていく瞬間に収斂され、凝縮されていた。
岡とヴィオラや、後半の「緑の島」を演じたユタ・ヴィルドを見ていて面白かったのだが、どうしてもぼくは岡の動きや眼光に、鋭い精神性を見てしまうのだ。比較的に言って、岡の精神のありようの方が伝わり見えやすかったということだったのかも知れない。定められたラインを踏み外すこと、転落というよりも崩落といった方が相応しいような瞬間に立ち向かう精神の昂揚や不安が、岡の方からいっそう強烈に伝わったのだ。それを日本人だから以心伝心で、などとうそぶく神経はないが。
岡登志子の構成・振付・演出によるアンサンブル・ゾネ舞踊公演「One」(1997/11/14、KAVC)は、奇妙な印象の残る作品だった。その幾何学的な動きについて「断片的」と呼ぼうとすると、何かその言葉が冷たすぎるような違和がある。岡と他のダンサーが全く別の時間の中にいるかのように別の動きをとっていても、それが断絶としてではなく、淡い統一体としてインティメートな空気を醸し出す。それがたとえば伊藤キム+輝く未来の「あなた」(11/1、伊丹AI
HALL)との大きな違いだったように思う。それは優劣というのではなく、世界観を把持するという課題によるもので、伊藤の苛烈なまでの世界観の徹底的な提出は、それはそれで凄まじいものだったのだが。
岡はほとんど舞台の後方に位置して、扇のかなめのような機能を果たしていた。巽知史が断片をいとおしむように動きを動きとして堆積させようと動いている間、岡はほとんど自虐的に見えるほどの見せ所の少ない激しい緊張を伴う動きをとりながら、一つの連続性として、全体に存在する。この時、岡は理性的存在ではないが、感情であるより意志というべき形をとっているように見えた。
岡は奇妙な覚悟を決めたというか、ちょっとずれた真面目さにあえて自分を置くことを課したようだ。存在するための意志のありかを確認するために、普段は当たり前としてやり過ごしていることをあえて真っ向から問うという作業のように思えた。(JAMCi1998年2月号掲載)

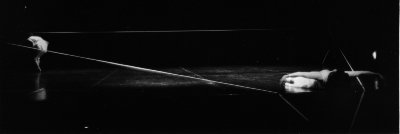 数年前に伊丹で上演された「落ちていく瞬」をメンバーを変えて再演したPart1、その主題<Dropping>に基づく即興のPart2。振付(Choreograph)と即興(Improvisation)を対比させ、同一主題にアプローチするという試み。チラシに記されたコンセプトは、「即興と振付 ダンスと音楽という空間に関する二つの位相によってダンスを多義的に表出させる試み」「drop=おちるという行為をテーマとする、おとされるのではなく、自ら大きな力を受けとめながらおちていくときに生まれる<永劫の瞬>を移ろいゆく空間にヴィジュアルとして残す試み」とあって、主宰の岡登志子の強いコンセプトメーキングに基づいた作品提示であったことが知れる。
数年前に伊丹で上演された「落ちていく瞬」をメンバーを変えて再演したPart1、その主題<Dropping>に基づく即興のPart2。振付(Choreograph)と即興(Improvisation)を対比させ、同一主題にアプローチするという試み。チラシに記されたコンセプトは、「即興と振付 ダンスと音楽という空間に関する二つの位相によってダンスを多義的に表出させる試み」「drop=おちるという行為をテーマとする、おとされるのではなく、自ら大きな力を受けとめながらおちていくときに生まれる<永劫の瞬>を移ろいゆく空間にヴィジュアルとして残す試み」とあって、主宰の岡登志子の強いコンセプトメーキングに基づいた作品提示であったことが知れる。