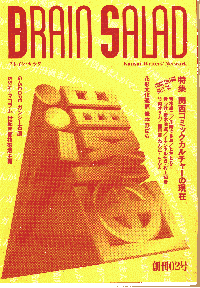 震災を断片化することの不可能性
震災を断片化することの不可能性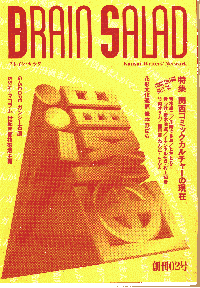 震災を断片化することの不可能性
震災を断片化することの不可能性
--「神戸」をめぐる演劇
4月21日に神戸のシーガルホールで開かれたシンポジウム「文化による新しいまちづくりをめざして」で、フロアから「いま舞台の感動が現実の重みに匹敵できていない。演劇を見て『よかったな』と思っても、帰りの阪神電車の窓から見える風景の方がすごいのだ」というような発言をした。震災後もぼくは多くの舞台に接した。劇場の中にいることであの日以前の自分を取り戻そうとしていたように思える。しかし、劇場を出た途端、もっとぼくを痺れさせるものはないのか、あるいはぼくはもう演劇によって感動することはできないのかと、溜息つくことの方が多かった。
その数少ない例外の一つが、劇団大阪新撰組の「寿歌」だった(*1)。核兵器による最終戦争のあとを描いたこの名作は「震災後の神戸に最もふさわしい劇」(*2)とも呼ばれ、ぼくの心を深いところで揺さぶった。イエス(ヤソ)になぞらえられるヤスオの惨めで無力な姿は、大惨事の後での宗教の、神の無力と、無力ゆえの救済の可能性を余さず語り、心にしみた。もちろんそれは、演出の当麻英始の舞台空間を熟知し、客席から見た美しさを計算しつくした役者の配置、キョウコ役の鈴木理枝子の思い切りのよいシャープな身のこなしと無垢の哀切によるものだったことは間違いない。
それだけに、神戸の劇団蜃気楼が「震災版・寿歌Ⅱ」(*3)をやると聞いたときの期待は大きかった。しかし「震災版」とあえて銘打たれたことでの不安もあった。果たして、不安が的中した。失敗の一つの原因は、劇中に挿入した神戸の人々の像にあった。若い役者たちによって演じられたそれは、声高に文句をたれ、怒鳴り声を上げるだけだった。黙々と水汲みに並び、救援物資に頭を下げていた神戸市民の一人として、それは耐えられるものではなかった。何かを非難するために、あえて告発する市民像を描いたのだとしても、それが一面的で矮小化されていては、共感の得られようもない。
もう一つの原因は、震災を断片化して挿入しようとしたことそのものにあった。どうしたって断片にならないのだ。舞台の上手・下手に据えられた小さなスクリーンに震災後の街の写真をスライドで映したりしたことは、リアリティを演出することに全くつながらなかった。本当は、そのような街にやってきた旅芸人の一座の脳天気ぶり、あるいはその一人が街を再開発という名で簒奪しようとするスパイ的人間であるという脚色のベースとなるはずだったのだろうが、木に竹を接ぐ格好になってしまい、バラバラになってしまった。
同様の失敗が見られたのが、神戸大学OBを中心とした劇団☆世界一団の「リアルること」だった(*4)。トム・ストッパードの「リアルシング」をベースに、劇作家の男を取り巻く男女関係を中心に据え、震災やサリンのことを登場人物たちの会話にちりばめ、それを「リアル」と呼ぼうとしたが、脳天気にこそなれ、決してこの現実に拮抗するものとはならなかった。しいて言えば、神戸からも東京からも遥かに遠い世界のどこかで、震災もサリンもボスニアもヨーロッパの大洪水も、ブラウン管の向こうのこととしか思えない人々を描いていたように思えなくもない。最もリアルから離れたところに彼らの現在があると認識しているのなら、それも一つの覚悟ではあるが。
逆に震災の体験に正面から取り組み、成功したのが、KOBE高校演劇合同公演「VOICE」である(*5)。家が全壊したスタッフの一人の実体験をそのまま再現したリアルな1時間だった。主に父親役が発する下手なダジャレやユーモアも、ぼくたちが避難所や停電した家の中で交わしたのと同じだった。
ラスト近く、いよいよ家が解体されることになり、一家が親戚宅に移ることになった前夜、何か取り出しておきたいものはないかと聞かれたおばあちゃんは「強いて言えばアルバムかなぁ」と呟く。翌日、孫たちが崩れかけた家の中に入ってアルバムを探す……(知人にこのあらすじを話すと、「うちでもそうだったよ。アルバムだけは何とかとね」と淋しく笑った)。劇ではこのアルバムというメタファがエンディングの「私たちは歴史を生きたのだ」というモノローグにつながるのだが、この芝居の成功の原因は、このようなどこにでも転がっていたありふれた事実の断片を、いとおしく拾い上げて大切に自分たちの等身大の表現にできたことにあった。
残酷や悲劇が圧倒したこの現実の中で、彼らはそれでも自分たちが日常を生きていくことを再確認し、語り継ぐべき歴史として直視した。その眼ざしは、はからずも人の営みの一つ一つに頬ずりするような慈愛に満ちたものとなった。この劇を見ることができたことで、ぼくもずいぶん救われたのだ。
*1 4月14日、四天王寺前、スタジオガリバー。作=北村想
*2 瀬戸宏「阪神大震災と演劇」。「JAMCi」17号
*3 6月10日、元町、兵庫県民小劇場。演出=棚橋洋一
*4 5月5日、梅田、カラビンカ
*5 5月4日、神戸北野、シアターポシェット。作・演出=中井由梨子
震災後の演劇をめぐって--なぜことさらに醜さを暴くのか
今年(1996)の「神戸市成人お祝いの会」で地震を寸劇で再現したところ、叫び声やサイレン音のリアルさに、列席者から「もうやめて」の声があがり、退席した人もいたそうだ(1月16日付毎日)。記事によると、劇じたい「あんなに甘いもんじゃないと思う」と言われるような出来だった上に、効果音などが必要以上に生々しく「ちょっとキツかった」ということだったようだ。
県立芦屋高校の卒業生を母体にした劇団傲慢の「パンク直します」は、芦屋のある避難所の四ヶ月間の出来事という設定だった。二人の市職員(保母)、二人のボランティアが経験する、人間関係を中心としたさまざまなトラブルは、おそらく実際に起きたことをベースとしたものだっただろう。それらのほとんどは、避難者の理不尽なわがままとして、ぼくたちをボランティアや職員にシンクロさせる結果となった。
特に印象的だったのが初老の婦人(山門泰子。好演)が職員・朋子(堂崎道子)をいびる場面だ。芦屋浜の高層マンションに住んでいる朋子に、ちゃんと建っているのに半壊認定で見舞金をもらえてよかったねぇ……うちはこんな歪んでるのに一部損壊で一円も出ないのだとか、市職員だから手当はたくさんもらえるのだろうとか、避難所の救援物資を持って帰ったりするんだろうとか、口調は丁寧だが聞くに堪えないような言葉が矢継ぎ早に浴びせられる。いくぶん戯画的に処理をしたつもりかも知れないが、全く笑えないのでは、戯画にならない。
じっさい、ぼくは聞くに堪えなかったのだ。客席からは山門の好演に対して拍手さえ出ていて、そしてじっさい彼女の演技は大したものだったが、何もそのようにしてまで人々の醜さをあげつらわなくてもいいではないか、みんなぎりぎりのところで暮らしているのに、とほとんどうつむいていた。
震災のあとの日々に起きた事柄の内、多くは心をあたためるものだったが、悲しみに追い討ちをかけるようなつらくむごいこともいくつかは耳にしている。ぼくのように家も家族も無事で、避難所も一泊しか経験していないような立場ではたいそうなことは言えないが、殊に震災後に生じた市井の人々の間のむごい話、人の醜さを暴くような話は聞きたくない。
このような姿勢は、演劇という表現に浅からず向き合っているぼくとしては、恥ずかしいことだ。生理的嫌悪感や違和感を与えることで成立してきた演劇は多く、ぼくもそのような舞台を好んで評価してきたはずだ。震災をめぐる人々の酷薄さに対するぼくの嫌悪の強さは、これまでのぼくの観劇体験の浅さを証しているのではないか? 本当の意味で、これまでの観劇体験はぼくの生理の深くに届いていなかったのではなかったか? 特定のテーマを、その題材によって忌避してしまうというのは、表現にかかわる人間にとって欠陥ではないのか、しかもそれは自らが当事者として体験した出来事であるのに。
一方、なぜ殊更にこのような醜さを、真実だから、じっさいにあったからといって舞台で暴くのかという疑いめいた思いも悔しまじりにわき上がる。前号で触れた『震災版・寿歌2』でもそうだったのでいっそう訝しく思うのだが、市井の人々が、それはつまりぼくたち自身のことだが、ぎりぎりのところでさらけ出してしまう醜さを高みからあげつらい、断罪するような態度が、演劇を創る者に生じてしまうということだろうか。それが人間の真実の姿であることを<発見>したことを喜び、着想に溺れる愚かさがありはしないか? 「生理的な嫌悪の心を超えて真実を直視しなければならない」というような、「神戸市成人お祝いの会」主催者と同様のお節介な教育的配慮がありはしないか?
震災でアトリエを失うなど大きな被害を受けた劇団道化座の「あした晴れる日」でも、一人の若い男性の設定に関して最後まで入り込めないまま終わってしまった。松竹新喜劇を思わせるようなテンポのあるよくできたお芝居で、主宰者の須永(=父・大山杢太郎)やその長男の妻・愛子役の馬場晶子の好演もあって、もう少しのところでたいへん満足できるものになっていたのに、残念だった。
その青年(=一郎)は、愛子の娘(=恵子)の結婚相手。二人は震災後のボランティアで知り合って結婚したが、新婚旅行中に喧嘩して恵子は一人で実家に戻ってきてしまう。驚いて理由を聞くと、一郎はつきあっていた頃とは一転して何かと自分勝手で、ばったり会った大学の先輩につきあわされ、揚げ句、恵子をほったらかして二人で飲みに行き、午前様になるに至り、恵子はキレてしまったという。ここまでで恵子の落ち度は見えず、ぼくは恵子に同調するほかはない。
問題は、一郎がボランティア時代とは変わってしまったとされるところだ。あのころは何でも自分の判断でできて生き生きしていたが、今は元通り会社の歯車の一つ、大学の先輩も大事な取引先でおろそかにはできなかったと弁明し、それでも何とかついてきてほしいと言う一郎には、恵子ならずとも、歯がゆく思い、ため息をつかざるを得ないだろう。恵子はその後いくつかのきっかけがあって、一郎の許に戻っていくのだが、それは結果的に震災前の生活の価値観を追認し、また男女役割を固定化してしまうようで、結局震災から新しい何ものも生まれなかったことを思い知らされたようで期待はずれの結末だった。こんなものだ。
震災はぼくたちの何も変えていないというのが大方の見方だろう。物欲がなくなっただとか、物事に執着しなくなったとか、直後には言われたが、サラリーマンのボランティアが増えたり、自動車の交通量が減ったり、節水や省エネを心がけたりしているか?
震災から数ヶ月、また一年が過ぎ、あのころのぼくたちの「連帯」がどうも一時の興奮に過ぎなかったことが明らかになっている。それは当然のこととはいえ、宮沢賢治が描いた「貝の火」のきらめきがほんの一瞬(「たった六日だったな、ホッホ」)だったように、人々が限りなくやさしかった日々は去ってしまった。そして、そのころに「温度差」と言えば「被災地」と東京の間にあったのが、今は神戸の中で、被災地の中に深い溝として横たわっている。ぼくがこれから抱え見つめて受け入れていかなければならないのは、その酷薄さなのかも知れない。
(1996年6月発行「Brain Salad」3号所収)
* 劇団傲慢「パンク直します」 作・演出=重光透、新神戸オリエンタル劇場、9月2日
* 劇団道化座<生きる>シリーズ1「あした晴れる日」 作=渡辺鶴、演出=須永克彦、新神戸オリエンタル劇場、3月25日
© Shozo Jonen 1997, 上念省三