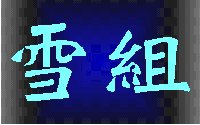
「君を愛してる」「エリザベート」「ベルサイユのばら」「スサノオ」「追憶のバルセロナ」「愛 燃える」「猛き黄金の国」「凱旋門」(役替り公演) 「バッカスと呼ばれた男」「ノバ・ボサ・ノバ」「浅茅が宿」「春櫻賦」「真夜中のゴースト」
君を愛してる
蓮城まことと愛原実花の二人が初主演ということで、それぞれにテーマがあったと思う。蓮城は、身長や姿の大きさと、時折見せるチャーミングではあるが子どもっぽい印象がアンバランスに思えることがあり、その稚気をどう料理するのかがポイントだっただろう。愛原は、役に完全に没入し、役が乗り移ったかのような名演を見せた『エリザベート』のマデレーネ役を経て、一日限りの新人公演でどのような役づくりを見せるかに興味があった。結論を先走れば、蓮城は予想以上の好演、愛原はなるほどと思わせる及第点といったところだったといえるだろう。
入団4年目の愛原(マルキーズ。本役=白羽ゆり)は、初主演とは思えないほど安定していた。必要に応じて、白羽の演技の間合いや声調をうまい具合に取り入れ、時折声音まで学んだことがわかるような個所もあった。新公ではよくあることだ。本役をなぞる以上の、観る者を驚かせるような逸脱は見られなかったとはいえ、洗面器でジョルジュをぶつ序盤の見せ場など、白羽への当て書きと思われるような場面でも、きっぱりと勢いよく腕を伸ばせていて、よくしたものだと感心した。
彩吹真央本役のアルガンを演じたのは、大湖せしる。彩吹がかなり徹底して悪役らしさを強調したのに対し、その破壊的にチャーミングな容姿を生かして、マルキーズへの思いを前面に出し、クールさをやや抑えたのが成功だったといえるだろう。彩吹に難をいうのではないが、ジョルジュの魅力が増すことでアルガンと拮抗する形になり、ドラマの軸を明確にしたといっていいだろう。少々弱かった歌が大いに進歩していたのは頼もしい。秘書・レイチェル(本役=美穂圭子)の千はふりとのコンビネーションも、少し立場を近めに設定していたようで、好感が持てた。
目立ってうまかったのが、ドビルパン(本役=一樹千尋)の大凪真生とエレーヌ(本役=天勢いづる)の晴華みどりの夫妻。二人とも(特に晴華)歌のうまさを前面に押し出し、それをコミカルなまでに誇張していくあたりが、演出(新人公演担当=大野拓史)の遊びと演技力か。二人の達者なコメディセンスのおかげで、第十一場はいい意味で新公らしからぬ余裕のある遊びが感じられる、しゃれた場面となった。
同じくベテラン役でも、未来優希の本役に当たると、当然歌で苦労することになるが、レオン神父の沙央くらまは、歌でも十分な水準をクリアしたし、未来ほどの歌唱力がない分は、人々を豊かに包み込むような優しく大きな人柄を表わす演技で、感動させる舞台を作り上げた。その構築力は、非常に優れたものだったと思う。動きを少しゆったりと大きくすること、いつも低めに作っている声を、より丁寧にふくらませるようにして、相手にかぶせるようにしていくことで、きっちりと人柄の大きさ、包容力を表現できるようになっていた。
フィラント(本役=音月桂)の香綾しずるは、軽快にテンポよく、きっぱりさっぱりと好演。動きにキレがあり、歌声ものびやかによく通ってさわやか。音月よりもさらに小柄に見えるが、身体の前で面を作って押し出していくような動きが身につけば、大きさが出てくるのではないだろうか。持ち前の性質かもしれないが、結果的に役の性格をよく表現できたといえるだろう。アルセスト(本役=凰稀かなめ)の凛城きらは、役のわりにはあまり目立つところがなかったが、繊細さや心細げな表情はうまく出せていたといえるだろう。
娘役にはあまり目立つ役がなかったが、セリメーヌ(本役=大月さゆ)の純矢ちとせは、はじめのうちこそ柄の大きさに違和感があったが、懐の深い達者な演技を見せた。特に大凪と晴華にわたりあう場面では芯の強さが感じられ、面白い役作りとなったといえよう。リュシール(本役=山科愛)の沙月愛奈が、少女役というステレオタイプに収まらず、マルキーズへの好意やアルガンへの反発など、様々な感情を幼さとともにきっちりと演じられていた。
クレアント(本役=緒月遠麻)の透真かずきは、大柄で魅力的な容姿をいかして、鷹揚でおっとりとした人のいい弟役を好演した。演技に落ち着いた風格があり、それが独特の間合いになるのか、味のあるたたずまいをしている。その妻アンジェリック(本役=晴華)の早花まこも、容姿の愛らしさを発揮して、クレアントとの仲のよさを上品に見せることができた。
蓮城のジョルジュは、本役の水夏希には見られない、若い愛らしさを見せたのが、成功したといえるだろう。冒頭にも述べたような彼女特有の稚気を全体的には抑え、ここぞというような要所ではきっちりと出すことができていたのが、富豪の跡取りという育ちのよさに通じ、男役ならではのコケットリィのようなものも垣間見え、効果的だった。
![]()
「エリザベート」
『エリザベート』の新人公演は久しぶりに観た気がするのだが、時間を縮めたことがこんなに不自然で無理があるように思えた新公は初めてだったように思う(新公担当演出=小柳奈穂子)。そのために一番仕事が増えたのがルキーニ(本役・音月桂)の大湖せしるで、「それでは、パーティーの様子をご覧ください」などと、誰に向かって喋っているのかと唖然とするようなト書き的なセリフがあるなど、様々な意味で乗りにくかっただろうが、チョイ悪な感じをうまく出していて、セリフ回しや少しゆがめた姿勢のとり方がよく、クネクネした動きも役柄によく合っていた。
フランツ=ヨーゼフ(本役・彩吹真央)の大凪真生、部分的に歌で苦しいところもあったようだがよく歌えており、声を丁寧に前に出そうとしているのがいい。皇帝として男としての苦悶の表情もはっきりと出ていたし、銀橋での「急すぎるね」の演技やシシィの居室で「開けておくれ」と訴える声音、鏡の間での優しく穏やかで情のこもった歌い方など、丁寧に人物像を押さえられていた。ひげもよく似合っており、役になりきっていたようだ。
エリザベート(本役・白羽ゆり)の大月さゆ、おそらくこれまでのどのエリザベートより人間くさく、感情の起伏が激しく、生々しいシシィだったと思う。少女時代は非常にかわいらしく、寝室にゾフィーが来たときの怯えの表情など、感心するほどよくできていた。このゾフィーとの応酬での表情の変化は豊かで的確で、納得できるものだったといえよう。名曲「私だけに」は、少し急いでしまった印象があるが、間奏の後は堂々とした姿になった。居室にフランツ=ヨーゼフが訪ねてきた時に見せた憤慨ぶりの激しさ、トートに「出てって!」と叫ぶ激しさ、鏡の間での自信と威厳に満ちた強い表情、ルドルフの告白に対して「わからないわ」と返す声のつやを消したような乾き方、と随所に強さとその中の孤独があふれているようだった。これまでの宝塚でのエリザベート像はもちろん、宝塚の娘役の様式をも逸脱しようとしているかのような大胆なアクの強さ、奔放さが見られたように思うが、やはりウィーン版来日がプラスに作用したのではなかっただろうか。
難役と思われたマックス公爵(本役・立ともみ)の紫友みれい、落ちつきがあり、低音もよく出ていて好演。ルドルフ(本役・凰稀かなめ)の蓮城まことは、純粋さと幼さがよく出ていて、本公演で演じたジュラよりこなれていたといえるだろう。銀橋での眼力も強く、歩き方、ダンスのキレと柔らかさ、発砲後の表情まですばらしく、深い闇を現出させることができていた。少年ルドルフ(本役・冴輝ちはや)の詩風翠は、実に可憐な演技と歌で、よくポイントをつかめていた。
ヘレネ(本役・涼花リサ)の愛原実花は、細かい芝居がうまく、役への理解力と、自己アピール力の両面で、やはり大したものだと思わせられた。リヒテンシュタイン(本役・美穂圭子)の早花まこ、肩の力を抜いた自然体に思えるようなたたずまいに好感が持てた。マダム・ヴォルフ(本役・晴華みどり)の純矢ちとせは、発声の子音の使い方がうまく、強さとちょうどいい程度の品のなさが十分に出ていた。顔も唇も青くしたマデレーネ(愛輝ゆま。本役・愛原)は病的で適切な役作り。ゾフィー(本役・未来優希)の晴華は、音域が合わないのか、低音部が客席に届かず、苦労していたようで、そのためか全体的に精彩を欠いたのは残念だ。
さて、トート(本役・水夏希)の沙央くらまは、オスカル以来の新公主役で、またもや難役に挑戦することになった。最も気になったのが、声調が不安定で連続した情緒を維持するのが難しいようだったこと。沙央は男役らしさを出すために、ややこもりがちの低い声を作ろうとしているが、新公主役のような長丁場でそれをコンスタントに維持するのは、やや難しいのだろうか。その点以外は、不気味な笑い方や人間くさい淋しさの表現も含めて、トートの雰囲気がよく出ていたことは評価できる。
![]()
ベルサイユのばら
バウ公演などで進境著しい沙央くらまの初主演、しかもオスカルとあって、大いに期待されたが、やはり全体にベルばらは「型」に由来する様式性が重要だから、リアルな演技に傾いている現代のタカラジェンヌには、どんどん難しくなっているのだろうかと、本公演より強く実感させられる結果となった。逆に言えば、意外のようにも思えるが、朝海ひかるは強く様式美を備えた役者であるということを痛感させられるわけだ。
それは結局、一般論だが、細部の演技はよく工夫され、表情や小さなしぐさは行き届いていたとしても、全体の印象としては今一つ薄く、空回り気味に終わってしまう、ということになるのではないかと思われる。だから具体的にあそこがどうというふうには説明しにくい。セリフの押し引きやメリハリが物足りなかったり、きっちりと静止しておいてほしいところがスッと流れてしまったりというふうに、逆説的だが、流れの中でこそ生きてくる「型」というものの決め込みが希薄化しているということか。
すると、一般論にとどまらずこの日の公演もそうだったのだが、セリフや演技の応酬が少しずつずれてしまい、ポイントとなる場面での対応が流れたり遅れたり、また大きすぎたり浮いてしまったりすることにもなる。それは個々の力量というより、劇の流れの決め込みの問題だと思われる。
繰り返すが、沙央は細部を見ると悪くなかった。総じれば好演といえるのだが、所々で課題を残した。アンドレ(凰稀かなめ。本役・湖月わたる他)が毒を入れたワインを勧めようとした後での、立ち尽くす姿は迫真だった。ただ、この後で「アンドレ…」と女の声で呼びかける演技は微妙。名曲「愛の巡礼」は、声の太さは評価したいが、逆に揺らぎがなく情感や厚みに欠けたようにも思われた。マロングラッセ(麻倉ももこ。本役・灯奈美)に髪を梳かれるときのたたずまいは大変チャーミングで好演といえる。ただし、いよいよ戦闘場面での長い独白でのセリフの間の取り方、メリハリの付け方は物足りない。「行こうー」での腰の沈め方も物足りない。しかし、最期の「フランス、万歳…」の呼吸、言葉の飲み込み方はすばらしかった。
アンドレの凰稀も魅力と課題を残してくれた。まず登場は、声も安定していて大きさ、大らかさが好ましかった。ただ、凰稀のキャラクターによるものか、アンドレに備わってほしい独特のアクのようなものがない。銀橋での「ブロンドの…」は、残念ながらメロディをなぞっているだけでまだまだ力不足、刃が立たない。しかしオスカルの部屋にワインを持ってきたところでは、やつれたようなつらさが現れていて、その迫真に目をむいた。「結婚式だ!」を聞いたときの微笑み、そして最期の笑みは実にすばらしかった。
姿の美しさで目を引いたのがジェローデル(本役・貴城けい他)の谷みずせ。プロローグから鮮やかな姿は群を抜いていたのだが、ジェローデルの出自や立場が風情のように匂い立ち、オスカルへの諭すような語りかけに人柄の大きさも出て、さわやかな印象を残した。
メルキオール(本役・壮一帆ほか)の大湖せしるは、歌にメリハリがあり、演技も細やかでいい。アラン(本役・水夏希ほか)の緒月遠麻は、出だしこそややぎこちなかったが、安定した存在感を見せた。「バスチーユに…白旗が」の名セリフには深みがあってよかった。ベルナール(本役・未来優希)の宙輝れいかは、セリフ回しが丁寧でいい芝居をする。第二部で格段に表情が締まり、シャープさをたたえたのがよかった。ダグー大佐(本役・飛鳥裕)の衣咲真音は、随所でコミカルな間合いやメリハリをつけ、篤実な人柄のよさを巧みに表わし、ラストではアランと共にオスカルの悲運を悼む姿の好演にうまく結びつけられたといえるだろう。小公子(本役・沙央)とニコラス(本役・悠なお輝)の凰華れのが口角が美しく舞台映えするいい表情をしている。音程がやや不安定なようだったが、声は前に出ているので心配ないだろう。
娘役では脇役が光った。マロングラッセの麻倉は愛らしく、オスカルの出立を惜しみ悲しみかきくどく場面、わが孫アンドレの名を遠く呼ぶシーンなど、哀感が込められた名演といえるだろう。ルイーズ(本役・天勢いづる)の愛原実花はセリフのテンポとメリハリが的確で、よく目立った。イザベル(本役・晴華。沙月愛奈)、ディアンヌ(本役・山科愛。大月さゆ)もセリフのうまさで目が止まった。アランの母シモーヌの華岡らら(本役・美穂圭子)は絞り気味の声で落ち着きがあり、情味のあるセリフ回しがよく、子守歌はちょっと劇を止めるかと思うほどすばらしかった。
ロザリー(本役・舞風りら)の晴華みどり、娘役トップの役とはいえ、しどころが少なく、気の毒ではあったが、ちょっと大人っぽすぎる感じとか、セリフ回しがナチュラルなのか上滑り気味なのか判断に苦しむところとか、座りがよくない印象。入れ込みにくく、作り込みにくい役だったのだろうか。ナチュラルな演技ではベルばらには合わないという、一つの典型となってしまったのかもしれない。
![]()
「スサノオ」
入団一年目の若手を登用していたせいもあってか、群衆(民)が出てくる時のスピードが今一つ物足りなかったり、群舞が全体に少し子どもっぽく見えたりしたが、特に目立つアラもなく幕を下ろせたのは、何よりである。舞台転換も少なく、ほぼ同じ暗さの
中で展開するこの劇は、様々な意味で強引ともいえるような力業を必要とするものだったが、それを若い役者たちでやりおおせることができたのは、新公ならではの一回限りのエネルギーの奔出ということもあっただろうが、やはり作品自体が闇を切りひらくよ
うな鋭い力をもっていたからだ。太鼓を打つという形であれ、群舞という形であれ、一人ひとりのエネルギーが劇を推し進める力であるということが、まざまざと実感できてゾクゾクするような感動が、皆に与えられたのではなかっただろうか。
まず月読(凰希かなめ。本役=壮一帆)が冒頭で怒りらしき激しい感情を満身に表わせていたのがいい。柄も大きく、声にも張りがあり、歌もけっこうマシになっていた。まずは充実した新公二番手ぶりだったといえよう。
特筆すべきは、アシナヅチ(本役・未来優希)の貴船尚。もちろんやりがいのある大きな役であるが、歌のうまさといい、感情の盛り上げ方といい、その感情を演技に反映させる実力といい、絶賛に値する。これまで風早優本役の三枚目的な役どころが多く、それも実に達者で芝居巧者ぶりを見せていたが、いよいよ本領発揮といった感があった。イナダヒメの山科愛(本役・舞風りら)とのデュエットも息が合う以上に劇の方向性をずんずん進める力があり、これからの雪組に欠かせない存在となりそうだ。
アオセトナ(本役・水夏希)の緒月遠麻は、前半で演技をしていない時の表情が物足りなかったり、柔らかい歌で音程に不安なところが出、弱さが感じられたりしたが、後半どんどんよくなった。「これがヤマタノオロチだ」には強さが集約されていたようで、力があっただけに、前半の乗り切れなさが惜しい。出番が少ないのはアメノウズメ(本役・音月桂)も同様だが、神月茜はその祝祭における役どころがじゅうぶん理解できていなかったのか、シーンを創る役割としての存在感が出せていなかったのが残念。
山科は、セリフの声がよく、歌う時の表情や口の形が美しい。表情もよく変化し、それをきちんと見せることができている。もう少し歌の声が前に出るといい。その姉麻樹ゆめみ、舞咲りんの歌がひじょうにレベルの高いもので、シーンをよく締めた。白羽ゆりは専科の初風緑が本役を務めたアマテラス役で、スケールの大きさを見せた。特に階段の半ばで見返って歌うシーンなど、身体のフォルムの線の美しさもあいまって、大きな力で舞台を覆ってしまうような力が感じられた。しかし、最後の「天上界」での光臨の際、おそらく初風はわざと表情を消すことで無垢なる存在として大きさを出せていたように思うが、白羽は大きさを出すことに腐心したあまりのことだろうが、舞台全体を呑もうとするような表情が正面に出過ぎて、かえって大きさを出せなかったように思う。まことに演技というものは難しいものだと思った。
いつも同じようなことを書くが、音月桂はまったく危げない。イナダヒメに「弟の名は?」と問われて「スサノオ」と答え、ニヤリといった表情を見せるところなど、小憎らしいばかりの好演である。一つの役の中に様々な表情を盛り込み、舞台の上での柄の大きさや振幅を最大限に見せることができている。今回は何よりも、力を揮う時の強さや粗暴さまでをどれほど出すことができるかがテーマだったと思われるが、これがひじょうに強く押し出せていたことが大きな評価ポイントだ。しかもその強さの中でも、彼女ならではのキュートな魅力を保っていたこと、これはスター性といってよいのではないだろうか。瀕死の演技も的確で、劇的でありながら自然さを失わないところは、まさに迫真といってよかろう。新鮮さや初々しさをもちながらも、もう新公のレベルではないような本格的な感動を味あわせてもらえた。
![]()
『追憶のバルセロナ』
本役との相性からいって、わりとやりやすい新人公演だったのではないかと思っていたが、その分逆に本役の大きさを思い知らされる場面もあり、ある意味では新人公演らしい舞台となった。一つには、壮一帆(フランシスコ、本役・絵麻緒ゆう)の上品な優等生らしさがなかなか抜けきらず、声の硬さもあいまって、なかなか大きさや迫力が出ず、ドラマの激しさが出てこなかったことが挙げられる。しかしその壮も、後半の黒い旋風としての登場ではさすがに鮮やかで、それに続く父の死を語る場面、アントニオ(天勢いづる。本役=成瀬こうき)との議論ではいい密度と緊迫感が出ていた。また、ちょっとかがみ込んで話しかけるような姿勢が、フランシスコあるいは壮の人柄をよくあらわしているようで、微笑ましい。壮はどちらかといえば上品な王子様タイプであるように思えるが、新公ではスケールの大きな役への挑戦が続いている。身体の細さを逆手にとって、観る者が驚くような大きさを見せられるよう、役や客席を呑むようなつもりで挑んでほしい。
逆にというべきか、身体は小さいのにスケールが大きく堪能させられたのが、天勢いづるだった。声がよく、まず歌でひじょうにしっかりと男役の迫力が出ている。ラスト近くの「私も手を挙げたら、旋風になれるか?」というセリフなど、万感のこもったすばらしい重みのあるものだった。一つだけ気になったのだが、うっかりするとかわいらしい歩き方になってしまうところがある。上半身の小ささも衣装でずいぶんカバーしようとしていたようで、本人が一番身体の小ささを悔しく思っているだろうなと感じた。
ロベルト(本役・朝海ひかる)の音月桂も小柄だが、小ささを感じさせない。顔の作りにメリハリがあるからということもあるだろうが、いつも歩き方がガシッガシッと地面を大きくつかんでいるようなところがいい。出づっぱりだった戦闘シーンのダンスや、いすを使ったダンスでは、身体のキレのよさを存分に見せてくれたし、歌も低音に迫力がありスケールが大きい。劇の中でこの存在がやや斜めに立っている感じをみごとに出せている。芝居の全体像をきっちりとつかめているように思えた。
娘役で、白羽ゆり(イサベル、本役・紺野まひる)には、改めてやはりこういう勢いのある役のほうが合うなと認識。本役とはまた違ったワイルドさがあり、声のトーンの変化も多様で、面白かった。第十七場「街路」の銀橋で再認識したが、姿は人形のように愛らしい一方、歌は地声と裏声の転換がスムーズで、ひじょうにうまい。ただ、時折芝居にタメを欠くように見えるところがあったり、足の運びがガチャガチャしているのが気になる。最後にフランシスコとじゃれ回るようなダンス、愛らしいのだが、意外にもといっては紺野に悪いが、紺野のほうがずっとしっとりしていた。白羽はおそらく役柄の幅の大きな本格的な娘役として育っていくと思うが、今後の新公でどんな本役をなぞることになるかで、その出来は大いに変わってくるだろう。
マリア(本役は男でモレノ、麻愛めぐる)の千咲毬愛がキレがあり、飲み屋の女主人としての芝居もダンスにもキレがあり、とてもテンポがいい。なぜ退団するのか、残念でならない。抜擢だと思うが、麻樹ゆめみがセシリア(本役・白羽ゆり)。声や芝居はまずくないようだが、役作りのバランスの問題か、ちょっと湿っていたのが気になる。
エンセナダの奏乃はると(本役・未来優希)の歌がすばらしかった。ミゲルの牧勢海(本役・風早優)は声が渋くセリフ回しも落ち着いており、シャウトのトーンも的確で、芝居心を感じさせた。ジャン・クリストフの聖れい(本役・貴城けい)の姿が堂々と大きく、しかもシャープ。
イアーゴーの貴船尚(本役・未沙のえる)、専科の役を新公で演じるのはかなりきついのが常だが、ひじょうにうまく未沙の雰囲気をなぞれていた。捕まるところではちょっとワルっぽい表情が出せていたし、もだえ方が傑作。「基地がやられた…」のところでは貴船のリアクションに拍手がわいたほどだった。フェイホオの凰稀かなめ(本役・音月桂)もこの役のポイントである芝居の間合いがほぼ的確で、走り方もしっかりしていた。レオポルトの玲有希(本役=美郷真也)は難役に挑んだが、出だしで少し落ち着きに欠けたようで心配されたが、ひげもよく似合っていたし、さすがに声がよくきっちりと芝居を見せてくれた。急な退団が惜しまれる。
アンジェリカの澪うらら(本役・五峰亜季)のダンスがすばらしかった。出立前のちょっとした芝居もきっちりとしていて、ある種のせつなさが出ていたのがいい。エスメラルダの汐夏ゆりさ(本役・森央かずみ)もダンスのキレがあり、表情がいい。ビアンカの舞咲りん(本役・愛耀子)も強く存在感を出せていた。
新公担当演出は、児玉明子。全体には、間合いがあきすぎたり、逆にセリフがかぶりすぎたりした場面もあり、テンポのよしあしにムラがあったのが残念。また、群舞に勢いが感じられなかったのが惜しい。細かなセリフの変更があったようだが、成功していたとは言いがたく、必然性も感じられなかった。
愛 燃える
今回は準トップ役(范蠢。本役・絵麻緒ゆう)に回った音月桂に、本役にはなかった暗い情熱が強く感じられたのが、ひじょうに新鮮に思えたのと同時に、役の解釈としても演技の表現としても的確であると感心させられた。それを最も強く感じられたのが、第十二場の西施に鳥を差し入れる場面で、有無を言わさず女を動かしてしまう姿が柄の大きさと重々しさを感じさせ、久々に骨太でスケールの大きな男役スターとして確立されようとしていることをうれしく思った。冒頭からまず姿の美しさで客席を引きつけ、西施に呉に行くことを命じる場面では、表情にほのかながらつらさが表われていたのもいい。刀さばきも問題なく、歌にも力強さと共に陰影がにじみ出て、少なくともこの公演に関して言えば、非の打ちどころのない立ち現われようだった。
夫差(本役・轟悠)の壮一帆は、細い身体が華奢に小さく見えはしないかと心配していたが、なかなかどうして、冒頭から声も太く存在感も確かで、美しい。槍さばきで身体の線がまっすぐで美しく、張りがあったのが目を引いた。演技や表情も的確で、初めて西施を見た時に「美しい」と声を洩らす時の陶酔した眼、後半の怒りの表情の厳しさ、「また狂ってゆく」からのセリフの迫真など、シーンの大筋をつかんだ上での細かい演技がきっちりとできていた。意識的なのかどうか、動きの端々にピクッと間をもたせるようなタメがあって、それが結果的に動きに大きさを与え、彼女を舞台映えさせているように見えたが、こういうことは教わってできることではあるまい。今後妙な癖として固定化しない限りは、彼女の優れた特徴として大切にしていくべきだと思った。欲を言えば後ろ姿に大きさが出るようになればいいと思うのだが、そんなことができればトップの中のトップだな。
紺野まひるがまだ娘役トップを務めなければならないのは、追試験的な意味あいがあるのかと思わざるをえないが、この新公の前にトップ内定の発表があったのだから、実に無意味なものとなった。演技については微妙な表情ができているし、セリフの間合いもいい。しかしそのようなことは新公の批評としてなら立派なものだとたたえることもできようが、トップ娘役として見ると、それらの技術が断片に終わっているようで、役全体としての揺れとして伝わってこないきらいがある。いっそう痩せたようなのも心配。
王孫惟(本役・貴城けい)の蒼海拓の刀さばきや腕の形が美しく、見開いた眼に迫力があった。歌にも力があって、役者として花開いた感がある。最期のシーンでは、上体を揺らさずに膝をつき、後ろに倒れるさまが美しく、強い説得力があった。
天勢いづる(伍封。本役・朝海ひかる)は、声は太くてよかったが、ちょっと年かさに作りすぎたきらいがある。化粧で、顔の中央を青く塗りすぎていたのに違和感があったせいかもしれない。弟の伍友が死んだ時の叫びもやや唐突に思え、全体に乗りきれない感じが残ったのが惜しい。歌には粘りがあり、合格点。
柳蓮(本役・灯奈美)の花純風香が、立ち姿で身体の線が美しく、声にもいいふくらみがあって、見せた。白羽ゆり(婉華。本役・紺野まひる)は、前半では絶世の美女ぶりを見せつけたが、後半ではやや入れ込み過ぎたか、少し重そうに見えたのが気になったところ。しかしさすがに西施の殺害を企てるところでは、勢いと鋭さがよく出ていて、この鋭さについては本役を上回ったと思われた。端役だが山科愛がセリフのない部分を大きな表情で埋める、わかりやすいいい演技ができていたのが、愛らしさとあいまって好感が持てた。澪うららの歌が、艶があってよかった。舞坂ゆき子の歌にある、かすかなふるえには、やはりゾクゾクさせられる。さほど大きな役ではないのに千咲毬愛が目立っていたことは、次回以降のために覚えておきたい。
男役では、張良(本役=未来優希)の神月茜が見違えるほど締まり、声にも張りが出ていたのに驚いた。孫武(本役=立樹遥)、劉生(本役=壮一帆)の聖れい、玲有希が共にいい姿を見せ、ここでの壮の語り口が真に迫っていたこともあって、締まった場面となった。勾践王の風美佳希、華康の安城志紀、文種の牧勢海の三人の名乗りが、棒ゼリフのように見えて、大きさがあって、きちんとした様式性を持っていたことを評価したい。作中唯一笑える場面の張九(水純花音。本役・風早優)、陳林(貴船尚。本役・美郷真也)らによる「兵士たち」の場面は、残念ながら空振りに終わった。余裕とか間合いの大切さとか、表情の作り方とか、すべてにおいて本役のうまさがよくわかったことだろう。伍友(本役・音月桂)の沙央くらまは、ずいぶん太い声を作った上で、大きくまっすぐ出ていたことは頼もしい。演技にも、まず懸命さが出ていたのが微笑ましく、今後の成長を楽しみに思う。
「猛き黄金の国」
これまで少年系の役が多かった音月桂がいきなりヒゲをたくわえて土佐のいごっそうを演じなければならないというのだから、本人もファンもさぞやハラハラしたことだろう。ところが予想に反してというべきか、音月は声が太く、ひじょうにいい与太ができていて、柄の大きさを見せた。ヒゲが似合っていたのもいい。科白の流れの中での声の絞り方など、勘どころをつかんだメリハリのつけ方も自由自在で、センスのよさをうかがわせた。たとえば母の美和(花純風香。落ち着いたセリフ回しがいい。本役=灯奈美)に江戸への出立を見送られ、根なし草にはならないと誓う場面での振り返る顔、表情、歌、未来への喜びに満ちて観る者を圧倒する力があった。結果的に身長の低さがほとんど(白いロングジャケットの三菱ダンサーのシーン以外は)気にならない。ラストの回想の難しい一人芝居で、劇場全体への視線の配り方が周到で、実にいい芝居になっていたのには驚かされた。
紺野まひるは、六度目の新人公演ヒロインだが、「下級生と組ませていただくのは初めて」ということで、新しい経験もあったかもしれないが、まず登場から力があり、バイタリティと愛らしさをよく表現できていた。インタビューなどで本人も言っていたが、登場の場面が時間的に大きく飛んでいるが、その間の歳月を的確に演技で表現できていたのはよかった。セリフ回しは相変わらず落ち着いていたが、今回一つ気になったのは、弥太郎との歌のデュエットで、「こーれから続く…」という歌詞のところ、最初の「こ」の音の頭が強すぎた。高い音ではあったが、もう少し柔らかく出さないと、デュエットとしてはきつすぎる。最後の喪服姿が美しかった。
丸奴(本役=紺野)の千咲毬愛は、もう少し顔を小さく見せる工夫をしたほうがいいと思ったが、いい芝居をした。舞坂ゆき子(いね。本役=五峰亜希)が表情がよく、声の絞り方に渋味があるのには感心。
坂本竜馬(本役=絵麻緒ゆう)の天勢いづるは、なかなか美しく見える場面もあり、歌もよく演技も合格ラインだと思うが、振りの始まりが少し速すぎるせいか、タメが足りず、大きさが見えてこなかったのが残念。お竜(麻樹ゆめみ。本役=愛田芽久)との場面で、ニヒルさがよく出ていて、役の読み込みの深さが感じられた。真波そらの武市半平太(本役=立樹遥)は、アゴの出し方や恨みの視線が的確で、演技のうまさがよく伝わった。桐野利秋(本役=すがた香)の安城志紀にいいまっすぐさが見えたのが好感をもてた。初めは居心地が悪そうだった川田小一郎(本役=貴城けい)の神月茜の顔が、芝居が進むに連れてみるみる締まってきたのにも驚いた。歌も悪くないし、科白の声が高く、若さがうまく出ていた。小栗上野介(本役=未来優希)の奏乃はるとは、表情にいい硬さを出し、声もよくセリフ回しも大きく堂に入っている。沖田総司(本役=蘭香レア)の柊巴は、キラキラしたまっすぐさを表現できたのがいい。後藤象二郎(本役=湖月わたる)の蒼海拓が、歌で低音にヒスがあり、太く渋い情感を出せていたのには感心した。川上音二郎(本役=音月)の凰稀かなめに純粋さが正面に感じられ、よかった。
現代の三人、本公演よりずっとテンポがよく軽薄で、賛否半ばするかもしれないが、とにかく楽しかった。神宮寺(本役=美郷真也)の牧勢海の三枚目ぶりが不自然でなく、矢島(本役=朝海ひかる)の聖れいもあわせて笑いを取る演技がから回りせず、きちんと別の空気や人物像を作り上げられていたのがよかった。ヒトミ(本役=愛耀子)の山科愛もルースソックスや厚底靴に違和感がなく、喋り方などもOK。病院での放送「産婦人科の石田先生…」といった細かいギャグも、不愉快ではなかった。
また、鹿鳴館を摸したと思われる延遼館での舞踏会の場面も細かい笑いをいくつもとっていたが、これはこれで一つの鹿鳴館という時世への批評として成立しているようでもあり、なるほどと思えないでもなかった。なお、このシーンでは女中役の夏央小槇の美しさが目を引いた。
こういうおちゃらけは新人公演で時々あらわれ、今回新公担当の齋藤吉正は多用していたようだが、なかなか加減が難しいようで、グラヴァー(貴船尚。本役=天希かおり)、アーネスト(宙輝れいか。本役=天勢)らの場面では、ちょっとくどかったような気がする。殊に竜馬と象二郎の会見の後、竜馬がトンカチで隊士の頭をポンポンと叩いたのは、それに続く象二郎が竜馬のスケールの大きさをたたえる演技がよかっただけに、意味不明でもったいなかった。
雪組役替わり公演「凱旋門」 宝塚大劇場での所見
このような、なんというか「企画」が発表された時点から、ものすごく大きな期待と共に、かすかな不安めいた思いがひっかかってはいたのだ。以前某誌に「新人公演でトップを務めていない者がトップになるとすれば宝塚歌劇史上初めてだ」というふうな紹介をされたりして、何かと物議をかもしていたし、バウ公演もダブルトップながら無難にこなしたし、本公演でも特にショーでは抜群の存在感を示している。
それだけに、もしこの一日だけの役替わり公演という特殊な企画が、「朝海ひかるはちゃんと大劇場でも中心に立ちましたよ」というアリバイのためだけに組まれたのであれば、あまりに形式主義的で意味のないことだ。朝海は、このようなアリバイを作らなくても、トップに立つほどの力をもっていると、それは既に衆目の一致するところであった。にもかかわらず、失敗が許されない状態での役替わり公演を朝海に与えたことは、彼女に余計なプレッシャーを与え、観る者にも余計な(過剰な)期待をもたせることになった。
朝海(ラヴィック)にとって気の毒だった点が二つある。一つは、本役が轟悠だったことであり、もう一つは相手役が貴咲美里(ジョアン。本役=月影瞳)だったことである。
「凱旋門」は素晴らしい作品だった。今の轟−月影コンビに実に似つかわしく、二人もそれによく応えた。それだけに、轟とはかなり肌合いの異なる朝海には多少収まりの悪い結果に終わるのはやむを得なかった。しかも貴咲は今回で退団ということで、いわば「アガリ」の状態。ドラマの切迫感がほとんどなかった。残念なことだがやむを得なかった。
最も気にしていたことで、やはり課題として残ってしまったのは、朝海の大きさに関する不安だった。身体の大きさのことだけなら、安蘭けいも決して大きくはないが、安蘭が現れるだけで空気を変えられるだけの、何かをもっている。他人のために書かれた役だったから、やむを得ないとしても、この日の朝海からはそのような何かが感じられなかった。この日の公演だけ見ると、朝海は大劇場でトップに立つより、バウ公演を中心とし、大劇場では主にショーで本領を発揮するようにシフトするほうがいいと思った。新・専科制度ならそういう柔軟な処遇によって個々の特性を引き出すことが可能だろう。
彼女はかなり緊張しているように見えた。ふだんの「朝海ひかる」に比べると、スッキリしすぎてひっかかりがなかった。動きにもタメがなかったし、声もあまりうまくコントロールできていないようで、歌にもやや伸びがなかった。ラストで声が裏返ってしまったのは、ただその一つのあらわれでしかない。本人は最悪の出来だったと思っているだろうが、念のために付け加えておくと、あらゆる意味で普通の出来だったわけで、気の毒だった。
その分おいしかったのは、脇に回った安蘭(ボリス。本役=香寿たつき)と成瀬こうき(ヴェーベル。本役=汐風幸)で、気楽ではなかったかもしれないが、余裕をもってそれぞれの役をクリアした。同期の三人がトップから三番手までを独占するという記念すべき公演で、十分その実力を発揮した。安蘭の星組行きということもあり、いい思い出になっただろう。同じく星組へ行く毬丘智美(本役=矢代鴻)の歌がこんなに素晴らしいとは、知らなかった。組替えにノシを付けてもらえたようで、よかった。
いわゆる新人公演組にとっては、一回チャンスが減ったわけで、複雑な思いがあったかもしれない。麻愛めぐる(マルクス。本役=成瀬こうき)はいい科白回しをしていた。夕貴真緒(ローゼンフェルト。本役=朝海ひかる)が役のトーンをよく把握して的確に演じていたのはよかった。聖れい(ヴィーゼンホーフ。本役=蒼海拓)の姿が美しく、悩み顔が魅力的だったこと、牧勢海(タンゴの男)が鮮やかだったことは発見。山科愛(ユリア。本役=千咲毬愛)は高貴で上品でいい。夢奈さや(リュシェンヌ。本役=森央かずみ)が歩き方や表情が美しく、いい芝居ができていたのが目立った。春あゆか(ビンダー夫人。本役=毬丘智美)の熱演には胸を打たれた。鮎奈さえが娼婦役でいい雰囲気を出していたのが嬉しく、退団が惜しまれる。神麗華(シビール。本役=愛田芽久)がはかなげで美しかったが、タンゴの女、白い鳥といった肝心のダンスの部分で輝きが見られなかったのが残念だ。蒼海拓(アンリ。本役=立樹遥)は、惜しいことに今一つ立ち上がってくる大きさに欠けた。目から眉にかけての動き、つまり表情に乏しく、硬い印象しかなかったせいだろうか。立樹遥は今さらいうまでもないが、ギターを持つ姿が水際だっていた。
終盤、朝海が「さよなら、ジョアン」と呼びかける前後の声、表情が非常に真に迫り、さすがの芝居巧者ぶりを確認。ラストで三色旗を振る安蘭も感動的で、この公演が一日限りではなく、少なくとも数回あれば、もう少し観る者も演じる者も余裕をもって、熟した舞台になることができたろうにと、惜しまれる。
「バッカスと呼ばれた男」新人公演
ジュリアン(本役=轟)の未来優希(研七)、初の新人公演トップ役ということで、まずはそこに注目が集まったが、印象に残ったのはアンヌ(月影)の紺野まひる(研四)の王妃姿のほうだった。未来はもちろん悪くなかった。本公演でも衛士として豊かな声量を堪能させているように、歌はもちろん演技も身のこなしも及第点なのだが、やや「おさらい」の域にとどまり、新たなバッカス像を立ちのぼらせるには至らなかったように思う。
一回限りの新公ということでやむをえないとは思うものの、ずーっと押し一辺倒で、引きの部分が見られず、九十分の間、芯になって見せるためには、ややしんどい。滑舌がよく歌詞もはっきりと聴き取りやすいのだが、一部でかえってそれで余裕がない歌になってしまったようで残念でもあった。しかし、王宮に覆面の吟遊詩人として現れた「かあさん……」の歌はドラマチックで前後関係がわかりやすくいい歌になっていたのだから、やはり向き不向きというところか。
ミッシェル(香寿)の蘭香レア(研五)は歩き方が堂々としてきたし、動きがよく、美しい。ラズロ(朝海)の蒼海拓(研四)も声、身のこなし共によく、さわやかな若さがよく出ていた。特筆すべきはマンドラン(安蘭)の音月桂(研二)で、もともと本公演でも「おいしい役」ではあるものの、ちょっと巻舌にした歌にワイルドな男の魅力があふれ、水際だった美しさがあった。ダンスで指先まで神経が行き届くようになったり、歌で一つ一つの音にもっと伸びが出てきたりすれば、かなり大きなスケールが出てくるだろう。
本役・汐風を新公で演じるのはいつも苦労するのだろうが、やはりマザランの立樹遥(研七)は台詞回しが前倒しになってしまいかぶり気味になるなど、ゆったりと鷹揚なタメが見られず、役としてのこらえ所が流れてしまったのが残念。だがそれを求めるのは、いろいろな意味で酷というものか。ブランシェ(美郷)の冴月晃(研七)は、滑舌にやや物足りなさがあり、軽さを発声の浅さで見せようとしていたのがやや気になったが、いい雰囲気は出ていた。老三銃士(汝鳥、未沙、箙)のすがた香(研六)、麻愛めぐる(研五)、南帆香凛(研六)にユーモアと悲哀に満ちた年寄り臭さが出ていないのは当然として、三人の声のトーンが同じで演じ分けられていなかったのは物足りない。中では、さすがにアトスのすがたがよかったが。フローベル公爵(風早)の風美佳希(研五)はシリアスにまとめたが、平板ではなく、よかった。
フローベル公爵夫人(灯)の愛耀子(研七)は、さすがに声も台詞回しも非常にドラマチックで、演技にメリハリがあった。シャルロッテ(貴咲)の愛田芽久(研六)は、時折叫び過ぎに思われる部分があったが、大方は一途なお嬢様らしかった。その姉マルギッタ(有沙)の夢奈さや(研六)は動きがゆったりと美しく、台詞も丁寧でいい。アデル(五峰)の花純風香(研五)は純な感じの声がいい。ある種のがさつさを感じるところもあったが、それが演技ならたいしたもの。ポーレット(紺野)の澪うらら(研三)は姿も声もよく、鼻歌っぽいいい感じは出ていたが、動きにタメがなく、ハミングがちょっとこもるところ、声が少し上ずりがちなところは気をつけたほうがいいと思う。大勢口だが随所で愛らしい姿が目立った鮎奈さえ(研四)は、立ち居振舞いや表情にも情感がこもっていたように思う。また、旅回り一座がスタートしようという場面で、珠希かほ(研六)のいきいきしたダンスが目立っていた。
さて、「SAY IT AGAIN」のジュリーで令嬢と詐欺師という演じ分けが中途半端に思えたこともあった紺野まひる、今回は王妃役ということで手も足も出ないのではないかと心配していたが、見事に杞憂に終わらせた。声の出し方が不自然でなく落ち着きがあり、殊にシャルロッテ、ジュリアンとの緊密な会話が繰り広げられる第十一場の声の高低が実に巧みで真に迫っていたのがうれしい。愛田の「でも、心が逆らうのです」から、この新人公演はドラマとしてひじょうにレベルの高いものとなったが、ここで紺野が素晴らしかったのは、「女として、母として強く生きる」ことを自身で決意した後にシャルロッテらを促す「さあ」の声の威風と、ジュリアンにその愛を暗に確かめる「今でも?」と言う愛らしさの双方を、存分に表現しきれていたことにあった。王妃として、母として、女としての三つの顔を演じ分けるのが課題であると、紺野自身当日のプログラムに書いていたが、それ以上に、王妃の威風の中に女としていきようとするシャルロッテへの憧憬のようなものが入り混じっていたのは、本当に素晴らしかった。
歌に関しても、声がシルキーになっていたのには驚いた。紺野は本公演でも台詞のない、歌と表情、しぐさだけのポーレットを演じきった。吟遊詩人のミッシェル(香寿)のあとをついて回る姿は本当に愛らしかった。これによって表現力をずいぶん鍛えられたことだろう。そしてこの王妃アンヌ・ドートリッシュという耐える役をよく耐えたことで、確実に一つのステップを上がったといえるだろう。(2000.Jan.3)
「ノバ・ボサ・ノバ」新人公演
ショーの新公は、芝居とは違って役作りの深まりや解釈の違いで見せるということがしにくいだけに、ダンスや歌の技術の未熟さがモロに出てしまうおそれがあり、新人たちには厳しい試練となるのではないか。かえってその分、ぼくたちは粗削りでもその持っているものの大きさや華やかさをまず見ようとしなければならないと思う。
その意味で「ノバ・ボサ・ノバ」は、各人が多少の課題を見せつつも、スケールの大きなのびのびとしたステージを見せてくれたといえるだろう。まず立樹遥がソール(本役=轟)として、美しく現われた。目の使い方がうまく、大劇場の空間を爽やかに制しきれていたようだ。未来優希が裏声の美しい、そして裏声への移りの魅力的ないい歌を歌い、紺野まひる(エストレーラ、月影)がチャーミングで、すがた香(メール夫人、成瀬・朝海)がいい落ち着きを見せた。そしてぐっと目を引いたのが、蘭香レアだ。オーロという大役で、本役の香寿と比べられては負担だろうが、見た目に稔幸を思わせるような、華やかで明るい美しさを持っている。また、ブリーザの貴咲美里が本公演のラービオス役とはうって変わったコケットリィを湛えているのが目に入った。蘭香の傍らで「誰?」と思わせたのがボールソ(貴城)で、音月桂。
というように、幕開きからのあっという間に次々と期待のスターが目に入ってきたのは、星組のWSSと同様で、早々と期待が高まった。 このような高まりは、作品を観る上で、そのベースとなるテンションを決定づけるのだから、全体の印象や評価に与える影響は大きい。多少のあらにも目をつぶろうかという気になるが、そこをあえて。
立樹遥は、歌は決して得意ではないようだ。最初はマイクの入りが悪いのかと思ったが、高音の伸びが今一つだったり、わずかに音程がずれたりする。しかし低音の響きはよかったので、音域が合えばかなり克服できるだろう。この公演が全体にテンションが高く濃密な仕上がりを見せた、その中心となれたことが、まず最大の収穫だ。
オーロがエストレーラを(彼女の首飾りを)見つめる場面、二人の美しさと、蘭香の視線の妖しさが印象的だった。蘭香は歌も特に問題なく、ダンスと姿が抜群な男役だっただけに、これからが本当に楽しみ。
紺野まひるが本公演とはうって変わってしっとりとした女性を演じたが、恋する女の目ができていたようで、安心した。中詰めでのつぶしたような発声は、本人か演出担当の勘違いか。時折しっとり感に欠けて見えたところがあったが、地で持っていなかったり出しにくかったりする要素を、どのように身につけるかが、これからの大きな課題となるのではないか。そのような要素を身につけることこそ、方法論としての技術の獲得ということであり、それが発見できた時には大化けする可能性がある。もともと弾けるような魅力を持っているのだから、あえて貪欲に多面的な魅力を手に入れてほしい。それが手に入れられなければ、役柄が限定された偏跛な、あるいは特化されたというべきか、娘役になってしまうわけで、よほどの特殊化を図らなければなるまい。
技術というと、手先、口先だけの表面的なものという印象を与えるかもしれないが、たとえば「心中・恋の大和路」で知った瀬戸内美八の七色の声が、方法論としてどれほど的確に人物造形を決定していたかということを思い返せば、少なくともプロフェッショナルを志向する以上、どのような手法を身につければどのように見え、感じてもらえるかを、鋭く追求してほしい。
オーロ神父(汐風)の未来優希、シスター・マーマ(未沙)の愛耀子も、本役に劣らず芝居巧者で、間の取り方が絶妙だった。未来は視線の使い方もよく、ブリーザが落命した後の歌も絶品で、これからの本公演でのいっそうの活躍が楽しみ。
音月は、外見の美しさだけではなかったというか、美しく見えるだけの技術を具えていたようだ。背筋の伸び方に代表されるダンスの動きには、生唾を飲み込んだ。本公演の「再会」でも、随所でシャープな動きを見せているが、次のステップが期待できる。
初めてその存在を知ったのだが、クラブ・バーバのマダム・ガートで歌った春あゆかの声の豊かさには驚いた。また、マダム・Xの珠希かほの優雅な動きも目を引いた。本公演でもホテル・ウーマンとして紺野まひるの対面でいい動きを見せていたので目に留めていた。好位置で使って、雪組娘役中堅のダンスを底上げしてほしい。
ちょっと残念だったのがマール(安蘭、朝海、成瀬)の麻愛めぐる。童顔も災いしたが、歌声の伸び、ダンスの大きさが見られなかった。この役に抜擢されたということはいいものをもっているのだろうから、その表わし方、アピールする方法を体得してほしい。
最後の「シナーマン」は全体にたいへんテンションが高く、密度の濃い素晴らしいステージだったが、タテ乗りの中で独自にビートの効いた横揺れを交え、スパイラル感のあるダイナミックなリズムをとっていて感心させられたのが、蒼海拓。人一倍の運動量だったと思うが、激しい鋭さを見せて、感動した。最近、雪組の若手男役がひじょうによく踊れているのを、いくつかのショーで続けて見せつけられていたが、なるほどこのようながむしゃらな者が何人もしのぎを削っているのだなと、たいへんうれしく頼もしく思った。
その蒼海に代表される激烈さのまま幕が降りて、あぁこれが賛否を分けたフィナーレの付かないエンディングなのかと納得した。絶頂の内に終わるという、すさまじくも潔い美学である。しばらくは何が終わったのかわからないような状態で、すさまじい重力によって金縛りか何か、座席に打ちつけられ、ただ放心していた。見ることができて、本当によかったと思った。
だから未来に挨拶をさせるのは酷ではあったが、やはりぼくたちはもう一度彼女たちの姿を目にし、感謝をこめた拍手を送りたかったのだ。新公というのは、一度限りという意味でも、まさにこの「ノバ・ボサ・ノバ」という祭りを刹那として過ぎ行かせるカリオカたちの思いにふさわしく、もう戻らない時間ではあった。
「浅茅が宿」新人公演
雪組新人公演「浅茅が宿」は、十四場の途中、まさに眞女児が「吹く秋風に……」と歌おうとする時に電源系統等に障害が起き、10分近く中断してしまった、というハプニングがあったことで、痛烈に記憶されることになる。すぐにそれは落雷のためだと知れたのだが、そう思うよりは、眞女児らの怪異の力が暴走したのだと思ったほうがよほど空気に合っていた。それほどに、この劇の世界をよく映しえた、上出来の新公だったといえよう。
注目は、新人公演初主演の檀れい(宮木、眞女児の二役。本役=月影瞳)。「Icarus」で愛田芽久と並んで重用され、貴城けいとペアを組んで、まずその美貌で目を引いていた娘役だ。
幕開き直後は緊張のあまりか声は上ずり、からだも震えていたほどで、どうなることかと思ったが、少女時代(少女期=夢奈さや。本役=紺野まひる)から転じて勝四郎(貴城。本役=轟悠)と絡むところで、いい若々しさを二人が出すあたりから、落ち着いてきたようだった。
歌は時々音程がふらつくなど、けっして得意ではないようだが、何ともいえずいい雰囲気がある。藤谷美和子の歌のような、ちょっと危なっかしい、泣きの入った感じが妙にいい。こう書くと「ファンは盲目」といった空気が流れるが。……役への入れ込み、芝居のうまさは相当なもの。銀橋下手で小川か水たまりを飛び越えるところでの表情(緊張のせいか演技か、口元が震えていたが、これがいい演技に見えるところがよかった)、勝四郎が上京を切り出したところで柏木(水谷紫乃、好演。本役=飛鳥裕)に二人の祝言をと言われたときのうれし恥ずかしの表情、変化(へんげ)の後の唇を青く引いての妖しい美しさ、時貞少将(彩吹真央。本役=汐風幸)との立ち回りの迫力、最後の桜の樹の下での立ち方の風情(背の震え)、「もう離れないよ」と勝四郎に言われた後の恐ろしいまでの空虚な表情などなど、随所で細かい演技がよく深められ、歌の難を感じさせなかった。
不安視された踊りも、問題はなかろう。丁寧な身のこなしに好感が持てた。ただ、踊りだけでなくふだんの立ち姿でも、時々首が前に出て、少々見苦しいことがある。首が前に出ると背中が曲がり、お婆さんのような格好に見えるし、さびしげに思えてしまう。もっと美しさに自信をもって堂々と胸をはっていてほしい。トップ就任を機に、ドーンと自分を押し出す強さを身につけてほしい。
本公演でりん弥を好演した貴城けいも、適役。若々しい役柄だけに、ある意味では本役よりも初々しくはまっていた。特に、都へ旅立つに際しての野心のようなギラギラしたものが、キラキラした瞳の中に仄見えたのが素晴らしい。その野心の鋭さ、若さが劇にいいテンポを与えていた。
下総の家を離れるとき、曾次郎に「振り返るな、未練が残る」と言われて、まともには振り返らないんだけれども横目でちょっと見ている感じ、いい芝居だった。眞女児と初めて偶然出会ったときの表情もすばらしい。眞女児の館で歓待を受け、盃を交わすときの二人の見交わす視線もす深い。その帰り道で空中を歩いているような感じの足の運び方にも感心。立ち回りの身のこなしも、腰の位置がすわっていて足サバキがよく、さわやかなものだった。
曽次郎(本役=香寿)の立樹遥、本公演のショーのロケットボーイで一躍ホープとしての存在を明らかにした彼女が、やはりさわやかな姿を見せてくれた。立ち姿が美しいこと、最後の立ち回りで悲愴感さえ出ていたこと、など印象に残ったシーンは多い。
陰陽師(本役=箙)の未来優希は、さすがに素晴らしい。笑い方に神秘的な魅力があった。台詞回しや声の出し方で引き方を覚えたようで、一回り役者としての幅が広がった。
蒼海拓は、堂々とした歌いぶり、男役としての風情が見せる。
りん弥(本役=貴城)は、本役ほどの彼岸感はなかったが、美しい立ち姿が際立ち、歌もよく、華やかだった。
宮木の少女時代を演じた夢奈さや、愛らしさが出ていたのと、台詞の声がきれいに出ていたこと、はじめのシーンで着物を見せられて「まあ、きれい」と言うまでの間がよかったこと、いい芝居をした。
麻樹ゆめみの身のこなしの美しさが目を引いた。
春櫻賦新人公演
1月13日、雪組新人公演「春櫻賦」を観てきました。芝居の筋がしっかりしていたこともあって、特に破綻のない、まずまずの新人公演だったと思います。きっと評判はいいでしょう。オープニングの守礼の邦、最後の春櫻賦の群舞が、よく揃って、いいアンサンブルだったと思います。
新公主役3回目となる貴城けいは、「踊りも所作事も全然できなくて」と最後のあいさつで声を詰まらせていましたが、そんなことはない。十分できてはいました。美しさについては轟に匹敵するほど上品な美しさを持っている人ですが、大きさ、激しさで迫ってくる力に乏しいのが物足りないところ。ただ、これは、本役との芸風の違いというか、かわいそうなところとも言えるでしょう。でも、前半の「海のきざはし……」の歌で少し悲哀に欠けるところ、第5場の父との別れの場面でのテンポ・間(ま)がよくないこと、鬼太鼓の踊りで腕を回した後のフィニッシュが小さい為か踊り全体が小さく見えるのが残念なところ、劇の最後の第17場で数馬を送るところのせりふの受けの間(ま)がちょっと足りなかったところなど、細かい工夫の余地はありました。新人公演にこんな細部を求めるのは酷かな。特によかったのは、第16場「津軽じょんがら」の踊りでの立ち姿の美しさ、第17場の数馬との対決の緊迫感。「真夜中のゴースト」の新公に比べれば、ずっとよくなっていたと思います。
だからこそやはり、決定的に何かが足りないような気がします……というのは、ぼくの先入観、偏見でしょうか。後述の彩吹に比べると、優等生的過ぎて、何かわからないけど惹かれてしまう……という魅力に乏しいような気がするのですが、どなたか、かしげちゃんの魅力を教えてください。
小紫(月影)の紺野まひるは、相変わらず可愛らしいはじけるような勢いのある魅力をたたえていました。せりふを言うときに腕の扱いが宙ぶらりんになってしまう点は、ほぼ克服できたと思います。日舞は、上半身の扱いは問題ないのですが、腰から背の筋が、往々にして曲がっちゃったり、そっくりかえったりしちゃうのが残念。日舞だから腰を落とすということを意識し過ぎて、小さく縮んでしまっているのかなあ。からだの中心線をすっと立てながら腰がすわっている、というのは難しいのだろうなあ……。歌には強い力があったし、最後の長台詞も、うまく芝居に乗せていました。「龍山、あなたが好きなのよー」というような、余計なせりふが加えられていましたが、演出(大野拓史)のご愛敬か、紺野の若さを配慮してか、難しいところです。いずれにしても、必要なかったとは思いますが。せりふ回しの端々に月影から学んだらしい跡が見え、新人らしいと微笑ましくも思いました。
秋月数馬(香寿たつき)の彩吹真央、前半で、刀のつかに手を掛けて龍山をにらみつけるようなところで、アゴがあがってしまって剣豪に見えないところがちょっと減点。また、薩摩屋敷で樺山を斬ってしまうシーンで、もっと狂気に近いところが出せたらなと。でも、利山の最期のところやラストの心情の吐露などの演技、せりふ回しは堂に入ったものでした。特に第10場「万朶之桜」でのソロですが、明らかに低すぎると思われる音でもちゃんと揺れずに聞かせてしまうのには、本当に驚きました。空気が震えているだけみたいになっているのに、ちゃんと伝わってくるし、それがすごくセクシーでゾクゾクするんですね。やぁ、よかった、よかった。
龍山の父、利山(汝鳥)の穂高ゆうは、星組から移って初の新公。ちょっと歩き方が元気過ぎるかなと思ったようなところはありましたが、落ち着き、貫禄があり、せりふも声の絞り方をうまく会得しているようで、安心して観ていられました。利山は後半出てこないので、踊りなど多くのシーンに出ていましたが、恵まれた身長を生かして、伸び伸びと美しく見せていたと思います。
中城安辰(安蘭)の立樹遥が美しく、風格さえ備えていたのは収穫。
喜楽坊遊三(汐風)の未来優希、ゾフィー以来と言いたいんですが、久々にたっぷりと見せてくれました。芝居巧者の汐風の役をこれだけ立派に果たしたのだから、大したものです。長いせりふが続くときに、ちょっと単調になりかかるので、引きをマスターできれば、言うことなし。日舞の群舞のシーンでも、一際美しかったように思います。
美濃(汐美)の夕貴真緒はきれいで、あの雰囲気がよく出ていました。
いろんな老け役(佐事阿母、閑古鳥、おかつ)をやらされた貴咲美里ですが、あきれるほど達者でした。
三右衛門(風早)の南帆香凛が厳しい役をよく演じきり、津軽からの再出発を誓うあたりの展開も見事。
全体に、35人と人数の少なくなった新公ですが、何度も背筋がぞくっとした、密度の高い、将来に期待の持てる公演だったと思います。既述のように、随所に間(ま)の悪さが目立ちましたが、これは半ば天性のもの、半ばは何日かやっているうちに呼吸が揃ってできるものなんでしょう。
「真夜中のゴースト」新人公演
一言でいうと、組替えとか役替わりもあって、いろいろ大変だったんだろうなあ、ということ。<学芸会>といえばあんまりだが、エリザベート新人公演の時の雪組のあの興奮はどこへ行ってしまったんだろうというのが正直なところ。新人公演担当は植田景子。
主役チャールズの貴城けい。本公演のエルドリッジ少尉で素晴らしい演技をしていた(戦場で死の間際、あのペンダントをチャールズに渡す)ので期待していたが、ここでは主役であるにもかかわらず、大きく見えなかったのが何よりも残念。轟のあの存在感(濃さ)を出すための工夫がちょっと足りなかったように思う。自分の柄に合わない役でも、どれだけやって見せるかがこの時期のチャレンジだと思うが、ちょっとお手上げという感じ。
マリー役の愛田芽久。こう言っては失礼だが、本役に、いわゆる美しさでは勝ち目が少ないのだから、思い切った工夫が必要だったのではないだろうか。ただ淡々と役をこなしてしまったという印象。目がくっきりと大きいのを生かして、もう少しうまい化粧ができないものだろうか。立ち姿にも工夫の余地あり。
エリック(TVディレクタ=和央ようか)役の汐美真帆。姿も美しく、演技も的確で、もう少し歌の声が前に出れば文句の付けどころがないのだが。スーツの着こなしといい、立ち姿といい、表情の付け方といい、安定感があり、ほぼ満足。新人公演の学年だとは思えない。それが歌になると、本人も不安があるのか、音程を探るような歌い方になっているのか、声が出てこない。歌のときにちょっと首を突き出し気味に見えるが、真っすぐにあごを引くぐらいにして、空気の流れをスムーズにしたらどうか。
ウィリアム(チャールズの弟=安蘭けい)役の夢輝のあ。最初は、かわいい顔に似合わない役でかわいそうだなあと白けていたが、悪役をうまくモノにしていたのには脱帽。芝居の90分の中で、ずんずんと悪く(人格的に)なっていく感じで、次が楽しみ。歌にも、今日一番の迫力があった。
アラベラ(貴咲美里)役の紺野まひる。このお芝居の中ではおいしい役どころだけに、中では思い切った熱演・好演の部類。いつも衣装が大きすぎるのか(本当に?)、ブカブカしたりモコモコしたり、きれいに見えないのが残念。芝居のときの腕の手持ち無沙汰、高ぶったときに目が寄ってしまう、という欠点は、ほぼ解消されたように思う。あとは、ダンスのときの裾さばきが優雅になってほしいこと。そしてスケールを大きく見せる工夫。腕の伸ばし方一つでも、ちょっとした神経の込め方でずいぶん大きく美しく見えるはずだが、まだ彼女はそれをやっていないように思う。開拓の余地がたくさんある人なので、これからの成長が楽しみ。(1997.10.7)
![]()