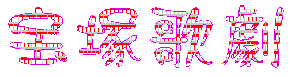
��ˉ̌��S�ʂɊւ���G�b�Z�C�ƁA��Ȃ̃����o�[�ւ̃I�}�[�W���ł�
��ȃG���J���b�W�R���T�[�g���m���X�g�b�v�ȔM�C�Ɣ������`�n���[�I�_���V���O��Young Bloods!
�������̑�\��Ɍb�܂�ā`����Ȃ珉�����z�Ƃ�����C�����ꂽ���D�`�����K�ɏo����K��
�u�����v�̖��́`�ɐD�����̗����������V���x�̃X�^�[�g�ɔ������z�ƁA�\�z����錶��
��l�̖��킢�A�Ȃ�̖��́|�ʊi�X�^�[�̑��݉��l���h���}�e�B�b�N�E�^���S�I
������W�u�����y���ނ��߂̎�̋ꌾ�v�����W�u��˂ɖ]�ނ��́v�`�l����\��˂͂��������Ă�
����������V�����^�|�ߋE�͔������@�̂Ɨ̊X�A��ˣ���j���^�J���d�J�ɂ͂܂闝�R�i�킯�j
��˂ɉ�����V�g�ƈ����|���͑P���̋����ɂ���
��ȃG���J���b�W�R���T�[�g
�@�҂��ɑ҂�����ȃG���J���b�W�R���T�[�g�A�悤�₭���ڂ����������B�����o�[�͎����Ə��Ȃ߂ŁA�e�l�����悻�l�Ȃ��̂��Ƃ��������Ղ�Ƃ����\���ƂȂ����B���ł�����̘b��́A�ԑg�匀������u�A�f���[�E�}���Z�C���v�ł̑ޒc���T�������Ƃ����ł���B�o�F�������̂́u�}�C�E���X�g�E�_���X�v�B���Z�Z�N�̃~���o�̃f�r���[�ȂŁA���y�w�Z���ナ�T�C�^�����ɍs�������ƁA�A�n�v�����ޒc�̎��ɐA�c�a�����쎌���������̂ł��邱�ƁA��������ɂ��Ă����_���X�Ƃ͈ꐶ�ǂ�Ȍ`�ł���ւ���Ă��������Ǝv���Ă���A���̉̂����݂̎������g�Əd�ˍ��킹�ĐS�����߂ĉ̂������A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ𖾂邭�W�X�ƌ���Ă��ꂽ�B�G���J���b�W�R���T�[�g�ł����x�����グ���Ă������Ȃ��A�����Ă����Ŕޏ������グ��Ƃ������Ƃɂ��āA�l�X�ȕ��ʂւ̎v�������߂āA�s���͂���������������肾�����B
�@��Ȑ��ɂ�邱�̃R���T�[�g�̖��͂̈�ɁA���̂悤�ȋȂ̊Ԃ̂��b�̏d�݁A�ʔ��݂Ƃ������Ƃ�����B�[�Ήđ�搶���悭�̂��Ă炵�āA����ȉ̂��̂���N��ɂȂ�����̂������Ǝv���Ă����Ƃ��i�݂������u�W�v�V�[�̗��́v�j�A�W���Y�{�[�J���̐������c�搶�̃��b�X���ɒʂ��Ă��āA�����̂��Ƃ�����k�o���R�[�h�Ɂu�̂Ƌ��ɐ�����V�r�����ցv�ƃT�C�����Ă�������������ł���ȏܖ��������肬��܂ʼn̂킹�Ă�����Ă��邾�Ƃ��i��㍃�uAll of Me�v)�A����ł������̂�̏d�݂����肰�Ȃ����[���A�ɕ�ݍ���Ŕ�I���Ă����B��Ȑ��Ȃ�ł͂̑��݂̏d�݂Ǝ��݂��ł���B
�@���̌��̖��͂́A���̂܂܋Ȃ̒��ɐ�������Ă���B���́u�M�w�l�v�̓`�F�[�z�t�̋Y�Ȃ��v�킹��悤�ȕi�̂���h���}��Ɖ��̂��鍂���ŕ������Ă������̂��������A�����q���w���E�~�[���u���x����uBring Him Home�v���p���ʼn̂��O�ɓ��{��Ō���Ă��ꂽ������A�w���[�c�@���g�I�x����́u������~����v�̂��Ƃ��b�́A���̌��t�����ړI�ɓ͂��Ă���悤�ŁA�܂��Ƀ��m���[�O�E�h���}�ƌĂт��郌�x���̍������̂������B�O��ɑ���������͂܂��u�z���o�̃T���g���y�v���̂������A�Ȃ�قNJm���ɂ��̒Z�������낵�����i���A����قǂ܂łɃX�P�[���̑傫�ȋȂƂ��ĕ�������͖̂��̕\���͂̋����ɂ����̂��Ɣ[��������ꂽ�B
�@�܂��A�ԑt�Ȃǂł̒Z���U�t�̃L����A�o�b�N�_���T�[�Ƃ��Ă̑��݊��̑傫���i���H���u�Z���v�j���A�ڂ���������̂������B���̉��̂��郔�B�u���[�g����ۓI�������u�t�������R�E���b�N�v�̃o�b�N�ŗx������q�A����A���̓����͉��Ƃ����݂ŁA�X�P�[���̑傫���������ɏo�Ă������A����̔M���u�W�^���E�f�E�W�^���v�̃o�b�N�����̃Z�N�V�[�ȍ��̓����ɂ̓]�N�]�N������ꂽ�B�݂Ƃ����A�u�W�v�V�[�̗��́v�ł̕G�̗h�炵���A�uLittle Boy Blue�v�̓f���̂��Ȃ��A�^�[���̃_�C�i�~�b�N���ɂ��X�P�[���̑傫�����������A�܂��Ɂu�L���O�v�i�w�m����m����V���K�[!!�x�ł̖𖼁j���ق��ӂƂ������B
�@�������̂��A���O���̑I�Ȃ̖��Ɖ̂ɍ��߂�v���̏d���A�؎����B��ꕔ�ł͒������́u���ɂȂ�v�u�F�B�̎��v���A��ł̓A���W�F���E�A�L�́u�T�N���F�v���̂����B���ʂ�e�N�j�b�N���ǂ������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����܂��̂��̂ł���悤�Ȍ��I�Ȑ��X������ттāA�������Â��ɗD�����̂������Ă��ꂽ�B���Ɂu�F�B�̎��v�́u����Ȃ����炢�ł����v�Ƃ����̎����̂��Ȃ���A�����Ǝ��L���Č��������ɂ́A�����ɑ��݂��Ă��Ȃ��A�u�F�B�v�ƌĂԑ��͂Ȃ����������v���̋����ƈ��������`�ƂȂ��Č��ꂽ�悤�ŁA��ɂ��o����悤�ȏՌ����������B�ڂ��͍�҂̒����̂��Ƃ͒m��Ȃ������̂����A������͂�W�X�ƁA�u�F�B�̎��v�͒����̏\�܍̎��̍�i�ł��邱�ƁA�����ꐫ��Q�����\�����l�ł��邱�Ƃ������Ă��ꂽ�B��˂ł͏��X����ǂ��I�Ȃ��ȂƎv��Ȃ��ł��Ȃ��������A����ȎהO�𐁂�����悤�Ȑ⏥�ł������B��́u�T�N���F�v�ł́A�X�L�b�v�ł����Ă��邩�̂悤�ɂ���₩�ɏo�Ă��āA���܂��Ƃ��A���킢���Ƃ��A�\���͂Ƃ������悤�Ȕ�]�I�Ȍ��t���ǂ����Ȃ��Ĕn���n�������Ȃ�قǁA�`���[�~���O�ŕ\��L���ȉ̐S�����ӂꂳ�����B���������l���A�����̒��ł����Ə��Ɏg���Ăق������̂��ƁA���݂��݂Ǝv��ꂽ�B
�Ό��ł����������Ƃ̂ł��Ȃ��d�݂□�킢�Ƃ������̂�����̂��낤�B���I�̃R���T�[�g�����グ�����ɂ��q�ׂ����A�~�n�̖��͂��g�����Ȃ��鉉�o�ƁA���킦��ϋq�A���̑o�����K�v�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�q�Ȃ̔M�C�Ƌ������画�f����ɁA�ϋq�̂ق��͏������[���Ǝv���̂����B�i2007�N9���j�@
![]()
�m���X�g�b�v�ȔM�C�Ɣ������`��n���[�I�_���V���O�
�@�_���X�̓��ӂȎ��Ɍ������^���悤�Ƃ�����|�Ŋ�悳�ꂽ�A����_���X�Łu�G���J���b�W�E�R���T�[�g�v�B�܂��͏o���҂̔M�C�ƌ������ɐS�ł���A��˂̃_���X�̃��x���Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ��債�����̂��ƍĔF��������ꂽ�B��H�y�Ɋςɍs�������Ƃ������������߂ł����邾�낤���A�o���҂̗x�肫�����Ƃ������������Ђ��Ђ��Ɠ`���A�M�̂��������������������Ƃ͊m�����B�G���J���b�W�E�R���T�[�g�Ɠ��l�A�����Ŋ����҂��A�匀���o�E�̌����ł�����ʂ�������Ă���̂�����ƁA���̊�悪�����X�e�b�v�ɂȂ����̂��ȂƎv���Ă��ꂵ���Ȃ�B���������@�\���ʂ����������������킯���B
�@�e�������A�ꕔ���������ē������ڂƂȂ��Ă���̂ŁA��ׂ�ꋣ�킳��錋�ʂƂȂ������Ƃ́A��������z�肳��Ă���A�����[���Ƃ��c���Ƃ�������B���Ɂu�n���[�I�^���S�v(�U�t���H�R�I���)�́u�䂪�����̃u�G�m�X�A�C���X�v�u�^���Q�[���v�ł́A�g�̂̃L����p�x�͂������A�^���S�Ƃ������̂ɑ��闝���A�p�[�g�i�[�Ƃ̊W�̎����ȂǁA�\���͂�l�X�ȓ_�ł̒��Z�A�I�ق�L�����A�̍����@���ɖ��炩�ɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ����悤�Ɏv���B
�@�܂��A���̃V���[�Y�́A���ʓI�ɕ�˂̃_���X���ǂ̂悤�ȗv�f���琬���Ă��邩���D�������Ă݂���悤�ȍ\���ƂȂ����Ƃ������邾�낤�B���_���A���_���o���G�A���e���A�^�b�v�A�^���S�A�W���Y�ƁA��{�I�ȃV���[�̑g���Ƃقړ����ŁA���̈̑�Ȃ�}���l���Y���ɂ��Ă����߂ĔF��������ꂽ�B��˂̏_��́A�l�X�ȃW�������̊O���̐U�t�Ƃ�������Ă������AKAZUMI-BOY�������Ă͂Ȃ��Ȃ��������蒅���Ă���悤�ɂ͎v���Ȃ��B����Ȓ��ŁA�ߔN�^�b�v�_���X�ɗ͂����Ď��g��ł���̂́A�����ɉ��炩�̐��Z�������Ă̂��ƂȂ̂��낤�B
�@���̌����̊��ƁA�ߔN���OG�̃_���X��O�ʂɉ����o���������������Ă��邱�Ƃ́A�����炭�����߂��V���N�����Ă���ƍl���Ă������낤�B�ڂ��������A�x��g�̂�ڂɂ��ċ�����������̂́A�悭�B�����ꂽ�g�̂������юU�点�āA���̏u�Ԃɖ���R�₵�Ă��邱�Ƃɋ����킹�邱�Ƃ��A���������M���̌������炾�B���̊����́A�����⌾�t�łȂ��A���ړI�ɓ`�����̂��B���̂��Ƃ��A��˂łȂ�iOG���܂߂āj�G���^�[�e�C�������g�Ƃ��Ė��키���Ƃ��ł���B���̋H�����Ɗϋq�ɂƂ��Ă̊�т��A��˂͂��ꂩ�����ɂ��Ăق����B�u�n���[�I�_���V���O�v�̎蔏�q��J�[�e���R�[���̔���́A�o���҂̊��̗ʂɔ�Ⴕ�Ă��A���̌������M���������悤�Ɏv�����B�܂����Ă��A�o���҂��G���J���b�W��������ł��������̂�������Ȃ��B
�y���g�z�@���̊��̑��e�Ƃ������ƂŁA��T��̂悤�ȃX�^�[�g�������Ƃ����悤�B�`���ł́A�U�t����ꂽ�������Ȃ����Ă���悤�Ȃ������Ȃ�������ꂽ�B�g�̂̊J�������s���낢�ŁA�r�̉^�тɂ�������i�̔S�肪����Ȃ��悤�Ɏv���A���g�`���̔Z�����Ɍ�����悤�Ɍ������B�܂��A���̌����̐c�ƂȂ邱�Ƃ����҂��ꂽ�ʊC�����́A�c�O�Ȃ���^���S�̎��������R���[�⋃����\������ɂ͎����Ă��Ȃ������悤�ŁA���N�I�ȎႳ���o�߂����悤�Ɏv��ꂽ�B����Ȓ��Ŗڗ������̂́A���T�����B���ꂩ��V���[�v�ȓ����ƕ\��Ŗڗ����Ă͂����̂����A��^�b�v���S��B��Ŏ��i���Љ��e���|�̎������N�₩�ŁA�������烁���o�[�S�̂�����Ə������悤�ȋC������B�ߔ����[���H���܂���̢��l�����̃_���X�`�S�͂��ࣂ��A�o�����X�̂����f���G�b�g�ŁA�ߔ��ɕЃ��t�g���ꂽ�܂܋H�����r���X���[�Y�ɏグ��^�C�~���O�A�t�H�����A�o�����X�����炵�������B
�y��g�z�@�`������S�̂ɘr��傫���g���A�S��̂��铮�����ӎ����Ă���悤�������B�^���̂���A�����Ӗ��ŃA�N�̋����������ł��Ă���̂��悩�����B���[�_�[�i��������߂��ȉ��A�g�̂̎����Ԃꂸ�A�s���ƃX�s�[�h���悭�o�Ă����B��������͍��̒��ߕ���w�̔���ɁA�g�̂̃o�l���ӎ��I�Ɏg���ă_�C�i�~�b�N�����o�����Ƃ��Ă���悤���������A�����Ƃ̃A�C�R���^�N�g��g�̂̎��̗��݂�f���̎g�����������������B�S�P��������������̃f���G�b�g���l�����̃_���X�`�R�[�C�k�[���(�U�t�����q����q)�͌�������S�ʂɉ����o���ď���ӂ����̂ŁA�����̔�������������ۂɎc�����B�S�P�͂ǂ̃W�������̃_���X�����܂����Ȃ��A�������∤�炵���ȂǗl�X�Ȗ��͂̈����o�������������Ă���悤���B
�y���g�z�@��F�t�������y�̂��ݕ��̃Z���X�̂悳�A�r���グ�鎞�̓�i���P�b�g�̂悤�Ȕ����ȃ^�C�~���O�̎����A���̓��������̔������Ȃǂ̓����̃L���͂������A�̂ł��͋������������B�^���S�̏�ʂł͎�F���P�đ����͂��߂Ƃ��āA�^���S�̃X�s���b�g��S�����A�����Ȃ肪�o���Ă����B�P�Ă̑N�₩�ȃX�e�b�v�̌�A�Q������\���Ɉڂ��Ĉ�l�X�e�[�W�Ɏc������F�̕\��̃h���}�e�B�b�N�ȕω��́A�ς�҂��l�X�Ȏv�����ʂ������ɉ������邱�Ƃ��ł���悤�ȁA�Ïk���ꂽ���ԂƂȂ����B�ԉ������u�p�b�V���l�C�g�E�_���X�v�ł��������Ƃ�����������������A���Ď闢���X�^�C���b�V���ȃi�C�X�K�C�Ԃ���I������A���ǂ��떞�_�B���g�̖����A�V�������A�^�b�v�Ń^�������ԍ����̎����̂悳��A�����Ȃ����̕\��̂����ɋ����悤�ȋP��������A�q�Ȃւ̃A�s�[���̂������ɂ����������B���l�����̃_���X�`��֣(�U�t�����q)�ł́A�������������L���ȕ\��ƈ��炵���e�p�ŁA�h���}�̐���オ����������B
�y���g�z�@�`���́uBENNY RIDES AGAIN�v�i���U�t�������_�E�w�[�o�[�}���A�U�t�A�h�o�C�U�[����Y�݂����j�ň�ۂɎc�铮���������Ă����̂��A��������B�܂��ޏ��́A���̃_���T�[�Ƃ͈قȂ鑬�x�ƍL����������Ă���B�ꌩ�A��g�ɂ������Ɠ����Ă���悤�Ɍ����A�������x���̂��Ǝv���ƁA���Y�������I�m�ŁA�x��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�g�̂̎��͂������肵�Ă��āA�u���Ȃ������グ�邱�Ƃ��ł��Ă���B�����Ĉ��ڗ������Ă���̂ł͂Ȃ��A�^����u���[�L���l��{�����A�]�T�������ē����Ă���悤���B����������������_���T�[���ł���̂��A���̌����̑�햡�ł���Ǝ���������ꂽ�B�܂��A�^���S�̏�ʂŕ��̑傫�����o�������P��l�A�݂��Ƃȉ̐�����������܂�ȁA�H��܂ȁA�u�p�^�p�^�v�ł��������Ƃ����\��Ɠ��������������T�䂩���ڗ������B�uWEST SIDE STORY�v���v�킹���\���uOver The Rainbow�v(�U�t���ɉ�T�q)�́A�S�̂ɃV���[�v���ƃX�s�[�h���ɂ��ӂ�Ă��āA�F�̌����ȑ�����������C�������悭�\�킵�Ă����B�����Č��s�������ꂽ�悤�Ȃ����\������Ă����B���l�����̃_���X�`�^�����e���|�߈��(�U�t���H�R)�́A��������Nj������悤�ȃf���G�b�g�_���X�B��S���́A�ŏ��̓o���G�e�N�j�b�N�ɏG�ł��_���T�[�Ǝv��ꂽ���A���X�Ɋ���̗����h���g�̂ɒ��ړI�ɕ\�������_���������A�S�C����悤�ȃV�[���ƂȂ����B�F���D�Ƃ̃R���^�N�g���Ԃ��肠���悤�Ɍ������A�H��̃J�Q�\�����������������A�M�����䂾�����B
�y�ԑg�z�@��ˋ��w�̃_���T�[����̂ǂ����A��������Ď��ɏ�ʂ�����Ȃ���A�̖̂��͂����X�Ɣ������A�������ɉ��ƔS��̂��铮���A�I�m�ȃ^�C�~���O�ŋq�Ȃ𖣗������B�����̏�ʂ����������X���݉������F�ɉ����Ď��͂��J�Ԃ������B���Ɏ��̓�����r�̕Ԃ����������A���J�ɐg�̂̊O�����ӎ����ĉ������Ƃ��ł��Ă����B�����炭���̂��߂��낤���A�Ɠ��̕��V��������B�w���P�x����ߌ��̃q���C���������Ă��邪�A�z���̉₩�����������B�M������悩�����̂́A�܂��x�邱�ƁA�̂����Ƃ̊�т��_�C���N�g�ɓ`����Ă������ƁB�����ɍL���肪����A�������͗܂��܂����قǂ������B�،��R���̓������_�C�i�~�b�N�ŁA�̂������O�ɏo���Ă����̂������B�^���S�������������̃X�e�b�v�����ɔ����������B�����W���A�R���f�B�Z���X�̂��炵�������łȂ��A��Ԃ�ȓ����̃V���[�v���𑶕��Ɍ����Ă����̂��悩�����B�i2007�N�j
![]()
Young Bloods!!
���g�@Sparkling MOON
�@�V���uYoung Bloods!!�v�̑��e�͌��g�́wSparkling MOON�x�B�剉�͐V�l�����ł�����o���̂Ȃ����^���A�\���E���o�̓�����ɂ��u���ό�3.2�v��15�l�����o�����Ȃ��Ƃ�������A�`���Ƃ�������Ȗ`��������܂��B�����Ɍ����āA���I����đ��̊��z�́A�����4500�~�́A���܂�ɍ�������A�Ƃ����R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɑ��Ă̂��́B�J���[�^�Q�F��6�y�[�W�̃v���O�����������z�z���ꂽ�Ƃ͂����A�g�̏��g�b�v���剉���ē�\�������o��o�E�����Ɠ����l�i�Ƃ����̂́A������Ɣ[�����ɂ����B
�@�\���E���o�͓�����������A�O���̎ŋ��u�n�[�t���[�����z�ȁv�́A���̑啔�����߂�Q�[���̂����݂��킩��ɂ����A�������ݒ��q�x�t�i���^���j�Ƃq�d�l�h�i������j�̎Ⴂ���l�����̂킪�܂܂Ԃ肪�ڂɗ]��悤�ȂƂ���������āA������Ɨ���ɓ��荞�݂ɂ��������B�Q�[���ւ̓���������˂ŁA�ϋq�ɂƂ��Ă͂��u���Ă��ڂ��H���Ă��܂����悤�ȑa�O�����������悤�Ɏv���B�����̗��l���{���ɋ�ʂł��邩�Ƃ����₢��������A������M����Ƃ��ڂɌ�������̂�������Ȃ��Ƃ��A�l���̓Q�[���A�Ƃ��������P�߂������_���㖡�������B
�@���͉̂��_���X�����Z���B�҂Ńe���|���悭�A���b�N�X�������܂ŃL���[�g�A�ǂ�ǂ�t�@���������Ă������낤�Ǝv����B���ʂ̂���������_���X�ɓ����Ă����Ƃ��́A�ӂƂ������������̓������Ђ��傤�ɖ��͓I�Ȃ̂��ڂ��������B�V���[�uHot Blooded Moon�v�ł��A�����V���E�g��N�[���ȕ\��Œj�炵�����������Ȃ���A�_���X�̃Z���X�̂悳���������B
�@�ڗ������̂��}���}���i�����Ђ܂��j�ƃv�b�`�i�����邤�j�̓�l�B�����͗ʊ��̂��鐺�ŏ�ʂ���߂����A�����̓Z���t���������肵�Ă��Č��̃e���|�����Ă���B�~�X�����C�i���P�����j�A�~�X�^�[�v���C�i�����������j�Ƃ����̂��A���̃Q�[���̎d�|�l�B�����̓V���[���܂߂ĂȂ��Ȃ��a�����Ŗ��͂����Ă����B���P�͓����̏��Ȃ��A�ј\�̂悤�ȑ��݊��������Ȃ�������Ȃ����������̂��낤���A������Ɩ������܂��邫�������������Ă��܂����悤�ŁA���ɏ㊊�肵���悤�Ȋ�������B�V���[�ł̒������ǂ���uBlackbird�v���A���Ƃ������ƃL���[�g���Z�N�V�[�ɂ��Ă݂�Ƃ��A�������E�������������������߂������悩�����悤�Ɏv���B�_���X�̃L�����悭�A�̂��n���̖��͂��ł��Ă����̂ŁA������H�v�Ŗ��͂��{������̂ł͂Ȃ����B
�@���z�̒j�E���z�̏��A�Ƃ������𖼂�����������P��l�A�G�Ԃ�肠�A���������������ɓO���邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ��������̂��낤���A�N�₩�ȗ����p�ŁA�q�x�t�Ƃq�d�l�h�����f����ɂӂ��킵�������B�����G���͏�i�Ȋ痧���ƃo�����X�̂悢�X�^�C�����������B���Z�ł͂������_���X�̍ו��ł̕\��L���ŁA�o���G�̃V�[���ł̋p�����������A�ЂƂ���ڂ��������B
�@�V���[�̃o���G�̃V�[���́A�������F�悭�x��Ă������A���t�g�ɍ���y�����╂�V�����Ȃ������̂́A�j���Ƃ̃^�C�~���O�̂������B�u�C�[�X�g�C���f�B�A���_���X�v�i�I���W�i���U�t���W���b�N�E�R�[���A�U�t���P���W�����j�́A���ɂ����邪����₩�ȉ��𗧂Ă�̂��y������i�B�N�[���ȕ\��A��ׂ̍��ȓ����A�o�N�]���܂߂��傫�ȏ㉺�̓����ȂǁA���𒆐S�ɓ���������悭�܂Ƃ߂��B�����t�H�b�V�[�́u�X�`�[���q�[�g�v�́A�����A���P�����S�ƂȂ����͉��A�G���̃A�s�[�����`���[�~���O�Ŗڗ������B�q�Ȃ���o�ꂵ�����ɂ��\���u�I�[���U�b�g�W���Y�v�́A���̃X�P�[���̑傫�����o���Ă����̂������B���������̋Ȃɂ��u���B�[�i�X�a���v�́A���������̌y�₩�����Ђ��傤�ɐV�N�ŁA���̌�́u���E�N���p���V�[�^�v�Ƃ̑ΏƂ��o�����̂��D���o�B�������P���������\��Ń^���S�̖��Ȃ��悭�x�肫�����B�P���W�����̍Ō�̃s�[�X�uFACADE�v�́A���߂̒��Ɉ�l�����G���W�ŗ��R���g���X�g���������A�N�[���Ń~�X�e���A�X�ȃh���}���n�܂�悤�ȍV�g��������ꂽ�B���̃V���E�g�ɗ͂�����A���P�A���P�̉̂��������B
�@�����S�̂̃o�����X�Ƃ��ẮA�l�������Ȃ��̂͂������Ȃ����A���������R�[���X����������Ƃ��A���̃��X�g�̃\���uYoung Bloods�v�ł̓o�b�N�_���T�[�����ĕ���ɉ��߂�����Ȃǂ����ق����悩�����悤�Ɏv���B����ł��A����܂ŊςĂ����O�g�̒��ŁA�P���W�����̃t�H�b�V�[��i�̕��͋C����Ԃ���ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����炭��ԎႢ�����o�[�ɂ��������낤���A���݂��������Ȃ������͎̂c�O�Ƃ͂����A������X�s�[�h�͑傢�ɓ`����Ă����B���������o�[�ɂ͂����o���ɂȂ����������낤�A����̔������҂������B
�ԑg
�@���́wYong Bloods!!�x�Ƃ����V���[�Y���́A�P�Ƃ̃`���V��|�X�^�[���Ȃ��̂ŁA�ǂ�ȓ��e�̌����Ȃ̂��Ƃ������́A�ϋɓI�Ɏ��W���Ȃ��Ɠ����Ă��Ȃ��B�ڂ��������ӑĂȂ�����������Ȃ����A������ː����������������y���݂��ȂƂ����v���ĐȂɒ����A���Ȃɒu���Ă���v���O���������āA�{�{�����Ƃ������Ƃ́A���{���H�ƋC�Â����ƂɂȂ����B
�@�������\���E���o���V���g���́A�����̓��{���ɂ͂����A�{�{�������{���͉��a�Ȍv���ƂŁA���X�؏����Y�Ƃ̌����O��畏����Ă����Ƃ��돬�M�����Ɋ������܂�A�����Ƌ��Ɍ���̍��Z�A�������������Ƀ^�C���X���b�v���Ă���A�Ƃ����w���R���f�B�Ɏd���Ă��B�Ȃ��A�����Ń^�C���X���b�v������j��̗L���l���i�����������j�Ƃ����ݒ�́A��q���̏����w�N�̖��c���x���t���܂Ɏؗp�����Ƃ����Ă������x���Ȃ����낤�B
�@���̉����Ԃ�Ŗڂ��������̂��A�����Y�i����̃V�[���ł̓R�W���[�j�������W�B�������X���b�v���Ă��������w���������̏h�G�A�����w�@�������̃G�[�X�ŁA�A���q�������������̑��q�����A�Ƃɂ����C�P�D���Ȃ��z�Ƃ����ݒ�̖����A���ɂ���炵�������������̂́A�Ȃ��Ȃ��̂��̂������B
�@�ː��́A���̘r�O�͖{���̂Ƃ��둽���S���ƂȂ������Ƃ����l�����A����ӂ�ď�Ȃ��A�����������đ��߂Ȃ��D�l���Ƃ��ĉ����ʂ����B�����Ƃ��ẴJ�b�R�C�C�\����������A���́c�Ƃ����C�P�e�Ȃ��g�z�z�Ȏp���A����ł��Ђ��ނ��Ɏ����ɗՂގp�A�ӂƐl�̓��̂悤�Ȍ��t���k�炷�\��A�X�[�q�i�Y�T�������j�Ɍ������R�W���[�ɕ��𗧂Ă��|�߂鐳�`���Ԃ�A�Ȃǂ������̖ʂ��y���߂��̂͂悩�����B�ǂ�Ȗʂ������Ă��A�ϋq�̎��ڂ�������z���̖��͂������Ă���̂����炵���B�ŋ��A�́A�_���X�A�����Ƃ��Ă��Z�p�I�ɂ͉��̖����Ȃ����A�ŋ��ł͎�ɃR�~�J���Ȗʂ��A�V���[�ł̓_���f�B�ȕ������⊶�Ȃ������ł����̂́A�悩�����B
�@�w���R���f�B�Ƃ������ƂŁA�����܂�̏��q���������̓o��B�܂��������L���v�e���̃X�[�q�i�Y�T�j�����A�D�����^�C�v�̉��Z�͂��Ȃ��A���������ӂ��̂ɂ͋��������͂�����B�Z�[���[���p�͂�����ƃA�j���̃q���C����t�B�M���A���ۂ��o�[�`�����Ȗ��͂�����A��˂̒��ɕ����߂Ă����̂͂�����Ƃ��������Ȃ��C�������قǁB���^�ȃZ�[���[���A��肵���������A�ƃr�W���A���ł��G���n�Ƃ�����ł��낤�悤�ȃc�{���������Ă��āA���o�Ƃ̂���ł��傤���A�Ǝv���Ȃ����Ȃ����A�t�B�N�V���i���Ȑݒ�̕���̒��ł̃��A���e�B�Ƃ����Ӗ��ŁA����肪�悩�����Ƃ������邾�낤�B���Z�ł́A��������͂茳�̎���ɖ߂�Ƃ�����ʂł̐؎����͌������B
�@�����������^�ȃq���C��������ƁA������l�͗��q���C���Ƃ��āA�_�[�e�B�Ȗ��ǂ���������ƂɂȂ�B�����ŃX�J�[�g�������ĕs�o�Z�ŃX�P�ԂŃ��[���[�܂ł����A�s�Ǐ��q�����̃X�e���I�^�C�v����g�ɏW�߂��悤�Ȗ����K�v�ɂȂ��āA���ꂪ�W�����i�Ԗ삶��肠�j�B���́A�C��ɂȂ镐����E�C�Â�����n�b�p����������A��������������ɗY�X�����ɗ��������������̎p�ɋt�ɗE�C�Â����čX�����A�Ō�͐��^�ŃL���[�g�Ȏp�Ō����A�Ƃ����U���̑傫�Ȗ��ǂ���B�Ԗ�͓˂����������Z�����݂��݂Ƃ����鉉�Z�����킢���p�������Ȃ����������Ă��Ȃ��Ă��āA���S���Č��Ă�����B�V���[�ł́A�ȑO���璍�ڂ��Ă����_���X�͂������A�̂ł��t�F�~�j���Ȗ��͂𑶕��ɔ������A����܂��Y�T�Ƃ͏�����ނ̈قȂ�A�C�h������U��܂����B
�@���̓�l�ɑ��āA�ː��Ɠ���������̂ǂ����A�I�[���h�~�X�̋��t���ŁA�R�~�J���Ƀo�^�o�^�������Z��ʂ��A����U�����̂ɂ͋������ꂽ�B�������V���[�ł͈�]���ăL���ƗD�낳�����킹�������_���X�����\�����Ă��ꂽ�킯�ŁA�g�ւ��ƂȂ�ː��ƃy�A�̃_���X�������Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ȃ�̂��Ђ��傤�Ɏc�O�Ɏv��ꂽ�B
�@���ɂ́A�����������i�G�q�j��������Ɣ]�V�C�ȏ��q�������D���B�]�k�����A�wYoung Bloods!!�x�́A�ŋ��̖𖼂��|���∤�̂������������̂ɂȂ��Ă���A�ϋq���o���₷���悤�ɂł��Ă��ď�����B
�@���̂悤�ɁA����܂ŎO�g���Ă����wYoung
Bloods!!�x�̒��ł́A�A�C�h�������܂߂������̃��x���̍�����傢�Ɋy���߂���i�ƂȂ������A����������o�[�S�̂Ƀ_���X�̃��x�������ɍ����������Ƃ��ςĂ��Ċy���������B�ː��A����Ƃ����_���X���[�_�[�ɗ������āA�����ɓ�����邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ��������̂��낤���A�A�b�v�e���|�ȃX�g���[�g�n�̓��������Ƀs�b�^���Ƃ͂܂��Ă����̂́A�������ɎႢ����̌����ł��邱�Ƃ������������B�܂��A�����[���炢���͂��ߎ��j���̉̂����x���������A�ԑg�̑w�̌�����m�邱�Ƃ��ł����B
���g�@Twinkle Twinkle
STAR
�@�wYoung Bloods!!�x���O�g�ڂɂȂ�ƁA���̑_���⊨�ǂ��낪���ƂȂ��킩���Ă���悤�Ɏv����B���������Ă��܂��Ă����̂��ǂ����킩��Ȃ����A�ے�I�ɂƂ炦��A�剉�̈�l���ɂł��X�^�[�ł���Ƃ����ӂ��ɂ܂肠���āA���Ƃ̏\�����ɂƂ��Ă͂��m�Â̋@��Ƃ����悤�Ȉʒu�Â��B�N�[���Ɍ����A��˂��ǂ̂悤�ɃX�^�[�Ƃ������݂�グ�邱�Ƃ��ł���̂��Ƃ����V�X�e�����̂��̂��͂�����ƌ����Ă����悤�Ȏd�|���̃��[�N�V���b�v�ł�����B
�@���������g�́wTwinkle Twinkle STAR�x�́A���ɑ傫�Ȗ������߂�̂ɉ��̕s�����Ȃ��M��特���剉�̃`�F�����J�߂������ɁA�M��̖��͂Ƒ��݊��Ɋւ��ẮA���ɕs����^������K�v�͂Ȃ������B�ނ���A�M���Ȃ��V�[���ő��̎҂���������ɂǂꂾ���ْ������������邱�Ƃ��ł��邩�A������̖����̒��ɁA�ǂꂾ���L�]�Ȏ҂��������邩�A���e�[�}�Ƃ��ăo�E�z�[���ɑ����^�Ԃ��ƂɂȂ�B��͂�V���[�ł́A�M��̏o�Ȃ��V�[���ŁA������Əꂪ�����Ȃ��悤�Ȉ�ۂ��Ă��܂����B
�@�M���̖��͈͂��|�I�������B�_���X�A�́A���Z�A���݊��A���ׂĂɂ킽���āA��l�œԗ]�̕���Ɋϋq���������Ă����B�L���ȕ\���͂Ɉ�w�̖������������Ă���B����͂����Ă����q�ׂ邾���ɂƂǂ߂Ă��܂����B�����傫�ȕ���ŁA�����Ƒ傫�Ȗ��Ō������B
�@�����ōł��傫�Ȗ��ǂ�����̂́A���I�̑受�D�E�~�[�V�����ؔ��䂤���B�����炭�y��_�ł͂���̂��낤���A�M��ɔ�r����A�V���[�̐��E�ł��̐�y�i�ɓ�����受�D�Ƃ����ݒ�ɂ́A���������������������ƌ��킴��Ȃ��B���ʓI�Ƀ_���X�ɂ��]�T���Ȃ��悤�Ɍ����Ă��܂����̂͋C�̓ŁB�����A���ς�V���[�̔��^�Ȃǂ����Ă���ƁA�����������̂悤�ȑ傫�ȃ`�����X���̂�����A�����Ǝ�������������͓I�Ɍ����邽�߂̍H�v��w�͂�����]�n�͂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���镔�����������͎̂c�O���B
�@���Ԃ���́A�|�\�������̎В����ŁA���[�����X�ȉ��Z���܂߂ĂȂ��Ȃ��̎ŋ��I�҂Ԃ�����������A������ƍd�����Ƃ�Ȃ��悤�������̂��ɂ����B�̂��\�����܂��̂͂킩��̂����A�d�����������ɂȂ��āA�����Ƃ��ĕ������Ă��܂��Ƃ��낪����悤�Ɏv�����B�X�y�C�����痈���O�l�̎Ⴂ�_���T�[�����炩���Ă��鎞�ɂ͂ӂ�����Ɨ]�T�̂��邢�����Z�������������ɁA�c�O�������B
�@�d�v�Ȗ��ł͂��������o�Ԃ�����������Ȃ������̂��ȁE�m�m�[�V�����Ԃ̂̂��B�a��ŁA�����y���y���̃����s�[�X�𒅂Ă���Ƃ������ŁA�e�̔����������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A������C�̓łȖ��ǂ���B�t�ɈĊO�ڗ������̂��_���T�[�̗��ƌ����������A�i���L�A�����Ԃ܂���B�h��ł͂Ȃ����A�Ђ��ނ����̂悤�Ȃ��̂��o�Ă����B
�@���̌����Ŗ����̔����Ƃ����A�M��ƃo���G�u�h���E�L�z�[�e�v��x�����}���������H���܂���B�܂����c��N�ڂƂ�������A�唲�F�ƌ����悤�B�u�h���E�L�z�[�e�v�̃q���C�����ł���L�g���Ƃ����|���������炢������A�o���G�ɒ����Ă���̂͂Ȃ�قǂƔ[���ł������A�V���[�ŋ��̕��ɂ��Ă����邢�\��Ől�̖ڂ���������₩���������Ă���B�Z���t�̊ԍ����Ȃǂ܂��܂������ׂ��_�͂��邾�낤���A�v���Ԃ�ɉ₩�����������������������B
�@�j���œ�Ԏ�i�ƂȂ����̂́A�ʊC�����B�����I�Ȗ��ǂ���ŏo�Ԃ�������������A�����o���ɂȂ������Ƃ��낤�B�ޏ��̈ꐺ�Ŏŋ����n�܂�A�_���T�[�Ƃ́A�Ƃ�����ۓI�Ȑ����Z���t�ɓ���A�̂��n�߂�Ƃ����A�܂��Ɏŋ���]�������ǂ���ŁA��������̂̏�B�Ԃ�������邱�Ƃ��ł����B�����̑傫����������̂͂܂��܂����B�g�̂������Ƃ��Ɏl���������ƐL�т�悤�ȃ_�C�i�~�b�N����g�ɂ��Ăق����Ƃ���B
�@�j���̔����Ƃ����A��͂���c��N�ڂ��V�������B�ŋ��ł̓`�F�����J�̑��q�E�~�N���t�Ƃ����āA�q���炵�����ǂ��Ȃ��₯�Ȃ��������܂����������Ƃ������x���������A�V���[�ł͓�N�ڂƎv���Ȃ��قǁA�j���̐��A���X�Ɖ₩�Ȃ������ŋ������͂�U��܂��Ă����̂ɂ́A�������B���ɒ���Ɖ��̂��鐺�������B�\����L���Ŏ���������������̂�����悤�����A�����ł���ɃL����������ꂽ��A���܂葁������ߓx�̊��҂���̂͂悭�Ȃ���������Ȃ����A�����q�����낤�X�^�[�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�@����ē̃A�Y�i��邠�����j��v���f���[�T�[�̃J�[�}���i�����F�C�j���A�茘�����Z���������B��������́A�ŋ��̃��X�g�ŕ�Ɉ₳�ꂽ�~�N���t��A��ė���Ƃ��������������A�������D�����A��̂��鉉�Z���ł����̂́A�傫�Ȏ��n���������낤�B
![]()
�������̑�\��Ɍb�܂�ā`����Ȃ珉����
�@�Ƃ��Ƃ���������߂�B���̂��Ƃɂ��Ċ��S��[������l�͑������낤�B��͐V�E��Ȃ̂�����i���邢�͂Ȃ��Ȃ���j�ɂ��Ă̎v���ŁA����ɂ��Ă͑��̐l���l�X�Ȋp�x����l�@�A���͂��Ă���邾�낤����A�����Č���Ȃ��ł������B
�@�����ɂ��ẮA�̂�_���X�≉�Z�̖��͂���������A�l���̂悳�A�����܂ł����Ӗ��ł̃N���o�[���ɂ��Č���邱�Ƃ������B�匀��ł̃T���i���̈��A���A�Ђ��傤�ɂ悭��������ӂ�s���������̂ŁA�����������炠�ӂ�Ă�����̂����炦�Ȃ���́A�f���炵�����̂������B�l�I�ɂ��܂��ܒm�荇�����A�����ȃz�[���Ń_���X�����̃{�����e�B�A�X�^�b�t�����Ă������j���̏����́A�ޒc��������̏o�镑�䂾���͂��ׂĊςĂ���悤���������A�����ɂ́u�Ƃɂ����A�₳�����Đe�ł������悭�Đe�g�œ����悭�āv�c�c�ƌ��t�����������Ă�����Ȃ����炢�̐S���Ԃ肾�����B
�@�u�l���̂悳�v������l�ɂƂ��ăv���X���}�C�i�X���A�ȂǂƂ����₢���́A���������Ȑ���ςɂƂ���Ă���悤�Ɏv���邪�A�����̏ꍇ�A���ꂪ���̂悳�Ƒ��܂��āA�^����ꂽ���ւ̊����͂��[�܂邱�ƂŁA����ɑ傫���v���X�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B���ꂪ�ޏ��̖��Â���̕��̍L���ł���A�ǂ�Ȗ��ł���������Ǝv�킹�����̐[���������B�@
�@�v���A�P�K���畜�A������̈ɐD�����Ƃ̃_�u���剉��w�N�ɗ����ă��r�����X�x�i���㎵�N�j�̃��f�B�[�͖��邭�����҂̍D�N�A���̎��e���Œ��C�Ђ��邪���������ȑ��݊����o���Ă����̂��A�u���̊�������B���g�Ɉڂ��āwEl Dorado�x�ł́A�}�������Z�ŕ��G�ȐS����\�����������E�K���V�A���D���B���̍�����A�ޏ��̒ቹ�̖��́A�j�q���ȕ\��A�甼���̏��ɏ��X�ɂЂ����悤�ɂȂ������Ƃ��v���o���B
�@���N�́wWEST SIDE STORY�x�́A�������̃A�j�^�����������������A�����̃��t���W�F�b�g�c�̌����[�_�[�Ƃ��āA�����đ啿�ł͂Ȃ��̂ɂ�������Ƃ������[�_�[�V�b�v����������A�g�j�[�i�^�Ղ��j�̑O�ł͒핪�炵�����Ȏp����������A���ʂȖ��͂������B���ȁu�b�������v�̎n�܂�̂����ꂽ�悤�ȏ����̖��͂��܂߁A�M���������B�w�������x�̃V���@�[�u�����ő��܂���Ƃ��Ă̗v�f���o�������Ƃ����邩������Ȃ��B�l�����n���ɂ��ĕ@�ŏ��悤�ȕ\��A�����̗₽���A�h�X�̌������Ⴂ���A���錫�����܂߂��v�Z�������ǂ���A������ȂǂȂǁB
�@�����āA�P�Ǝ���͈ӊO�ɒx���������A�����܂ł̘H���Ƃ͂����ĕς�����悤�ȓO��I�Ȋ쌀�A�w���瑛���x�i�����N�j�B����͂����̂��܂���A����܂���̃W�F�b�g�R�[�X�^�[�̂悤�Ȋ쌀�ŁA���̑��x�������Ƃ��č��グ�邱�Ƃ��ł����̂�����A�|�B�҂Ԃ�A���[�_�[�V�b�v���債�����̂��Ǝv�킹���B������A���S��A����喲�A���쓵��̍D�����A�ꃖ���ł����ꂽ�炷�ׂĂ����ɋA���Ă��܂������ȃA���T���u�����A�悭�܂Ƃߏグ���Ƃ����邾�낤�B���N���́w�v�����@���X�̕ɂ���x�ł��t�B���b�v�Ƃ���������D������B
�@���ɂ��̂�����ŁA���ɔ������������������Ȃ���I�[�����E���h�v���C���[�Ƃ��ďd�v�Ȓn�ʂ��m�����Ă������������A�����̓g�b�v�H���Ȃ̂��ǂ����Ƃ����_�ł́A�����ȂƂ���ɗ�������Ă����̂�������Ȃ��B�ǂ�Ȗ��ł��茘�����Ȃ��A�d�v�Șe���������Ă��Ă����B�^�Ղ��g�b�v�ɒu���A�����ɑ����O�Ԏ�i�����A���ɂ͑�a�I�́A����喲�A���S��Ɛl�C�����͂����ꂼ����F���������L�]�����T���Ă���B����Ȓ��ŏ����́A���X�ɎO���q��������ŋ��I�҂Ƃ����ʒu�ɒ�܂��Ă����悤�ȕ����ɂȂ��Ă����̂��낤���B
�@�����Đ�Ȃւ̈ٓ��B�g����͎����Ɠ�l�B���g�w�Ԃ̋ƕ��x(��Z�Z��N)�̈��{���s�́A���K�̋ƕ����T�|�[�g���闧��Ŏ����Ȕ����𑶕��ɔ��������B�w�K���X�̕��i�x�w�����̈�ȁx(��Z�Z�O�N)���o�āA�����炭�w�X�T�m�I�x(��Z�Z�l�N)�̃A�}�e���X�I�I�~�J�~���A�܂���\��̈�Ƃ����邾�낤�B����菉���̃X�P�[���̑傫�����h���}�̐c�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��ؖ����������ƂȂ����B���N�́w�G���U�x�[�g�x�̃t�����c�E���[�[�t�́A�����ׂ̍₩�ɏ��s�������m�[�u�����������ꂽ�A��̋ɓ_�ł���A�T���i�������ƂȂ����w���Ɍ��Â����x�̃��[�i���݂́A�������̋ɓ_�������B���ʓI�ɂ͍Ō�̎O��i�ł܂��ɑ�\��ƌĂԂɂӂ��킵���l�X�Ȗ�������ꂽ�̂́A�{�l�ɂƂ��Ă��ڂ������ɂƂ��Ă��{���ɍK���Ȃ��Ƃ������B
�@�ł���Ō�Ƀo�E�����łł��A�����̃X�P�[���̑傫�Ȕ����������Ă݂����������A�g�b�v�ɂȂ�Ȃ������j���̍Ō�Ƃ��ẮA��˂Ⓦ��̑�K�i�������ӂ��킵���A���̎p�������قɂƂǂ߂Ă��������̂�������Ȃ��B������t�ő�K�i������Ă���p�ɁA�����ߏւɐg���݊K�i�̏�Ŏ���L����A�}�e���X�I�I�~�J�~�̎p���d�Ȃ����肷��A�����̔����p�������p���A���ׂĂ������ɏW�ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�{�e�ł͂����ď������P�K���畜�A�����ォ��̑��Ղ����ǂ��Ă݂��B���̓E�F�u�����܂���Ă��āA�ł���ۂɎc���Ă���̂��A�u�T���P�C�X�|�[�c�v�̃T�C�g�œǂA����G�q���Љ�Ă���G�s�\�[�h���B���㎵�N�A�Z���̌̏�œ]���A�]�����܂Ȃǂ̏d�����������́A�ꃖ�������@����B�u���@���A�ԃC�X�Ő擪��鏉���̌�ɑ��̊��҂������g�J���K����y���h���ł����B�c�c�u�F������������ɗ��Ă��������ł��B���ł���Ԓ������t���������Ă��邨�����܂́A���̕���������������w���C�ɂȂ�����x���ď�Ȃ��ŕ�����ł��ˁB���̎p������ƁA�������Ŋ撣���Ă���Ӗ�������Ȃ��Ďv�����ł��v�v�ƁA�~�܂�Ȃ����炢�̐����Řb���Ă����Ƃ����B�Ȃ��ڂ����ޒc��̏����̊����ǂ������āA�J���K���݂����Ɉ��炵���͂Ȃ��ɂ���A�j�R�j�R���Ȃ��猀��Ɍ��������ƂɂȂ肻�����B�i2005�N�ޒc�j
�z�Ƃ�����C�����ꂽ���D�`�����K�ɏo����K��
�����K�������������̂́A�Љ��m���q��̖�������Ƃ������Ƃ���A���{���͂������ɂ��܂���˂Ƃ�������ς�������Ȃ���A����͂�����Ɩ��������A����ȏ�̑��݊��̋����������ĕ�������͂������Ă������Ƃ��B
���܂����邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ����A�ޏ��̓����͍ו��܂Ŕz�����s���͂��Ă����ɁA���R�ŏ_�炩�ȋȐ���`�����Ƃ��ł��Ă����B�ꌩ��p�Ȗ��҂Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������������������Ȃ����A��������͂܂�A�����͎��݂Ŗ��͓I�������B���߂Č����܂ł��Ȃ����낤���A���ɓ��{���ł́A���̓������Ƃ��Ă��A�����҂Ƃ͂�����Ǝ���������Ă����B���Ƃ��u�Ԃ̕��y�L�v�ʼn��߂ċC�Â����̂����A��l�ޏ��͐g�̂̐c�Ƃ��Ă̍��̈ʒu����܂��Ă����B�����炻������Ƃ��đ��̉^�т���̂̓��������݂Ɏ�邱�Ƃ��ł��A�D��Ŕ������A���݂̂Ȃ��o�����X���l�����邱�Ƃ��ł��Ă����B�ꌾ�ł����u���܂�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�ߔN���Ƃɓ��{���ł͂��̂悤�Ɂu���܂����v�Ǝv�킹�铮���̂ł�����҂͏��Ȃ��A�Ђ��傤�ɋM�d�ȑ��݂������B
�u�S���E���̑�a�H�v�i���㔪�N�j���f���炵�������̂́A���������ޏ����̕���ɍނ��Ƃ������{���Ŏ剉����̂�����A���̌������炢���Ă��������炢���Ă��A���R�����ƂȂ邾�낤�Ƃ������҂����邾���̃h���}�̐[����\��������Ă������炾�B���ɍ��ł��L���Ɏc���Ă���̂́A����̏�ʁB���̏�ʂ͂��̌��̒��ł��ˏo���āu�`���|�\�I�v�ł͂Ȃ��Ƃ��낾�Ƃ�������B�Ɩ��≹�y�̈������炢���Ă��A���Ȃ�P�����I�ȗv�f�̋�����ʂ��������A�����Ŕޏ��͈��̕��V���Ƃ��Ăׂ�悤�ȋ�������\�����A�����̂��ɖ|�M����Ă��܂����݂̎コ�ƁA���̗����̖��͂��⊶�Ȃ����������B
�ޏ��̂����������̂́A�����q�Ƃ����j�̂ǂ����悤���Ȃ�����������ƕ\���ł��āA�Ђ��傤�ɖ��͓I�ł������Ƃ����A�ߏ���������ł��낤�ʂ�̐l�ԑ���\�o�����Ă����Ƃ���ɂ���B�u�����ځv�{���{���ł��S�͂����Ɓu�ځv�Ƃ́A�Γc���炪�u�₿���̗��v�i����Z�N�j�̃��X�ɂ��Č�����I�m�ŊȌ��ȕ]�������i�u�̌��v�������j�A����͒����q�ւƒ������鑜�ł��������B�ߏ��ɂ��Ă����ɂ��Ă��A���܂��Ă��邪�䂦�̐l�Ԃ̔��_��]���Ƃ���Ȃ��`�������玞��z������͂�����������Ƃ����A�r�F����Ă���Ƃ͂����A��ˍݒc���ɂ��̂悤�ȈِF��ɕ����b�܂ꂽ�̂́A�^�Ǝ��͂̑o�������˔����Ă��Ȃ���A���肦�Ȃ������͂����B
�����u�T���i���v���e���������тɁA���̂悤�ȉߋ��`�Ō�邱�Ƃɂ�邹�Ȃ��v��������̂����A�S�c�肪����������B��́A�ޏ��̎剉�삪���́u�S���E���̑�a�H�v�ōŌ�ɂȂ��Ă��܂������ƂŁA���ꂪ���ƂȂ��Ă͕s�v�c�ł�����A�c�O�ł�����B�m���ɔޏ��͓G����a���e�����݂��Ƃɉ������閼�e���Ƃ����ʒu�ǂ�ŁA���̖��͂����鑶�݂ł͂������B�������A����������ȂƂ������R�ȏ����ɂȂ����̂�����A�ޏ�����˂ɂ���Ԃɂ����ł��Ȃ��悤�ȁA�j�V�r�ȍ�i���i�₿���̍ĉ��ł���������j��悵�Ăق��������B
���łɁA�V�E��Ȃɂ������Ă������A�V�E��Ȑ��̃o�E�z�[����i�o�����ɒ[�ɏ��Ȃ��悤�Ɏv����̂����A����͎c�O�Ȃ��Ƃ��B�����͂���܂ł́u���Ƃ�����͓��̒��̗��̂悤�Ɂv�i�����N�j�A�u�{���W���[���E�V���b�N�X�p�[�I�v�i�����N�j�A�u��������ׁv�i����l�N�j�A�u�₿���̗��v�ƁA��A��N�����ɂ̓o�E�����ɏo�Ă����̂ɁA�u�S���c�v�Ȍ�̓o�E�o�����Ȃ��B�ޏ��̂悤�ɒ��J�ł��߂ׂ̍������Z�̂ł���l�̎p�́A�o�E�łȂ�Ȃ��̂��Ɗϋq���������ނ͂��ŁA�����ŗ����������������I���Ă���Ă��悩�����B�V�E��Ȑ����匀��Ⓦ����ˌ����ł́u�w���v�v�ɖZ�������Ă�����A�O���o�������Ă���ԁA�o�E�����͐V�E��Ȉȉ��̎��g�b�v���⒴���i�H�j�̃��[�N�V���b�v�i�Ɩ������āA�������Ȃ�I�j�Ȃ���̂ɏI�n���A�������ɂ��R�����A���������x�����������̂́A�Ђ��傤�Ɏc�O�łȂ�Ȃ��B
�b�x��B�O���o���́u�������v�͊ςĂ��Ȃ��̂łӂ���Ȃ����A�ߔN�̎����œ��M�ɒl����̂́A���g�u�Ԃ̋ƕ��v�̓�����o�i������ˌ���̂݁j�A���g�u�V�j���[���E�h���E�t�@���v�̃��h���t�H�A�����ē������u��ˉԂ̕��y�L�v�́u�f�x��̒j�v�������B�����ċ��ʍ���T��A�ǂ̖����������z�Ƃ����p������Ɉ�ۂɎc���Ă���B�����́A��ː����Ō�̓�N���ŁA���������p���ڂ������ɏĂ����Ă��ꂽ�B
���̂悤�ɐU��Ԃ�ƁA��͂莬���Ƃ������҂́A���{���ő傫�Ȗ��͂��������Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�������A�u�̌��v�������ŒJ��������I���Ă��邪�A�ޏ����g�́u���{�������ӂƎv����̂��h���v�ƌ����Ă����Ƃ�������A�킩��Ȃ����̂��B�����炭�ޏ��ɂƂ��ē��{���������邱�Ƃ́A���̖��҂����Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ傫�ȃv���b�V���[�̂������厖�������ɈႢ�Ȃ��B�ޏ��̒��ł̓��{���ɑ���y��_�A���ϓI���x���Ƃ����̂́A���̌��c���Ƃ����o�ƂƂ�����āA�ٗl�ɍ������̂������͂������A������N���A���邽�߂ɉƑ��≏�҂��ǂ̂悤�Ȍ������l���𑗂��Ă��������n�m���Ă���ȏ�A�����Ɂu���{���ł������܂��v�Ƃ��������Ȃ��̂��o���킯�ɂ͂����Ȃ������͂����B�ޏ��ɂƂ��ẮA���̌��c���ɔ�ׂē��{�������܂��Ƃ��ǂ��Ƃ��A�����������x���ł͂Ȃ��t�B�[���h�Łi�����̒��ŁA�Ƃ������Ƃ��܂߁j����Ă����킯������A����͂܂��Ƃɐh�����Ƃł������낤�B
��]�u�����t�̉ʂĂɁv�Ŏ����͏����ɉ�����B�V�E��Ȑ��������ɔz���邱�Ƃɂ��āA�ڂ��̓��X�g�����̎Ј��̍ďA�E�����̂��߂̌��C�ȂǂƂ����A���܂��i�ł͂Ȃ��������ŋꌾ��悵�����Ƃ����������A�����ɂ��Ă������Ɍ����ƁA�悭������Ƃ͎v�����̂́A�ޏ��́A���ƌ��������̂��A���^�ʖڂ��Ƃ��s��p���������ɂȂ��Ă��܂����悤�Ɏv�����B���ł���ʓI�Ɍ����Ă��̂悤�Ȕz���́A���������z���グ�Ă����j���Ƃ��Ă̑��݊���X�L�����A�꒩�ɂ��ĕ������˂Ȃ��������Ǝv���Ă���B
����������ł��A��͂�ڂ������͔ޏ�����ˉ̌��c�ɏ������āA��������ɔޏ��̓��{���̖������������ςꂽ���Ƃ��A����Ƃ��čK���Ɏv���B�����Ĕޏ������{���ɑ���p���Ɠ����������ŁA���ʂ��痦���ɓ��{���ȊO�̉��Z�ɂ������������A�Ō�̃��h���t�H�̂悤�Ȍ��������Â���Ɍ����������Ƃ���т����Ǝv���B
�Ō�̌����ƂȂ����u��ˉԂ̕��y�L�v�ʼn��������ꂵ�������̂́A�u�f�x��̒j�v�Ƃ����p���ςꂽ���Ƃ������B���V�G���̉��y�����������Ɗi���̍������̂������B�����̓����ɂ��ẮA�`���ɂ����t���炸�Ƃ͂��������q�ׂ����A���������̓�����p���ɂ���Č���̋�C��z�w�Ƃ������̂ɕς��邱�Ƃ��ł��Ă����B�ޏ����g�̐����Ă������\�N���A�ޏ��ݏo�����`���̉��S�N���A�j���Ƃ��Ă̔ޏ��̏\���N���A���ׂĂ̍Ό��������������悤�Ȕ������p�ł������B���߂Ă��̂悤�ɔޏ��̗�������U��Ԃ�ƁA�ޏ����g�����������b�܂ꂽ��ː����������Ǝv���ȏ�ɁA�ޏ������Ă��ꂽ���ƂŁA�ڂ������������Ԃ�b�܂ꂽ���Ƃł������ƁA���ӂ������C�����ł����ς��ɂȂ�B�i2003�N8���ޒc�B���݂̌|���͕Љ��T�`�j
�u�����v�̖��́`�ɐD�����̗�������
���荞�܂ꂽ�Ƃ����̂��A�ɐD�����Ƃ����Ɓu�G�f���̓��v�V�l�����i����ܔN�j�ł̃L�����E�g���X�N�����܂�ɋ�����ۂɎc���Ă��܂��Ă��āA�Ȍ�̂قƂ�ǂ̖��ɂ��̖ʉe��ǂ�������悤�Ȍ��������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă����B���܂����v�������ɔ�߁A�ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ď����ɑ���@�ׂȐN�B�����������łȂ���ΈɐD�ɖʔ��݂͂Ȃ��A�ɐD�́u�����v������Ȃ��Ɖ�����������Ȃ��āA�ޏ��ɂӂ��킵�����ł͂Ȃ��悤�ɂ����v��ꂽ�B
����قǂɁA�u�G�f���̓��v�������������Ƃ������Ƃ��B���ɑa�܂ꂽ���j�V�̔߈����S�҂�ʂ��Ă��ӂ��悤�ɕ\������A���Ƃɕ��̕a���ŎD���𗐕������ċ����Ƃ����Ƃ����ʊ���̍V�Ԃ�ɂ́A�z�[���𓀂点��悤�Ȕ��͂��������ƋL�����Ă���B
���㎵�N�́u�N�ɗ����ă��r�����X�v�́A�����ƃ_�u������ŁA���ƉƂ̎q���I�[�r�b�g�B�S�̂Ƀe���|�̂������C�g�E�R���f�B�������Ǝv�����A���͂��̎��ڂ��́A�������A�咹�ꂢ�̓�l�̖���������ۂɎc���Ă��Ȃ��B�R���f�B�E�^�b�`�̈ɐD�͂ǂ������S�n�������A�������Ă���悤�ȋC�������Ă����A���ꂪ�L��������������������ς������̂��ǂ����B���N�A���Ђт��剉�́u�������v�ł́A���ԁB����͂܂��ɈɐD�ɓK���Ǝv��ꂽ�B����ς�ɐD�́u�����v������Ȃ��ƂˁA�Ǝv������A�t�ɂ��ꂪ�ޏ��̌|��̋������ӎ���������悤�ł�����A����ޏ��͂ǂ��Ȃ��Ă����낤�ƐS�z�ɂ��v�����B
�����Ă��悢�旂���㔪�N�A�C���h��ɂ����uEndless Love�v�Ńo�E���̒P�Ǝ剉�B�ɐD�A�咹�ꂢ�ƁA��藧�Ăă_���X�����ӂȃg�b�v��z�����킯�ł��Ȃ������̂ɁA�U�t�ɃR���e���|�����[�E�_���X�̑哇���I�q�i�g�E�A�[���E�J�I�X�j�����Q���������ƂŘb��ɂȂ����B���̂���A�ڂ��͈ɐD�ɑ��āA�̂�_���X�≉�Z��A�������ɒ��ڂ��ׂ��X�L��������킯�ł��Ȃ��A�����I�ȑ��݊��A�����ĉ������͂܂�������̂��炵��������ׂ����҂ł���ƔF�����Ă����B������A���̃o�E���剉�ƂȂ邱�̌����ŁA�ޏ����ǂ̂悤�ȐV�����ʂ�������̂��ǂ����A���������������Ă����B
�ޏ��͂��������悩�����B����܂ł���قǖ��͓I���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂��_���X���A���̗���ɉ����āA������������ƍ��߂邱�Ƃ̂ł�����̂ɂȂ��Ă���A�ޏ��̊��̂悳�A�_�o�̉s������������ꂽ�B�����ŋ����D���Ȃ낤�ȂƍD���������Ƃ��ł����B
���̌��͗։��]�����e�[�}�ɁA�ɐD����ꖋ�ł͑咹������C�M���X�l�����W���[���Ɖ^���I�ȗ��ɗ�����C���h�Ɨ��^���̓��m�o�V�[���A��ł͐��܂�ς���ăW���[���̑��q�}�[�N�Ƃ��ēo�ꂷ��Ƃ������̂ł���B�u�G�f���̓��v�Ƃ͈���āA��Ɏq�ǂ��Ƃ��Ă͈����ꂸ�A���Ĉ������j�̐��܂�ς��Ƃ��đa�܂ꋑ�܂�Ȃ�����A��������Ɉ����Ă��鑧�q�Ƃ����A��q�Ԃ̓|�������������}�[�N���ꂵ�߉Ղނ̂����ǂ���Ȃ̂����A���������グ�ĕ����p�A�˂����߂�悤�Ȏ����A�̂̃V���E�g�A�r�̐U��ȂǁA�����ɂ���̂Ȃ�����̋������o��A���̊����}�����ϖオ�����A�ɐD�̖��͂������Ă�������ƁA�[���͂ł����B���o�̎��ʖ��q���A�o�E���剉�̈ɐD�ɑ��āA����܂Œ~�ς��Ă������͂���������ƌ����邱�ƂɈӂ𒍂����̂��ȁA�Ƃ��v�����B
�������A�S�̓I�ȃX�P�[���A�b�v�͌���ꂽ���A���̌���ޏ��͂Ȃ��Ȃ����̘g�����Ȃ��悤���������A�����̘g�̒��ɂƂǂ܂����悤�Ɏv���B������̂��Ǝv���B�ޏ��͂Ƃɂ�������������ɖ|�M�����悤�Ɂu�����v�̓�����͖{���ɂ����Ă��ŁA���̒N���������ӂ��킵�������Ǝv�����A���̏�Ԃ֊����グ�Ă������Z�����炵�������B�f�̊�܂ŁA������̂悤�Ɍ����Ă����B�u�����v�����炵������炵���قǁA�u��������߂݂��v�i��Z�Z�Z�N�j�̔��̂悤�ɁA���o�Ƃ������ޏ��ɂ��̂悤�ȁu�͂܂���v�����^���Ȃ��Ȃ����悤�Ɏv�������A����ɂ͔ޏ��ɂ͂���Ȏŋ����������ĂȂ��悤�ɂ����v�����B
�ɐD�̖��ς�����悤�Ɏv�����̂́A��͂��ȂɈڂ��Ă��炾�B�u���[�g���B�q�U���v�i��Z�Z�Z�N�j�̃f�����N�n�C�����݂��悩�������A���Ƃ����Ă��u�J�X�e���E�~���[�W���v�i��Z�Z��N�j�̃A���g�j�I�ŁA�G���ɂ܂���č������͂��o�����̂��悩�����B���N����l�̒j�ɂȂ����悤�Ɏv�����B���́u�����v���A��Ȕz���Ƃ������Ƃł̐S���܂��̂悤�Ȃ��̂ɂ��̂��A�j���\��N�ł̐��ʂȂ̂��A�O���o���u�L�X�E�~�[�A�P�C�g�v�ŏ����i���C�X�A�r�A���J�j�����������f�Ȃ̂��͂킩��Ȃ����A�j���̔��͂̂悤�ȋ�������������悤�ɂȂ��āA�傢�ɋ������B
���āA�ޏ��͕�ˉ��y�w�Z����Ȃő��Ƃ��A�������珫�������]����Ă����킯�����A�u�G�f���̓��v�ł̐V��������͓��c���N�ڂƊ��荞�݂ɋ߂���Ԃ������B�������O��̃o�����X��g���̎���������ɂ���A���y�w�Z�ł̐��т��炷��ƁA���p�b�Ƃ��Ȃ����c��ł���B���ہA�������l�l���W�܂����uSwitch�v���ςĂ���ƁA�ɐD�̗D�����炵���͓`�����̂́A���݊��Ƃ����_�ł́A�������̓g�b�v�������������đ��̎O�l�Ɗi�i�̈Ⴂ������Ƃ͎v���Ȃ������B���̌����͂����܂ňɐD���剉�ŁA�Ό��킽��͓��ʏo���A�����ĉÌ��G���Ɣ���\�q�Ƃ������C���A�b�v���������A�����ɂ����ĈɐD�ȊO�̎O�l�̂ق��ɖڂ��s�������������B
�E�l�S�̈ɐD���悩�����̂́A�Ό�������E�H���^�[�Ɂu���̐��ł��܂��̑��q�ɁA�����V�т��R�قNj����Ă�邳�v�ƌ������悤�ȋ����Ԃ�ł������B�Ό��Ƃ̗����̏�ʂ����^�̗͂�����A���̌�̈ɐD�̐Â��瓮�ւƈڂ�̂��h���}�e�B�b�N�Ŕ��͂��������B�������A�S�̂ɂ́A�Ό��ȉ��O�l�̎ŋ��I�҂Ɏx�����Ď��������A�ɐD�̉ԓ��̂悤�Ɏv���Ă������Ȃ������B��ł��A�q�Ȃɍ~�肽����Ƃ����ċq��������ł��Ȃ��A�ނ���N���C�}�b�N�X�Ɏ����Ă����ł��Ȃ��A�����Ƃ���������������Ȃ����A���ȃX�e�[�W�ɂȂ肩�˂Ȃ��̂��~�����̂́A�Ì��瑼�̎O�l�̗͂��傫�������B
��Ȃ�g�b�v�Ƃ������Ƃ��A�ǂ������v���b�V���[�ɂȂ��Ă��܂����̂Ȃ̂��A���̌o�����Ȃ��̂ł킩��Ȃ����A�u�g�b�v������v�͗e�ՂɁu�g�b�v�Ȃ̂Ɂv�ɂȂ邾�낤�B�ǂ̃W�����������������ł���Ƃ������ƂŁA�ʔ��݂Ɍ��������ɂȂ邱�Ƃ́A�{�l����Ԓm���Ă����̂ł͂Ȃ��������B���Ƃ��Ɣޏ��͖������u�]���Ă����Ƃ����B�u�L�X�E�~�[�A�P�C�g�v�ɑ����A�ӎ�b��i�ւ̍g��_�ł̏o�������܂��Ă���悤���B�ŋ��D���Ŋ����悭�āA�j���猩�����̖��͂�m���Ă��鏗�ŁA������ƕs��p�Ȃقǐ����c�c�����̏����͂�����Ă���B�������ƂȂ邱�Ƃ����҂��Ă���B�@�i2003�N�ޒc�A���݂̌|���͈ɉ��������j
�V���x�̃X�^�[�g�ɔ������z�ƁA�\�z����錶��
�@�ڂ��͂����A�����]�ȊO�͂��܂菑�������Ȃ��Ǝv���Ă���B�ڍׂ͏ȗ����邪�A��˂��߂���_�́A�s�т��B������A���̐V�E��Ȑ��x�̃X�^�[�g�ɂ���āA�ڂ����������������̂́A������_�A�ǂ�ȍ�i�łǂ�ȑg�ݍ��킹��������̂��A�Ƃ������Ƃɐs���Ă���B
�@���̐��x�̔��\�́A���g�u�����̃t�@���I�v�匀������̍Œ�����������A�ڂ������͌��\�S�z�����B�G������ʋP�́A�����炸�ɂ�����ƕ���߂Ă��邾�낤���A�Ƃ��B���ɂ��̐��x�����������̂́A���g�o�E�z�[�������uFREEDOM�v�Ŏ������̌��������u��ȁv�ƂȂ��Ă������Ƃ��������A��i�̏o���͂悩�������A���R�̂��Ƃ�����a���͂Ȃ������B�����匀������̐�g�u�M����v�A���g�u�]���͊C���z���āv�ł����̑g�o�g�҈ȊO�̐V�E��ȏ����҂̏o���͂Ȃ��A�m�Â⏀���̓������ނ����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����������\�������x�������I�ɋ@�\���Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��v��ꂽ�B���g�̃V���[�u�~���j�A���E�`�������W���[�v�ŏ�߂����E���ɂ���ƑS���̔w�Ɂu���v�Ƃ����[�b�P�������ꂽ�Ǝv������A�Ό��̂��̂����u��v�ɕς�����Ƃ����A�f���ɂ͏��Ȃ��Γc���o�炵�������l�^�����������A�����������Ƃ��T�����Ɖ����Ă���Ƃ���A���c�����ϋq�����قNj����Ȃ��~�߂Ă���Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@�V�������x�̔��\�ɓ������āA�v���f���[�X���鑤�͐헪�I�ɁA���ꂪ�����ɂ��܂��@�\���A�f���炵�����ʂ��c�������A�����ɂł��ڂɌ�����`�Ŗ��炩�ɂ��A�t�@���⌀�c���ɋN���肤��s����s�������������ޕK�v���������B�������A��͂��ˉ̌��c�͂��̂悤�Ȏ��łĂ��A���O�҂ɂ́A���̐��x�̔������\���Ɍ�������Ă��Ȃ��A�v���t���̂��̂ł���悤�Ɍ����Ă��܂����B
�@�����̂��Ƃ����炩�ɂ���Ă��Ȃ����ŁA�C�ɂȂ邱�Ƃ́A�܂��V�E��ȂɈڂ����\�l�̒�����A�g�b�v�ɏA�C����҂�����̂��ǂ����A�����Ă��̐��x��������p������̂��Ƃ������Ƃ��B�܂��̓I�ɂ����A���g�����g�b�v�͒N�Ȃ̂��A���ꂪ�V�E��Ȃ���I�ꂽ�ꍇ�A���g�̐V���g�b�v�A�O�Ԏ�͐�ȂɈڂ�̂��A�Ƃ������Ƃ��B���ꂪ���炩�ɂȂ�A���ケ�̐��x���ǂ̂悤�ɓW�J����̂��A�����悻�킩�邱�ƂɂȂ�B
�@�����_�ł͂��̐��x�������I�ɋ@�\����i�Ƃ����Ă��A�����̋x�����č������������Ƃ������������j���g�匀������u�[���_��̗��v���n�܂��Ă��Ȃ��̂ŁA���̐��x�������ɑf���炵�����̂��Ƃ����A�o���I�Ɍ��Ȃ��̂��c�O���B���ʂ̔z���͐��x�����Ɠ����ɔ��\�����ׂ����������A���̒��ŋ������������̂��A�V���[�����ɎQ������Ƃ����P�[�X�����������Ƃ��B�����������R����������Ă���̂Ȃ�A���҂͂��Ȃ�L�����Ă����B
�@����ɂ́A�g�̘g�̒��ɐ�Ȃ̎҂�U�蕪���Ă����̂ł͂Ȃ��A��Ȃ̎҂��������̌����̒��S�ƂȂ��āA���R�ɑS�g����I�[�f�B�V���������ŏo���҂��W���A��{�̌�����ł��Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B���Ƃ��ΐ��ˍ�i�������A�����A�����A�����A�����ď����̖������Z���N�g���ĉ����ď㉉����Ƃ��B�R�{���ܘY���̂������A�G�����A�Ό��𒆐S�ɂ��Ă��Ƃ��B��Ȃ̏\�l�����ŁA�N���͏����ɂ��Ȃ��Ĉ�{�̟������~���[�W�J�������Ƃ��B�������ĕ҂��Ȃ�����B���̂悤�ɍl���Ă����ƁA�z���͖��z�ƂȂ��]�ƂȂ��āc�c�͂��Ȃ������Ă����̂��낤���B
�@�����A���̂悤�Ȋ��������Ă����Ƃ͎v�����̂́A���ꂪ�嗬�ƂȂ�悤�Ȃ��Ƃł�����A�e�g�Ɉ�l�̃g�b�v�X�^�[�����݂��邱�Ƃ�O��Ƃ����s���~�b�h���x�͕���Ă������낤�B�t�B�i�[���ő�K�i���~��Ă��鏇�ԁA�H���̑召���ǂ�����̂��A�Ƃ��������I�Ȗ�������B�g�b�v�X�^�[���o�Ă���������A����̋�C����A�O�x�オ��悤�ȋْ����A�V�g�����Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ̓i���Z���X�ł���悤�Ɍ����Ȃ���A����܂ł̕�ˉ̌��́u���ˉ���I�v�Ȉ��S�����x���Ă������̂ł���A��O�����Ƃ��Ă̕�ˉ̌���ۏ��Ă������̂������B��˂̍쌀�͂��̂悤�ȃg�b�v�X�^�[���x�Ɉˑ����ď��߂Đ������镔�����傫���A�����E���Č��݂̉��o�Ɛw���܂Ƃ��ȋY�Ȃ�n�����������邩�ǂ����A������͂Ȃ͂��S���Ȃ��B
�@�����Ă���ɂ��낢��̂��Ƃ��l������S�z�����肷��̂����A�ǂ����ł́A�V�E��Ȑ��x�Ȃ�ďW�q�͂̒ቺ�Ɋ�@�������Ă���̌��c���ł����A�ꎞ�I�ȋN���܂ɉ߂��Ȃ����A�Ƃ��v���Ă���B�V����̃I�[�v�j���O��A���܂��ɉ\�̐₦�Ȃ��x����āX�������邽�߂̂��̏ꂵ�̂��ł���Ƃ��B���ǖ|�M�����̂́A���c���ƃt�@�������A����ꂳ��B�c�c������A�����]�ȊO�̂��Ƃ́A���܂菑�������Ȃ��Ǝv���Ă���̂��B���킩�肢�����������낤���B
��l�̖��킢�A�Ȃ�̖��́|�ʊi�X�^�[�̑��݉��l
�@�f��E�A�����E�Łu�����j�D�܁v�u�������D�܁v�Ƃ����̂́A���҂ɂƂ��čō��̌M�͂Ȃ̂ł͂���܂����B��N�x�́u��P���˃A�J�f�~�A�E�A�J�f�~�[�܁v�ł́A���ꂼ���������A�˂����́E��h�ꂢ���E�v�H�������ƂȂ����B�������A�ޏ������̂��̉��Z��������������߁A���킢��[�߂����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B����A�Ȃ�ƂȂ��g�b�v�H���ɂ͏���Ă��Ȃ��悤���Ȃ肪�A���͂ƂȂ��ċz���͂����Ă��邱�Ƃ��������Ȃ��B
�@�ߔN�̕�˂̌X���Ƃ��āA���g�b�v�͘e����g�b�v�̑R�Ƃ��Ă����A�����g�b�v�Ƃ��ė\�s������ǂ���Ɏ��܂��Ă��܂����Ƃ������A�����̔��w�A�a�����o��������ӂ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ŋ߂ł́u�k�t�m�`�v�������~�i�u���C�A��)�A�u�^���S�E�A���[���`�[�m�v�����Ђт��i�J�[���j���g�b�v�ɑΗ�������Ƃ��Đݒ肳��Ă������A�������r�C��Y�̍�i�ŁA�ނ̍쌀�̈�̓����Ƃ����Ă������̂�������Ȃ��B
�@���X�����̂ڂ�A���������r�́u�J�T�m���@�E���̂����݁v�����H�����i�T���W�F���}�����݁j�A�������̂����u�n�E�E�g�D�E�T�N�V�[�h�v���C���Ђ낫�i�M���b�`�j�Ȃǂ́A�������߂��炵����A�F�Z���g�b�v�ƑΗ������肷������A�ŋ߂ł͐�Ȃ�g���E���g����̃x�e�����w�ɓ��Ă��Ă���̂��A���Ȃ��炸������Ȃ��v���Ă���B�����炭�����������Ƃ���˂̃A�C�h�����Ƃ����Ă��邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B�g�b�v�H���ƌĂ�鏘�O�Ԏ�A�l�Ԏ�A���邢�͑g�ɂ���Ă͌ܐl�ځA�Z�l�ڂƐ������Ă��܂��悤�ɂȂ��āA�ǂ������̃A�C�h�������ɑ��܂����F�Z��������U�蓖�Ăɂ����Ȃ��Ă���悤�Ɏv����B���̂��ƂŌ������҂�������ɂȂ�A��i�̐[�݁A���Z�̐[�݂������Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���Ƃ��������������ŋ߂͈��炵���������͂��o���Ă���̂́A�ޏ��̐l�C�̂��߂ɂ͂悢���Ƃł��낤���A�u�i�e�j�v�i�܂����Ă����r��i�����j�̃t�[�o�[�����̂悤�ɃL���L��������قǂ̑��炵�����������Z�������A�ǂ����Ă��������̂��B�m���Ɉꎞ�������͋�ݑ��������N�j���̍��C�∫���̔��w���ӂ�܂����������A�e��H�����Ƃ��A�g�b�v�A�C�͓���̂��A�ȂǂƉ\���ꂽ���A�܂���˂ɂ��̂悤�ȐF�Z���g�b�v�����������ŋ��������Ă������A�ڂ������������������܂݂��y���߂�ӏ܊���������ق����A�y�����͂����B
�@���āA�u�ʊi�X�^�[�v�ȂǂƂ�����ƁA�^����ɊC���Ђ낫���v�������ׂĂ��܂����̂����A�܂�g�b�v�⏀�g�b�v�ɏ���Ƃ����ʎ��͂�����A�ޏ������ɑR����قǂ̑��݊�������B�����ɂ����ẮA�F�I���������������悤�ɁA�Ⴂ�g�b�v�������t�H���[���邾���łȂ��A������f�I�Ȗ��͂������������A��w�A�^���̏��A�܂��͕ꐫ�I�Ȃ����o�I�Ȗ��͂Ńg�b�v���݂��ނƂ��������ǂ���ƂȂ邾�낤�B
�@�������A�j���Ȃ牽�Ԏ�Ƃ����悤�ɏ���܂��Ă���悤������A�ʊi���������̂́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɩ����i�����j�̂ق��������̂�������Ȃ��B��̓I�Ɍ����A�ȉ��̂悤�Ȏ҂���������B��O������A���낢��Ƃ��٘_�͂��邩�Ǝv�����A���e�͂������������B
�@�@�ԑg�@�������A������
�@�@���g�@�ĉ͂��A�����u���A�����^��
�@�@��g�@�ܕG�A�����K
�@�@���g�@�����ԁA�v��j
�@�@���g�@�˂����́A�������
�@���̒��ɂ́A�����_�ŕʊi�������Ă��܂����Ƃɒ�R�������āA���ۂ��ꂩ��g�b�v�ɂȂ邩������Ȃ��X�^�[������B�X�Ɍ���ƃ_���X�̃X�y�V�����X�g�����邪�A�����͎ŋ��I�҂Ƃ��ċL���Ɏc���Ă���B���Z�Ȃ炢���閼�e���Ƃ��āA���邢�͉̂ł��_���X�ł��A�ϋq�̋L���Ɏc�郏���V�[������ۂÂ��Ă���鑶�݂��Ƃ����Ă������낤�B
�@���̒��ŁA�����Ƃ��Ĉ�ۂɎc���Ă���̂��A�uLove Insurance�v�Ń��x���g���D�������v���B �����ł͂Ȃ��������́uCrossroad�v�̃f���V�����́A���傤���Ȃ��j�̖��ŁA������܂����e���̈�̖��ǂ���Ƃ��Ď����̖��͂𑶕��Ɍ������B���̓�̍�i�́A�������ː��F�ɂ����̂ŁA�uSAY IT AGAIN�v�����������������C�Ђ������A��͂肵�傤���Ȃ��������\�t�������悤�ɁA��������ˍ�i�ɂ��̎�̘e����������쌀�����҂������B
�@���e���Ƃ��Đ�����ɂ́A�ЂƂɃR���f�B�A���Ƃ��ċq�Ȃ�����Ƃ�����������͂����B��Ȃ������̂������͂��߂Ƃ��āA�ޒc�����^�R�t���ɘA�Ȃ�H���ł���B�������邱�Ƃ��킹��ق�������Ƃ������A���̃^�C�v�̖��҂��{���Ɏŋ��I�҂ł��邱�Ƃ́A�����́u�S���E���̑�a�H�v�ɂ����鑷�E�q�傪�ؖ����Ă���B�����ł́A��L�̖��҂ɂ�����Ƃ��̂悤�Ȗ����v�������Ȃ��̂��c�O���B�^��݂����^�Ղ��̂悤�ɁA�g�b�v���V�тŏ킹��̂Ƃ͈���āA�L�ѐ���̃g�b�v���ɏ����̃C���[�W�����Ă��܂����Ƃ́A�����炭�{�l�ɂ����̃t�@���ɂ����Ȃ���ʒ�R������ɈႢ�Ȃ��B�����̍�i�Ő�Ȃ̎҂������ɓ��Ă��Ă���̂��A�ŋ��̍I���Ƌ��ɁA�������������ɑ�����̊���肪�ł��Ă��邩�炾�낤���B
�@���������Ӗ��ŁA�����ł������D���M�d�ȑ��݂ł���B���ɂ��߂��Ă��܂��Ċ��邱�Ƃ����邾�낤���A���|�V�쌀�I�ȁi�Ƃ����Ċ��ȊO�̕��ɂ͂킩��Â炢���낤���A���R�����Ƃ��j���Ɨ܂̂Ȃ��Ɍ��́A�����Đl�ԂƂ������̂̐^���𖾂炩�ɂ��Ă������ǂ���ł��邱�Ƃ������͂��ŁA���̂悤�ȃ^�C�v�̖��҂������Ȃ����Ƃɂ́A��ˉ̌��̕���ɖc��݂͏o��܂��B
�@�ڂ������̊ό��̎p���Ƃ��āA���ׂ���ʂł͎v����������ăR���f�B�A�������̓w�͂ɕĂ��Ȃ��ẮA�ޏ���������ꂪ�����Ȃ��Ƃ������̂��B�J��Ԃ����A���ˍ�i�̒��ɂ́A�ŋ��̃^�C�~���O�ŏ킹��㎿�ȃ��C�g�E�R���f�B������B�b�㐫�͂Ȃ����ǃJ�b�R�悭�āA�ǂ����g�{�P�Ă��đ��߂Ȃ��A�Ƃ����悤�Ȗ��͓I�Ȓj���A�����Ƒ匀��̕���̏�Ŗ��������Ă���Ȃ����낤���B
�@�����Ƃ����A�ӊO�ɂ��Ă����A�K���ǓށA�ĉ͂��A���s�q�ȂǁA�����ɂ����R���f�B�G���k���������Ƃ́A�������������ˉ̌��̈�̓����Ƃ��ċ������Ă�����������Ȃ��B�{���͂������l�������̂����A��˂ɂ����Ēj���������ȋ��\�Ƃ��āA�낤���n�_�Ő������Ă���Ƃ�����A�������ɏ����̂ق����킹�邱�Ƃɂ͋߂��̂��Ǝv����B�n�ōD���Ȃ悤�ɔ����ł���̂́A�{���ɂ͂ނ��돗���̂ق��ł͂Ȃ����ƁA�����ł͂���ȗ\���������w�E���Ă��������B
�@��������ɂ́A�����̏��A�^���̏��Ƃ������͓I�Ȗ��ǂ��낪����B���A�ܕ�A�����̂悤�ɁA�x�e�����̈�ɒB���悤�Ƃ��������ɂ́A���̂悤�ȏ�w�̖��킢�Ŏ���̐l����c�߂Ă��܂����͂����܂��\���ł���@�����A���̏�ł��܂��N���d�˂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B���_���X�̌ܕ̍ŋ߂̉��Z�ʂł̏[���́A�������B�u���҂̉���v�ŕ����������C���[�l�̍Ŋ��̏�ʂ̐��₳������Ȃ��������A�u�v�����@���X�̕ɂ���v�̔����̃W�F�����[�k�ɂ��ĉ��߂Ă����܂ł��Ȃ��낤�B�ޏ������ɋ��ʂ��Ă���̂́A�����܂ł��Ȃ����Ƃ����A�����Ƃ�Ɣ������Ƃ������Ƃ��B�ĉ͂͂����̂Ƃ��떂���I�Ȗ��������āA������Ƒ������Ă���悤�Ɏv���B�L���L���A�o�^�o�^�������A������������l�̏��̉ĉ͂��������B
�@�u��������߂݂��v�ŞO��������������ɂ��Ă��A��͂�������̐l������x�͑傫������߂����ƂŁA���Ƃ��Ă��A���҂Ƃ��Ă����ɉs�����������B�u�^���S�E�A���[���`�[�m�v�ł͌��������w�B�Ɠ��ȋC�i�ƐF�C�����܂��o���Ă����B�ǂ��炩�Ƃ����Ƃ��킢���^�C�v�Ȃ̂ɁA�����Ԃ�l������߂��A���j���C�ȕ��͋C���o���Ă���̂��A�傫�Ȗ��͂ɂȂ��Ă���B
�@���A���������́A���Ƀg�b�v�����ɂȂ��Ă��悩������������Ȃ����A���҂������Y���Ă��܂��āA���̊����킵�Ă��܂����Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă���B����������͕K�������������Ƃł͂Ȃ��āA���̂悤�Ȋς�҂̎v�����݂��A�ޏ������̑��݂ɖ��킢��[�߂鍁�h���ɂ��Ȃ��Ă���B�˂ɂ��ẮA�u�G���U�x�[�g�v�ŋ������B���f�b�V������A���Ƃ����������A�D�����߂����B�q���C���̓g�����X���Ȃ��B���������e���͔���U�藐���Ă��߈˂��Ăł��A�l�Ԃ̈�ʂ��m���Ɍ����Ă���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�˂̃��B���f�b�V���͕�˂ɂƂ��ċM�d�ȍ��Y�ł��葱���邾�낤�B
�@������ƕς�����Ƃ���ł́A�u�v�����@���X�̕ɂ���v�Ŗ{���j���ł����k���������������G�f�B�b�g���A�܂��f���炵���j���ł������B�ޏ������̂悤�Ȗ��҂ɂ́A�����Ƒ�{�ɂ͏�����Ă��Ȃ��A�����̎v�f���Ӑ}���\�͂��������̂����A�����~��Ă���u�Ԃ�����̂��낤�B����ȗ\�z�ȏ�̖ʔ��݂Ƃ������̂́A�g�b�v�������̂��ɂ���e�������ɑ�����������̂��B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�����������A�����̂悤�Ȓj���̂ق����Ǝ��̖��͂������o�����Ƃɋ�J�����Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�u��������߂݂��v�ŕ��͎鐝��Ƃ��������^����ꂽ�B�������o�E�́u�S���E���̑�a�H�v�Ŕ��E�q��A��N�́u���������̗��v�ŃW�����E�T�����@�h������Ɠ���������Ă���B�ǂ�����������Ē����Ă��邾���ł͂ǂ��ɂ����܂�̂��Ȃ��A���|�A�j���̕K�v�Ȗ��ǂ��낾�B
�@���̕�˂ł́A���̂悤�Ȗ��ǂ���ɂ������K���ł��ӂ��킵���B�����炭�ޏ��́A���������炦�邱�ƁA�������Ȃ����Ƃɂ���Č�������[�݂�g�ɂ��Ă���B�����ɂ��̂悤�Ȗ������������Ɖ��o�ƂɎv�킹�邾���̖��͂�����B����ȍD�z�̑����p���A����̖��͂��i�i�ɍ��߂Ă����B�c���Ȃ��Ƃ�������Ȃ����A�ǂ����Ŏ�����ʊi�ł���ƈʒu�Â�����́A�^����ꂽ���̋@����A���x���A�b�v�̂��߂̐��O��Ƃ��ď����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���˃A�J�f�~�A11�
�@��ȃu�[���͋������Ƃ͂����A�݂�ȃ^���S���D���݂������B�ꗬ�̃N���V�b�N�̉��y�Ƃ����\���[���[�E�}��N���������s�A�\���Ƀg���r���[�g�����A�����A���o�����o���Ă���B
�@���s�𒆐S�Ɋ������Ă����A�X�g�����R�̖ʁX�A���Ƀo���h�l�I���̖�ދI�����A���̉��t����p�����Ă���ƁA�܂����̃J�b�R�悳�Ɍ��t�������B�_���f�B�Ƃ������ƁA���V�i�X�^�C���j�������Ă��邱�ƁA���̏�Œj�������A�����j�����ނ��߂̎����ǂ��������Ă���B���y�͂��̊|���������~���ɂ܂��͂��������ߌ��I�ɐi�߂邽�߂̏������̖������⊶�Ȃ���������B
�@�A�X�g�����R��m�����̂́A����ˉ̌��c�ԑg�̃g�b�v�X�^�[�A��Y�݂����́uChe Tango '99�v�i7��11���A��˃o�E�z�[���B�\���E���o�����䐟�v�j�ł������B��Y�͕�ˉ̌��c�̌�������A�����_�E�w�[�o�[�}���̐U�t��i����Ƃ����j���[���[�N�n�̃V���[�v�ȃ_���X����ɓ��ӂƂ��A�u�_���X�̉ԑg�v���`�����Ă����B���̃_���X�͊m���ɑf���炵�����̂��������A�ǂ��炩�Ƃ����ƃL������ɗ����āA�����ۂ��̖ʂł����Ԃ���悤�Ɏv���Ă����B������A�����O����ޏ����i�����_���T�[�Ƃ��āj�^���S�ɖv�����Ă���ƕ����āA���ӊO�Ɏv���Ă����B
�@��Y�̃^���S�́A���X�����ɖ����Ă����B�^���S���n�߂ĉ��N�������Ă��Ȃ��Ƃ��������ɁA�X�e�b�v�͂��܂蕡�G�ɂ����A�ǂ������璍�Ӑ[���A�����Ӗ��ł̉��a���\�傫������Ȃ��̂Ɍ������̂��Ƃ����h���̂悤�Ȃ��̂��������Ă����̂��悩�����B���ꂪ�A�o���������̒j�Ə��̏��X���������Ђ��̂悤�Ȕ��܂������������Ă����̂��A�����悩�����B�y�A��g�t���I�E�A���e�X�̍D���[�h���������Ȃ��B
�@���āA���̌����͉��l���̐U�t�Ƃɂ�鋣��ł��������̂����A�u�p���̃J�i���v��u���E�N���p���V�[�^�v�ŃV���[�v�ȍ\�����������P���W�����́A�������������ɑ����邪�A�uAtmosphere�U�v�Ƒ肷�邻�̃J���p�j�[�𒆐S�Ƃ��������ŁA���Ƃ��Ƃ�����ˉ̌��c���g�b�v�����ƃ^���S�uASHITA�v��x�����i5��30���j�B����͑�Y�̂Ƃ��܂��������C�ŁA���̃X�����ɖ������A�����X�e�[�W�������B�ޒc���Đ��N�����͂܂��܂��������悤�ɔ������A��������j�Ə��̐V�����l�����n�܂��Ă��܂������ȗ\���ɖ������h���}�`�b�N�ȃ^���S�������B�����̓����̃X�s�[�h�ƃL���A���̍�i�Ō������W�����v�̗͋��������߂ē��L���Ă��������B
�@�Ō�܂ŕ�˂ł����Ă��܂����B�V�A�^�[�E�h���}�V�e�B�����ŁA�_�˂��������z�[���ɏ���ς��čĉ����ꂽ���g�u�u�G�m�X�A�C���X�̕��v�i7��18���B��E���o�����ː��F�j�́A�剉�������~�̃^���S�̃X�e�b�v���j�Ə��̖����ւ̖��ƕs�����V���[�v�ɕ`���Ēɐ������B���Ĕ����{�^���̃Q�����������j�����͂ēX�ŗx���Ă���B�����ƈꏏ�ɗL���Ȋy�c�̃I�[�f�B�V�������邱�ƂɂȂ������̓��ɁA�̂̒��Ԃ̃A�N�V�f���g�Ɋ������܂��c�c�B�^���S���h���}���̂��̂ł���A�^���S������グ�A��s�������Ă����B�w�炵�����z���ɒn�ʂ����߂�߂̎p�A�����A�\��A�e�c�c�����̂��ׂĂ��A���̑傫�ȃh���}�̃G�b�Z���X�ƂȂ����B�iP.A.N.Press�f�ځj
�u��˃A�J�f�~�A�v������W�u�����y���ނ��߂̎�̋ꌾ�v
�@�ڂ�����˂����n�߂����A�g�b�v�����͐X�ނ݂͂�A���`�܂�A���T�����A���邠�₩�A�̎l�l�������B���ꂩ��ԑg�͐X�ނ������~���ƈꏏ�ɑޒc���āA�^��݂��Ɠ����Ƀg�b�v�ɏA�����̂����������A�����ŏA�C������ق������^��Ɠ����ɓd���ޒc���āA�咹�ꂢ�����݂�Ɠ����Ƀg�b�v�A�C�B��g�͉��`����H�^�P�A����ӂԂ��A���I�ƃR���r��g�̂����g�ɑg�ւ����āA������Đ��g�Ńg�b�v�������������e���B���g�͖��T���V�C�S��A�v�������ƃR���r��g�̂��ޒc���āA���ԕ��������Đ^�Ղ��ƃR���r��g�݁A���Ԃ̑ޒc��A�h�ꂢ�B���g�͔��邪�ޒc�̌�A���e���������������H�����ƃg�b�v��g��A���ޗD�������e�ƌ�ւŃg�b�v�ɏA���A���H�̑ޒc�̌�A���K���}����A�Ƒ�ւ�肵�Ă����B�ڂ���菭���N���������g�b�v�������A���̊Ԃɂ��������N������Ă��܂��A���ꂾ���łȂ������ɂȂ����悤�ȋC�����Ă��܂������������̂����A������l�����Ă����Ȃ��Ă��A���̃g�b�v�����̃��C���i�b�v��������Ȃ��Ƃ��A����肷��Ƃ����悤�ɂ́A�K�������v��Ȃ��B�����͔|���뜜����Ȃ�����A����O�N�̎��_�ŐX�ށA����A���T�����U�A���`�Ɏ����Ă͌��S���������Ƃ��d�ˍ�����A���͌��e�A���ނ���10�A���`�����X�A�h�����W�A�ʼn������̑咹�ł����V�ƁA�F����Ȃ�̔N�����o�Ă��Ă���B�����╗�Ԃ����ށA���e�Ɠ������������Ƃ��v���A���̍��̑������A���ٗl�Ȃ��̂Ɍ����Ă���B
�@�_���X�Ȃ琯�ނ�����B�咹�͉̂������B�ŋ��̃Z���X�Ȃ猎�e�B���`�ɂ͐��^�Ȕ������Ɋј\�����o�Ă����B�h�ɂ͔��e�ɉ����A�ŋ��D���Ƃ������_������B���ꂼ����ȕ��삪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��悤�����A���ꂪ��i�̏o���Ɍ���I�ȃ_���[�W��^����قǂł͂Ȃ��Ƃ����Ă����̂ł͂Ȃ����B
�@
�@�����́A��͂�ǂ����Ă��g�b�v�X�^�[�i�j���j�Ƃ̊W���A�����ɂ���č��E����Ă��܂��������傫���B���`�����g�Ɉڂ��Đ��܂�ς�������Ƃɂ��āA�q�ׂ����Ƃ�����i�w��˃A�J�f�~�A�T�x�����u�����̒a���ƍĐ��v�j�B���g�ٓ���̔ޏ��́A�u�G�N�X�J���o�[�v�u�G���U�x�[�g�v�u����v�̎O��ŁA�O�l�̏������݂��Ƃɉ����������B�^�X�Ƃ�������l�I�ȊO���������Ȃ���A���X�Ƃ����Ќ����ӂ�鉉�Z���A���f�I�ȃW�v�V�[���̂�����悤�ȕ\������݂ɌJ��o�����Ƃ��ł���B��g����ɂ́u�^�钆�̃S�[�X�g�v��u���ꂽ���ɂ͉i����������v�Ō���̏�����������܂��̂悤�Ɍy�����Ȃ��Ă��邵�A���������������w�������������A���g��̉��Z���s���R�ł͂Ȃ��A�I�[���}�C�e�B�̖��͂��l�����Ă���B
�@�ޏ��́A�h�^�h�^�����ƌ����Ă͈������A���ނ����ȑ�������D�����A�Ƃ����������Ƃ�����B���̑������A���܌�����v���߂��悤�Ȗڂ�����́A������ς��������Ă��邪�A�[���̗ߏ삪�����ɖ����ɂȂ��āA���͂̂��Ƃ����������Ȃ��Ȃ��ē˂������Ă���悤�Ȋ낤���������āA���ꂪ�ޏ��̖��͂����Ă���B
�@�Ƃ͂����A�_���X�͂��܂蓾�ӂł͂Ȃ��悤�����A�͈̂����Ȃ������X�A���b�Ǝv�����Ƃ�����B�u�G���U�x�[�g�v�̉̏�������҂��āA�V���[�̃����V�[���̉̂����x���Ŋ��҂��ĕ����ƁA�������肷�邱�Ƃ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�ޏ��͂����炭�������Ȃ��Ɖ̂��Ȃ��A�܂��ɕ�˂̕���̂��߂̉̂���Ȃ̂��낤�B����͂������Ď�_�ł͂Ȃ��B
�@
�@�u�����̒a���ƍĐ��v�ł́A���e�����g�����g�Ɉڂ��āA�������̂悤�Ɏŋ��I�҂Ԃ���ł������Ƃɂ��ӂꂽ�B�ŋߍ�́u�ĉ�v�Ŕޏ��̃R���f�B�G���k�Ƃ��Ă̖��͂����������B����͊�������Ƃ����A�ϋq�Ƃ��Ă͏��Ă�������̂������藧�ĂĖ��Ƃ���ɂ͓�����Ȃ��̂����A���S�z�ȓ_���Ȃ��ł��Ȃ��B���e�̂���܂Ŗ���ʂƂ���Ă���V�[�����v���o���Ă݂�ƁA�u�t�N���v���X�g�߂��̋⋴�ł̓Ɣ����͂��߁A�ޏ���l�������オ�����Ɖ��̏�ʂ������悤�ȋC������B�u�ĉ�v�Ŏ��̂��A�}���قł̒��p�����ȂLj�l�̂������̂�����������ł����āA�|�������ɂ�鑊��Ƃ̊ԁi�܁j�̂��������ł͂Ȃ������悤�Ɏv���B���ۂɂ͊|�������̃V�[���������͂Ȃ��̂��낤���A��l�̃V�[�����ˏo�����ۂ�����̂͂Ȃ����낤�B�ޏ����g�����Z�ʂœw�͂��H�v���d�˂Ă���̂͂悭�킩��̂����A������Ƃ̊W����z���ď�ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ł́A���C���}���ăo�^�o�^���Ă��܂��X��������悤���B���Ƀ��u�V�[���ɂȂ�Ǝ��̓W�J���}���ł��o�^�o�^���Ă���悤�Ɍ�����X���ɂ���悤�Ɏv���B�u�ĉ�v�̂����V�[���Ń|���|���Ƒ���~���Ă��܂��Ƃ���ȂǁA�G��Ƃ͂����A���ꂪ�ޏ��̎������ɒ��ڂȂ����Ă��܂������ɁA�����ɂȂ�Ȃ��Ƃ��낪�������B���u�V�[���ł̋��S�n�̈����Ƃ����̂́A���ɂ���Ă͂ƂĂ��������ɂȂ�Ǝv�����A�����̐e�ߊ����o���邱�Ƃ��ł���A����I�Ȃ����L�����N�^�[���Ƃ͎v�����A�����̂悤�Ȗ�����ł͕�����Ȃ��B���ɃV���[�ł̃f���G�b�g�_���X�����߂Ƃ������݂��S�z���B
�@�Ǝv���Ă�����A�G�X�g���[���i�u�m�o�E�{�T�E�m�o�v�j�͔ޏ��ɂƂ��Ă����Ԃ����ɂ��Ȃ�A�����Ă��̐��ʂ𑶕��Ɍ�����ꂽ�悤���B�䎌���Ȃ��A�\����Ō����鉉�Z���ł���悤�ɂȂ��Ă����B�ȑO���炫�߂̕\���A���炵�����邭��Ƃ��������`���[�~���O�ȕ\��͓��ӂƂ��Ă������A����͗��ɗ����������̕\��ł��Ă����̂��悩�����B�������������́A�r�{�ɂ��肢����ق��͂Ȃ��B��x�����Ƃ肵�������鏗���A���e�ɐU���Ă���Ăق����B
�@
�@��g�ł͓���ʒu�ɂ��������A���e�Ƃ̑g�ւ��ŌÑ��̐��g�̃g�b�v�����ɍ��������ޗD���B�D�]�̔����������u�䂪���͎R�̔ޕ��Ɂv�𖢌��̒i�K�ł����ƁA�����_�ł̔ޏ��̑�\��́A���܂��ɐ�g����́u���ʂ̃��}�l�X�N�v�̃g�D�[���x���v�l�ł���悤�Ɏv����B�������u�_���E���[�N�̗��v�u�c��v�uWEST SIDE STORY�v�Ɛ��g�Ńg�b�v�ɏA���Ă���̍�i���A���ꂼ��ɔޏ��̖��͂��悭�o���Ă������A���M�ȏ����̔ϖシ��p����������������Ă��̔ޏ��́A��シ��������p���ł���ۓI�ɏo�����̂��g�D�[���x���v�l�������悤�Ɏv���B
�@���ނ̓_���X�̐l�Ƃ����A�V���[�ł��̖��͂�����Ԃ�ɐU��܂��Ă���̂͂������A�n�B�����_���T�[�Ȃ�ł͂̕i�̂���g�̂��Ȃ��ŕ�����������߂Ă���B����ȕi�i�̂���p�ƁA�A�e�̂��₷���\������܂��āA���M�Ȕϖオ�܂��Ƃɂӂ��킵�������ɂȂ����킯�����A��g����̔ޏ������Ă���ƁA�����ɏa���������A���܂������Ƃ��Ęe�ɉ���Ă��܂������ŁA�S�z�������B
�@���̈Ӗ��ŁuWEST SIDE STORY�v�̃}���A�͑傫�ȃ`�������W�ł������킯���B���Ƃ��Έ���l�N�́u��������̂Ƃ�̒��Łv�Ŕ������Ă��������炵�����A�Ăтǂ̂悤�ɏo�����Ƃ��ł��邩�B��g����ɘe�̈ʒu�Ŋl���������������������Ƃ��Y��Ăł��A�e����悤�ȉ₩�����Ăъl������K�v���������킯������B���ہA���ނ̃}���A�͓��������ő匀�������肩�Ȃ�悭�Ȃ����ƕ����Ă��邪�A������X�e�b�v�ɂ���A�������ł͐V�������P�����ł��������Ă��͂��ŁA���悢��匀��������y���݂��B
�@��͂�_���T�[�ł��������Ԃɔ�ׂ�ƁA���ނ͖��_���T�[�ł͂����Ă��A���S�ɂȂ��ėx�肫��^�C�v�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�f���G�b�g�_���X�̒��Ŕ�����������A��˂̐����I�Ȗ����ł���悤�Ɏv����B���̈Ӗ��ł́A�����悤�Ƀo���G���x�[�X�Ƃ��閫�Ƃ̃R���r�ŁA�܂��܂�������������Ă������Ƃ��낤�B���̌�����Ƃ́A���ɂڂ��������Җ]���Ă������̂����A��͂��l���ۂ������Ƃ肵���F���Ƃ������ׂ����C����悤�ȏ�ʂ̂��Ƃ��Ǝv���Ă���B
�@
�@�咹�ꂢ�����ڂ��W�߂��̂́A�u���F���j�b�N�v�̃A�K�[�g�Ƃ����ԉ��̏���l�������Ƃ����邾�낤�B���X�Ƃ��Ă������A�����݂��Ƃȉ̐��ɕ������ꂽ�B�������Ȃ���A�����܂ł����̃q���C���͐�ق����ł���A�咹�͘e���ł߂�F���ۂ��I�o�T�����B���ނƓ��l�A�咹���e�ɉ��̂��Ǝv�������Ƃ��������B���āA�ł̓g�b�v����I�ڂ́u�閾���̏��ȁv�ŁA�ޏ��̃g�b�v�����Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȕ��_�������邱�Ƃ��ł������낤���B
�@�V�����g�b�v�����ɂ́A�ǂ��������ď��X���������߂����B�Ƃ��낪�A���̂���Ƃ������ŁA�ޏ��͂Ȃ��Ȃ����炵�����o�����Ƃ��ł��Ȃ������B�����̒u�����ň�Ԃ̌|�W��������z���A�����݂���̔������������Ēj�ɂ��ėm�s����Ƃ��납��n�܂�A�Ȑ܂̓��Ƀt�����X�ŎЌ��E�̒����ƂȂ�A�v�ƑΗ��A���{�ɖ߂��ĕa�ɓ|�ꂽ�v���Ŏ��A�Ō�Ɏ��������̗��������m�肷��Ɣ��X�Ɖ�������Ƃ������ǂ���ł́A�ޏ��̊ј\�͏o���Ă��A���̗v�f�͂Ȃ��Ȃ��\��ꂸ�A�g�b�v�����Ƃ��Ă̔ޏ��̕]���ɂ��Ă͕ۗ�������Ȃ������Ƃ����̂��A�����ȂƂ��낾�����B
�@�u�^���S�E�A���[���`�[�m�v�ŁA�ޏ��͂܂����Ă��l�Ȃł���B�g�b�v�X�^�[�̈��݂ꂪ��w�����ƁA�����ƎႭ�Ȃ������ƂŁA�咹�̗������������͋C���������Ėڗ��i�D�ɂȂ����B�������w�������̂��M���̈��l�ɂȂ��āA���ʂ��A���݂̗{���ɂȂ��ė��������Ă܂������������킯������A�ǂ��������ėc�ȍȂƂ͌����Ȃ��B�ǂ������ɂȂ����f��𐏕����F���Ă��邻��������A�l�ȂƂ����̂����߂ċ��łɕς��邱�Ƃ��炢�͊ȒP�ɂł������낤�ɁA���r�C��Y���������Ȃ������Ƃ������Ƃ́A��͂�咹�ɂ͐l�Ȃ��������Ǝv���Ă���Ƃ������Ƃ��B
�@����͈�̓��ď����Ƃ��Ĉ������Ƃ��Ƃ͌����܂��B�ޏ��̓������悭�������Ă���Ƃ������Ƃ��B�������A��˂̃g�b�v�����Ƃ��āA�Ȃ�Ƃ��ޏ�������Ȕ������A���炵���������o�����Ƃ��ł��Ȃ����̂��B���ނɃ}���A�����������Ƃ́A�����炭�傫�Ȑ����ƂȂ��Ĕޏ��̖��̕����L���邱�Ƃ��낤�B���̂悤�ȃ`�������W���A�����咹�ɗ^���Ăق����B�������Ȃ��ƁA���̖����L����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@
�@���̈Ӗ��ŁA�h�ꂢ�̃g�b�v�����Ƃ��ẴX�^�[�g���A�S���c�A�[�����u���������̗��v���������Ƃ́A�b�܂ꂽ���Ƃł������B��g�u���h�v�ŐV���ŏI�w�N�ɂȂ��Ď���ɔ��F���ꂽ�킯������A�����̃t�@���ɂƂ��Ă͂��܂��ۂɎc����̂Ȃ��A�܂����ς�������Ă��Ȃ����k�������B�u�₿���̗��v�̋ʔ�����_�ȉ��ρA�O���ڂԂ�ʼn��߂Ęb��ɂȂ��Ă���̂́A�ޏ����g�b�v�ɂȂ������炾�B
�@�u���h�v�V���A�u�����̃I���t�F�v�Ɠ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����������Ă��邪�A���̂��ɂ͔ޏ��̖̕����L���Ƃ�����ۂɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B�������A���Ȃ������\�ɏo�āA����Δ��e�䂦�̔ߜƊ�����ɗ����Ă��܂�������������Ȃ����A�ޏ��̈�r�Ȏŋ��ɑ��鐽���������������������Ԃ̂��ƐM���Ă͂���B
�@�u�̌��v�̃|�[�g���C�g�Ȃǂ����Ă��A���߂Ă��̔��������D�܂����v�����A�ޏ��̍ő�̌��_�́i���͂܂������ׂ����炵���Ƃ������邩������Ȃ����j�A�����邱�ƁA�����邱�ƂɊ���Ă��Ȃ��Ƃ����_���Ƃ����邾�낤�B����͔ޏ����X�^�[�H���𑖂��Ă��Ȃ��������߂��낤���A�ڂ����ĎO�w�E���Ă����̈ʒu�̈����ɂ��Ă������������Ƃ��낤���A���ςɂ��Ă������Ɛ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ߑ��̒����ɂ��Ă�����������Ɖ��Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ǝ����䂭�v�����Ƃ�����B���������̔��e�Ȃ̂Ɏ��ܕ\����h���ɂȂ邱�Ƃŕ���Ă��܂��̂��A�����͓������B�������́A�{�l�̎��o�ƌ������K�v���Ǝv�����A�����K�v�Ȃ̂́A�ڂ������ϋq�̎����ł���A����𐳖ʂ���ޏ����~�߂Ă���邱�Ƃ��B���̂��߂ɂ́A���������A���Ԃƌo�����K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@
�@���߂ɂڂ��́A���N�O�̖����g�b�v�����U�ȉ��ł���A���̔ޏ������ɔ�ׂ�͂邩�Ɂu�Ⴉ�����v���Ƃ��w�E�����B����𐬏n�ł���ƌ����Ƃ��āA����͂��Ƃ��Βj���Ƃ̊W�����i�ɐ�߂�ʒu�ɁA�Ȃ�炩�̌��ʂ������炵�Ă���͂������A������������͉����낤���B���Ƃ��A�g�b�v�����̒n�ʂ͏オ�������낤���H�@�c�O�Ȃ��ƂɁA���ꂪ�͂Ȃ͂������ɓ����Â炢�ݖ�ɂȂ��Ă��܂��̂��B���`�̓i�^�[�V���A�G���U�x�[�g�Ƃ����悤�Ƀ^�C�g���E���[���𑽂������Ă���B���͂Ɩ������܂���]���Ă����Ɏ����Ă���Ƃ����邾�낤�B���Ԃ��o�E�ŁuLast Steps�v�������������Ƃ́A��˂̗��j�Ɏc�邱�Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B�_���X��������z���Ă���Ǝv��ꂽ�ޏ����A���Z�ł̕\���͂��}�L�A�̏��͂������ȃ��x���܂ŒB�������́A�{���ɂ݂��Ƃ������B���ނ����ăG�X�v���z�[���ŁA�M�邯���ƍ����̌`�ł��������f�B�i�[�V���[��������B�����������́A�g�b�v�ɒ������邱�Ƃւŏ����������̂�������A��z�����Z�ʂɌh�ӂ�\�킵�ޒc��ɂ��ނ��̂�������A�g�b�v�ɏ�����n�ʂɊÂĂ��邱�Ƃւ̈��̂��l�тɋ߂��z���̂悤�Ȃ��̂̂悤�Ɏv�����B����Ɩ��T����l�Ńf�B�i�[�V���[�uSo long�v�����Ă��̂��A���T�̑ޒc��ɂ��ނ̂ƁA���邪�����Ƃ��Ă̑傫���𑝂��Ă��邱�Ƃ���ԂƂ��������ł���A���邢�͂��Ɍ���ǂ�������ڗ����Ȃ������邽�߂̃W���C���g�������悤�Ɏv����B
�@�܂�A���ΓI�ɂ��̐��N�Ԃɖ����̒n�ʂ��オ���Ă����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���܂��ܗ͂̂���g�b�v�����������ďo�Ă����Ƃ������Ƃɉ߂��Ȃ��悤���B�ޏ������̌X�̗͗ʂ�݈ʂ̒����ɂ���āA���X�ɒn�ʂ��ςݏグ���Ă��������ŁA����͌X�l�̒��ɂ����~�ς���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B���ۂ̂Ƃ���咹���h���A�g�b�v�����Ƃ��Ă̈�̓��̃X�e�b�v����i���瓥�ݕ����Ă���悤�Ɏv����B�ł��ێ�I�Ȃ̂́A�t�@���Ȃ̂�������Ȃ��B���Ƃ��A�������o�Ă������A�����̉̂��I��������ɔ�������邱�ƂɁA�q�Ȃ͂Ђǂ����a�Ȃ悤�Ɏv����B�܂��A�q�\�q�\�b��C���^�[�l�b�g�̈ꕔ�T�C�g�Ō��킳���A�V���ɏA�����g�b�v�����ɑ��鈫�ӂɖ����������̐��X���A�ޏ������̂Ђ��ނ��Ō����ȔM�ӂ��킮���ƂɂȂ�˂������Ɗ肤���肾�B
�@
�@���āA�g�b�v�ƃg�b�v�����́A��˂ł͗��Ɋׂ邱�ƂɂȂ��Ă���B�������Ȃ���A�߉��p���q�����g�S���c�A�[�u���������̗��v�ɂ��āA�u���Ɖ��肩���l���o�ꂵ�Ă���A�������̓�l�͗��ɗ����Ă�����܂��v�ł���͂��Ȃ̂Ɂu�^�Ձ��h�ɂ͂��̊i���Ȃ��v�ƒf���Ă�����悤�Ɂi�u���������E�ւ̋ߓ��v�A�w��˃A�J�f�~�A�x�W�����j�A���̋�C���A�E�v���I���Ɍ���Â���Z�������A���ׂẴg�b�v�����������_�Ŋl�����Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ́A��͂蕨����Ȃ��Ƃ��킴��Ȃ��B���̔Z�����Ƃ́A�Z�p�I�ɂ͎����̔M���Ƌ��ɁA������Ƒ��������̗����ʒu�A����ɂ���Ď����I�Ɍ��肳���g�̂̊p�x�A�w�̔���Ȃǂ��琶�ݏo�������̂��Ǝv���B���̂悤�Ƀe�N�j�J���ɉ����ł����_�ł���A�����ɉ��P�����͂��^�ׂ��ł����āA���قǐ[���ł͂Ȃ��B
�@�������ڂ����{���Ɋ뜜���Ă���̂́A�u���E�V�F�C�N�X�s�A�v�̌����]�ł���⒆�r���[�Ȍ`�łӂꂽ���A���ꂪ��ˑS�ʂ̃i�`���������ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B�q�[���[�ƃq���C�����o����Ď��������������r�[�A�Â₩�ȉ��y�Ƌ��ɃX�|�b�g���C�g����l�ɓ�����A��l�̓��Ɍ���n�[�g�}�[�N�c�c���̂悤�Ȍ��i���{���ɖڂ̑O�œW�J����Ă��܂��A�ڂ������́u�P�b�v�Ƒ������邩������Ȃ����A���́uWEST SIDE STORY�v�̑̈�ق̃_���X�V�[���ł̏o����傴���ςɂ��������������悤�ɁA�ڂ������͂��̂悤�ȃX�e���I�^�C�v�������Җ]���Ă���̂ł͂Ȃ��������B
�@�m���Ɍ��g�u���������̗��v�ł́A�܂��g�b�v��I�������Ƃ������Ƃł���ȔZ���������҂���͍̂���������������Ȃ����A�܂��`���̎w�E�ɖ߂�A���N�Ԃ���������Ă����낤�A�܂�����̃g�b�v�X�^�[���ǂ����ĂȂ낤�A�Ǝ���X�������Ȃ��Ă��܂��B�h���咹���A���e�ł������A�j���̋��ɔ�э��݁A���ׂĂ��ς˂邱�ƂɁA������Ɖ��a�Ȃ̂�������Ȃ��B�������A�~�߂�j���̕��̖����w�E���Ȃ���Εs�����ɂȂ邾�낤�B���߂̌���ɐg���ςˁA�����l�����ɔ�э���ł��܂�����ŁA�����炭�͔ߌ��ɏI���h���}���n�܂�B����Ȃǂ��ɂ����悤���Ȃ��^����Ԃ��Ă����̂��A��˂̃g�b�v�R���r�Ɋ�ꂽ���҂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����B����������Ɨ����Ă����悤�ȁA���퐫�ɗ��r�����쌀�������A���ꂪ�������ł���悤�Ȑ��k�������Ă��܂��ƁA�ŋ��̕��͂܂������A�V���[�̂����Ƃ肵���f���G�b�g�_���X�Ȃǂ͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��ƁA�S�z�ɂȂ�B
�@���ܔ��܂����v���̂��A�V�l�����Ŏ��̖������{���̏㋉���i�������ł������肷�邱�Ƃ����邪�j�̔����A�����A�}�g�A�\��c�c���ׂĂ���������ɐ^���Ă���悤�Ȏ����B����܂Ђ邪���e�A���琬�����˂����́A���Ђ��肪���Ԃɂ������肾�������ƂȂǂ��A�������v���o�����Ƃ��ł���B���܂��܂Ȍ`�ŕ�˂̖����炵���Ƃ������̂��p������A���邢�͔ے肳�ꂽ��ǂ��z���ꂽ�肷��̂��낤�B�����ɂ����āA���̕M�҂����y����邾�낤���A���̖������Ȃ��Ȃ�����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���鍡�A���݂̃g�b�v�����́A�����̏o���Ƌ��ɁA����̖��������ɂǂ�Ȕw���������Ă����邩���A�傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���Ǝv���B
�@��˂̃t�@�����������ς���Ă���B�u�閾���̏��ȁv����ԃt�@�������Ȃ������̂́A���k�̂����Ƃ������́A�����̈ӎ����\���N�̓��ɕς���Ă������ƂƁA��i�̒��ɗ���Ă����������o�≉�Z�Ƃ������u�ɂ���ĉB���ł��Ȃ��������Ƃɂ��Ƃ����悤�B�T���ĕ�ˉ̌��̏����ς́A�����炭�����ϋq���ӎ��������쑤�́A�����Ċϋq����̌����܂��͎����ɂ���āA���������ێ�I���Ƃ����悤�B����ł�����͏������^�C�g�����[���Ƃ�����i����������A�������Ђ��傤�ɑ傫�Ȗ������ʂ�����i���������肷�邾�낤�B���ɂ��̖G��͂���B�������̉ߓn���ł���Ƃ�����A����ɗ����������Ƃ̂ł��鐶�k���ڂ��������A�Ђ��傤�ɍK�����B���̍K�����A���Ɉ�ĂāA���̎���ɓn���Ă������B
���W�u��˂ɖ]�ނ��́v�`�l����\��˂͂��������Ă�
�@�^�D�R�G���ނ߂����ɁA���ɂ킩���Ă������Ƃ��B�L�]�Ȑ��k���ǂ�ǂ�ނ߂Ă����B�g�b�v�݈̍ʊ��Ԃ����܂�ɂ��Z���B�����͂��ׂē����ŁA�v����Ɉ������g�b�v�����`���͂т����Ă���Ƃ������Ƃ��B�̌��c�ɂ��A���k�ɂ��B����͗��Ƃɂ�Ƃ�̂悤�Ȃ��̂ŁA�̌��c�̎g���������k�̈ӎ�������Ă������A���k�̈ӎ��������Ȃ�̌��c������������Ȃ��Ȃ��Ă����A�Ƃ������̂Ȃ̂��낤���B����A��͂萶�k�̗���͎ア�B�����̖��Ɍ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ���i�������A�g�b�v�ɂ��������ꂪ�Ȃ��Ƃ��������������Ȃ�A�g�b�v�H�����O��Ă��܂������k�����@��������Ă���悤�Ɏv���Ă��A�v�������Ȃ��Ƃ���ł��������낤�B
�@���݂̕�˂��A���\�ܔN�̗��j���~�ς��Ă�����Y�̍ė��p��}���āA���̌��݂𑝂����Ƃ��Ă���̂́A�������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���B����̍ĉ��́A���ڂ����Ԉ��Ȃ���Ί��}���ׂ����Ƃ����A�n�f�̂�����u�z�[���J�~���O�v���l�I�����ԈႦ�Ȃ���Α������ނ��Ă����ϋq�ɂƂ��Ă��z�[���J�~���O�ł���A������悾�Ǝv���B
�@�������A�_�b�����ꂽ��i��l���Ăь����邱�ƂŁA�������݂�����Ɍ�����Ƃ�����A�t���ʂ��r�������Ƃ������ƂɂȂ�B���̂Ƃ���́A�u�|�p�Տ܂��Ă����Ă��A�����������ƂȂ�����Ȃ����B����ɃA�i�N������ˁv�Ƃ��A�u�������̖���V���[�A���k����������ˁv�Ƃ��������x�ŁA���݂�Q���悤�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ǝv�����A���̂��Ƃ����݂̃��x����ቺ�����邨���������B
�@��ɂ́A���o�Ƃ����̍�i���\�̋@��̌����Ƃ��������̂��ƁB������́A���݂̑g�\���f���Ă��Ȃ���i���㉉���邱�ƂŁA�z���ɖ������o�Ă�����A���R�����Ǝg����͂��̐��k�ɂ����������Ȃ��Ȃ�����A���ɍ���Ȃ�����U��ꂽ�肷�邨���ꂪ����Ƃ������Ƃ��i�������u�����ҁv�ȂǂƏ̂��č�i�����ς���Ƃ�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�����Ă��͉����Ƃ������ʂɂȂ邾�낤�j�B
�@���ʓI�ɂ��̂悤�Ȉ�Y�̍ė��p�����݂ɑ傫�Ȗ�����^���Ă���Ƃ�����A���̂Ƃ�����͐��k�Ɗϋq�ɒ��˂�����A�ŏI�I�ɂ͊ϋq���̌����Ƃ����`�ʼň��c�ɋA���Ă����B�������ƂɁA���̑O�ɂ͔����~���[�W�J���������Ă����������������B��i�̎��̖ʂł͂悩�������낤���A���H�����̃g�[�g�Ƃ��������Ƌ����悤�ȑ哖������������Ƃ͂����A�������̖������܂�ɏ�����������A���ɂ͍ĉ��Ɠ��l�Ɏ������I�ȉ��ڂ��������B����Ɉ������ƂɁA���̂悤�Ȍ��݂ւ�ᰊ��A�����ɂ͂����Ƒ傫�ȃc�P�ƂȂ��ė��܂��Ă����B
�@���t��҂̑f���炵���Ƃ���́A����^���Ȃ�����҂���Ă邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B�̌��c���s�̎G���̍��k��Ȃǂ�ǂ�ł���ƁA��͂肢���铖�ď��������Ă��邱�Ƃ��悭�킩�邪�A�u�ޏ��ɂ���ȃq�[���[���������������v�u�ޏ��̂���Ȗʂ����Ă݂����v�Ƃ����v���̏W�ς��A��̌�������Ă����̂ł͂Ȃ����B����ɂ���đ����̐��k������̌���L���ɂ��A�Z�ʂ����߁A���͂�{�����Ă����̂��B
�@�ĉ����┕�����ł͕K���������ꂪ���܂���]���Ȃ��B�������A���ď������ꂽ���̂ł͂Ȃ����āA�e����悤�Ɋk��j�鐶�k�����邾�낤�B�������A���c�̂����Ă���͂�S�̂ɒ�グ�ł���̂́A���̂悤�ȁu�܂��ꓖ����v�ł͂Ȃ����낤�B
�@���߂̕��ŏq�ׂ��A�L�]�Ȑ��k���ǂ�ǂ�ނ߂Ă����Ƃ������ƁA�������͂��̎���ɂ����������Ƃ�������Ȃ��B�������A�ڂ����u�������g�b�v�����`�v�Ƃ������̂́A�g�b�v�A���邢�̓g�b�v�̐��k�ɂ����������^���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B���e���ƌĂ��X�^�[�����܂�邽�߂ɂ́A�{�l�̂�����x�̎v����i������߁A�Ƃ����Ă�������������Ȃ��j�ƁA���̎v����ɉ����邾���̌������p�ӂ��邱�Ƃ��K�v���B�u�G���U�x�[�g�v�Ƃ�����i���f���炵�������̂́A�O�l�����ɂ��Ȃ���A�}�b�N�X�A�]�t�B�[�A���B���f�B�b�V���ȂǁA������̂���e����������Ɨp�ӂ��Ă������ƂŁA����ɂ���Ăڂ�������������A�o�_���A�˂�����������\���邱�Ƃ��ł����킯���B�������㉉��i�I��ɓ������ẮA���̂�����͂��イ�Ԃ�z������Ă���Ǝv�������̂����A�uWEST SIDE STORY�v���g�b�v�ɂƂ��Ă����K�������K���ł͂Ȃ������悤�ɁA�ǂ����Ă������̂���z���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ͔������܂��B
�@���������L�]�ȕ�˂̒j���ɂƂ��āA��̕�����ƂȂ�̂́A�������g�b�v�ɏA�������ɂȂ��Ɨ\�����鎞���낤�B���炩�̌`�ł����ʍ�����邱�Ƃ�����ƕ����Ă���B�e���Ƃ��ĕ�����x���Ă������Ƃ�����ɉۂ����A���邩�B�O�҂�I�ڂ��Ƃ��Ă��u���������Ă��ŋ߁A�e�����āA�낭�Ȃ̂Ȃ���˂��v�ƍl������ł��܂��悤�ł́A�撣���Ďc���Ĉ������Ė��ɊÂ悤�Ƃ����C�ɂ��Ȃ�܂��B�����ӂ߂邾���́A��˂ɉ䖝���Ȃ���ł��c�葱����Ӗ����ڂ��͔ޏ��ɐ����ł��Ȃ����낤���A�����������Ǝv�킹�邾���̑����I�Ȗ��͂����̕�˂��������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁA���������X�Ƒނ߂Ă����Ɏ����Ă���̂��낤�B
�@���쓵�́u���ޒc�v�́A���Ɏc�O�����������������A�S�̓I�Ɍ���A�������Z���Ƃ����Ă��鏗���̕��ɂ����e��������悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B�ڂ��̍D�݂ŋ����Ă��A�ĉ͂��A�o�_���A�����u���A�M���݂ǂ�A�Ă����A�ܕ�A�����M���A���X�B���c����\�ܔN�O����o���ޏ��������A�ŋ��ŁA�_���X�ŁA�̂łƁA���ꂼ��̌����P�����ĕ�����������߂Ă���̂�����ƁA�ƂĂ����������A���S���Ă�����悤�Ɏv���B�����͏����Ƃ��đ��݂���Ƃ����������o����A�ĊO�����傫�ȑ��݂Ƃ��āA���������₩�ɑ����邱�Ƃ��ł���̂�������Ȃ��B
�@����ɑ��āA�j���͂ǂ����B�j���̏ꍇ�A���݂ł̓g�b�v�A���g�b�v�ɑ����A�O�Ԏ�A�l�Ԏ�A�ȂǂƂ����������㑶�݂��Ă��āA����͂قڊw�N���ɐ������邩��A�N����������ł��āA���Ԏ�ƌĂ�Ă��Ȃ��j���́A�����Ƙe�̖��ǂ���ɉ�炴������Ȃ��Ȃ��Ă���B���A�����Ɋe�g�ŏ��g�b�v���㋉���������ŁA�g�����̊����ɂȂ��Ă��Ȃ����k��������ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�@�@�ԑg����āA�唺�ꂢ��
�@�@���g����������A�^�R�t��
�@�@��g�����ʂ����A�n��W
�@�@���g���ɂ������A��܂Ȃ�
�@�@���g���^���Ђ���A�z�͂邫
�@������L�b�ƈ������߂�A�ʍD�݂ł��Ԃ���̖����҂�������Ă��đf���炵���̂����A�����Ɍ����āA�g�b�v�𑈂����Ƃ����鐶�k�́A��l���c���Ă��Ȃ��B�������A�N���Ƌ��ɐl��������A�g�ւ��ɂ���ăg�b�v�H���̎҂��e�g�ɎU�炵�Ă����Ƃ������Ƃ����邾�낤�B����ɂ��Ă���˂ł͂��̎���ł������Ȃ̂��낤���A�g�b�v��ڎw���ăg�b�v�ɂȂ�Ȃ������j���́A��˂����邱�Ƃ����ł��Ȃ��̂��B
�@����ł͕�˂̎ŋ��͑����Ă��܂��B�u�X�^�[�̏������v�̃C���^�r���[�ŖP�����A�g�b�v�͉̂ł��_���X�ł��Ȃ�ł���тʂ��Ă��܂��K�v�͂܂������Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă������A�������Ȏ��͂̂��鐶�k�������e�ɉ���Ďŋ�����߂Ăق����B�C���Ђ낫�̂��Ƃ��v���o���Ă���̂����A���̂悤�Ȏ��͂��A�����Đl�C�������āA�o�E�����̎���邮�炢�̐��k���A�g�b�v�̘e�Ŏx���Ă���A���������g�\�����߂������w���A��i�Â���A�`�Ԃ��Ƃ�Ȃ����̂��B�Ƃ肠�����͐��N��Ɍ����āA��ɋ������悤�Ȋe�g�ɉ��l������e��w�ɁA�ڈ�t�����������Ă��炤���Ƃ��B���ꂪ�����������̂��߂ɂ������h���ƂȂ�A�����z�ނ��낤�B��������A���Ƃ����^�R�ꂨ�̂悤�ȃ`���[�~���O�Ȑ��k���ޒc���悤�ȂǂƂ͎v��Ȃ��ł��ނ��낤�B���̂��߂ɂ́A�x�e�����̎��͂ɕ����Ȃ������̌��݂̂���r�{�Â��肪���߂���̂��낤���A�����v�����Ĉꎞ�I�ɂ���O���̍�Ƃɓ��ď������Ă��炤�����Ȃ��̂��A�Ƃ��v���Ă��܂��B
�@�������A�����̐��k�͉���ԁA���e���������Ă��炤���߂ɐ�Ȃ�����Ƃ���ӌ������邩������Ȃ��B�������A����ł͎Ⴂ�e�����ł��Ȃ��킯�����A�g�̐����Ƃ����ʂ��猩�Ă��ǂ����B���Ƃ��Β��g�͑g�����Ⴍ�A�S�̓I�ɎႢ�g�����A����ɂ��Ă��u�G���U�x�[�g�v�������������A���ЂÂ��Ƃ�����Ȃ̂��o��͂��������Ȃ������B�����̃}�b�N�X���݂͂܂����X�Ƀy�[�X�ɏ�ꂽ�Ƃ͂����A���̃��h���B�J�͂ǂ����Ă����̌��̃e���|�ɂ��Ă������A���Ă��ċC�̓ł������B�ڂ�����˂����n�߂Ă���̐��N�A�g���E���g���Ɛ�ȂƂ̓���ւ��͂��������̂́A�����̐��k����Ȃɓ��������m��Ȃ��B�܂��Ȃ͍���̈�r��H���Ă���킯�ŁA�����̐��k�ɂƂ��āA��Ȃɓ��邱�Ƃ��܂��������͂������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ̏؍��ł����邾�낤�B
�@�����̃x�e�������k����Ȃ��g������Ă��Ȃ��Ƃ�����Ԃł́A�z�[���J�~���O���A�ߋ��̖��삾�ƕ��ׂ�����A���̎��Y��L���Ɋ��p���Ă��������Ƃ��������Ȃ��B�܂��͌����̐��k�Ɍ����������āA����ɗ��������Ă悩�����Ǝv�����������Ă������Ƃ��}���Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�@���āA�ڂ���������[���ɐS�z���Ă���̂��A���̖����̂��Ƃ��B�Ȃ�̎�����Ȃ��s�o�����������N�̂s�b�`�X�y�V���������A�e�g�̖����̃��C���i�b�v�́A�ȉ��̒ʂ肾�����B
�@�@�ԑg���������A�錜�O�R��A�������
�@�@���g����h�ꂢ���A�Ԑ��݂����A�����O�b�A�����
�@�@��g���M������A���c��v�A����܂Ђ�
�@�@���g���H���邢�A�H�������A�����G���J�A�ܗ����]
�@�@���g���˂����́A���Ђ���
�@�����ɏo�Ă��Ȃ���薺���ŁA�����J�����_�[�ɍڂ��Ă�����A���N�̃o�E�ŏd�v�Ȗ���������悤�Ȃ߂ڂ����҂�������ƁA���g���v�H������A���삠�����A�ԑg���������݁A�ʔT���Ȃ��Ƃ������Ƃ��납�B
�@�b��[�܂邪�A���̒��Œ�R�Ȃ��u���v�ƌĂׂ�҂ɂ��Ă����ƁA�o�E������V�l�����ł͎�������������o��������Ƃ͂������̂́A�����͂܂��{�����̃g�b�v������S�z������قǂ̔��͂�L�т₩����g�ɂ��Ă���Ƃ͌����������B����ɂ��j���̘e���Ɠ����̖�肪����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�܂�A������l�̖����ɓK�Ȍ������^�������i�����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B�g�b�v�������Ⴂ�����ɗ^������������Ȃ��悤���B�����ȂǁA���̑ΏۂɂȂ�Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��ƁA���ʓI�ɐl�{���Q�ł��ǂ���̂Ȃ����Z�ɏI�n���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��g�b�v���߂���O�p�W�̓�Ԏ肩�A���g�b�v�̗��l�Ƃ������ǂ���ŁA��ۂɎc����̂��ӊO�ɏ��Ȃ��B�ŋ߂ł́u�v�̃g�D�[���x���v�l�i���ށj�����ʂ���������x���낤���B
�@�܂��A�u�G�N�X�J���o�[�v�̃P�C�g�́A�{���͗˂����̂ł͂Ȃ����Ђ��肪���ׂ��������Ǝv���̂����A�����ł̓x�e���������Ƃ̐��������B���ɂȂ��Ă���悤�ŁA���̂��߂ɂ��ꂩ��g�b�v�ɏA���ׂ�������������Ȃ��L�єY��ł���悤�Ɏv�����B
�@��˂ɓ��c�����ȏ�A�N�������ꂼ��̌`�Ŏ��͂��⊶�Ȃ��������A�ł���Ώ\���N���炢�A���̍ݒc���Ԃ��[���������̂Ƃ��Ă܂��Ƃ��������Ǝv�����낤�B�ڂ����������āA���k�̈�l��l�������ł�������ƍ���A�{�����z���グ�A���ꂪ�ǂ̂悤�ȉԂł���A���ɊJ�����Ƃ�����Ă���B���ꂪ�����Ȃ�Ȃ���A���܂�ɂ炭�A�ڂ���������˂����ɍs�������Ƃ������̂��Ȃ��B���́A�������Ăق����B�@
����������V�����^�|�ߋE�͔������@�̂Ɨ̊X�A��ˣ1999�N5��1���������@��ނ̂��߂̃���
�@�ڂ����g�́A�����鏬���ꉉ���Ƃ��A���_���_���X�Ƃ��͂��[���ƌ��āA����ɂ��Ĕ�]�߂������͂���������͂��Ă�����ł��B�ŁA���[���F�B�ɗU���ĕ�˂����Ȃ�M�S�ɂ݂�悤�ɂȂ�܂��āA���x���U��ꂽ��ł����A���ۂ��Ă���ł��ˁB�u�N������̂͂��܂�Ȃ����ǁA�ڂ����������܂Ȃ��ł���v���āB�悫�����҂ł͂����Ă��A�����҂ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ă��������ł����B�ڂ��̒��ł́A��͂��ˉ̌��Ƃ������̂́u��O�|�\�v�ł���Ƃ��āA��i�Ⴍ����ӎ����������̂����m��܂���B
�@���x���U����f����Ă�����ł����A�Ƃ��Ƃ��u���x�̂͐��������v���ėU���āA���Ⴀ�܂��s�����A���Č����̂����g�́u���������̗��v�ŁA���ꂪ���������ʔ���������ł���B�X�g�[���[���\�������y�����Z���A�����Ȃ��A�Ǝv������ł��ˁB�u���Ⴀ�A���ꂩ������X����H�v�u������v���āA���Ɍ����̂��V�A�^�[�h���}�V�e�B�œ������g�́u���C�g���V���h�E�v���Ă��������Ȃ����ŋ���������ł����A�����łڂ��͖����M���Ƃ��������ɍ��ꍞ��ł��܂�����ł��B�v���A���̂ڂ�������Ă���̂́A���̏u�Ԃł��ˁB
�@���ꂩ��A���̖����M���Ƀt�@�����^�[���o������A����ɕԎ���������A���Ă����悤�Ȃ��Ƃ������āA�ǂ�ǂ�~�[�n�[�t�@���̓����܂�������i��ł�����ł��ˁB�ł��A���̍��́A�ڂ����{�i�I�ɘ_���ׂ��t�B�[���h�͂�͂菬���ꉉ����_���X�A������p�ł����āA��˂͑������A�������Ⴄ�A�Ǝv���Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@���ꂪ������ƕς�����̂́A�k�Ђ̂��Ə��߂Č����A�u�Ⴋ���͖̉̂Y�ꂶ�v�Ƃ���������������������܂���B�k�Ђ���2�T�ԗ]�A�������K�X���~�܂����܂܂̐_�˂��o���āA�������Вn���b�N�Ŗ��É��܂ł��ǂ蒅���Č��������ł��B���̎��ڂ��́A���������Ђ����狃���Ă���ł��ˁB���̂��ŋ��͓�������́u�䂵����v������Ƃ��Ă��āA�^���Ɋ������܂��l���̔߂�����A�v�����߂���c�����肵���܂܋����Ă����l�̔߂��݂��A�������`����Ă����ł��B���ꂪ�k�ЂƂ������̂��o�����������ւ̖����̂悤�Ɋ�����ꂽ�Ƃ������Ƃ��������Ǝv���܂��B�Ƃɂ������������̎��A��˂�����Ă悩�����A�Ƃ����ȏ�ɁA�ڂ��̐l���ɕ�˂������Ă悩�����A���Ă������A��˂Ƃ߂��肠�������Ƃ̍K����Ɋ�������ł��B�M���V���ߌ��ł�����J�^���V�X���Ă����������̂������ƁA�{���Ɋ�������ł��B�k�Ќ�A�܂��낭�Ȃ����Ƒ����̐l�������܂����A�ڂ����悭����ŋ����悤�ɂȂ�܂����B
�@���ꂩ��ڂ��́A�����ꉉ�����_���X����˂��A���ꂪ�W�������Ƃ��č����ł���Ƃ������I�ł���Ƃ��A����������A������Ȃ������ꉉ��������A�����I�ȕ�˂�����킯�ł����A�Ƃɂ��������������Ƃ����A���ꂪ�ڂ��ɂƂ��Ăǂ̂悤�Ȗ����ł��邩�A�J�^���V�X�ł��邩�A�Ƃ������Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B
�@����Ƃ����̂́A�����̋�Ԃł��B���̒��ŁA���҂�Ɩ��≹���A�I�P���A�ڂ������ɂǂꂾ���̖��������A����𗣂ꂳ���A�ʂ̎���ɘA��Ă����Ă���邩�A���ꂪ�ڂ�����������ɑ����^�ԍő�̗��R�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@��˂������̂́A���܂������Ƃ��l����K�v���Ȃ��A���������������Ƃ��A�߂����Ƃ��A�ǂ��Ղ芴��ɐZ���Ă�����Ƃ���ł��B���������Ӗ��ŁA��ˉ̌��ɂ́A���܂��]�͐������Ȃ��Ƃ������A�s�v�Ȃ̂�������܂���B��҂̐��E�ςƂ��A�\���̎��Ƃ������������Ƃ��˂ł͂��܂���ɂ���K�v������܂��A�^���ɍl����Ɠ����ɂ��Ȃ�悤�Ȃ킯�̂킩��Ȃ���i������̂������ł��B��{�I�ɂ́A��˂̓X�^�[�̖��͂��ő���ɔ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��č���Ă��镑��ł�����A��˂�����R�c�́A�܂��ڂ��������M�������āA��������Z���Ă������悤�ɁA�܂��N����l�̃X�^�[�����߂邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���ڂɂ���ẮA�S�̂�����A�X�g�[���[���y���ނ��̂�����܂����A��˂͂܂���l�̃X�^�[�̐g�̐��|�������A�_���X�̃L���A�̐��̑f���炵���A�������̉ؗ킳�A�ɒ��ڂ��Ă����Ǝv���܂��B����𒆐S���Ƃ��āA���̃X�^�[�����A�ŋ���V���[�̑S�̂����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B
�@���匀��ł���Ă����g�̃V���[�u�m�o�E�{�T�E�m�o�v�́A���Ɍ��g�ő�������܂��B�����V���[���Ⴄ���҂Ō��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����������A�ʔ����@��ł��B���Ƃ����A��������������Ă���̂��A���Ɏ����~���ǂ�Ȃӂ��ɂ��̂��A���������X�^�[�̈قȂ閣�͂��������Ă����Ƃ����y���݂𖡂킦����A�����ǂ��Ղ�ւ܂������炾�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
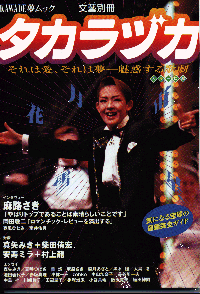 �j���^�J���d�J�ɂ͂܂闝�R�i�킯�j
�j���^�J���d�J�ɂ͂܂闝�R�i�킯�j
�@���Ƃ���_�ԂɏZ��ł��āu���l�t�@���v���ƍL�����邱�Ƃ́A������x�̃��X�N�����Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B���̂悤�ɂ܂��͂���ȏ�ɁA��_�ԂɏZ��ł��Ă��u��˃t�@���v�ł��邱�Ƃ�j�����L������Ƃ������Ƃɂ́A������ʗE�C���K�v���B�u���͎��A��ˍD���Ȃ�ł����ǂˁv�ƌ����ƁA�K���u�����H�@�܂��A�ǂ����āv�Ƃ����悤�Ȕ����ɂ������Ƃ��قƂ�ǂ��B���͂ڂ������N�O�܂ł́u�����H�v�ƕ����Ԃ����������B�z��҂Ɍ�������Đ��g�����u���������̗��v�i���쁁�A�r�F�E���o���ēc��G�B�剉�����H�����j������܂ł́B
�@�_�˂Ɉڂ��Ă���A�z��҂͗F�l�ɗU���ĕ�˂����Ȃ�M�S�Ɍ���悤�ɂȂ����B�ڂ��͂����鏬���ꉉ���͌��Ă������A��˂ɂ͋����������Ȃ������B��x�ޏ����u���x�̌����͂�������A���Ă݂Ȃ��H�v�Ɛ������������A�ڂ��́u�N����˂ɔM������̂͂��܂�Ȃ����ǁA�ڂ����������܂Ȃ��łق����v�ƃN�[���Ȓf��������Ă���B����͉ԑg�����u�S�̗��H�v�i�r�{�E���o���B�剉�������~���j�������킯�ŁA���ɂȂ��Ēn�c�ʓ���ʼn��������Ă���̂����B����ł����߂Ȃ������ޏ��́A�u���x�̂����Ă܂�Ȃ��Ǝv��ꂽ��A�����ꐶ�U��Ȃ��v�ƌ����Đ��ɂڂ������������Ƃ����B���ꂪ�A�����䂤�̃P�K�ɂ�������H����������Ŏ剉�߂��u���������̗��v�������킯���B
�@���āA�ڂ��͂Ȃ���˂�����Ă����̂��낤�B����������Ƃ��Ȃ������킯������A�H�킸�����ɈႢ�Ȃ��A�܂�͈�ʓI�Ȑ���ςɊ�Â������̂������킯���B�����ꉉ��������̂Ɋ����ɂƋ��͂����Ă��A��˂����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ƁB�����ꉉ���͌��āA�l���A�_����ɑ��邪�A��˂͂����ł͂Ȃ��A�ƁB����͂����炭�A�傰���Ɍ����A���w�_�Ɛg�̘_�A�Y�Ș_�Ɣo�D�_�̕���ɂ��̂ł͂Ȃ����B
�@�����ꉉ���̌����ł́A����Ƃ̖��O�ƁA�Y�Ȃ̎��̐�߂銄�������ɑ傫���B�u��c�G���̐V�삾���v�u�[�ÓĎj�A�ݓc�Y�ȏ�܌����I�v�Ƃ����ӂ��ɁB��˂ō�Ƃ̖��O����荹������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���ɒu�����̂͂�����g�b�v�X�^�[�ł���B�܂�A�����ꉉ�������A�_���邱�Ƃ́A��Ƙ_�ł���Y�Ș_�A���o�_�ł���A�܂�Ƃ��땶�|��]�ł���B�������A��˂�����Ƃ������Ƃ́A��i���盦������X�^�[�����邱�Ƃł����āA�|�\�ӏ܁A�]���L�ɋ߂��B���̂悤�Ȍ���W�������Ƃ��Ă̊i�t�����A�ڂ����˂��璷���������Ă������̂������ɈႢ�Ȃ��B�U��Ԃ�ΎO�\�N�ȏ���̊ԁA�ڂ��͂��̂悤�Ƀn�C�J���`���[�ɐg��u�����ƂŎ������䂵�Ă����킯���B
�@�f�n�͂������B���̂���ڂ��͊��ŗB��̉������������u�i�`�l�b���v�ɔ��荞��ŁA�_���X��]�̘A�ڂ��n�߂Ă����B�����ڂ��̓_���X���A�\����v���b�g�̓W�J�����߂���m�I�ȃA�v���[�`�ɂ���āA���̑S�̐������]���邱�Ƃ��\���Ǝv���Ă����B�������A�����𐔑������邤���ɁA�}���Ƀ_���T�[�����̐g�́E���̂��̂��̖̂��͂ɗ��ߎ���Ă����B�j�����킸�A�_���T�[�̔畆�̉��A���̌��A�����̉s���ɖ�������Ă����B���̖��͂�`�B����̂ɁA�m�I�ȍ�Ƃ͖��͂��Ƃ킩��������B����ł��A���Ɋ��ɂ����ă_���X�������܂Ń}�C�i�[�ȑ��݂ł��邱�Ƃ������āA�R���e���|�����[�_���X�║�������A���͂������Ƃ������Ƃ��n�C�J���`���[�ɑ�����c�݂ł��邩�̂悤�ɍ��o���Ă����B���̃X�m�r�Y�����A��˂Ƃ����u��O�|�\�v���݂��Ƃɑł��ӂ����ƂɂȂ�B
�@�u���������̗��v�́A�ĉ��Ƃ������Ƃ�����A��i�Ƃ��Ă悭�ł��Ă����B���邠�₩�͉��ŁA���H�����́A�̂������Ęb��ɂ��Ȃ���Ύ�X���������������ȍc���q�Ԃ肾�����B�悩�����B�������Ă����B�������A�ڂ����{���ɂ����Ȃ��Ă��܂����̂́A���ɔz��҂��ڂ��g�V�A�^�[�E�h���}�V�e�B���ʌ����u���C�g���V���h�E�v�i�r�{�E���o�����c�����j�ɑ��荞�������B��������̓��ɔ�s�@���s�������Ăǂ������Ƃ����悤�Șb�������Ǝv�����A�����łڂ��͘e���̂x�l�Ƃ��������̔������ɎQ���Ă��܂��B���Z���߂̔��e�A�p�̋C�i�A�����̗D�낳�A�����o���L�����Ȃ����A�v����ɂ�������Ă��܂����킯���B
�@�U��Ԃ��āA��˂̌����Ƃ��āA����͐������B�����[�����̐��k�ł����Ă��A��l���A��_���Î����邱�Ƃŕ���̗��ꂪ���������Ɣc���ł���B����́A��˂�����̑S�̐��������k�̐g�̔\�͂̌ʐ��ɑ������Ă��邩�炾�B���̑S�̂�c������悤�w�߂�����A�X�̐��k�̖��͂����\����ق��������Ɗy�����A���̋�C�̂悤�Ȃ��̂��ۓۂ݂ł���B�ڂ��͐�قǂ��q�ׂ��悤�ɁA���鎞�_����_���X�║����S�̓I�ȍ\����v���b�g�̓W�J�A�����Ƒ傰���ɂ����Ύv�z�◝�O�Ƃ������S�̓I�ϓ_���牉㈓I�ɔ�]���邱�Ƃ͂��Ɗ����Ă����B�_�͍ו��ɁA�ł͂Ȃ����A�ו����Î����A�����Ɋ��Q����Ƃ��납��A��i�̂��ׂĂ͋A�[�I�ɔ��f�����ׂ����A���Ȃ��Ƃ��ڂ��͂���ȍו��ւ̊Ⴔ�����ɂ��Ă������Ɗ̂ɖ����Ă����B�����Č����A���Ɍ����j���I��]����͉������������Ƃ�������Ȃ��B���i�ɐU�肩�Ԃ��Ďv�z��N�w����邱�Ƃ���߁A���Ⴊ�݂���ŋa�̑�������߂Ă���悤�ȊႴ���������ɉۂ����̂�����B���̂��Ƃɂ���āA���߂Ăڂ��͌ʂ̐g�̐��Ɛ[���t���������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������������Ƃ������C�u�ȃW�������́A�ۉ��Ȃ����҂̐g�̂����������肷��B���̏�~���[�W�J���A�I�y���A�̕���A�o���G�Ƃ��������y���A���x���ł���A��҂̎v�z��Y�Ȃ̊ϔO���͗y�����i�Ɉ����Ă����B�́A�_���X�A���Z�A�e�p�̂��ׂĂ����߂����˂́A���ł����̓x�������傫���ƌ����Ă������낤�B��˂ŃX�g�[���[�͑��`�I�Ȃ��̂��B�b�̋A���y�A������p�ȂǁA���ׂĂ͑��ɃX�^�[���P�����邽�߂̑��u�ł����āA��҂̂����鎩�ȕ\���~�����M�́A�{���قƂ�ǖ���Ȃ��B�و���̌����j�V�r�ƌĂ��悤�ɁA��˂̌��ɖ�����j�]���ǂꂾ�����낤�ƁA�X�^�[�̌������������ƍ���Ă�������A�悢��i�ł���B�u���ʂ���Ȏ��ɗx�����v�Ƃ����悤�ȂƂ���ł̃_���X�V�[���ł��A���̗x�肪�f���炵���A�ޏ��̖��͂��\�S�ɔ�����������̂Ȃ疞������B��������ɂ���Ȃ�̕K�R����T��o���Ă������邱�Ƃ͐�]�I�Ȃقǂɂ͓���Ȃ��A�����̏ꍇ�ڂ��͂�����ˊό��̖��y�Ƃ��ĕ]�����邱�Ƃɂ��Ă���B����ł����܂�ɔj�V�r�̓x���߂��邱�Ƃ������āA�������Ƀt�@�����o�ዾ���~�낵�āu���������c�c�v�ƙꂭ���ƂɂȂ�킯���B
�@�����̃t�@���͓���̒N����o�ዾ�Œǂ��Ă��邩��A�M�S�ȃt�@���قnj��̑S�̗̂����m��Ȃ��A�Ƃ����̂����X��k�ł͂Ȃ��B�ڂ������āA�x�l���[�����ŗx���Ă��鎞�ɁA�^�ŒN���x���Ă��邩�Ȃ�ĂقƂ�ǒm��Ȃ��B�u�}���R�����i���H�����j�̃��t�g�A������������˂��v�ƌ����āu����Ȃ́A�����������v�Ƃ��݂��ɐ�傷�邱�Ƃ������ł���B
�@���āA�x�l�ɂ�������ƂȂ��Ă��܂����ڂ������ɉ����������Ƃ����ƁA�t�@�����^�[���������̂ł���B�����̃~�[�n�[�ł��B�����Ă��낤���Ƃ��A�ޏ�����Ԏ�������B��ⳓ́u���莆�v�ł���B���Ƃ����Ɏ����āA�ڂ��ƕ�˂̊W�́A�l�I�R�тƂȂ�B�Ԃ����Ƃ܂Ō����Ă͔ޏ��Ɉ����̂Ŏ~�߂Ă������A���̕�����n���n�����Ȃ��猩��Z�̐S���ɏ�����B
�@��˂����邱�Ƃ̈�̊�т́A���̂悤�ȓ��B�\���z���邱�Ƃɂ���̂�������Ȃ��B��˂͌|�\�E��ʂƂ͈قȂ�A�v���_�N�V������}�l�W�����g�̃V�X�e�������镔���ŋ��łł͂Ȃ��A������Ń{�����^���[�Ȑ��x�Ƃ��Ă������k�X�̃t�@���N���u�����݂��Ă��Ȃ��̂ŁA�t�@�����X�̐��k�������i�����j�Ŏx���Ă���Ƃ����ӎ��������B�������r�M�i�[�ł������ڂ��͂����܂Ŗ��m�Ɉӎ����邱�Ƃ͂Ȃ��������A����҂��E�o�҂��Ŕޏ������̑f��ɂӂ�邱�Ƃ͂���������Ƃł͂Ȃ��B���ɖ����͎�芪�������Ȃ��A�ޏ������Ƃ�����Ƃ��������b�����킷���x�̊W�ɂȂ�̂́A�H�����l�̍����j���t�@���ɂƂ��āA���قǓ�����Ƃł͂Ȃ��悤���B�����炱���ڂ��ɂ���x�l����u���莆�v���͂����̂��Ƃ�������B
�@����u�Z�̐S���v�Ə��������A���l�Ƃ����̂Ƃ͂�����ƈႤ�悤�ȋC������B�ڂ����ȑю҂��Ƃ�������������̂�������Ȃ����A��˂̐��k�Ƃ����̂́A�����ł����������z���đ��݂��Ă���̂ł͂Ȃ����B��˂͉��҂̂��ׂāA�ϋq�̂قƂ�ǂ����������̏W�c�ł���B�����ł̒j���́A���Ɍ����u���z�̒j�����v�̃G�b�Z���X�z�����o�������̂ŁA�����ɂ͂��肦�Ȃ��j�������\�z���Ă��܂��Ă���Ƃ����Ă������B�ԑg�̃g�b�v�X�^�[�����������~�����ޒc��A����ŋ��̌m�Ï�ŁA�Y�{�����͂����o�D���֎q�ɍ��|���Ă���̂����ċ������Ƃ����B��˂Œj���́A�Y�{�����͂��Ă���ȏ㗧���Ă��Ȃ�������Ȃ��̂��B��˂Œj�́Aᰂ̊�����Y�{�����͂��Ă��邱�ƂȂǁA���肦�Ȃ��̂��B�c�c�B�j���������ł���ȏ�A����ɑ��閺�������肤�ׂ��炴�鏗�����Ƃ��đ��݂��Ă��ē��R�ł͂Ȃ����낤���B�����ė��҂͓��R�̂��Ƃ����I�W�̐����̉\�������炩���ߔے肵�Ă���킯�ŁA�䂦�ɂڂ��͗��l�I�ȊႴ���𑗂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�����ɖ������i�H�j�Z�̊Ⴔ���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B������������������˂́A���̂悤�ɋ������u�Ƃ��ē����Ă���̂�������Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA�ɂ�������炸�ڂ��͂x�l�ɂقƂ�ǐ��������Ȃ��̂ŁA�z��҂�������Εs�v�c�����Ă���B�܂Ƃ��Ɍ��t�����킵���̂́A�k�Ђ̌�u�����̂Ȃ��n�}�v�̏o�҂��ŁA���݂��̖���������Ƃ��炢���B���q��̐}���قɋ߂Ă���ڂ��ɂƂ��āA�Ⴂ�����ɐ���������͎̂d���݂����Ȃ��̂ŁA���̒�R���Ȃ��B�Ȃ̂ɂx�l��O�ɂ���ƁA�����A�g���A�d�����Ă��܂��Đ���������ꂸ�A�������v���̂����ɂ��̔������p�������邱�Ƃ����ł���B�������A�����������Ƃ���ŁA�ǂ�Șb����������Ƃ����̂��B�u�����̏�ʁA�f�G�ł����ˁv�Ƃł������̂��낤���B����ȓO���ŁA�ޏ��ւ̎v����\�킷���ƂȂǂł��悤���B�q�Ȃ̋����牓���Ȃ��Î����A�����������Ă���ق����A�ǂ�قǍK�����B
�@�x�l�͂������ĕ���̒��S�Ō������������i�߂������S�����݂ł͂Ȃ��B����Ȗ������D���ɂȂ����������ŁA�ڂ��͕�˂��瑽���̂��Ƃ��w�сA������邱�Ƃ��ł����悤�Ɏv���Ă���B��g�ɐ��\�l�̐��k���Ђ��߂��Ă���̂�����A�X�|�b�g��������䎌�����ǂ��납�A�u�����哹��v�Ƃ��Ă����@�\���Ȃ����k�����Ă�������B�g�D�̒��Ő�����҂̉^���ł͂���B�������ڂ��́A����Ȕޏ������̎p������̂��{���ɍD�����B����ȋ������ŁA�����Ɩ������Ă���ޏ������̎p����A�l�����ɂ������������ڂ����ǂ�قǖ����ւ̊�]�ƗE�C����������Ƃ��B�܂��A������e���Ƃ��čD�ʒu�Ɍb�܂ꂽ�x�l���A���g�������������Ɠ����Ɍ����������ߗD��ɗ������߂ɁA�ǂ�قǂ̍H�v�Ƌ�J���d�˂Ă��邩�B����Ȃ́A����ɗ��ȏ�͓�����O����Ȃ����A�Ǝv���邩������Ȃ����A�ޏ��͂��Ƃ��Ε���̏Ɩ������������ƁA���ɂЂ����ގ��A�Ȃ������̏�����������A����������قǂ̋����\����c���Ă��邱�Ƃ�����B����Ȏp����������̒��Ɍ�����ƁA�����Ȃ��Ƃ���ɐS��v�����Ƃ��A���̌����x���Ă���̂��ƁA�S�������B�傰���łȂ��A�ڂ��͔ޏ�������l�ԓI�ɑ��h���Ă���B��������f��͒m��Ȃ����A�b�܂ꂽ�˔\�A�����ł͂Ȃ��C���A����ւ̓���Ƒg�D�l�Ƃ��Ă̐g�̏������A�����̃A�}���K���Ƃ��Ẳ₩�Ȏp�����邱�ƂŁA�ڂ��͂ڂ��Ȃ�ɐl���̏��������w��ł���悤�Ɏv���Ă���B�������������b�����T�����[�}���P�I�Ȍ�����������A���g�̎p���Ǝ˂����蔽�]�������肵�Ă���B
�@�������āA�ڂ��̐l���̓��X�̗���ƕ�˂͋����V���N������B������ł��[�������A����Â����̂́A����ܔN�A���g���É������u�Ⴋ���̉S�͖Y�ꂶ�v�i���쁁��������B�r�F�E���o����֍O���j�ł���B��\���قǑO�̐k�ЂŁA�Ƃ�Ƒ��ɔ�Q�͂Ȃ������Ƃ͂����A�s���R�Ȑ������������Ă����ڂ������́A����ƊJ�ʂ�����_�d�Ԃ̐؉w�܂ŕ����A��Вn���b�N�̂܂ܐV�����ɏ��B�T�C������w���R�v�^�[�̔����̂Ȃ��Â��Ȗ�A���R�Ɏg���邨���i�����܂��킪�Ƃł͐������K�X���ʂ��ĂȂ������j�A���X�ύ��݂��ǂ�c�c�B�����čĂь��邱�Ƃ̂ł�����˂̕���́A���؈�ࣂƂ��₩�Ƃ��ʐ��E�Ƃ������퓅��ŕ\�킳���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B���ꂪ�����ɂ��邱�Ƃ̈��g�I�@���E�̉B
�@��������u�䂵����v���r�F�������̍�i�́A�͂��ߎ����䂤�剉�ŏ㉉����A�ޏ��̑ޒc���Ė��H�����剉�Ŗ��É������ƂȂ������̂��B�����Ŕޏ������́A�^���̉ߍ���Q���A�l�̐��̂���Ⴂ�ɗ܂��A�v�����c���ċ����Ă����҂̖��O��������B�q�Ȃłڂ��́A�ޏ������Ƌ��ɓ�������̐��E�ɐ����A���ɖ߂邱�Ƃ̂ł��Ȃ����Ԃ�ɂ��݉���B�k�Ђ���̓�\���ԁA�����̊�������̂��̂ł͂Ȃ��悤�ȁA����̍V�Ԃ���ւ���ꂽ�悤�ȒW�X�Ƃ������X�𑗂��Ă����ڂ����A���߂ċ����v���̗h���̌����邱�ƂƂȂ����B������Ǝv���Ԃ��Ȃ��܂��j��`���A���ꂩ��͉�������悤�ɁA�����ǂ������Ƃ����āA�قƂ�ǂ��ׂĂ̏�ʂş�̗܂ɂ���Ă����B�܂��ɃJ�^���V�X���ߌ��ɂ���p�ł���B����ɂ���āA�ڂ��͎����̐l������˂Ƌ��ɒԂ��Ă������̂ł��邱�Ƃ��A�[���[���������邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɂ��āA�ڂ��͗��h�Ȉ�j���t�@���Ƃ��āA�����ɂ������đ��݂��Ă���B��˂̐��k�����ƁA��������邫��������^���Ă��ꂽ�z��҂ɁA���ƂȂ��Ă͊��ӂ��Ă���B
�@��˂ɉ�����V�g�ƈ����|���͑P���̋����ɂ���
�@�t�����X��œV�g�i�A���W���j�͒j�����������������A��ˉ̌��ɂ����Ė��ҁi���k�ƌĂԁj�͂��ׂēV�g�ł���ƌ����Ă������N�炩�ɁA�����������������v�Ƃ����e�[�[�ɂ�������Ă���悤�ɁA�����ɂ͑��∫��X�͂����������݂��Ȃ��B
�@����ł���˂ɂ͂����Έ������o�ꂷ��B���Ƃ��u�t�@�E�X�g�v��|�Ă����u�V�g�̔��A�����̗܁v�i'90�N�A���g�����B���r�C��Y��j�͓�Ԏ�̗����^�����₽���\��őV�g���������t�B�X�g���D�������B�����������܂ł��Ȃ����A����͂����܂ł��g�b�v�Ńt�@�E�X�g���̌��K�̖��͂��������Ă邽�߂ɑ��݂���̂ł����āA�����̓g�b�v���x�����Ԏ�j���̖����ł������肦�Ȃ��B�t�ɁA�g�b�v�͏�ɐ��`�ł���B���N�̐��g�����u�J�T�m���@�E���̂����݁v�i���r�C��Y��j�ŁA��Ԏ�̖��H��������������̘B���p�t���T���E�W�F���}�����݂��A�閧���Ѓt���[���C�\���̑g�D�𗘗p���Đ��E��������݂Ȃ���A�Ō�̓g�b�v�̎����䂤������J�T�m���@�i�F���t�ł�������A���̖]�݂̎����̂��߂ɐg�������D���Ƃ��ĕ`�����j�ɔs��Ă��܂��̂Ǝ��Ă���B
�@��˂ł͂����A���̂悤�ȓ�Ԏ�̈����͂����������ǂ���Ƃ���Ă���悤���B��˂̃e�[�[�ɂ͔�����̂����m��Ȃ����A�����̏ꍇ���`���������̕������͓I�ł���A�������A�܂�����̏�Ŗłт��}���邱�Ƃ����������Ɉ��̔��w����������B���͂����Ă��j�q���ŃN�[���Ȉ��̑��ɂ��Ă���A���̈Ӗ��Ŗ��H�͌��p�̔������A�q�Ȃ��������ވ��|�I�ȃA�E���ɂ���āA�悢�����X�^�[�ɂȂ��f�������Ȃ��Ă���B�����̂��Ƃ��ăg�b�v�ɏA�����H���A��˂ɂ�����V�����g�b�v����\���͑傫���B
�@���āA�l�Ԃ̓��ʂɓV�g�ƈ�������������Ƃ����̂͒��Ȍ��������A��˂ł͈�l�̃X�^�[�ɂ��̂悤�ȕ������i��^���A���ʂ̊������Y�����������邱�Ƃ͍D�܂�Ȃ��悤���B���Ƃ����N�̌��g�����u���Ƌ��ɋ���ʁ\�\�o�g���[�ҁv�i�V�C�S��剉�j�ł̓X�J�[���b�g�E�I�n���𖺖��̖��T�����ƒj���̐^�Ղ��Ƃ�����l�ɉ����������B������ʂɓ�l�̃X�J�[���b�g��o�ꂳ���A�ޏ��̓V�g���ƈ������i�Ƃ����̂������߂��ł���A�Љ�Ɠ��ʁj�����������������̂��B
�@�܂��A��N�̐��g�����̃V���[�u�p�p���M�v�̒��́A�������_�w���i���H�j�ɗ�������u�L���G�|������A�C�c�E�v�ł́A����������̎p�����ɕϐg�����Ĉ��̐��A��}�낤�Ƃ��邪�A�������̔������p�𖺖��̔��邠�₩�ɁA�����̖{�Ԃ����ɂƍI���ɗx�蕪���������B����͐_�w������������ǂ������Ă����ƁA���ς��̂悤�Ȃ������ŃA�C�c�E�i�T���A��ň����j�Ɏp���ς��Ƃ����X�������O�Ȃ��̂ŁA�X�s�[�f�B�ŃG���e�B�V�Y������_���X����ۓI�������B
�@��l�̐l�Ԃ̑Η������ʂ��l�̖��҂ɉ���������̂́A���o�I���ʂ��炢���Ė��͓I�ł͂��邪�A�l�����^�������ɁA���ꂼ��̖��҂̒��ł͕��ɂƂǂ܂��Ă��܂������Ȃ͎̂c�O���B�������A���ʂ���l�ʼn���������Ƃ����ď�ɖ����[�܂�킯�ł͂Ȃ��B�u���Ƌ��ɋ���ʁv�ɂ̓X�J�[���b�g�𒆐S�ɐ������u�X�J�[���b�g�ҁv�������āA���N�̐�g�����ł͈�H�^�P���X�J�[���b�g����l�ʼn������̂����A�ǂ����C�̋������肪�ڗ����Ă��܂��A����̗��ʂ��\�S�ɕ`���ɂ͎����Ă��Ȃ������悤�Ŏc�O�������B
�@�������A��˂ɂ��m���ɐV�����g�������Ă��Ă���B���낻��V�g�ƈ����̗��ʂ����킹�������I�Ȑl�ԑ���`���A������X�^�[���o�Ă��Ă����������B���͈��ƒʂ���Ƃ��ɍō��̃��x�����l������B���̈Ӗ��ŁA�u�u���b�N�E�W���b�N�v�i���ː��F��j���D�����������~���i�ԑg�g�b�v�j�▃�H�Ƃ����A�E�������������͓I�ȃX�^�[������A�g�b�v�����ɂ����M���Ɗ댯�Ȕ������A�G���e�B�V�Y�������˔���������A�@���t�ŃR�P�e�B�b�V���Ȗ��͂������T�Ƃ������͓I�Ȍ|�B�҂����邱�̎������`�����X�ł͂Ȃ����B���܂��Ɉӗ~�I�Ȏ�����𑗂葱���Ă��鏬�r��˂�A�Ⴂ����̍�Ƃ������̂��Ă���B�ޏ��������]���̕�˂̘H������E���悤�Ƃ���Ƃ��A�V�g�ƈ���������������̂ł͂Ȃ��A�����������݂Ƃ��Ă̈�̐l�i��������A�V�����X�P�[���̑傫�ȃh���}����˂œW�J���ꂤ��͂����B�i�uJAMCi�v1994�N12�����j
![]()
![]() �@�z�[���֖߂��@�@
�@�z�[���֖߂��@�@
Copyright:Shozo Jonen,1997-2009�@��O�ȎO