男がタカラヅカにはまる理由(わけ)
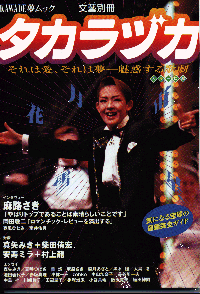 たとえば阪神間に住んでいて「巨人ファン」だと広言することは、ある程度のリスクを伴うことを覚悟しなければならないだろう。そのようにまたはそれ以上に、阪神間に住んでいても「宝塚ファン」であることを男性が広言するということには、少からぬ勇気が必要だ。「実は私、宝塚好きなんですけどね」と言うと、必ず「えっ? また、どうして」というような反応にあうことがほとんどだ。実はぼくも数年前までは「えっ?」と聞き返す側だった。配偶者に口説かれて星組公演「うたかたの恋」(原作=、脚色・演出=柴田郁宏。主演=麻路さき)を見るまでは。
たとえば阪神間に住んでいて「巨人ファン」だと広言することは、ある程度のリスクを伴うことを覚悟しなければならないだろう。そのようにまたはそれ以上に、阪神間に住んでいても「宝塚ファン」であることを男性が広言するということには、少からぬ勇気が必要だ。「実は私、宝塚好きなんですけどね」と言うと、必ず「えっ? また、どうして」というような反応にあうことがほとんどだ。実はぼくも数年前までは「えっ?」と聞き返す側だった。配偶者に口説かれて星組公演「うたかたの恋」(原作=、脚色・演出=柴田郁宏。主演=麻路さき)を見るまでは。
神戸に移ってから、配偶者は友人に誘われて宝塚をかなり熱心に見るようになった。ぼくはいわゆる小劇場演劇は見ていたが、宝塚には興味を示さなかった。一度彼女が「今度の公演はいいから、見てみない?」と水を向けたが、ぼくは「君が宝塚に熱中するのはかまわないけど、ぼくを巻き込まないでほしい」とクールな断り方をしている。それは花組公演「心の旅路」(脚本・演出=。主演=安寿ミラ)だったわけで、今になって地団駄踏んで悔しがっているのだが。それでも諦めなかった彼女は、「今度のを見てつまらないと思われたら、もう一生誘わない」と言って遂にぼくを口説き落とした。それが、紫苑ゆうのケガによって麻路さきが代役で主演を務めた「うたかたの恋」だったわけだ。
さて、ぼくはなぜ宝塚を避けていたのだろう。もちろん見たことがなかったわけだから、食わず嫌いに違いなく、つまりは一般的な先入観に基づいたものだったわけだ。小劇場演劇を見るのに割く暇と金はあっても、宝塚を見ることはない、と。小劇場演劇は見て、考え、論ずるに足るが、宝塚はそうではない、と。それはおそらく、大げさに言えば、文学論と身体論、戯曲論と俳優論の分裂によるのではないか。
小劇場演劇の公演では、劇作家の名前と、戯曲の質の占める割合が非常に大きい。「野田秀樹の新作だぞ」「深津篤史、岸田戯曲賞受賞後第一作!」というふうに。宝塚で作家の名前が取り沙汰されることはほとんどなく、第一に置かれるのはいわゆるトップスターである。つまり、小劇場演劇を見、論じることは、作家論であり戯曲論、演出論であり、つまるところ文芸批評である。しかし、宝塚を見るということは、作品から屹立するスターを見ることであって、芸能鑑賞、評判記に近い。このような言わばジャンルとしての格付けが、ぼくを宝塚から長く遠ざけていたものだったに違いない。振り返れば三十年以上もの間、ぼくはそのようにハイカルチャーに身を置くことで自分を御してきたわけだ。
素地はあった。このころぼくは関西で唯一の演劇誌だった「JAMCi」に売り込んで、ダンス批評の連載を始めていた。当初ぼくはダンスを、構成やプロットの展開を解釈する知的なアプローチによって、その全体性から批評することが可能だと思っていた。しかし、公演を数多く見るうちに、急速にダンサーたちの身体・肉体そのものの魅力に絡め取られていく。男女を問わず、ダンサーの皮膚の艶、汗の光、動きの鋭さに魅了されていた。その魅力を伝達するのに、知的な作業は無力だとわかりつつあった。それでも、特に関西においてダンスがあくまでマイナーな存在であることもあって、コンテンポラリーダンスや舞踏を見、文章を書くということがハイカルチャーに属する営みであるかのように錯覚していた。そのスノビズムを、宝塚という「大衆芸能」がみごとに打ち砕くことになる。
「うたかたの恋」は、再演ということもあり、作品としてよくできていた。白城あやかは可憐で、麻路さきは、歌をあえて話題にしなければ若々しく美しい見事な皇太子ぶりだった。よかった。満足していた。しかし、ぼくが本当にこうなってしまったのは、次に配偶者がぼくを星組シアター・ドラマシティ特別公演「ライト&シャドウ」(脚本・演出=太田正則)に送り込んだせいだ。たしか南の島に飛行機が不時着してどうこうというような話だったと思うが、ここでぼくは脇役のYMという娘役の美しさに参ってしまう。やや濃いめの美貌、姿の気品、物腰の優雅さ、言い出せばキリがないが、要するにぞっこん惚れてしまったわけだ。
振り返って、宝塚の見方として、これは正しい。多少端っこの生徒であっても、一人を、一点を凝視することで舞台の流れが生き生きと把握できる。それは、宝塚が舞台の全体性よりも生徒の身体能力の個別性に多くを負っているからだ。劇の全体を把握するよう努めるよりも、個々の生徒の魅力を堪能するほうがずっと楽しく、劇の空気のようなものを丸呑みできる。ぼくは先ほども述べたように、ある時点からダンスや舞踏を全体的な構成やプロットの展開、もっと大げさにいえば思想や理念といった全体的観点から演繹的に批評することを無力だと感じていた。神は細部に、ではないが、細部を凝視し、そこに感嘆するところから、作品のすべては帰納的に判断されるべきだ、少なくともぼくはそんな細部への眼ざしを大切にしていこうと肝に銘じていた。あえて言えば、世に言う男性的批評からは遠ざかったことかもしれない。大上段に振りかぶって思想や哲学を語ることをやめ、しゃがみこんで蟻の隊列を見つめているような眼ざしを自分に課したのだから。そのことによって、初めてぼくは個別の身体性と深く付き合うことができるようになったのではないだろうか。
そもそも演劇というライブなジャンルは、否応なく役者の身体が多くを決定する。その上ミュージカル、オペラ、歌舞伎、バレエといった音楽劇、舞踊劇であれば、作者の思想や戯曲の観念性は遥か遠景に引いていく。歌、ダンス、演技、容姿のすべてが求められる宝塚は、中でもその度合いが大きいと言っていいだろう。宝塚でストーリーは第二義的なものだ。話の筋、音楽、舞台美術など、すべては第一にスターを輝かせるための装置であって、作者のいわゆる自己表現欲求や情熱は、本来ほとんど問われない。黙阿弥の劇が破天荒と呼ばれるように、宝塚の劇に無理や破綻がどれだけあろうと、スターの見せ場をきちんと作ってさえいれば、よい作品である。「普通こんな時に踊らんやろ」というようなところでのダンスシーンでも、その踊りが素晴らしく、彼女の魅力を十全に発揮させるものなら満足する。もちろんそこにそれなりの必然性を探り出してこじつけることは絶望的なほどには難しくなく、多くの場合ぼくはそれを宝塚観劇の愉楽として評価することにしている。それでもあまりに破天荒の度が過ぎることもあって、さすがにファンも双眼鏡を降ろして「おいおい……」と呟くことになるわけだ。
多くのファンは特定の誰かを双眼鏡で追い回しているから、熱心なファンほど劇の全体の流れを知らない、というのも満更冗談ではない。ぼくだって、YMが端っこで踊っている時に、真ん中で誰が踊っているかなんてほとんど知らない。「マリコちゃん(麻路さき)のリフト、すごかったわねぇ」と言われて「そんなの、あったっけ」とお互いに絶句することもしばしばである。
さて、YMにぞっこんとなってしまったぼくが次に何をしたかというと、ファンレターを書いたのである。ただのミーハーです。そしてあろうことか、彼女から返事が来る。便箋二枚の「お手紙」である。ことここに至って、ぼくと宝塚の関係は、個人的紐帯となる。赤い糸とまで言っては彼女に悪いので止めておくが、妹の舞台をハラハラしながら見る兄の心境に昇華する。
宝塚を見ることの一つの喜びは、このような到達可能性を夢想することにあるのかもしれない。宝塚は芸能界一般とは異なり、プロダクションやマネジメントのシステムがある部分で強固ではなく、非公式でボランタリーな制度としてしか生徒個々のファンクラブが存在していないので、ファンが個々の生徒を自分(たち)で支えているという意識が強い。もちろんビギナーであったぼくはそこまで明確に意識することはなかったが、入り待ち・出待ちで彼女たちの素顔にふれることはそう難しいことではない。特に娘役は取り巻きが少なく、彼女たちとちょっとした立ち話を交わす程度の関係になるのは、稀少価値の高い男性ファンにとって、さほど難しいことではないようだ。だからこそぼくにすらYMから「お手紙」が届いたのだとも言える。
先程「兄の心境」と書いたが、恋人というのとはちょっと違うような気がする。ぼくが妻帯者だというせいもあるのかもしれないが、宝塚の生徒というのは、娘役でさえも性差を超越して存在しているのではないか。宝塚は演者のすべて、観客のほとんどが女性だけの集団である。そこでの男役は、世に言う「理想の男性像」のエッセンスを夢想し抽出したもので、現実にはありえない男性像を構築してしまっているといってもいい。花組のトップスターだった安寿ミラが退団後、ある芝居の稽古場で、ズボンをはいた俳優が椅子に腰掛けているのを見て驚いたという。宝塚で男役は、ズボンをはいている以上立っていなければいけないのだ。宝塚で男は、皺の寄ったズボンをはいていることなど、ありえないのだ。……。男役がそうである以上、それに対する娘役もありうべからざる女性像として存在していて当然ではないだろうか。そして両者は当然のごとく性的関係の成立の可能性をあらかじめ否定しているわけで、ゆえにぼくは恋人的な眼ざしを送ることができなくなってしまい、慈愛に満ちた(?)兄の眼ざしになってしまうのではないだろうか。清く正しく美しい宝塚は、このように去勢装置として働いているのかもしれない。
ところで、にもかかわらずぼくはYMにほとんど声をかけないので、配偶者からも半ば不思議がられている。まともに言葉を交わしたのは、震災の後「国境のない地図」の出待ちで、お互いの無事を喜んだことぐらいだ。女子大の図書館に勤めているぼくにとって、若い女性に声をかけるのは仕事みたいなもので、何の抵抗もない。なのにYMを前にすると、興奮、紅潮、硬直してしまって声をかけられず、悔しい思いのうちにその美しい姿を見送ることしばしばである。しかし、声をかけたところで、どんな話をすればいいというのだ。「○○の場面、素敵でしたね」とでも言うのだろうか。そんな二言三言で、彼女への思いを表わすことなどできようか。客席の隅から遠慮なく凝視し、ただ見呆けているほうが、どれほど幸せか。
YMはけっして舞台の中心で劇を強く推し進める役割を担う存在ではない。そんな娘役を好きになったおかげで、ぼくは宝塚から多くのことを学び、癒されることができたように思っている。一組に数十人の生徒がひしめいているのだから、スポットが当たり台詞がつくどころか、「動く大道具」としてしか機能しない生徒だってたくさんいる。組織の中で生きる者の運命ではある。しかしぼくは、そんな彼女たちの姿を見るのが本当に好きだ。そんな隅っこで、溌剌と躍動している彼女たちの姿から、人生半ばにさしかかったぼくがどれほど明日への希望と勇気を受け取ったことか。また、いわゆる脇役として好位置に恵まれたYMが、自身を美しく見せると同時に劇を引き締め優雅に流すために、どれほどの工夫と苦労を重ねているか。そんなの、舞台に立つ以上は当たり前じゃないか、と思われるかもしれないが、彼女はたとえば舞台の照明が消えたあと、袖にひっこむ時、なおも劇の情感を持続させ、増幅させるほどの強い表情を残していることがある。そんな姿が薄明かりの中に見られると、見えないところに心を致すことが、その劇を支えているのだと、心が動く。大げさでなく、ぼくは彼女たちを人間的に尊敬している。私生活や素顔は知らないが、恵まれた才能、並大抵ではない修練、舞台への憧れと組織人としての身の処し方、それらのアマルガムとしての華やかな姿を見ることで、ぼくはぼくなりに人生の処し方を学んでいるように思っている。いささか下世話だがサラリーマン訓的な見方さえ会得し、自身の姿を照射したり反転させたりしている。
こうして、ぼくの人生の日々の流れと宝塚は強くシンクロする。それを最も深く感じ、決定づけたのは、一九九五年二月、星組名古屋公演「若き日の唄は忘れじ」(原作=藤沢周平。脚色・演出=大関弘政)である。二十日ほど前の震災で、家や家族に被害はなかったとはいえ、不自由な生活を強いられていたぼくたちは、やっと開通した阪神電車の青木駅まで歩き、被災地ルックのまま新幹線に乗る。サイレンやヘリコプターの爆音のない静かな夜、自由に使えるお湯(当時まだわが家では水道もガスも通ってなかった)、味噌煮込みうどん……。そして再び見ることのできた宝塚の舞台は、豪華絢爛とか華やかとか別世界とかいう常套句で表わされるようなものではなかった。それがそこにあることの安堵! 世界の回復。
藤沢周平「蝉しぐれ」を脚色したこの作品は、はじめ紫苑ゆう主演で上演され、彼女の退団を受けて麻路さき主演で名古屋公演となったものだ。ここで彼女たちは、運命の過酷を嘆き、人の世のすれ違いに涙し、思いを残して去っていく者の無念を語った。客席でぼくは、彼女たちと共に藤沢周平の世界に生き、共に戻ることのできない時間を惜しみ悔やんだ。震災からの二十日間、自分の感情が自分のものではないような、感情の昂ぶりを禁じられたような淡々とした日々を送っていたぼくが、初めて強い思いの揺れを体験することとなった。あれっと思う間もなく涙が頬を伝い、それからは堰を切ったように、何がどうしたといって、ほとんどすべての場面で滂沱の涙にくれていた。まさにカタルシス=悲劇による浄化作用である。これによって、ぼくは自分の人生が宝塚と共に綴られていくものであることを、深く深く実感することになる。
このようにして、ぼくは立派な一男性ファンとして、ここにこうして存在している。宝塚の生徒たちと、それを見るきっかけを与えてくれた配偶者に、今となっては感謝している。

 ホームへ戻る
ホームへ戻る
Copyright:Shozo
Jonen,1997-2005 上念省三:jonen-shozo@nifty.com
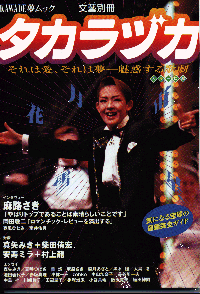 たとえば阪神間に住んでいて「巨人ファン」だと広言することは、ある程度のリスクを伴うことを覚悟しなければならないだろう。そのようにまたはそれ以上に、阪神間に住んでいても「宝塚ファン」であることを男性が広言するということには、少からぬ勇気が必要だ。「実は私、宝塚好きなんですけどね」と言うと、必ず「えっ? また、どうして」というような反応にあうことがほとんどだ。実はぼくも数年前までは「えっ?」と聞き返す側だった。配偶者に口説かれて星組公演「うたかたの恋」(原作=、脚色・演出=柴田郁宏。主演=麻路さき)を見るまでは。
たとえば阪神間に住んでいて「巨人ファン」だと広言することは、ある程度のリスクを伴うことを覚悟しなければならないだろう。そのようにまたはそれ以上に、阪神間に住んでいても「宝塚ファン」であることを男性が広言するということには、少からぬ勇気が必要だ。「実は私、宝塚好きなんですけどね」と言うと、必ず「えっ? また、どうして」というような反応にあうことがほとんどだ。実はぼくも数年前までは「えっ?」と聞き返す側だった。配偶者に口説かれて星組公演「うたかたの恋」(原作=、脚色・演出=柴田郁宏。主演=麻路さき)を見るまでは。