森 美香代
Mikayo
Mori
インタビュー全文
西野バレエ団にて、故西野和子に師事。退団後渡米。89年、マーク・ハイム率いるリスボンダンスカンパニーに所属し、スペイン、ポルトガル各地で公演。帰国後ダンスグループ<バームヴークス>を結成。95年よりソロダンスシリーズ「Solo&Soul」もスタート。自然体で、まわりの空間や時間と溶け込むような独自のダンスが好評を得る。また93年からはMATOMAのフランス公演に毎年参加。現在、ひとりひとりが自分の身体を見つめて動きを試行するワークショップを行っている。
阪神大震災やオウム・サリン事件や「9.11」や……のあとで、ぼくたちはどのように踊り、演じ、見、書けばよいのか。正解のない問いに対して、いま改めて自分に課すのは、正面から、という向き合う姿勢と方向、そして細部へのこだわりだ。こう書いてきて改めて思い出すのは、森美香代を久々に観ることができた「もう一つの花」だ(6月15日、アイホール)。彼女の深い蓄積から萌え出た動きは、一つ一つが世界と存在をいつくしむような柔らかな美しさに満ちていた。
彼女の動きに見入っていると、ただ身体が動くという本質から、一歩も身を引いていないことがわかる。一瞬一瞬、一つ一つの動きを観ることが幸福であるという、強く深い癒しを受け取ることができる。何のしかけもない、ただの一個の身体の動きが、すべての<私>にとって救済でありうるのではないか、そんな希望がもてた、30分だった。(PAN
Press、2002.7から)
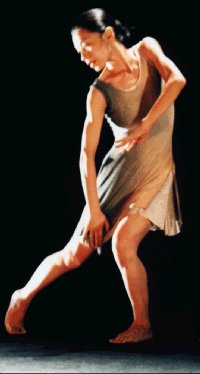 森美香代(写真左)は珍しく、「manatsuの蝶~プシュケのため息」(1999年8月11日、TORII
HALL)当日に配布した洒落たプログラムに、たくさんのテキストを書きつけた。そのテキストは交互に2種類から成っている。一つはシュナック著『蝶の不思議の国で』から、一つは森自身の「稽古雑記」(記録=青木恵子)から。蝶の動きを分析する前者と、自身の動きのためのメモである後者から、まずぼくたちは彼女の動きを蝶の飛翔との共通性という観点から見るという視点を設定することができる。実際、大きさ、力強さを感じさせる一連の動きは、身体と空気との抵抗の存在を認識させ、つまりそれが蝶の飛翔の源であるということを思い出させる。蝶の羽ばたきを思わせるような腕の動きも、軽やかさであるよりは力であり、生命の重さを感じさせた。また、足を開いて走るがむしゃらな姿などから垣間見た、美しさでは括れないもの、美しいだけでは現わせないものを見せようという志向や、極端な激しさを自分に強いて、何か徹底的で新しいものを開こうとする志向を感じられたのが、うれしかった。
森美香代(写真左)は珍しく、「manatsuの蝶~プシュケのため息」(1999年8月11日、TORII
HALL)当日に配布した洒落たプログラムに、たくさんのテキストを書きつけた。そのテキストは交互に2種類から成っている。一つはシュナック著『蝶の不思議の国で』から、一つは森自身の「稽古雑記」(記録=青木恵子)から。蝶の動きを分析する前者と、自身の動きのためのメモである後者から、まずぼくたちは彼女の動きを蝶の飛翔との共通性という観点から見るという視点を設定することができる。実際、大きさ、力強さを感じさせる一連の動きは、身体と空気との抵抗の存在を認識させ、つまりそれが蝶の飛翔の源であるということを思い出させる。蝶の羽ばたきを思わせるような腕の動きも、軽やかさであるよりは力であり、生命の重さを感じさせた。また、足を開いて走るがむしゃらな姿などから垣間見た、美しさでは括れないもの、美しいだけでは現わせないものを見せようという志向や、極端な激しさを自分に強いて、何か徹底的で新しいものを開こうとする志向を感じられたのが、うれしかった。
森美香代「Moonish」
あとで衣装に合わせたからだと聞いたが、裸足で生ま足で立っているので驚いた。ある種の覚悟があるのかと思って、ちょっとこちらも緊張した。
順序だてて説明するのは難しいのだが、彼女の、瞬間が凍っているような動きが、空間というものそのものに働きかけているような、一種の直接性を持っているように思った。空間の中に、自分がどういう位置をとればいいのか、どれほどの容積を占めればいいのか、または占めることをゆるされているのかということを、空間に分け入り、直接的に問いかけ、答えをつかみ取ろうとしているように見えた。
それを自分なりに説明づけるなら、これもまた自分流の言い方で恐縮だが、彼女の動きには独特の、ブレーキがきいたような艶があるからではないか。ぼくがブレーキとしか呼べずにいるものは、たとえば声でいうなら「ハスキー」とかいう場合の魅力のことだ。身体が空間とたたかっているような、だからちょっとザラついた摩擦の力=抗力を帯びている。じゃあ、それがなぜ美しさや艶であるのか、と問われれば、うまい説明はできないように思うのだが。
空間との抗力をもっているということは、彼女がそこで立っていることが、どのような力によってなのかということを明らかに示してくれているということでもある。彼女の身体の動きを見ているだけで、ぼくは空間を、世界を見ることができる。それが森美香代を見ることの最大の喜びだと思う。
最後の長い溶暗の中で、ゆらゆらと消えていき、静かに終わろうとする彼女の身体に目を凝らし、そして灯りが消えてぼくの目の中の残像がなくなるのを、ぼくは深く長く惜しんだのだった。(1999年3月16日、TORII_HALL)
豊崎東会館で「水のKimochi」(作・演出=塙香奈芽)を見る。昨年秋の同名の公演に続く、パートⅡ。基本的な線は、前作とあまり変わらず、その意味で衝撃的な鮮度はなかったが、マチュアにこなれた構成になっており、柔らかく美しい動きによってどのように美しく見せるか、優雅でしかも緊張した空間をいかに作り出すかという点でひじょうに高いレベルを示す公演だった。
にもかかわらず、というか、それだけに気になった点を。一言でいうと、からだが遠く感じられた、ダンサーが引っ込み過ぎているように感じられたという点だ。これがこの作品の弱さであるのかどうか、即断はしかねるが。優雅さと生々しさは、常識的には決して相容れないものだと思うが、ぼくは本当に優れた表現では、どのような対立的概念でも両立しうると思うのだ。対立を包含してしまう大きさ、強さを、最も高みにある表現には備えていてほしい。ぼくはそれを森美香代というダンサーには求めている。 たとえば、初めのほうで、指をクルクルと回すことから始まり、まるで指が自分で動いてしまっていて、やがて自身を突き刺すに至るというような動きがあった。これがヤザキタケシのようなダンサーなら、憑依や自我の崩壊といったふうに見え、ある種鬼気迫るような緊張感を醸し出す。ところが美香代では、ロボット振りのように見える。動きが身体の表層に貼り付けられているように見える。
最初は、ステージの奥半分を中心に使うせいかとも思ったのだが、それだけではあるまい。確かに物理的な距離の遠さ近さということで、見る印象が大きく変わることはある。たとえばTORII_HALLのような小さなスペースでの公演を桟敷で見ると、本当にダンサーの汗が飛び、風を受け、踏んづけられそうになることだってあるぐらいで、すごい迫力だ。それでも、風は受けるが互いの身体どうしの直接性にはつながらないことはある。
この遠さに思えるものが彼女のスタイルであって、ぼくの要求はないものねだりなのかもしれない。この公演での主眼は、冒頭で「優雅で緊張した空間」とも述べたように、中二階がバルコニーのように張り出した美しい会場を巧みに使ってダンサーたちの関係を複層化させる、複雑な空間構成にあったように思うからだ。3人(美香代、加藤久恵、浅田睦)がフロアで水族館の魚たちのようにゆらゆらとひらひらと踊っているとき、バルコニーに一人が立っているというシーンがあったが、そこでの水平の、また垂直の緊張関係には激しいものがあった。それでもフロアではあくまで優雅にさざめいている……それが一種のティージングのような効果さえ醸し出していたのには、感服した。
彼女はさらけ出すことがなく、常に動きをコントロールしているように見える。ぼくらがダンスにしばしば内的表現を求めるのをたしなめるかのように、きっちりした美しさを見せてくれる。これを歯痒く思うのは、ダンスに個人の内面表現を過剰に求める、ぼくたちの心性のゆえだ。こういうダンスは必要だ。しかし、裸の美香代も見たい、ぼくはあくまで貪欲なのだ。(1997年4月5日)
再び森美香代を、今度はソロで見た/冒頭では紗幕の向こうでうごめく彼女の脚が強い官能を見せ、ぼくの涙腺はゆるんだ/彼女の動きは空間を斬るのではなく、宥め、慰める/ゆるやかな動きが空間に風となり波となって伝わり、ぼくの心に達する/人の思いというのは、空間の波動なのだろうか?/たとえば彼女にとって倒れる、撓むことは重力=大地との引力というコミュニケーションの一つの方法ではないか/零度の表情を崩さない時間の中で、倒れることの反覆が徐々に笑顔を帯びてくるのを目の当たりにしながら、このダンスはもしかしたら愛の交感ではないのだろうか、故に彼女のダンスは常に美しくあらねばならないのではないかと、半ば嫉妬し放心もしていたのだ
バームヴークスダンス公演「4
SOLO
DANCE-down ward, in ward」「森美香代ソロダンス公演」 5月3、4日 伊丹・AI
HALL 演出:塙香奈芽 (JAMCi '96.8)
フランクフルト・バレエ団のマイケル・シュメイカーと森美香代、安川晶子、ヤザキタケシのワークショップの果実であるセッションは、女をめぐるゲームの形をとって、大変よく計算された美しい殺陣のようだった/階段、中二階、出入り口といったホールの空間を最大限に活用した構成力の自由/「ちょっと待って」という言葉、ペットボトルの受け渡しといったプロットへの放埒でユーモラスな肉付け/ヤザキの内攻する自棄としての動きの激しさ・鋭さ/何よりもシュメイカーと森のエロチックで妬ましいまでのコミュニケーション/絶望を垣間見たようなクールな表情のシュメイカーと、抑えきれない喜びにからだが反応してしまう森/……このように一つ一つの要素を並べてもこのパフォーマンスを見終わった後のぼくたちの興奮を十全に表すことはできない/空間は隅々まで彼らの動きと共に形や温度を変え、見る者は彼らと共に動き、呼吸し、からだをぶつけ合う痛みと快さに陶酔した/ダンスとしても無言劇としても身体芸術、舞台芸術の頂点として長く語り継がれるパフォーマンスだった
(JAMCi
'96.10)
森美香代の「零の空間」について、前号でふれたシュメイカーとのコラボレーションにおける構成や、ヤザキタケシの動きからの影響等を見て、否む評者がいるかもしれないが、ぼくはその難を採らない/一見類似の表現をとっていても、そこから滲み出てくる情緒や、見る者が受け取る感情が大きく異なる以上、そこに至るプロセスは全く異なるものであったはずだ/たしかに指を鳴らすような速い動き、壁の使い方などはヤザキの動きに似ているが、それは憑依や狂気を表現するのではなく、彼女の身体の全く新しい位相を開くものとして、語源の通りのdiscoverの喜びを与えてくれた/速い動きが、森の身体の官能性、感情表出を切っていくのかと予想されたが、彼女の身体はどこまでも零度にならない/振り払っても振り払っても無機的になり得ない身体……それはもしかしたら、現代を生きるぼくたちの希望ではないのか?/ソロ・ダンスと銘打ちながら加藤久恵、藤原理恵子とのトリオだった/2人はほとんど森の影として機能し、森を巧く引き立てた/といっても、特に加藤の動きや表情にはかなりの力があり、目を引くものがあったことは特筆しておかなければならない/終盤の、森と加藤の長机とのダブル・デュエットは実に優雅で官能的だった/加藤がニュートラルまたは微笑みを湛えた表情に終始するのに対し、森がややさびしげで泣きそうな表情を見せるのも、美しい対比だった/冒頭の、扉の隙間から指、腕、脚を少しずつ見せるティージングの美学、中盤の水族館(海遊館という設定)での風景、扉の向こう側や中二階といった空間の奥行きの使い方など、心憎いばかりのステージだった
森美香代「零の空間-Solo
Dance vol.Ⅲ~mizu
no kimochi~(axaxaxas!)」 10月5、6日 天六・豊崎東会館。演出=塙香奈芽 (JAMCi '97.2)
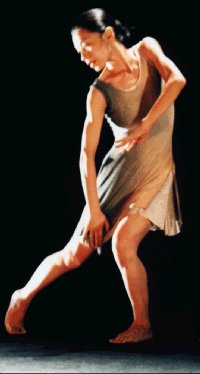 森美香代(写真左)は珍しく、「manatsuの蝶~プシュケのため息」(1999年8月11日、TORII
HALL)当日に配布した洒落たプログラムに、たくさんのテキストを書きつけた。そのテキストは交互に2種類から成っている。一つはシュナック著『蝶の不思議の国で』から、一つは森自身の「稽古雑記」(記録=青木恵子)から。蝶の動きを分析する前者と、自身の動きのためのメモである後者から、まずぼくたちは彼女の動きを蝶の飛翔との共通性という観点から見るという視点を設定することができる。実際、大きさ、力強さを感じさせる一連の動きは、身体と空気との抵抗の存在を認識させ、つまりそれが蝶の飛翔の源であるということを思い出させる。蝶の羽ばたきを思わせるような腕の動きも、軽やかさであるよりは力であり、生命の重さを感じさせた。また、足を開いて走るがむしゃらな姿などから垣間見た、美しさでは括れないもの、美しいだけでは現わせないものを見せようという志向や、極端な激しさを自分に強いて、何か徹底的で新しいものを開こうとする志向を感じられたのが、うれしかった。
森美香代(写真左)は珍しく、「manatsuの蝶~プシュケのため息」(1999年8月11日、TORII
HALL)当日に配布した洒落たプログラムに、たくさんのテキストを書きつけた。そのテキストは交互に2種類から成っている。一つはシュナック著『蝶の不思議の国で』から、一つは森自身の「稽古雑記」(記録=青木恵子)から。蝶の動きを分析する前者と、自身の動きのためのメモである後者から、まずぼくたちは彼女の動きを蝶の飛翔との共通性という観点から見るという視点を設定することができる。実際、大きさ、力強さを感じさせる一連の動きは、身体と空気との抵抗の存在を認識させ、つまりそれが蝶の飛翔の源であるということを思い出させる。蝶の羽ばたきを思わせるような腕の動きも、軽やかさであるよりは力であり、生命の重さを感じさせた。また、足を開いて走るがむしゃらな姿などから垣間見た、美しさでは括れないもの、美しいだけでは現わせないものを見せようという志向や、極端な激しさを自分に強いて、何か徹底的で新しいものを開こうとする志向を感じられたのが、うれしかった。