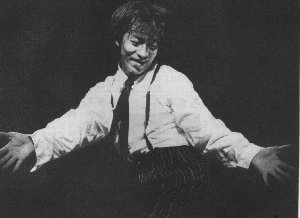 ヤザキタケシ
ヤザキタケシ
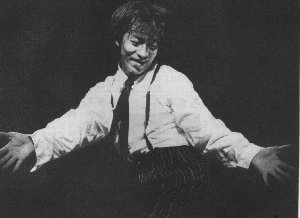 ヤザキタケシ
ヤザキタケシ
82年よりジャズ、バレエを渡辺タカシに師事。89〜90年、NYへ留学、この間、アルビンエイリー・アメリカンダンスシアター30周年コンサート、他多数オフブロードウェイの公演に出演。92〜98年、日仏共同企画「MATOMA」に参加、パリ、リヨン、モンペリエ他フランス主要都市で公演。94年よりすべての要素をフュージョンさせた独自の作品制作を始め、98年バニョレ国際振付賞にノミネートされる。'00年、カンパニー・ケレメニスでフランス、チュニジア、南アフリカ公演。他,フランス,ニューヨークなどで多数の招待公演。
恋してるみたいなダンス〜ヤザキタケシのワークショップ
ヤザキタケシ率いるアローダンスコミュニケーション(ADC)は、京都府南部にある城陽市の文化パルク城陽で、まず6月23日に「HAN☆PUKU」の公演を行った。これは以前Art Complex1928(京都)で上演した作品で、率直に言うとその時にはいささかまとまりを欠いた寄せ集め的な作品のように思えていたのだが、今回はうまい具合に剰余と思えた部分は刈り込まれ、メリハリがついてカッチリとまとまったように思えた。
 さて、今回ADCを取り上げようというのは、この公演が単独の公演にとどまらず、ワークショップ生募集のための一つのプレゼンテーションであったことを面白いと思ったからだ。この公演で20名のワークショップ生を募り、10回のワークショップを経て、7月21日に同所で発表公演「京の真夏の運動会」を行うという、1ヶ月の時間はどのようなものであったのか。公演のチラシに「『コンテンポラリーって何やねん?』と言われる方は」まず6月の公演を見ろと書いてあったが、ジャズダンスやバレエの経験はあっても、コンテンポラリーに接したことのない多くの人には、映像+ノイズで流れを断ち切ったり、美しい動きをあえて崩し壊したり、あえてみっともない動きを見せたりといった「HAN☆PUKU」は、たいそう新鮮だったろう。また、ヤザキや松本芽紅見の<狂異的>(造語)でグルーヴィな動きにも、度肝を抜かれたことだろう。(写真はワークショップ風景)
さて、今回ADCを取り上げようというのは、この公演が単独の公演にとどまらず、ワークショップ生募集のための一つのプレゼンテーションであったことを面白いと思ったからだ。この公演で20名のワークショップ生を募り、10回のワークショップを経て、7月21日に同所で発表公演「京の真夏の運動会」を行うという、1ヶ月の時間はどのようなものであったのか。公演のチラシに「『コンテンポラリーって何やねん?』と言われる方は」まず6月の公演を見ろと書いてあったが、ジャズダンスやバレエの経験はあっても、コンテンポラリーに接したことのない多くの人には、映像+ノイズで流れを断ち切ったり、美しい動きをあえて崩し壊したり、あえてみっともない動きを見せたりといった「HAN☆PUKU」は、たいそう新鮮だったろう。また、ヤザキや松本芽紅見の<狂異的>(造語)でグルーヴィな動きにも、度肝を抜かれたことだろう。(写真はワークショップ風景)
「京の真夏の運動会」は、自由なおしゃべりからそれこそ運動会の入場行進、威勢のいい掛け声と、楽しく祝祭的に始まった。メンバーの表情がイキイキしていたのが何よりである。バレエなどのダンス経験のある人も多かったようで、動きにキレのある人も散見された。動き自体はシンプルなものが多かったが、段取りの指示も適切だったようで、モタモタしたところがなく、見ていて心地よかった。
印象に残ったのは、中盤でヤザキと松本が見せた男女のコンタクトのせつないような表情の提示だ。2人の男女のゆらぎや同調が、恋のスリルのようだったし、去りぎわの視線の交差も熱かった。それに続いて、全員が集団の中で自分の相手を見出し、手を振ったり微笑を交わしあったりするところでは、身体がふれあうという初源的なコミュニケーションの重みが、心のゆれにつながっていくことを直接的に見せられ、このようにシンプルなコンセプトによって、意外なほどに大きな感情のあふれが見られたことを、とても貴く思った。
この一連の流れは、城陽市の外郭団体である財団法人が中心となって進めたようだが、このような形で多くの人に、ダンスがまるで恋みたいにドキドキするものであることが伝わったことが、何よりよかった。(PAN PRESS 2002.9)
この世界でダンスするということ
多くのダンサーがニューヨークには特別の思い入れがあるようで、「9.11」について、前回ふれた山下残に続き、砂連尾理+寺田みさ子、ヤザキタケシが取り上げていたのが印象に残っている。(中略)
ヤザキは、1ヵ月にわたるフィラデルフィア、ニューヨークでの滞在(レジデンシー)を踏まえて、京都で作品づくりに当たったが、この時点では未完のままの発表となった(6月1日、京都芸術センター)。しかし、「No FACE」という作品のここまでの仕上がりを見ると、彼が近年追究しているSPACE(空間)というテーマと、ニューヨーク等から京都にまたがって作られた作品であるということが、これまた微妙で重要なシンクロをなしているようで、せつなかった。
中央で彼が十字の形になり、客席に背を向けてブルースシンガーになり、腰や背中をセクシーに嗚咽するように揺らす。もちろん彼のことだから、これだけでは終わるまいが、ここはいっそ思いきってシンプルな作品に仕上げてみたらどうだろう。
シンプルにということでぼくが強調したいのは、妙な趣向を凝らして「9.11」のことを一つのエピソード、挿話として、作品の中で相対化するようなことはよしたほうがいい、ということだ。それをやってしまったのが、実は意外にも宝塚歌劇雪組のショー「ON THE 5th」で、詳細は省くが、結果としては取ってつけたようなことになってしまい、無惨だった。(後略)(PAN Press、2002.7から)
「本 能」
休憩を挟んで、ヤザキタケシの「本能」。柱に抱きついてクネクネしたり片脚を上げてピクピクしたり、シャドーボクシングならぬシャドーカンフーでカミ手からシモ手へ向かっていったり、両腕をすごい勢いで回転させたり、動きの見本帖のような楽しさがあった。また、突然笑い出したり、トイレに行ったり、くつろいでみせたり、顔の運動をしたり、「アメンボアカイナ」と発声練習を始めたり、自由奔放な次から次への展開は、アトラクティブで楽しいものだった。
しかし、いみじくもそれを彼自身が「本能」と規定して「能書きたれんと、はよ踊れい」とプログラムに書いているように、それらが何に対する奔放さであるかとか、何に面してシャドーカンフーのように闘っているのかという切実さは、見せていない。ここには、そのような切実さを見せることに対する、彼一流の照れのようなスタイルもある。切実さを放棄して(開き直って)、「本能的でありたい」というのも、半ばは本音であろうし、韜晦でもある。こういうヤザキのアンビヴァレントなためらいに対しては、少なからず物足りなく思うことがある。特に今回のように東アジア諸国の女性ダンサーが、自己のありようと正対している作品のあとで観ると、その斜の構えが回避、逃避の姿勢に見えなくもない。
しかし、それが現在のぼくたちの姿なのだ、ということにもすぐ気づくことになる。陳腐な表現になるが、闘うべき相手はあるか。掘削すべき自我はあるか。掘削の新たな手法はあるか。ぼくたちの現在は、そのような問いを問うことさえ気恥ずかしいほど、……何と言えばいいのだろう、病んでいる? 成熟している? ぼくたちはその一見の成熟に身を浸すことで、表現の本質に到達する方途を失いかけているように思える。
ヤザキの闘いは、実はそのような現在そのものに対するあらがいであるのではないか。それはとてもメタで末期的な闘いではある。いわば「闘うものがないことへの闘い」という逆トートロジー的な円環を描いてしまうからだ。この闘いは不毛で、ヤザキが勝利を収めることはないように思えるが、この中からきっと別の地平の何かが見えてくるに違いない。表現者にとっては困難な社会だと思わざるを得ない。(2001.10. アジア・コンテンポラリー・ダンス・フェスティバル TORIIホール)
最後のアローダンス・コミュニケーション「何もない時間」(振付=ミッシェル・ケレメニス、アレンジ=ヤザキタケシ)は、ヤザキと松本芽紅見の動きの組み合わせがひじょうに面白かった。この二人は互いにタイミングを測るような様子を見せず、それぞれがフルに踊っていながらきっちりと合わせることができている。ゆったりした動きの続きでポーンとスピードが与えられる時の起点が目覚ましく美しい。コンタクトとしても二つの身体の関係性の質が高くスリリングで素晴らしいのだが、個々に見ても一つ一つの身体の形が美しい。また、こういう作品の流れの中で笑えるタイミングをきっちりと提示できているのもいい。ダンス・ショーケース(パフォーマンス・アート・メッセin大阪2001) 7月31日 グランキューブ大阪
「ケッテンショウキ」(International Contemporary Dance Session "Edge 2" 2001年5月8日 Art Complex 1928)
ENTENの佐藤健大郎が舞台の下手で白く顔を作っている。バックは越路吹雪の「愛の賛歌」。そこへヤザキが金髪のヘアピースをつけ、化粧をし、異様に背を高くして口パクする。……という始まりからは、何だか色ものめいた作品に思える。次にヤザキは内臓を摸したシャツ姿になり、続いて脳を外すとタガが外れたように動き出す。化粧、性差、身体(内臓)といった問題が、表層的に次々と提示されていく。
ダンス作品にどうテーマを与えるかというのは、ちょっと難しい問題だ。身体の前で言葉は、すぐに記号になってしまって、身体に覆い被さる。身体が持っているはずのノイズが、言葉によって簡単に整理され、動きの振幅が捨象されてしまう。ややもするとテーマはそのきっかけになってしまい、世界を歪小化することにつながりかねない。
ここでそれが回避されたのは、ここまでの提示のされ方があまりにあっけらかんとしていて、思わせぶりでなかったこと、ここからの動きが素晴らしかったこと、に尽きる。それによって、最初の畳みかけるような問題の提示が、ここから効果的に一つの視点の仮設として有効に機能したのだった。
まるで虚空から何かをつかみ取るかのように、腕が滑らかにあざやかに動き出した。黒衣を着て影として動いていた松本芽紅見が脱衣されたドレスを点検するように見た後、ヤザキが化粧を落とし始めると松本も黒衣の顔の部分を外し、上衣を脱いだ。はじめ松本はまさにヤザキの影のように動いていたのだが、徐々にコンタクトの度を高めていった。別々に動いていたのがスッとシンクロするのを見た時のしびれるような快感、この二人の動きは、ひじょうにレベルの高い、素晴らしいものだったと思う。
ついに佐藤が顔を(滑稽に、あるいはグロテスクに)作って、ドレスを着るに至る。作品の構成、コンセプトがしっかりしていて、その枠の中で自在に動けたということで、観る者に親切な作品だったとも言えるだろう。最後に佐藤がキーファーが描く服だけの女性のようだったのが、ひじょうに深く印象に残っている。
Kyoto Scene〜リヨンビエンナーレ招待作品/公開リハーサル 2000年9月3日 京都芸術センター
3つ目に置かれたのはヤザキタケシの名作「スペース4.5」。ヤザキがダンサーとして個の人間としてその内面を深く掘るような作品を出すと、ダンスは究極的に一人称の表現だということがよくわかる。広い舞台の中の狭い空間配置ということも、その面白さに拍車をかけた。
ヤザキタケシ&アローダンスコミュニケーション「MAMBO JAMBO」 2000年8月9日トリイホール
ヤザキタケシが率いるユニットは、アローダンスコミュニケーションという。「アロー」はヤザキの「ヤ」を取ったものだろう。もちろんarrowというからには、何ものかを指し示す鋭い方向性があるという意味が込められているのも当然のことだと思われる。「MANBO JAMBO」と多少軽いタイトルを付けられたこの日のステージで示された世界は、どのような方向性を持っていたのか?
ぼくたちがヤザキタケシという優れたダンサーに期待するのは、どのような世界なのか。鋭く激しい動きから生み出されるのは、パラノイア的な青年の異常な情熱であったり、底が抜けた破滅的な笑いだったり、ある種の意表を突くような演劇的な筋立てを的確に表現したり、ただ動きそのものの美しさへの陶酔であったりする。
今回ヤザキが志向した世界は、笑いを中心としたものだった。新作のヤザキ自身のソロ「ici(ここ)」は、他のメンバーだけの作品「スペース6」の後に置かれたので、やはりヤザキには華があるなと再確認したところから始まった。ハ虫類を思わせるような(ということは、タモリのイグアナのような、ということでもあるのだが)痙攣的で微細で滑稽な動きが続く。これについて、これまでのヤザキの作品の動きをぼくが知っているから面白いのだろうかどうかと考えた。確かに、いつものヤザキの痙攣から滑稽へと連なる流れを知っていれば面白い。しかしぼくは、これは初見のほうが面白いのではないかと思った。それはある部分、この動きの見せ方に新味を感じられなかったからではなかったか。または、この動きがここで留まってしまっているのでは物足りないと。
ヤザキの作品の新味とは、どのように提出されてきたものだったか。たとえばストーカーという設定、4畳半という制約、食べるというコンセプトなどの太い軸から、半ば自動的に動きがうまれ、ドラマがうまれ、笑いが生まれてきたそのプロセスは、とても自然で必然的なものだったと思う。 その中でぼくは、コンテンポラリーダンスにおいて、一つの動きというものの持つ意味と無意味の双方を理解してきた。
「ici」で物足りなかったのは、一つにはそういう太い軸を見つけることができなかった(それはぼくのが集中力を欠いていたためかもしれないが)ために、動きが個々に解体してしまったように見えたことだ。もう一つは、ある動きが次の動きを生み出す自律的な展開が見られなかったことだ。
たとえば足が前に進まずつんのめるようになる動きが、個人のドラマから必然的に導かれた動きではなく、唐突で笑いを誘う動きにしか見えなかったこと。このようなことは、これまでヤザキの作品で経験したことのない、居心地の悪さだったのだが。作品紹介として「彷徨い続ける魂の行方・彷徨い続ける肉の行方・彷徨い続ける骨の行方/確かに自分はここにいるはず/或いはいるつもりなのか?/不確かな物体である自分/さて・・・いったい私の立つ場所とは?」という文章が添えられていたが、そのような深刻さと作品との間に、いささかの齟齬があったといわざるを得ない。終盤の激しい口論の様子で汗を飛び散らせる一つのクライマックスも、いくぶんかはパントマイムの表現のようであり、十分内化されていないのではなかったか。
「U&K」という作品は、ヤザキが黒衣になって、ギター(マリオ・マリンコヴィッツ・前)と松本芽紅見らがからむもの。「ストーリーを追わずイメージで繰り広げられるうさぎとかめのレース」だったそうだが、全体に笑いを狙った余興のような印象で、よく笑っている観客も多かったが、そこに留まっているように思え、作品の構造自体、疑問を感じた。
「スペース6」は、「スペース4.5」がヤザキのソロだったのに対し、4人の作品にした分、4畳半から6畳に広げたもの。しかし、空間が広がった分、求心力が薄められたのはやむをえないとしても、4人が限られたスペースで動かなければならない分、やや動きが窮屈になっていたように見えたのが残念。作品の系列としては、むしろ「ESPACE」の流れの上にあるといえるのかもしれないが、少しコンセプトのつなぎにズレがあったかもしれない。
というように、ぼくは今回のヤザキの公演について、率直に言って頭を抱え、腕組みしながら見ていたのだが、もしかしたらそれはこのアローダンスコミュニケーションというユニットにヤザキが与えている属性なのかもしれない。今後のヤザキ個人とこのユニットの動きをじっくりと見ていたい。個々のダンサーは非常に魅力的であるが、皆が今回のような方向性に合っているのかどうかは、わからない。
以前トリイホールで上演した「スペース4.5」を、ヤザキタケシは「芸術祭典・京」で再演することができた(1999年6月13日、京都国際交流会館)。時間の制限もあったのだろうが、自らのエッセンスをみごとに抽出して、初演にも増していい作品となった。再演は、観客をも成長させる。4.5という数字が示す四畳半というコンセプトに表れた日常性に基づく身体の起居の面白さ、楽しさを、初演時よりはるかに深く味わうことができたように思う。初演時に比べて、展開によどみや休みがなく、身体性そのものを堪能できた。(PAN Press)
さて、ヤザキタケシはいつもシャープでスピーディな動きと、人を食ったようなユーモラスな味付け、そして自閉とも求心とも読み取れる沈潜の鋭さで、観る者をもスパイラルな渦に巻き込むような緊密な作品を見せてくれるが、「エスパス お茶の間」(11月23日、トリイホール)もまた、手に汗握るスリリングな作品となった。
今回は総勢11人で、デュエット(藤野直美と黒子さなえ、デカルコ・マリーとサイトウマコト、ヤザキと裴香子)や群舞の鮮やかでユーモラスな妙味も存分に見せてくれたし、ヤザキのソロも充実したものだった。舞台奥に襖を立て、奥は押入れ風に2段になっていて、ダンサーはそこから出入りする。押入れの向こう側(またはこちら側)は、日常空間としてのお茶の間であるかもしれないし、ストンと隔絶したファンタジーの世界かもしれない。何人ものダンサーによるいくつかの連作は、そんな二つの世界を往還し、めくるめく時間を与えてくれた。(DANCEART)
ヤザキタケシ「スペース4.5(タナトス小僧のエロスな気分)」
まず現われたヤザキが、舞台のセンターにかかとをつけて寝転がり、頭の位置にテープをちぎって貼っていった。そうしてポイントを置くことで、舞台に身長の2倍の長さの1辺をもつ正方形を作った。もちろんこれはリングのようにダンサーの動きを制限することになる。それによって、空間に断崖ができたようなスリルが生まれる。それによって身体の動きがアクセラレートされるのは、空間に枠を設けることで本当には自由さが獲得できるからに他ならない。この逆説は、定型詩である短歌や俳句の豊かな表現の可能性と相通じるものである。
そのポインティングのしぐさにキレがあり、それだけでじゅうぶん見ごたえのあるものだった。暗転の後、彼はその中に横たわっていた。横転の繰り返しが徐々に速度を増し、また手と足は床につけず、普通には接地しない背や脇を使って側転し、テープのエッジの寸前で止まったり、あぐらのまま側転したり、空間の切り取りと同じく、動きに枷をはめているのが面白い。結果的に、ヤザキの身体は、回転させられている、動かされているように見えてくる。そしてやがて、震え、はじかれるような動きが、不随意であるようにも見えてくる。そうした動きの見え方の微妙な変化をずいぶん楽しむことができた。
激しい動きを強調して証すように息を荒らげて座り込むと、銀髪のヘアピースが投げ込まれる。しばらく渋い顔をしていぶかしげに見ていたが、かぶったかと思うと痙攣するようなステップを踏み始めた。この激しい動きを中心とした部分は、うまい具合に笑いを誘うアクセントになり、これを挟んだ後半の大きなストロークを中心とした動きは、対比的な動きの構成としてヤザキの身体能力の高さとヴァリエーションの豊かさを示すものとしてよく機能した。 (1999年3月16日、TORII_HALL)
ヤザキタケシ×伊藤キム
1998年8月5日 於・TORII HALL。山崎広太×森美香代に続くDANCE BATTLEの第二弾。ヤザキについてはよく知っていると言えるが、伊藤についてはAI HALLで「あなた」を見ただけで、必ずしも鮮やかな印象が残っていたわけではない。ただこの時は、短い時間の内にほんの少し垣間見せた速く剛い動きに、いつか長いソロを見たいなと思っていた。
はじめはヤザキのソロ。はじめ恐竜(=爬虫類)のような動きだったのが、猿のようになり人のようになり、窮屈そうにワイシャツを着て下はトランクスだけだけど一応文明人、という風に進化していく。このような構成は上海太郎にもあったとはいえ、動きそのものの面白さ、楽しさは言うまでもなくヤザキのほうがずっと豊かである。ワイシャツで下はトランクスというのも、いくぶんかはボリス・シャルマッツを思い出させはした。本当なら下半身は裸でシャツだけを着ているはずだったのが、官憲によってというか新聞社によってというべきかパンツをはかされてしまった、あのボリスである。
人のようになってからも時折猿のような動きが混じるのが面白い。手を床に着けて掃くような動きなどをまじえ、一直線の進化の形ではないところが、ヤザキの面白さだ。頬を大きく膨らませて嘔吐をこらえて見せたり、息の吐き吸いを大げさに見せたりしていたが、やがてそれが苦しみのように見えたかと思うと、笑いに転じる。笑いに痙攣が伴い、便意を我慢しているような切迫の様が、様々にユーモラスな動きとなってこちらの笑いも誘う。笑いというものは明らかに増幅するものだと実感する。ただ、ここまでわりとスムーズな流れで来てしまっていて、笑いをはじけさせたり、笑いが陰影を持つための仕掛けが少々不足していたような気がしたのが、やや惜しい。
この後にテンポのあるスピーディな音楽をバックにゆるやかな動きをつけていく部分があって、動きの緩やかさに音が籠められていくような美しさを感じたのだが、リリースの美しさが特徴的に際立った。切迫による笑いを際立たせる仕掛けとして、リリースをうまく使う手もあったのではないかと思う。
また、動きのテンポと音のスピードが、全く別のようでいながら最小公倍数的に合っていたように思ったが、完全に外したほうがよかったのではないか。そして最後の音はフェードアウトではなく、カットアウトのほうがふさわしいと思う。音の処理がもう少しドライであれば、全体的にさらに締まったのではないかと思われる。
伊藤もやはりケモノのように、四つんばいで出てきた。桃のような美しいお尻が印象的だ。犬のようでありながら人のように何かを素早く探している。いつしか人形振りに転じている。不随意というのとも違う奇妙な不自由さだ。動きを統べる主体がその身体の外側にあるということがよくわかる、不思議な動きのように思えた。
次には正座し、水を掬うような柔らかい手の動きが美しい。と思うと、突然、熱した鉄板の上で熱さに跳ねる男のような動きをとる。この脈絡のなさ! 全身を伸ばすように、また屈曲させて、という動きが続き、関節のねじれ、ひねりで「まっすぐにならない身体」をみごとなまでに見せてくれるが、それが空間を開くような外部に向かわないことに少々苛々しもした。身体をひねるということは、それと共に身体に接着している空間をひねるという強引さを伴うものであるだろう。しかしキムの身体はそんな空間をすり抜けてでもいるかのように、あっけない。
また、ゆるやかだが柔らかくなく、しかも力がこもっているかどうかもわからない、と感じられるような動きも見せてくれた。ぼくの無能をさらけ出すようだが、どう受け止めたらいいのか、こちら側には解読する鍵のない符牒を与えられたような戸惑いを感じた。
同じ関節が動くということでも、腕が伸びているだけのように見える動きもあれば、空間が広がっていくように感じられる動きもある。何かの力を出したり出さなかったりすることを自在に調整しているようだ。同じゆっくりとした動きでも、いくつかの、「色」とでも言えばよいのだろうか、抜いたもの、こめたもの、ぬーっと出てくるもの、いろいろだ。そのような動きの諸相に幻惑されるように過ぎていったモノトーンの万華鏡のような、不思議な時間だった。
そして汗を拭いた途端、とめどなく笑う。客の扇子を取って笑う。それで客をあおいで笑う。ミラーボールが回る。客が笑う。全身が笑う。突如として終わる。
おそらく最後の笑っていた時間というのは、とってつけたようなものだ。しかし、その笑いのためにはそれまでの<モノトーンの万華鏡>が必要だったし、それはまた同じ力で押し返すように、笑いを必要とした。そうでなければぼくたちは終わることができなかったほどに、彼の動きは多様だった。そのためにぼくたちはバラバラになりそうだった。だから笑わざるを得なかった。簡単なことだ。
二人のセッションは、ラジカセから落語が流れてきて始まった。桂春団治の「法善寺横丁」だったそうで、このホールとは隣接している。
ヤザキがキムをいたぶっている。ヤザキの点を軸にキムが軟体として、こんにゃくのように動いている。ヤザキの作る点を中心に、キムが円を作る。続いて逆転し、ヤザキがキムを軸にして動くのだが、キムが点だったのに対し、ヤザキは面として動いているようだ。軸の持ち方として、どちらかと言うとキムの方がスリリングで危なっかしい。何かが外れるとすべてが終わってしまうような危うさを持っている。
続くパートは腕相撲を中心として、たのしかった。
Dance Circusという、一連のパフォーマンス・アトラクションの中で、斉藤誠、萩尾しおり、木村陽子による「条件反射」とヤザキタケシの舞狂青人Σ Ⅱ」が印象に残っている/5〜10分の小品をいくつかのソロやユニットが競いあう形をとるこのような催しでは、うまくすると凝縮したレベルの高い作品にめぐりあえる/ヤザキも斉藤も芝居心の豊かな、いい意味で器用なダンサーだ/この日の作品では、ヤザキがソロ・ダンスの典型として内攻する狂気を、斉藤が3人のコンビネーションによって身体の組合せのダイナミックな美しさを、余すところなく見せた/ヤザキは憑依の往還を、咆哮、身悶え、震えなどのダイナミックな、また繊細な動きによって、男のダンスならではのスケールの大きさとエロチシズムを振りまいた/斉藤らは、3人の身体が離散集合、くんずほぐれつすることで、空間のスケールを柔軟に変化させた/ヤザキが自らの身体を動かして心のベクトルを内攻させることで内部のエロスを表出したのに対し、斉藤らは3人のコミュニケーション・ラインに重点を置き、関係性を描くことによってエロスを外在化させた/これはソロダンスとグループダンスの典型として銘記される/そのような2つの営みに1つのステージで出会えることが、このDance Circusという企画の成功をあらわしている Dance Circus1から、斉藤誠、ヤザキタケシ。9月9日、道頓堀・TORII HALL (JAMCi '96.2)
![]()