演劇−さ
サードステージ
時空劇場 芝居屋坂道ストア 青年団時間と空間が渦を巻きはじめる現場
トランス
−サードステージ・プロデュース公演(12月19日(日) 大阪・阿倍野/近鉄アート館)登場人物は三人だけだ。その三人が客席後方の三方から現われ、舞台上に集まり、互いに牽制しながら舞台上に置かれた白衣を「暫定的に」「今日は、仮に」といった格好で長野里美が手に取ることによって、そこで初めて配役が決まったかのように芝居は流れ込んでいく。白衣を着た長野は精神科医である。そこへ高校の同級生の小須田がやって来る。自分が自分でないようだという小須田。ある夜おかまバーでぼられた小須田を助けたのがこれも高校の同級生で今はおかまの松重豊(背が高く体格のいいおかまをかわいく好演)。松重が苦しむ小須田の世話を焼いているうちに、ある日目覚めた小須田が(分裂症ないしは離人症として)いきなり天皇になりきっている。
まず、小須田の「陛下」としての立ち現われから見てみよう。それまで小須田はいまの自分は本当の自分ではないと言って、眠り続け、目覚めると夢の中では別の本当の自分だったはずだと焦燥する。まあ「今の自分は本当の自分ではない」という感覚はさまざまなレベルで多くの人が持っている感覚で、驚くには当たらない。たとえば四月の宝塚歌劇バウホール星組公演「ある日夢のとばりの中で−エジソンのもう一つの発明」で麻路さき演じるエリックも一カ月というもの夢に同じ女性が現われているのだが、やはり今の自分は本当の自分ではないようだと悩んでおり、ダンス・シーンでは重要なモチーフとして仮面(ペルソナ。阪急のカードの名前ではない)が使われるのだ。しかもその「本当の自分」が天皇だというのだから、それこそ宝塚の「ある日……」で典型例として「ナポレオンだとかクレオパトラだとかを本当の自分(前世の自分)だと言う人が多い」とされていたのと同じステレオタイプではあった。
しかし、それをステレオタイプに留めなかったのは、やはり小須田の異様な演技力だったとしか言いようがない。ベッドからむくっと上半身起き上がって「朕は……」と言った途端、小須田の表情は完全にトランスしており、会場に空気の色が変わるような衝撃が走った。一人の役者の現われが変わった途端に会場すべての空気が変わるというのは、役者の力を示す意味でも、脚本の緊密さを示す意味でも、そして改めて演劇というものの持つ力を確認する意味でもすごいことだ。つまりこのことから読めるのは、世界は構成員個々の幻想で成立していて、その内の一人の幻想が変容した以上、構成員全員にとっての世界の全体像も変わらずにはおれないということではないだろうか。
周知のように、ぼくたちは正常だか異常だかわからないような危うい日常を生きているから、ぼくたちを正常か異常かを決定するのは、日常をふつうにやり過ごすために支障がないかどうかということであるに過ぎない。ほんの小さなことで躓いたのでも、それがきっかけとなって日常を踏み外してしまうことは、よくある。
この芝居でも、一番まともに見える精神科医が、かつて新興宗教にはまり込んで普通の意味での日常生活を送っていなかったことが淡々と語られる。おかまというのも、おかまなりの日常はあるにせよ、あまり一般的な日常ではないように思える。皆同じようにどこかで何かを踏み外していることには違いない。そのことが最も激しい形で見せつけられたのが、大団円だったのだ。
小須田は精神科医に結婚を申し出る。それが彼女をこのような状態から救い出すための唯一の方法であると言って。また戯言が始まったと笑って見ていたら、どうも様子が違ってくる。これまで天皇であると分裂症の「フリをしていた」のは、自分が狂気となることによって彼女と松重にそれぞれの役割が与えられ、二人を救済することになるからだと、病いの底に安定した者の物言いではなく、治療者の真剣さと焦燥を帯びて熱く語る。その直後には松重が、いや自分こそが本当の治療者であって、お前たちは医師と患者の役割を果たしていただけなのだと言い張り、次には再び精神科医の長野が二人に、何を言ってるのよ、私が医師に決まっているじゃないの、というように、それぞれが自分こそが正常であると(治療者であると)強弁する。見ていて、それぞれの言い分が実にリアリティを持っていて、ああ本当はそうだったのかと、三人の言うことすべてがその刹那には正しく聞こえる。その次の瞬間には別の誰かが自らの正常を主張していて、さっきぼくが信じていた誰かがやっぱり異常だったことに気づかされることになっている。それが終わりなく思えるほど何度も何度もめくるめく繰り返され、やがて正解や真実はありえないことが、半ば朦朧としかけた意識のうちにもわかってくる。最後に三人がユニゾンで客席に向かって「本当に病んでいるのはあなたです」(うろ覚えで恐縮)と投げかけるのが、ぼくの内部に本当に働きかけ、ああ、ぼくは病んでいたんだったね、と頷く形になっていく。冒頭で白衣を取ったのがたまたまであったように見えたことが、ここで生きてくるのだ。正常と異常の境界の不明瞭などというようなことは、言葉にすると平凡かもしれないが、それを演劇という時間と空間の閉鎖の中で緊密に展開してくれた。まさに芝居の醍醐味である。
(視聴覚通信13号所収)![]()
海と日傘
−時空劇場第七回公演(1月30日(日) 大阪/扇町ミュージアムスクエア)公演のチラシがミニマルなとてもいい雰囲気を出していたので、事前の知識なしに観に行ったのが、予想をはるかに上回る、衝撃的で素晴らしい舞台だった。作・演出、松田正隆、制作・はしぐちしん、舞台監督・清水忠文、舞台美術・奥村泰彦、照明・大川貴啓、仲江義一。立命館の学生・卒業生で1990年に結成した劇団だそうだ。
「海と日傘」は、この間までどこにでもあった日本家屋の障子や襖のセットの中、縁側でむこうを向いて足の爪を切っている、高校教員を兼ねた小説家の夫(金替康博。朴訥な感じがいい)の背中を見ることから始まる芝居だ。約めて言ってしまえば、病弱の美しい妻(内田淳子。じつに美しい)が死んでいくだけの話。たとえば夏目雅子の晩年(!)を目の当たりにしていると思っていい。夫は医師から妻の余命が幾許もないことを知らされている。隣の夫婦の来訪だとか、町内会の運動会だとか、ごく日常的な出来事がいくつか淡々と描かれて時は流れていく。終始この夫婦の家の居間と縁側だけで展開する。場面と場面の間は、美しい音楽が流れる暗転でつないでいく。劇としてドラマティックな起結を意識していないことは、たとえば隣のおじいさんがどこかへ行ってしまったというエピソードが芝居の中では解決されずそのまま放置されていることからもわかるだろう。また、役者たちが使う九州の言葉は抑揚が小さく、このような淡々としたドラマにはうってつけだったことに改めて気づくことができる。
印象的な場面を挙げておこう。ある小雨の日、旅に出たいという妻の願いに医師の許しも得て、今まさにバスに乗って海へ出かけようとしているところ。妻はいそいそと着ていく服を選び、天袋からハンドバッグを取り出そうとして踏み台を探したりしている。そのうきうきしたさまが実にかわいく、どうかこのままお天気も持ち直し、おそらくは最後の小旅行を二人が無事に楽しく過ごすことができるようにと、見ていて祈るような気持ちになっていく。台本から引こう。
直子 …何?
洋次 口紅つけとるじゃなかか…。
直子 ……うん…。いかんと?
洋次 うんにゃ…。
直子 似合いますか…。
洋次 …うん…似合うよ…。
直子 うちも捨てたもんじゃなかでしょう。
洋次 うん。
直子 あ、お弁当…。
−と、直子、台所へ。洋次、ハンドバッグを取り、それを見る。やがて、玄関の方から声がする。
多田の声 ごめんください。
洋次 ……はい……。
夫を訪ねて女性編集者・多田(前の担当。辻美奈子)が転勤の挨拶にやって来たのだ。この編集者と夫の間に以前何かあったことを、ぼくたちは現在の担当の男性の編集者(亀岡寿行。さわやか)との話から既に聞き知っている。すべてを含んだ上で何もなかったかのようにお茶を出す妻。しかし塞き止めていた感情がついに溢れたかのように、自分の湯呑みをひっくり返してしまい、でも、そのまま動けない。夫に「拭かんか」と促されるが、動けない。多田にタオルを差し出されても動けない。タオルを取った夫が畳を拭くが、妻は夫の手をとって、自分の膝の上に置いてしまう。
このシーンがこの芝居の中では唯一「劇的」な場面だったのだ。そしてここに収斂され、この劇のすべてに流れていたのは、日常の何気ない一つ一つの瞬間に現われる、妻が人生の最晩年に到って夫と自らの時間(過去も現在も残り少ない未来も)をいとおしむ心の、あわれさと美しさである。こぼれたお茶を拭く夫の手を取ってしまうのも、このあと多田が帰ってしまってすぐに「おくらんでよかとですか」といって夫に送りに行かせるのも、妻の意地と解するよりは、そのようにして夫との時間をいとおしんだのだ。そう言われて送りに行く夫も夫だが、ひとり残された妻についての卜書きから引こう。
−直子、しばらく何かを見ている。…その「何か」は、誰にもわからない。直子にさえ…。
−雨はいつの間にかあがっている。
−直子、視線が庭へ行く。
−パアーッと陽光が庭に射す。
直子 …雨のあがったですよ…。
−ト、誰かに話しかける。そして立ち上がり庭へ出てゆく。陽光の中に確かに直子がいる。
ここで舞台の照明は最上限に明るくなり、その中で白いワンピースの直子は既にこの世のものとは思えないような美しさを見せる。直子は生と死のあわいの少し死の方に近いところに立っていて、洋次を少し遠い存在のようにまぶしく見ているのだろうか。思えばこの芝居は、妻の死を間近に控えた夫婦の、触れたらはじけてしまいそうな日常を描くのだ。死を控えた二人の日常は、もちろんすべてが生と死をあからさまに意識したものではなく、普通の夫婦のように日々を過ごしていくのだが、日々が過ぎていくことが確実に二人の時間を一日一日と削っていくということが底には確かに流れている。そしてそれゆえに残された日々が輝きを増すのはもちろんだが、そういってみても何にもならないのも確かなことだ。
−やがて洋次がもどって来る。(中略)庭の直子に気づかず、妻を探す。(中略)直子はじっと庭から洋次を見ている。
−そして洋次は、その椅子にうなだれてすわる。
直子 ……バス、行ってしもうたね。
洋次 (少し驚いて)……うん……。……すまん……。
直子 何で…。しょんなかですたい……。
−直子、洋次を見つめ…。
直子 雨のあがったとですよ。
洋次 そうや…。
直子 そっちから、見えとるですか。
洋次 うん?
直子 虹……。
洋次 ……。
直子 うちは今、虹ん中に立っとるとです……。
洋次 ……
直子 見えますか?
洋次 ……
直子 見えんとですか?
洋次 うん。
直子 それじゃ、あなたも今、虹ん中におるとです。そい けん、見えんとです。
洋次 ……ばってん、お前は見えとるよ……。
−直子、笑う…。無邪気に…。
直子 ねえ……
洋次 うん?
直子 うちのこと、忘れたらいけんとよ……。
洋次 ……うん……。
もう直子と洋次は違う世界にいて、直子は向こう側から洋次に語りかけている。ここでの直子と洋次の対話は、虹が見えるか見えないか、二人が同じ場所に立っているかいないかという危うい二重性の中で、とんでもない緊張とかなしみを醸し出している。そして唐突に直子は洋次を突き飛ばすかのように、既に向こう側に行ってしまった存在として愛を語りかけるのだ。眩しいほどの照明に真っ白に光ったワンピースと透き通るような表情、ここで内田淳子という女優の美しさは頂点に達する。
ぼくたちの時間というのは、どのように重層しているのだろう。日常が輝いたからといって何にもならないと、さっきぼくは書いた。それは短命に終わった者たちに残された者に対して「いい一生だったのよ、彼は人さまの百年分は立派に生きたのよ」と声をかけても慰めにしかならないという意味でのことだ。しかしせめて美しく輝くことによって、短かった生はその美しい像を、見送ることしかできない者の中に残すことができる。それによってぼくたちは、やっと身近な早世した者たちの生と死を安んじて「それはそれなりに完結していた。よかったのだ」と受け入れることができようというものだ。
最後に妻の葬儀を済ませた洋次が、一人になってちゃぶ台に座る。見ていてぼくは、洋次が号泣するかどうか、難しいところだと思っていた。すると彼はお茶漬けの用意をして、ふと外を見る。外には雪が降り始めていた。洋次はふと「おい……雪の降ってきたぞ……」と呼び掛ける。しかし誰が答えるわけでもない。やはりここでも泣くかと思った。そこへ聞こえてきたのは、彼がお茶漬けをかきこむズルズルという激しい音だった。参った。
なお、この稿を書くにあたって、時空劇場のはしぐち氏から、上演台本のコピーの提供を快諾いただいたことを深く感謝している。何度読み返しても、胸に込み上げてくるものがある。三月に京都の府民ホールALTIで行われた「紙屋悦子の青春」もこれまた内田が美しく、たいへん素晴らしいものだった。(視聴覚通信14号)
言葉はどこに向けられているのか
第1回OMSプロデュース「坂の上の家」1995年7月8日(土)・扇町ミュージアムスクエア
松田正隆の第1回OMS戯曲賞大賞受賞作。1993年に時空劇場で上演されているそうだが、ぼくは見ていない。時空でなら松田自身の演出によって上演されるものを、竹内銃一郎の演出によって、時空の役者ではなく見せるということから、時空ファン(内田淳子の、というだけではなくてだよ)にとっては、いささか心配でスリリングな公演となった。
松田が時空で見せてくれていた空間というのは、ひそやかな通奏低音のようにすべての瞬間を流れ続ける日常という平凡の中に、時折襲う軋みのようなものを、極力何もなかったふうに皆が緩やかに受け入れようとする態度だけで成立する空気の流れのようなものだったのではないだろうか?ここでまるで初めてのように、金替康博という役者の魅力を思い出す。茫洋と言っていいのか、あの声のトーン、松田が台本で多用する「……」という間(ま)を的確に表現する「口ごもり」など、セリフに表わされていない心の交感を舞台の中心で担っている役者であるように思う。それは、言葉で言わなくても理解している関係、大切なことをこそ言葉に表わさないことで守っている関係を、ひそやかに甘く描く時空の劇を根本で成立させていたと言ってよい。そのような空間を成立させることのできる劇団においてこそ、松田の脚本は深められ、高められていったのだろう。
そんな松田の脚本が、竹内の演出に委ねられるということで、どのような空間が出来するか、それはほぼ自明のことだったはずなのに、やはりどうしたって戸惑い、驚いた。それはまず、セリフも動きも、外に向けて発せられていたことにある。冒頭の「……何ばしよっとや」「うん? …うん」「こげん、朝早うから」といった兄妹で交わされる会話の声の大きさ、妹役の洪仁順(新人)が家の中を走り回るスピードは、きょうだいだけの家族が持つ若い慌しさとして描かれているとはいえ、時空でなら見られないものではなかったか。おそらく金替らなら上半身を動かさずに滑るようにバタバタ
(?) したろうが、洪や奇異は本当に前のめりになって走り回りバッタンバッタン音を立て、もちろんそれは新鮮で微笑ましくさえあったのだが。時空ではステージの上のごく内輪の閉じた共同体の中でのみ、言葉も動きも流通しているが、竹内演出ではセリフも動きも客席に伝えられるために外向きに存在し、演じられている。時空にとって演劇の空間というものはあくまで閉鎖された世界であって、それを客席のぼくたちは覗き見させてもらっているようなものだったのだ。松田の例によって、長崎が舞台である。水害で両親を亡くした兄、弟、妹の三人の一家と兄の婚約者、きょうだいの叔父が登場人物のすべてである。婚約者の来訪の朝から物語は始まる。妹の心づくしの皿うどんでもてなされ、すっかりうまくいくと思われた兄の縁談だが、突然彼女の方から断られたと知らされる。「前々から、心に決めとった人のおったらしか」というのが、兄が叔父に語るその理由である。しかし、兄は弟から、彼女が貧血がひどく体調を崩して入院していること、両親が被爆者らしいことを知らされる。驚きためらう兄(奇異保。虚航船団パラメトリックオーケストラ所属)に焦れて妹が彼女の入院先の大学病院に電話する。受話器を持たされた兄は電話口で「……そこからも見えとるですか、精霊流し……」とやさしく声をかける。
ここで時空が昨夏に西部講堂で上演した「月下之門」を思い出してみよう。このオムニバス連作の公演でぼくは、松田がわざと、殊更に酷薄さを押し出そうとしているように思った。はしぐちしんの車椅子に係るエピソードの取り上げ方、内田淳子が青年を言葉でいたぶる執拗さなど、これまで、こう言ってよければ予定調和的な穏やかで小さな生活世界で生じる小さなドラマを見せてきた彼らが、わざとらしくあけすけさを露悪的に強調し、観客にいたたまれなさを感じさせているようで、彼らが最終的な局面に逢着しているのか、これをきっかけに急変しそうな、そんな舞台だったように思う。それらが結局しばらくの活動停止ということにもなったのではなかったか。松田にとっては、既に昨夏の新作において時空の芝居を何かにぶち当てるかして、いっそ壊そうかとしていたところへ、ここで旧作をこのようなおそらくは全く別の形で演出される機会を得たわけで、ひじょうにタイムリーなことだったに違いない。……
きょうだいたちの両親が水害で亡くなったことをベースに、浪人中の弟が進学をやめて料理の専門学校に進むと言い出したこと、叔父さんがなぜ本家に寄りつこうとしないか、などこの劇にはたくさんのドラマがちりばめられている。登場人物の多くが何らかの悲しみや惑いや断念を抱えている。にもかかわらず劇はただ日常を再現しているような当たり前さを進んでいく。この中で最も大きな事件は、婚約の破棄とそれが被爆二世としての後遺症なのかも知れないというあたりだが、これが何とも唐突で無理があるように思えたのが残念だった。どういうことかと言うと、その婚約者・陽子(城之内和美)にはそのような事件が到来することを予感させるような何ものかが欠けていたということだ。もちろん、いわくありげに登場する必要はないし、思わせぶりであってはいけない。彼女の両親が被爆していたとしても、彼女自身はおそらくこれまでの人生の中でそれを意識しなければならないような不調や失調はなかったに違いない。ことさらそれを隠してつきあっていたというわけではあるまい。しかし、舞台で悲劇は、予感されないとしても、予定されているものだ。
ぼくが残念に思ってしまったのは、日常が常に悲劇の可能性を孕んでいることの当たり前さを、この舞台からはじゅうぶんに汲み取れなかったことだ。それさえあればどのような唐突な悲劇が展開されても、ぼくたちは人間のありうべき悲劇として、悲しみながら受け入れることができる。それがなければ、唐突な悲劇は作劇上の無理なヤマ場作りとか強引な展開として鼻白ませるだけのものになってしまう。松田が作り上げる静かに展開していく芝居において、クライマックスとは必ずしも舞台の上にあるのではなく、見る者の中にあるといってもいい。
水害で両親を失ったきょうだい、と言われると今のぼくたちは即座に、震災で何者かを失った誰彼のことを思う。悲劇は常に何の伏線も張らずに、あまりに唐突にやってくることをぼくたちは知っている。そしてその悲劇から、人々は、何もなかったようにとは決して言わないが、淡々と元に戻ろうとしている。しかし決してその道は平坦ではないようだ。ぼくの家の近くで、小学校で同学年だった人の家が全壊し、細君と小さな子どもが亡くなった。やっと大きな家が再建され、暮れには外装は終わったようだ。そしてそんな1月の初旬のある日、生花の絶えなかった敷地の一角で、うずくまって泣いているその家のおばあさんを見かけた時、その悲しみを共有することのできないぼくまで、道にへたり込みそうになってしまっていた。一年間、そこに花やおもちゃやサッカーボールやらを絶やさなかった人たちの思い、その人たちがやっと新築成って再びここで暮らそうとする……そこにしかし亡くなった者は暮らせないのだ。ぼくは再びこの土地に戻ってくるこの人たちに、「よかったですねぇ」とは、言えないだろうなぁ……。しかしこの人たちもぼくたちも、何もなかったような顔をして日常を生きていかなければならない。
ぼくたちの日常は、そのように、また別のありようをもって数々のドラマを秘めており、それを自分では殊更に言い立てはしないが、それぞれにそのようなドラマが秘められていることを沈黙の内に尊重しながら、たとえば朝夕の挨拶を交わす。演劇がそのような日常の劇性を淡々と描いて、それでドラマを感じることができないのなら、それが主に見る側のせいであっても、演じる側のせいであっても、人間に対する認識をいくらか誤っていることになるように思う。時空の芝居の大切さは、日常の「淡々」の尊さをぼくたちに改めて見せてくれることだったのだなと、時空ではない松田正隆の芝居を見せられて、ほんとうに気づいたように思う。(視聴覚通信16号)
![]()

重層するテキストと時間と空間
思い出せない夢のいくつか−
青年団プロデュース公演(2月27日(日) 伊丹・AIホール)平田オリザ作・演出の、すべてにわたって(貶めて言うのでは全くなく)ひじょうに温度が低い芝居だった。絶対零度を微かに上回って、すべてがほとんど静止して硬質の結晶でしかありえないような状態で展開される。だから、ほんの少しの空気の揺れや微かなざわめきがこの上なくいとおしいものに感じられる。このいとおしさを抱いたあとでは、ぼくたち自身の日常への視線が明らかに異質なものへと変化したように思う。
「ただ汽車に乗って歌手(緑魔子)、マネージャー(木之内頼仁)、付き人(平田陽子)の3人が、ずっとダラダラ喋っているというだけ」と平田自身が「Lマガジン」2月号のインタビューで説明している通りの、淡々とした一時間だ。ただ、たとえばジュースを買ってきたりタバコを吸いに席を立った(禁煙車しか空いてなかったという設定なのだ)折りの会話で、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の鷺を押し葉にする妙なおじさんがデッキでタバコを吸っていて話しかけてきたことがわかったりして、どうもこの三人はカムパネルラたちの列車に乗り合わせてしまっていることがわかる。他にも、彼ら三人が林檎を食べ始めると、ぼくたちはカムパネルラやジョバンニが灯台守から林檎をもらうシーンを思い起こす。そのようにしてこの作品は「銀河鉄道の夜」の作品世界を背中合わせに展開して、とんでもない深みを持ってしまっていた。
中でも目がくらむほどの衝撃を受けたのが、ジュースを買いに下手側の袖に下がった付き人が、しばらくたって突然客席後ろの扉から「わたしは 手でさわった……」(だったと思うのだが)と讃美歌のように歌いながら、手に林檎をもって現われたシーンだ。平田陽子の澄んだ歌声、シンプルなメロディが美しく、これもまた「銀河鉄道の夜」で「向ふの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。そのとき汽車のずうっとうしろの方からあの聞きなれた〔約2字分空白〕番の讃美歌のふしが聞えてきました」(引用はちくま文庫版全集第7巻による)を思い出された。
宮沢賢治の作品世界に隣接させることによって、この芝居の世界は大きく膨らんだ。3人の登場人物は、ふつうに考えれば売れなくなった歌手のドサ回りの途次でしかない。歌手はかつては大スターだった余韻をとどめて強烈なアウラを持っているし(緑魔子という女優だったからだろうが)、マネジャーはそれなりに俗物だし、付き人はふつうの歌手志望の女の子みたいではある。しかし、それが銀河鉄道に乗り合わせているということを知ったとたん、この世ならざる聖性を帯びて見えてくる。
さて、先に述べた付き人の一種の憑依に同調するかのように、歌手が立ち上がり、ペテルギウスや赤色巨星のことを語り始める。……赤色巨星は表面は三千度ほどの低温ですが、内部では一億度もの高温で、さらにこの星は、……と。じっさいぼくは、ここで付き人が本当に死んでしまったのか、またははじめからこの人たちは生と死の境い目の、少し死の方に近い方の崖をそろりそろりと進んでいたのかもしれないと思い、深く悲しかった(じっさい、あとで歌手も「死んじゃったのかと思ったのよ」と付き人に話しかける)。舞台と客席という隔たりを超えて、何十分かを一緒に過ごしてきた人たちの不在を悲しんでしまったのだと思う。このシーンはあくまで謎として残る。付き人は手に持っていた林檎を二人に手渡し、その林檎はこのシーンの後も二人の手に残る。眠っていたマネージャーが起きて、歌手がさっき付き人が来たことを告げるが、マネージャーは気づいていないので、林檎が手元にあることを指摘するのだ。だからこれは幻ではなかったのだ、と了解させられる。このシーンは本当にわからない。しかし、わからないことが不愉快ではない。少なくともここではわからないことが起こっているのだし、それが普通なのだと納得させるだけの世界を構築しえていたということだ。(視聴覚通信14号)
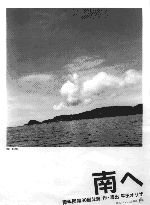
ある世界像の中の交換可能な存在
青年団
「南へ」 1995年10月1日 伊丹・AI HALL平田オリザの1990年の作品の再演。21世紀中頃を設定し、「外国人労働者」が増加して住みにくくなった日本を脱出し、遥か南方にあるという「もう一つの日本」をめざして豪華客船に乗った人々を描く。何カ月かをおいて、このような船旅に繰り返し深く引かれている。一つは桃園会の「beside paradise lost」という芝居、一つは島田雅彦の小説『沈む男浮く女』。船の上で起きる惨劇の度合いは異なるが、三者に共通する一種のクールさは、船旅という緩やかな時間の流れによるものなのだろうか。
青年団の芝居を見るのも何度目かになるが、こんなに役者の個性を感じたのは初めてだ。特に挙げれば、残酷な「人種差別」発言をするイトウ(安部聡子)、人買いのカザマ(志賀廣太郎)。この2人のセリフと役柄の強烈さは、これまで青年団の舞台から受けることのなかった体験だった。平田は、「戯曲家にとって、役者は交換可能な存在である。……交換可能というのは、同一であるという意味ではない。等価であるという意味だ」「役者は私にとって将棋の駒にすぎない」などと、あえて「挑発的な発言を続けてきた」(引用は、晩声社『平田オリザの仕事1 現代口語演劇のために』から)。役者の個性の発露は、彼の演劇の理論からははみ出るもののように思えるが、どうか。
その理論から言えば、たとえば「純日本人」ではないウェイトレスのゴトウ(和田江理子)もイトウも交換可能で等価であることになる。役者の個性によって人物が規定されることはない。イトウを演じる役者が瓜実顔であろうがなかろうが、ゴトウを演じる役者がちょっと猫背であろうがなかろうが、無関係でなければならない。平田はそれを「ニュートラル」と呼んでいる。しかしもう一方で平田は、戯曲についても「実は、絶対的なものではない」と言う。かけがえのない台詞などない、「役者が変われば、その不自由さの在りように応じて、台詞を変えればいい。それでも世界は崩れない。それで崩れるような世界なら、それを私は戯曲と呼ばない」と。ここで戯曲にとって重要なのは、平田の世界観なのだ。その中でならその役柄はこのようにあるはずだという範囲内で、台詞その他は任意に決定されることになる。
ここでぼくがゴトウとイトウにこだわるのは、次のようなシーンがあるからだ。船底に隠れて密航しようとしていたツカダが見つけられ、デッキに囲いを作って繋がれていたところ、ツカダがその囲いから出てしまった後。イシダはイトウの婚約者。(引用は当日会場で販売の台本から)
イシダ どうなったの?
ゴトウ いや、それがよくわかんないんですけど。
イシダ え?
ゴトウ いや、大丈夫だとは思うんですけど。
イシダ でも、あの人、何で、隠れてたの?
ゴトウ あぁ、港の近くで見つかるとヘリコプターで連れ戻されちゃうんですよ。
イシダ 連れて行ってあげるんでしょ、マペウリまで。
ゴトウ えぇ、ここなら、その方が近いですから、
イトウ ちゃんとして下さいね。
ゴトウ はい、すいません。
イトウ 私、外人って大嫌いなんですよ。
ゴトウ はい。
イトウ もう、最近とか、見るだけでもやなんですよ。
ゴトウ はい。
イシダ まぁまぁ。
イトウ そいで、日本逃げ出してきたんですから。
ゴトウ はい、わかりました。
イケヤ お待たせしました。(ジュースを置く)
イシダ ありがとう。
イトウ 本当は、あなたたちとだって、話したくないくらいなんだから、
ゴトウ はい、申し訳ありません。
イシダ やめなって。
イトウ どうして?
なぜイトウが外人を嫌うのか、ゴトウはどう「純日本人」ではないのか、そもそもこの時日本はどうなってしまっているのか、そのようなことはほとんど明らかにされないまま芝居は終わってゆく。ぼくたちはその欠落を自らの想像力によっておそらくは不十分な形で補完してゆくしかない。人物像--地位、なぜこの船に乗るに至ったかなど--についての説明もなされない。ぼくたちはこのイトウの残酷な発言を唐突に聞き、ある意味ではイシダよりも驚きあたふたする。
しかし、ぼくたちはそのような現実を生きているのだ。ぼくたちは周囲の誰彼のことを、ここでそうしたように、一瞬の動きや発言や噂から類推し想像して築いている。ぼくたちは隣人や友人やあるいは肉親についてもその断片しか知らず、断片を継ぎ合わせては手探りで全体像を築いているようなつもりになっている。神ではないのでぼくたちは、どのような方法にせよ知ることができる以上のことを知ることはできない。ぼくはここで起きていることしか知らない。常にそうだ。その上で、ジグソーパズルを埋めるような作業から、そしてそれが崩れるところから、劇は生まれる。この場所の現在のありようを超えた位置から、過去や未来や隠された内面をあらかじめ知っておくことなどできないのだ。
平田はありのままに世界を提示する覚悟がある。芝居は板の上だけだぞと言ってもいい。その世界の外のことは必要ないし、殊更に「神の視点」をもって滔々と説明すれば芝居の嘘になる。たとえばもしイトウが唐突に「実は父は外国人労働者に殺されたのよ」などと独白調で振り返るように説明したとすれば、それは愚かなことだ。そのことは劇としてそこで演じられたことではないからだ。たとえかつてそのようなことがあったとしても、それが今舞台の上の彼女にどのような影響を与えているかは、ぼくたちは舞台の中で嗅ぎ取ることしかできないし、それ以上のことは必要はない。現実は現実の大きさとしてしか存在しないし、劇の中でどのようなドラマが展開されるかは、現実がそうであるように任意のことなのだ。劇が始まる前のことをぼくたちは知る由もないし、劇が終わってから後のことをぼくたちは勝手に想像する他はない。平田の芝居が既に客入れの時から始められているのは、そういうことだと思う。このように劇の小ささ、あるいは日常と比べたときの大きくなさを認識し覚悟したところから、平田の芝居の大きさが生まれてきていると思うのだ。 (視聴覚通信16号)
Copyright:Shozo Jonen 1997-98, 上念省三:gaf05117@nifty.ne.jp