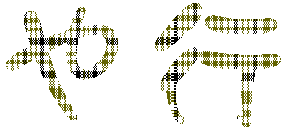
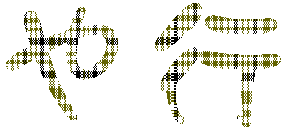
山崎広太
笠井叡に舞踏を、故井上博文にバレエを師事。'89年、フランスに招聘され、ダニエル・ラリューの作品制作に参加。'94年、バニョレ振付賞本選に"inflection"が選出され、パリで上演。'96年、カンパニーrosy co.設立。東急bunka村シアターコクーンにて"what's wrong"を発表、パリやロンドンなどでも自作を公演している。
Dance Battle 森美香代×山崎広太
1998年6月3、4日 於TORII HALL。大阪DANCE EXPERIENCE'98の第一弾として企画された公演。8月初旬には伊藤キムとヤザキタケシの公演が予定されているが、今回の森と山崎についていえば、ほとんど接点のない二人のダンサーがそれぞれの作品を持ち寄り、その後短いインプロヴィゼーションを行うという形となった。じっさい、二人はこの企画までほとんど互いの作品を見たこともなく、ビデオを見て共演を了承、1カ月ほど前に初めて合わせてみた、ということだったということを、前に天満で森美香代に聞いていた。
森の動きが柔らかでたおやかであるのに対し、山崎の動きは、一度短い作品を京都で見ただけだが、柔というよりは軟体に見え、両者の動き方にはかなり開きがあると思っていたので、ある意味では楽しみな公演となった。
まず山崎のソロ「ピクニックから」で始まる。山崎がうずくまっているところを、下手手前から上手奥に森がスーッと去っていくことから始まる。森の美しい歩き方から、去りがての悲哀が瞬間的に立ち昇るシーンである。それを切るように、山崎は手首の反り、関節のねじれなどを交えた激しい動きを激しい速度で連続させる。後である人はそれを非常に強いと言い、ある人は意外に硬いと言っていたのが面白い。ぼくは彼の動きは手先や指先の激しさとは裏腹に、身体の中心の軸となる線はあまり大きく動かしていないように思った。このことについてぼくは判断を留保している。いいことだとも悪いことだとも思わない。顔の表情をほとんど変えないこともあって、情感を促すことのない動きである、という印象も、そこから導き出されるのだろう。むしろ冒頭のシーンについてもふれたように、身体を動かすことで否応なく立ち上がってくる情感を積極的に切っていく動きであるように思う。そのための、軸の動かなさであり、尖端の激しさであるのではないか。
強く印象に残ったのだが、そのような動きの集積によって、彼は静止していることに対する恐怖でも持っているかのように、時間も空間も埋め尽くしていくようだ。前述の情感を切って思いを残さないでいくことと、この時空の埋め方は、ある種の潔さ、覚悟を観る者に突きつけるように思われた。
30分という作品の時間の構成上だろうが、中間部分はユーモアだか息抜きだか、「恥ずかしいなあ」と叫んでみたり、「ちょっとテンション落ちました」と告白して見せたりと、笑いをとって見せた。初日はそれが大受けで、客席は相当盛り上がったが、二日目はそうでもなかった。彼のいい意味での少年性を印象的に提出するシーンだ。この笑いの挿入についてもまた、様々な評価があるだろうし、彼自身のメリハリや必要性はあるのだろう。
唐突だが、由良部正美の「小町」の中間部の、ハンガリー舞曲か何かのユーモラスな場面を対比させてみよう。ここで由良部は、もう由良部ではないから、その中間部は小町の長い人生の中のそのような時間として挿入され、または小町という人間の他面として提出され、違和感を与えない。与えたとしても、それはのちに収斂できる違和として提示されている。
その点、山崎の作品の上で、それは同様には機能しない。なぜなら、ここで山崎の身体の人称が、とても微妙な位置に置かれているように思えるからだ。もちろん彼は誰かになるわけではない。彼は彼自身として立っているはずなのだが、妙にその「自己」は希薄さか何かをまとっているように見える。これもまた、先ほどから述べている情感を切っていることから発しているのだろう。このユーモラスな場面で彼が見せる少年性、彼自身の素(す)の表情、顔、声じたい、彼が彼自身を装っているように見え、ある種の戦慄と作り物めいたやりきれなさを覚えた。自己を仮構し、それを一度消した上で、無表情を装いながら、ある部分では笑いをとってつけて見せるというような、手つきが見えてしまっている。それがまた一つの手法なのだろうか。
森美香代は、立っているだけで、ある雰囲気を持っている、稀有なダンサーの一人だが、「Solo & Soul」は、彼女らしい滑らかな動きが連続するうちに、それらの動きが醸し出す情感が堆積し、溢れていく作品だった。中で今回面白く思ったのは、何かを表わしているような動きと、動きそのものである動きの交錯で、これによって観る者は動きが連なりとして意味へ近づいたり遠のいたりする揺れを楽しむことになったのではないか。水を掬って飲むような、とか、外に倒した指を舐めて見せる、とか、くちびるに紅を引くような、というふうに、意味の連なりが予想され、それがまた次の動きでは切られていく。結果としてぼくたちの思いは断片として宙ぶらりんにほうりだされる。ぼくが先に言った堆積というのは、そのような断片のことだったということがわかる。
森の動きは、決して憑依的だとは思わないのだが、やはりたしかに向こう側に接している。何か大きなもの、豊かなものに触れているということが彼女の身体からは感じられ、それに包み込まれること、そして包み込むことのたゆたいの中で大きな喜びに身を委ねているように見える。それが彼女のダンスを見ることの喜びなのだと、改めて認識させられる。
二人のソロ作品を終えて、二人のインプロヴィゼーションとなる。二人はお互いに不干渉で、たまたま同じ時期に同じ世界にいるだけのように思えた。それでも時折身体の折り曲げ方などが同調しているのは、どこか遠くの星で響きあっていたのかもしれない。そのようなことを再確認する、慎重な探り合いのようでスリリングなステージとなった。初日は、山崎が森を見つめているところで溶暗となったのが、二日目はそれに森が視線で応えて終わった。そしてどうなるのだろう、と思わせる洒落た構成をちょっぴり設けたことで、スマートな時間となったと思う。
山田せつ子
明治大学演劇科に在学中、舞踏研究所「天使館」に入館。笠井叡に師事。'79年の天使館閉館まで多くの公演に出演する一方、'77年よりソロ公演活動を始める。'83年アビニヨン・シャルトルーズ・フェスでの招待公演以来、ヨーロッパを中心に海外公演に数多く招待参加。'89年よりダンス・カンパニー枇杷系を主宰し、構成、振付作品も発表している。
会場にはいると、何とも魅力的なオブジェが目に入る。美音子グリマーの手になるもので、砂を敷いた上に木の枠を作り、水を張って土台とし、そこに薄い石の板を甲羅のように組み合わせて薄く広く広がるオブジェである。その上に、小石で固められた角錐が吊り下げられていて、時折水滴や小石が滴り落ちる。尖端に穴があいていて中から落ちているのかと思ったが、むしろ上の方や外側から剥がれるように落ちてくる小石を見て、凍らせ固められていることがわかった。開場から開演までの三〇分間、このオブジェと正対することになった。どんな作品でも、三〇分間それに接し続けることは、ざらにはない。「接し続ける」と書いたのは、それをただ見続けるだけでなく、上から落ちてくる小石や水滴が下のサヌカイト(讃岐岩)のような薄板に当たり玄妙な音を立てる、その音に聞き入ってもいたからだ。ししおどしのようでもっと高く乾いた、当然だが鉱物的な音が響き、それだけで一個の無人のパフォーマンスであり、深い感動を受けた。
さて、ダンスのことを語らなければならないのに、ぼくの五感はまだこのオブジェに囚われている。このオブジェを引きずる形で、舞台美術は、その後も天井から滝のように砂を落下させてみるなど、流れ落ちるものを事物として見せ、舞い手の身体の崩落、また舞い手がオブジェに働きかけやがてはそれを崩していくというような形でダンスと交差しながら、主調音となって空間を支配していたように思う。
山田は身体を美しくふるわせることのできる人だ。オブジェの角錐の下あたりに手を差し出そうとし、後に下の水をすくい取るような動きに出たかと思うと、水を払う。その時の手の甲が硬い別の物質に転じたようで美しく、角錐のエッジと掌の面が近づくときの緊張感の昂まりが心地よかった。他のいくつかのシーンでも、時間と空間の緊張を一点に集中させることができるような身体で、その美しい危うさが魅力的だった。
後半では、四人の女性が袋の中の羽を散乱させたり、武闘のように組み合う形で激しく動き、オブジェの底に溜まった水に顔をつけたかと思うと水を跳ね上げ、落下した小石を浚い、石板をバラバラに外しと、破壊的な動きに出る。これまで神のように存在していたものをめいめいが自分のものにしようとしてか、石板を持ち帰ってしまう。あるいは「月ノ蜜ヲ採ル」というのは、掠奪のニュアンスを湛えていたのだろうか。
山田は靴を脱ぎ、身体の重心を片側に寄せて不安定を作るが、これがまた実に美しい。神のような存在だったオブジェが冒涜され、瓦解した後に、代わって山田自身が憑依し聖化したようだ。石→水→砂→羽と、重要なモチーフはどんどん軽くなっていき、山田の身体や表情も急速に「無」に近づいていく。それもまたオブジェの氷の溶けていくさまと同じ時間を共有していたようだ。
どんどん氷が溶けていき、ついには角錐から小石がバラバラと激しい音を立てて落下する。その崩壊に輪をかけるようなダンサーたちによる破壊的行為。構成として、ぼくはこれにじゅうぶん納得したとは言い難いが、これを支えていたのは、やはり美音子グリマーのオブジェの力であって、最終的にはどうしても山田の印象が薄くなってしまったようで残念だ。(山田せつ子+枇杷系ダンス公演「森--月ノ蜜ヲ採ル」'95年8月19日 伊丹・AIホール) (視聴覚通信16号)
ヤン・リーピン「孔雀」
 ヤン・リーピンとぼくは、同い年だ。日本と中国のあらゆる差異や性差を踏まえた上でも、身体表現だからこそ、ある種の同時代性を共有できるのではないかと期待した。しかし、その超人的に研ぎ磨き上げられた身体に呆然としながら、共に今を生きる必然性を汲み取ることは困難だと言わざるを得ない。
ヤン・リーピンとぼくは、同い年だ。日本と中国のあらゆる差異や性差を踏まえた上でも、身体表現だからこそ、ある種の同時代性を共有できるのではないかと期待した。しかし、その超人的に研ぎ磨き上げられた身体に呆然としながら、共に今を生きる必然性を汲み取ることは困難だと言わざるを得ない。
実際、彼女のあらゆる身体の動きには賞賛を惜しまない。雲南省のペー族を出自とする彼女にとって、自然界を模倣し再現することは、少数民族の伝統を継承するという意味からも重要なことなのだろう。冒頭の「月光」では大きな月のセットを背景に、シルエットとして月の精になった。指の爪先に至るみごとな反り、震えのような繊細な指先の動き、肘を大きく使った腕の回転、腰のくねり……によって、あたかも月の光が粒子として降ってくる音を聞いたような思いがしたものだ。
その指はまた雨を表わし、孔雀の羽のふるえとなる。上半身の激しい動きは炎の舌になり、腰を中心とした肢体のくねりは蛇だった。そのような正確な喩として身体が様々なものを再現していくのを、ぼくは一つのスペクタクルとして楽しんだ。
民族の伝統から想を得ても、彼女はそれを作品とするにあたって「現代化」しているだろう。しかしその時、伝統から何が消去され、何が現代として付加されたのかが、蓄積のないぼくにはわからない。ただ作品の仕上がりから想像するに、彼女が想定している現代と、ぼくが考え感じている現代には、どの程度かの開きがあるようだ。彼女が伝統を現代化するための苦闘の跡は、そのあまりの美しさに覆われて、なかなか見えてこない。決して彼女が見せようとしない対象を、いつかナマな形で見てみたいとも思う。(音楽之友社「Ballet」掲載)
ユン・ウェイ-メイ
ユン・ウェイ-メイ(香港)の「Tango of Water Sleeves」は、踏まえられた言葉や人物について知っていないと、なかなか十全に理解するのは難しい作品だったように思う。京劇、ビデオで流される「流蘇」「管也管不著」等といった言葉が、ぼくには剛体な異文化として立ちはだかるように提示された。
しかしそれでも、この十数分の作品を楽しみ味わうための仕掛けはいくつもちりばめられている。まず、シモ手から黒いパンツスーツ姿で現れたユンの姿や動きが、ひじょうに美しく官能的だったことで一つの定まった世界に引き込まれる。背景の映像が左へ流れていくのが、時間の流れでもあるだろうが、風のようにも見え、官能的なゆるやかさとして空気を作る。ユンの動きもまたゆるやかだが、とても正確であるように思われる。でも、何に対して正確なのかはよくわからない。映像が終わると、あわてたように息を荒くしマッチで左腕を熱くなるほどかざす。続いて腕から顔をなぞるようにしてぬるい官能をあらわし、回転する。
続く蚊取線香の映像を使ったメタファは、日本においては新奇なものではないし、欧米等では理解されにくいと思うが、螺旋がどんどん短くなるのとユンが寝転がって激しく回転するのとで、時間論を提出することはできていたと思う。
次に京劇の女優(?)の映像とタンゴがシンクロするという不思議な場面に入る。タンゴがフェイドアウトして京劇の音楽になったり、またタンゴに戻ったりしながら、映像の女優とユンがユニゾンに近い動きで同調している。ユンの身体に京劇の身体が映り、ほぼ完全に重なり合う。この女優は、ユンにとってどのような存在なのかわからないので、これがどのようなことを意味するのか、わからない。そういうもどかしさを与えられながらも、何かとても大切なことが込められているような重みはずっしりと伝わってきた。また背景に文字が流れ、こちらを向いたユンはバラを口にくわえている。四肢の回転が大きな魅力的な動きをとった後、強い表情になり、モデルのように堂々と引っ込んでいった。この作品の背景にあるものをもっと深く知りたいと思った。
アジア・コンテンポラリー・ダンス・フェスティバル Aグループ 2001.10
ヨシ・ユングマン「Dualogue」 8月12日 トリイホール
アルゼンチンに生まれ、20歳でイスラエルに移住、バットシェバ・ダンスカンパニー所属のヨシが、ウクライナうまれのパーカッショニストのボリス・シーコンと「伴奏」の域を超えてがっぷりと組んだコラボレーション。
まずヨシの雲のようなボロのような不思議な布の動きを見せる短い作品と、ボリスの口琴や木琴の「超絶技巧」の披露。二人の顔見世、自己紹介のようなパートだったとは思うが、その後の数十分のために、必要な時間だったと思う。
二人は不思議な道行きを見せる。ヨシの軽妙な動きを目で追うだけで楽しく、もちろん一瞬ごとの形が美しいことにもすぐに気がつく。ボリスのハーモニカや親指ピアノ、ヨシの不思議な打楽器(ガラガラみたいな大きさで、ノコギリをバチで叩くような仕掛けで、そんな音が出る)という音の要素も非常に大きな役割を占めている。音と身体の動きが複層していることに気づく。
ボリスが掌の中のカスタネットのような楽器でカチカチとヨシを挑発したりして、ヨシの動きそのものを注視するよりも、二人のユーモラスな関係性を楽しむことのほうに重点が置かれているようで、ある意味では芸能的な空間だったとも言える。コンテンポラリー・ダンスということで、それをぼくたちはなんとなく芸能性や土着性とは遠いものだと思っているが、舞踏がある意味では世界でコンテンポラリーとして受け入れられているように、両者は決して矛盾するものではないようだ。ヨシは、1996年に大野一雄、慶人のもとで舞踏を学んだというが、そのことと作品の現れがよくマッチしていたし、ヨシがボリスの音楽を必要としたことも、よくわかるような気がする。
ヨシの身体の動きや表現力は、決して「超絶技巧」を前面に強調したものではなかったが、インテリジェントとユーモアにあふれた、言うまでもないがかなり上質なものだ。見ていて楽しくなると同時に切なさがこみあげて来るのが、おそらくは土着性によってきたるものなのではないか。そしてそれ以上に驚いているのが、ヨシとユニゾンでちょっと不器用そうにぎこちなく動く、ボリスの身体のいとおしさで、これには実に言葉を失った。(2000年8月)
Copyright:Shozo Jonen 1997-2003, 上念省三:jonen-shozo@nifty.com